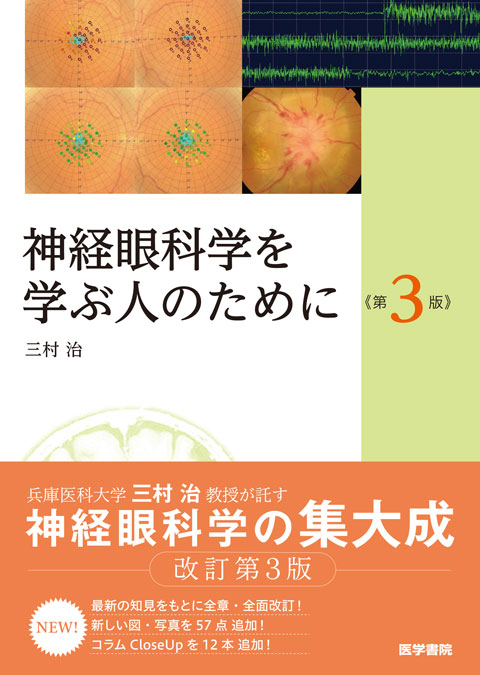MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2021.09.20 週刊医学界新聞(通常号):第3437号より
《評者》 藤井 誠志 横浜市大教授・分子病理学
整理して理解しやすいようにまとまった教科書
『組織病理カラーアトラス』は,病理学を学ぶ上で必要なことを初学者が整理して極めて理解しやすいようにまとまった教科書であり,著者らの長年のご経験と病理学に対する深い造詣が本書のような教科書のご執筆を可能にしたと感銘を受けている。医学を学ぶ学生にとって,興味を持てる内容であること,理解しやすい内容であること,学ぶべき内容量が多過ぎないこと,といった要素は賛否両論あると思うが,将来どの専門領域に進む医学生も診療面,研究面における病理学の重要性を学ぶ必要があることに鑑みると,重視されなければならないと感じる。
本書は総論と各論に分けて構成されることと合わせて,豊富な索引用語が巻末に用意され,総論と各論を行き来しながら読み返して内容を理解できるように配慮されている。病理診断学は分類学の一つであり,形態像を表現する病理学的用語の定義を正しく理解することは病理学を学ぶ上での出発点である。
例えば,肥大や萎縮といった総論で学ぶべき用語は,病因を意識したメカニズムによって分けられる用語であるものの,それらの形態像をひもづけて理解しなければ,知識と形態像が分離したままになり,病理学を学ぶ意義は薄れてしまい,最終的にはなじめない,ただの暗記が求められる学問として認識されてしまうことになる。本書はそれを避けるための十分な配慮がなされており,必要な言葉と簡潔でまとまった文章で解説がなされている。
実際の病理組織像を一人で学習する際には,どの組織像を認識すれば良いのかという問題にしばしば直面する。そういったことが想定される場合には,適宜イラストが併用され,医学生が直面しがちな問題の解消を担っている。病理学は病気の理を,形態学を武器にして探求する学問であることを首尾一貫して伝えており,常に病理形態像をイメージしながら,病理学の本質の理解を意識した構成と内容になっている。まさに“組織病理カラーアトラス”という名にふさわしい良質な教科書である。
各論については,各臓器についての疾患の紹介の前に,基本構造のチェックという項目が用意されており,正常とは異なる形態像の理解と病態の理解が円滑に進むように配慮されている。またどの臓器についても,極めてまれな疾患を含む分類上存在する疾患の全てをいきなり学ぼうとすると,病態の体系的な理解がおろそかになりがちになるが,それに対する配慮もなされており,まずは学ばなければならない必須の疾患が過不足なく選抜されて紹介されている。
ゲノム医療が推進される状況下では,病理医に求められることは増え,また病理学の位置付けも変わっていき,それに対応すべく病理学は日々発展,進化していかなければならない。病理学は形態診断学を武器とする学問であるが,それに加えて遺伝子異常が種々の程度で診断学にも組み入れられている。また分子病理診断の要素も求められ,治療病理学の側面も重視されてきている。本書はその基盤となる,変わることのない根本的な病理学全般の理解を十分に助け,読者を病理学の基礎から応用,発展へと導いてくれることが期待される。以上の理由から本書を推薦させていただく所存である。
《評者》 三井 貴彦 山梨大教授・泌尿器科学
当直の際に出くわす可能性のある疾患を幅広く押さえた一冊
泌尿器科は,新生児から高齢者まで幅広い年齢層を対象とした診療科ですが,対象疾患も泌尿器悪性腫瘍から下部尿路機能障害,小児泌尿器疾患,女性泌尿器疾患,腎機能障害,腎移植,内分泌疾患,外傷など,多岐にわたります。通常診療においても,これらの疾患に対する幅広い診療を行う必要があります。加えて当直の際には,経験する機会が少ない疾患や教科書にあまり詳細に記載されていない疾患に対する診療を行わなければならないことがあります。日中ですと上級医に相談すればよいですが,当直時には自分自身で判断しなければならないケースも珍しくありません。一方,経験する機会が少ない疾患や病態については,上級医であっても治療方針の決定に苦慮することも少なくないはずです。
本書は総論から始まり,外来診療および入院診療で緊急で対応しなければならない疾患,さらに泌尿器科医が対応に苦慮する疾患まで,非常によくまとまって解説されています。経験する機会が少ない疾患はもちろんですが,当直で経験する可能性のある各種疾患についても,「絶対に見逃してはいけないポイント」や「診療のフローチャート」が記載されていますので,限られた時間の中で診療方針を立てる際に役に立つと思います。また,救急外来で診る可能性のある急性期の疾患や,近年泌尿器科でも使用頻度が増えている悪性腫瘍に対する分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬などの有害事象への対処法は,通常の外来診療でも重宝できるかと思います。一方,超高齢社会を迎えた現在は高齢者の外科治療の機会が増えていますが,各種の術後合併症に対する対処法は,入院患者のケアに役立ちます。さらに,泌尿器科医があまり得意としない精神疾患や皮膚疾患に対する診療のポイントも詳細に記載されています。
このように本書では,当直をしている際に出くわす可能性のある幅広い疾患について,診療のポイントを押さえて記載されていますので,時間のあるときに目を通しておくことをお勧めします。きっと当直の際ばかりでなく,通常の外来診療や入院診療でも役に立つことでしょう。コンサルトを受ける側の上級医の先生方にもお薦めの一冊です。ぜひ手元に置いてご活用ください。
《評者》 園田
本書は2014年に世に出て,わかり...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

![組織病理カラーアトラス[Web付録付] 第3版](/application/files/8816/1881/2522/108972.jpg)