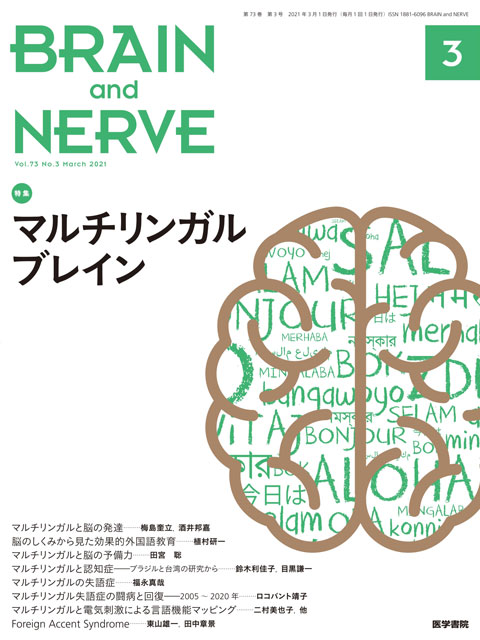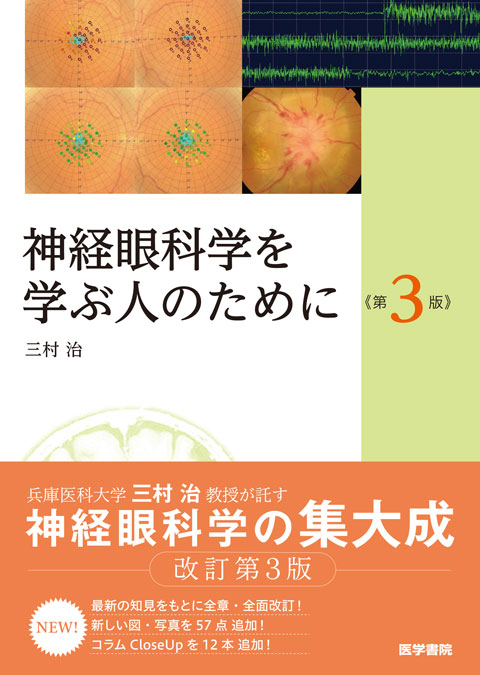MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2021.09.06 週刊医学界新聞(通常号):第3435号より
《評者》 藤田 郁代 国際医療福祉大大学院教授・言語聴覚学
言語を習得する脳の仕組みを多言語使用から解き明かす
言語は人間に固有の機能であり,言語と脳の関係を明らかにすることは,“人間とは何であるか”を知ることにつながる。脳研究の専門誌『BRAIN and NERVE』は人間にとって根源的なこの問いに“マルチリンガル”という画期的な視点から切り込み,研究に新しい窓を開いている。マルチリンガルは複数の言語を使用できることであり,特集では多言語を習得する脳の仕組みおよび脳病変による崩壊と回復について最先端の研究を紹介している。
第二言語の習得は一定の年齢を過ぎると格段に難しくなるが,これは多言語習得にも臨界期があることを意味する。しかし欧州などでは多言語を使用する人が珍しくなく,多言語の習得には何らかの規則性が存在すると予想される。この研究を第一線で推進している梅島奎立氏らは生成文法の「原理とパラメータのアプローチ」とFlynnらの「累積増進モデル」を紹介し,言語習得は普遍文法に基づきながら個別言語のパラメータ値を決定する過程であり,複数の言語の習得には累積効果があることを解説している。またこの神経学的基盤として前頭葉の局所的ネットワーク間の連携の増強に注目しており,全貌の解明が強く期待される。
この特集はマルチリンガルブレインに多角的にアプローチし,二村美也子氏らの電気刺激による脳機能マッピング,植村研一氏の多言語学習法,東山雄一氏らのForeign Accent Syndromeの病巣に関する研究を紹介している。脳機能マッピングでは,多言語使用に関与する脳領域の分布は個人差が大きいことが知られているが,二村氏らは複数の言語に共通する領域と各言語に特異的な領域を見いだすことに成功している。またこの領域分布には言語の習熟度や重要度が関係しており,言語習得理論と照合すると非常に興味深い。
本特集は多言語使用の失語症研究も紹介している。バイリンガルの失語症は多様な症状を呈するが,基本的にはパラレル・パタン(両言語が同程度に障害され並行して回復)と,ノンパラレル・パタン(両言語の症状と回復に顕著な差がある)が存在する。ノンパラレル・パタンの症例を紹介した福永真哉氏とロコバント靖子氏の報告から学ぶことは多い。特にロコバント氏による夫君の失語症経過の詳細な記述は,回復に環境が作用し,回復過程で言語間般化(crosslinguistic generalization)が生じることを実証した貴重な臨床記録となっている。
近年,多言語使用が認知症の発症を遅らせる認知予備能として機能する可能性が検討されている。これは多言語使用では言語の切り替えや抑制などによって遂行機能が高まって脳に機能的・構造的変化が生じるとの仮説に基づくものであり,田宮聡氏はこの研究の重要性と課題を的確に指摘している。また鈴木利佳子氏らは多言語使用が認知予備能になると同時に,言語衰退が妄想などを引き起こす要因にもなり得ることを指摘しており,この問題の奥深さを知ることができる。
グローバル化の進行に伴いマルチリンガル人口は急増しており,言語聴覚療法で多言語使用者に出会うことがまれではなくなってきた。この特集は実に時宜を得たものであり,研究者のみならず言語障害や認知症の治療・ケアに携わる臨床家にも得るところが多いことは疑いないと思われる。
《評者》 近藤 峰生 三重大大学院教授・眼科学
名著『神経眼科学を学ぶ人のために』がバージョンアップ!
日常の眼科診療では,眼球運動障害,視神経萎縮,原因不明の視野欠損など,神経眼科の知識を必要とする患者によく遭遇する。しかしその一方で,神経眼科の分野は少し苦手という眼科医はかなり多い。その理由は,神経眼科の疾患を理解するために眼球運動や瞳孔反応の神経回路や異常メカニズムを理解する必要があるからであろう。しかし,一度これらを理解し,いくつかのコツやパターンさえ身につけてしまえば,神経眼科は実にわかりやすく面白い領域である。その事実に気付かせてくれたのが,本書『神経眼科学を学ぶ人のために』である。これまでも神経眼科専門医の誰もが推薦する名著であったが,今回さらに大幅なバージョンアップがなされ,紙面もカラフルに生まれ変わった第3版が上梓され...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。