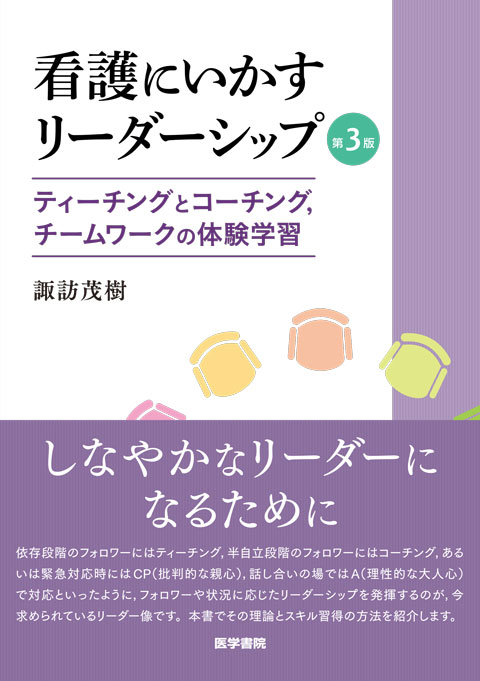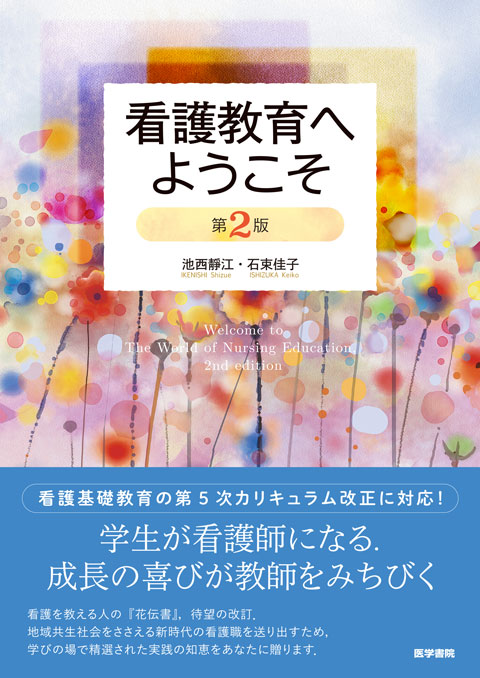MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2021.08.30 週刊医学界新聞(看護号):第3434号より
《評者》 林 千冬 神戸市看護大教授・看護管理学
リーダーシップの理論とスキルを学べる充実した書
2002年の初版から第3版を重ねた諏訪茂樹氏のベストセラーである。170ページ程度のコンパクトな一冊が,「理論編」と「トレーニング編」の2本立てとなっていて,“一冊で2度美味しい”点が本書の大きな特徴である。
前半の「I理論編 これまでのリーダーシップ論の流れ」は,「Question」と「Topics」(コラム的な読み物)を挟みながら,理解が深まる仕掛けとなっている。看護管理学のさまざまなテキストを眺めてみても,これほど原書に忠実に,しかもコンパクトにバランスよく,リーダーシップ論の流れを解説した本はまずないと評者は思う。初心者はもとより,リーダーシップ論を読み込んできたベテランにもお薦めしたい。
社会学を専門とする著者ゆえに,コンパクトにするためには,多くを削ぎ落とさざるを得ない苦労があっただろう。しかしだからこそ,リーダーシップ論の発展過程がストーリーとしてよくのみ込める。リーダーシップは,ピラミッド組織のトップだけではなく,一人ひとりのスタッフに必要であること。そして,それを育み強化していくための方策こそがコーチングだという結論に至り,トレーニング編に移っていく。初版の序で述べられた「自分の意思で自己決定した主体的な行為には,やりがいと責任を伴い,質の高いパフォーマンス(看護)へと結びつく」という著者のメッセージは,版を重ねても一貫している。
「IIトレーニング編 リーダーシップの体験学習」は,誰にでも実践可能な丁寧な手引書となっている。ここには,看護職,介護職をはじめとする対人援助職の間で大好評の,著者の研修のエッセンスが埋め込まれ,これらを用いた1日研修や2日研修の組み方まで説明されている。ここまで懇切丁寧なのも,「(リーダーシップは)受動的な座学だけで身につくものではなく,体験を通して自らが主体的に学ぶアクティブラーニングにより,はじめて手にすることができる」という,今日のようにアクティブラーニングが喧伝されるずっと前からの著者の主張ゆえだろう。
トレーニング編の前半は,「発達対応モデルに基づくトレーニング」で,「指示(積極的ティーチング)」と「助言(消極的ティーチング)」を学び,「支持(コーチング)」に必要な「熱意」「受容」「技法」と続き,最後に「振り返る」「改善する」で終わる。後半は,「場面対応モデルに基づくトレーニング」として,「チームワーク」「会議(カンファレンス)時の関係」「危機対処時の関係」「通常時の関係」を学び,最後は「フォロワーから見た自分を学ぶ」という重要な(でも,なかなかできない)フィードバックで終わる。
「リーダーシップを『目的を実現するために目標を設定し,目標を達成するために個人や集団に影響を及ぼすこと』と定義すると,実は看護行為そのものがリーダーシップである」と著者は言う。その言葉に背中を押されながら,学習に実践に本書を活用していきたい。
《評者》 波多野 文子 広島県看護教員養成講習会専任教員
ベテランから若手に贈る,教育現場の経験知の精粋
かかわることの種類が多過ぎて,どうしたらいいかわからなくなる……。新たに看護教員として着任した人の多くが,いざ仕事始めに当たって漏らす嘆きである。かくいう私もそうだった。授業と実習指導はもちろん,学生相談,教育課程の編成や運営,国家試験対策,学校行事などなど。それらがそれぞれ看護教育にどういう意味があって,教員としてどうかかわっていけばいいのか。30年以上前にさかのぼる私の場合は,業務の合間に先輩のベテラン教員に細かく教えてもらいながら前進することができた。しかし,現代はそうもいかない。働き方改革で「無駄な時間を省く」という職場環境では,ゆっくり話をする機会もなく,聞きたいことがあってもパソコンに向かっている先輩教員には声が掛けにくい。その上,このコロナ禍である。
そんな若い看護教員に初版以来,本書が頼りになる。看護教員として働く上で必要な多くの形式知と,長年,看護教育の第一線で活躍する著者が,その貴重な経験を後輩に伝えるために言語化しようとした試みが第2版でさらに精選され,詰まっている。
例えば「臨地実習の評価」では,患者や実習の場の状況など変数が多く,信頼性を担保した評価がしにくい。そこで著者らはパフォーマンス評価で用いるルーブリックの作成を試みるが,目標分析から入ると看護の実践の全体が見えにくくなるという過去の経験を思い出し,そこから再度学習をし直し,臨地実習で使えるルーブリックの作成方法の提案に至った過程が実際的に記されている。
また,新カリキュラムで提唱されている「臨床判断」や「アクティブラーニング」についても同様である。著者が数々の書物や資料を基に授業を構成して実施し,その結果からさらに工夫を重ねた具体例が,「私案」として紹介さ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。