MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2021.04.05 週刊医学界新聞(通常号):第3415号より
《評者》 片岡 仁美 岡山大病院教授・総合内科・総合診療科
糖尿病診療で「大事なこと」を網羅した本
素晴らしい本である。
こんなに糖尿病診療で「大事なこと」の全てを余すことなく網羅した本が今まであっただろうか。「かゆいところに手が届く」とはまさにその通りである。私がまず感動したのはイントロダクションである。「診療の心構え――治療法を考える,その前に」の一節はこの本の姿勢を表していると同時に,糖尿病診療の真髄だと思う。「糖尿病患者を診る際に大切な3つのこと」は,「最新の正しい医学的知識を持っていること」「患者やスタッフと協働して問題に向き合えること」「コミュニケーションをとる力」という簡潔な表現であるが,まさにその通りである。
糖尿病診療は知識や技術も必要である。マニュアル的にそれを学ぶことは難しくない。しかし,マニュアル通りに行ったとしても患者さんの状態は必ずしも良くならない。なぜだ? そんな話はよく聞く。しかし,そのときに「治療薬のチョイスや,マニュアル的なことは糖尿病診療のごく一部でしかないから」と心の中では思っても,では,どうすれば包括的にその方を良い状態にする助けになれるか,ということはなかなか言語化しにくいという思いもあった。しかし,この本は「言語化しにくいけれど大切なこと」を誠実に言語化し,さまざまな角度からそれを見える化してくれている。私は,糖尿病診療における担当医の役割は,マラソンランナー(患者さん)の伴走者であると思っている。そして,伴走者も一人ではなくチームである。あくまでもランナーである患者さんの走りを支えるとき,考えなければならないことは,その方の一部分だけでは済まないことは明白である。
また,治療と管理の章の前に,第1章として「診療のその前に:患者との出会い」という章があるのが素晴らしい。糖尿病が他の疾患と何が違うのか。「糖尿病は人生を問う」ものであるということ。そのことを明確に示している「糖尿病を抱える患者の心理を理解しよう」はじっくりと読みたい大切な項である。また次の,初診がいかに大事か,という「“健診で引っかかった”を上手に診よう! プレ初診~初診時の対応」も本当に秀逸で,糖尿病診療にかかわる誰もが知っておきたい重要ポイントである。継続外来についても,よくぞここまでと思うくらいに丁寧に,重要な点をわかりやすく伝えてくれている。どの章を読んでも必ずすぐに疑問点が明らかになり,今日からの診療に反映できることばかりである。本書を自身の伴走者として携え,患者さんに向き合うことができたら,糖尿病診療の質が変わると思うし,自身の糖尿病診療から得られる喜びや学びも格段に深くなると確信する。
《評者》 對馬 栄輝 弘前大教授・理学療法学
筋電計を使うとは思えない人にも読んでほしい
1990年代の理学療法に関連する研究では,表面筋電計がよく用いられていた。私も例外ではなく,理学療法士になった初年から研究テーマであった姿勢・動作解析のために,下肢筋の活動を表面筋電計で測定していた。当時は,まだペンレコーダ式の記録方式であり,筋活動を記録したロール状の記録紙を持ち歩き,対象者ごとに筋活動の様相を観察するという地道な作業に随分時間を費やした苦労は今でも鮮明に覚えている。
それほど待つ間もなく,パソコン接続用のアナログデジタル(AD)コンバータが普及し,筋電図をパソコンに取り込んで再現できる時代がやってきた。モニター上に筋電波形が再現され,ロール状の記録紙は,いつしかフロッピーディスクに変わった。いまやUSBメモリの時代だが。
パソコン上で解析できるとなると,見ることがなかった波形処理のメニューがたくさん登場してくる。波形を観察すればよいだけだった次元から,聞いたこともない用語に惑わされて,今度は波形処理の方法に悩まされることになる。当時は書籍も少なく,ましてや表面筋電計を扱ったものがほとんど見当たらず,養成校の先生にしつこく伺いながら,手さぐりで少しずつ問題をクリアしていくほかなかった。
もしそんなときに,この本があったら……と思わせられた良書が見つかった。しかも理学療法の視点から書かれている,表面筋電図と動作分析手法の書籍である。この本があったら,面倒な理論に悩まされることなく,もっと早く研究が進んだに違いない。また,理解が深まって研究成果を臨床での理学療法に応用できたに違いないと思わせられるほどだ。
本書は,表面筋電図に必要な基礎知識,筋電図を用いた計測,筋電図の見かた・最大随意筋収縮計測の方法,動作計測,データの解析方法,臨床における計測の実際まで,幅広く,しかもカラーで平易に,しかし手抜きすることなく説明が盛り込まれている。しかも,付録にはWeb動画まで付いている。この手の原稿では悪いことは書けない。しかし,悪いことが見つからなかった……。
筋電計は筋肉の活動を記録し,視覚的に確認できる唯一の測定法である。今では3次元動作解析装置も普及しているが,それとは違って姿勢保持・動作中の筋の活動を観察できる。動作と同時に筋電図を見ると,実に巧妙な筋同士の活動様式が観察できる。理学療法士であれば,これが非常に興味深い。まだ見たこともない人は,ぜひ臨床での測定に活用してほしい。今では,数万円で購入できる筋電計もあり,臨床現場でも難なく購入できて普及する日が来ると思う。その時になってから「もっと先に勉強しておけばよかった」と思っても遅い。初めて学ぶ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

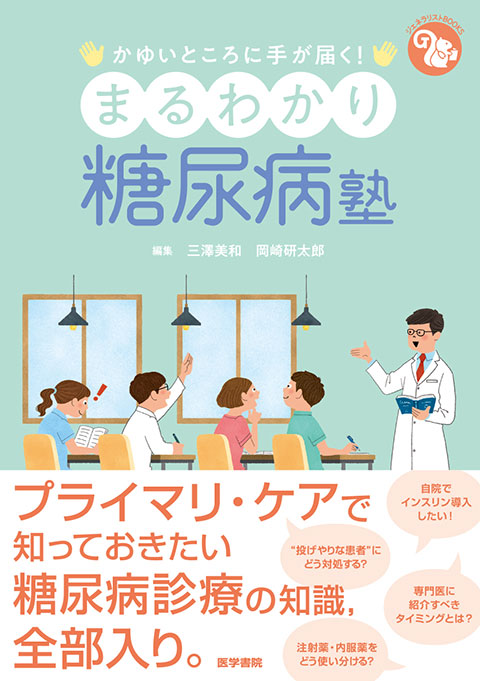
![臨床にいかす表面筋電図[Web動画付] セラピストのための動作分析手法](/application/files/6516/0679/0656/107181.jpg)