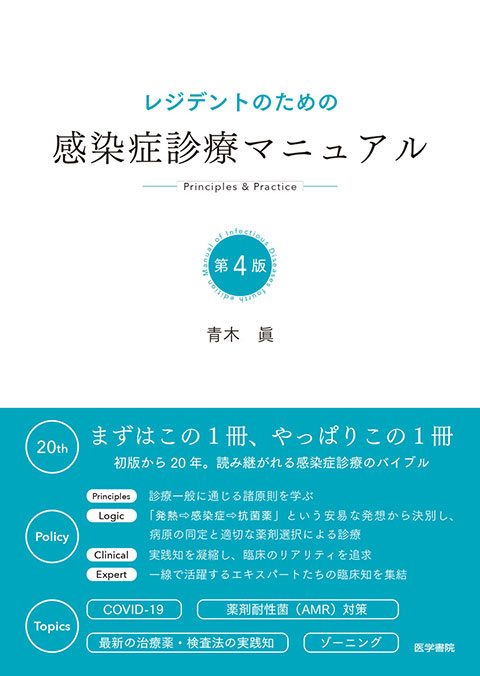臨床感染症2000~2021
変わったこと・変わらないこと
『medicina』誌58巻5号より
対談・座談会 青木 眞,上原 由紀,岡本 耕
2021.03.29 週刊医学界新聞(通常号):第3414号より
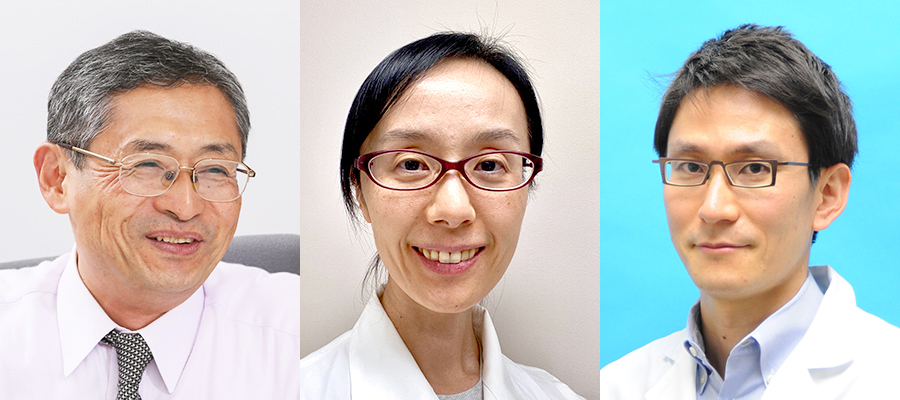
感染症診療のバイブルともいえる『レジデントのための感染症診療マニュアル』(医学書院)の初版発行から20年ほどが経過し,感染症診療を取り巻く環境は大きく変化した。日本の感染症診療の発展を支えてきた医師たちはこの変化をどのように感じているのか。『medicina』誌では,同書著者の青木氏をはじめ3人の医師が感染症教育の変化と今後見込まれる改善・成長の余地について語り合う座談会を企画。本紙では,その内容をダイジェストでお伝えする(座談会全文は『medicina』誌58巻5号に掲載)。
総合診療マインドの重要性
青木 感染症診療は,総合診療の中に取り込まれると健康な姿を見せます。最近,ある番組で「これからいろいろなパンデミックが来るはずだけれども,それに対する備えとして,日本に一番必要なのは何だと思いますか」と聞かれて,僕はそれは「総合診療マインドである」と答えたのです。
コロナも,血液凝固の問題から若者の脳血管障害で表現されたり,急性腎障害が出てきたり,糖尿病になったり,子どもだったら川崎病みたいになったりします。今後,どんな微生物によるどんな臨床像を呈するパンデミックが起こるかわかりませんが,普段からある程度全身のunknownを扱い慣れている総合診療とか,プライマリ・ケアの人たちの層を厚くすることが,とても重要だと思っています。
そういう意味でも感染症診療が,感染症診療だけを発達させるのではなくて,日本に一番必要とされる総合診療マインドを持ったホスピタリストとか,プライマリ・ケア,在宅の先生たちを増やすドライバーになってくれたらいいですね。その意味では,総合診療マインドを広げる,1つのいいきっかけとして感染症科が役立つといいなと思います。
上原 未知のものを扱うというのはとても大変なことですよね。10年ほど総合診療科に在籍していましたが,ちゃんとトレーニングもしないままに持てる知恵をすべて振り絞って外来をしていたので大変でした。でも振り返ってみると,on the job trainingで幅広い診かたを身につけることができました。
感染症科の外来をしていても,感染症ではない方が感染症科に紹介されて,診る機会があります。感染症である確率は5割程で,それ以外は試行錯誤しながら道筋をつけることも多かったりして,やっぱり感染症診療と総合診療は親和性が高いと思いますし,感染症のことだけやっているのは,危ういことかもしれません。
岡本 感染症診療では病因で捉えて臓器横断的に診るのが本質ですし,複数の臓器で問題が起きたときに,総合診療的マインドがあるといろいろな角度からアプローチしやすいですね。それに,上原先生が言われたように,感染症じゃないことがしばしばあるけれども,いろいろな科で「うちじゃありません」と言われて,気づいたら私だけがフォローしているようなこともあって(笑)。
上原 「うちじゃない科」ですね。
岡本 そうなんです。そういったときに,自分なりに頭をひねって,何だろうと考える。実際,感染症科だったり,感染症医が,感染症だけじゃなくて総合診療的なマインドを伝える役割を担っているというのは重要な部分じゃないかと思います。
青木 感染症マインドが総合診療マインドのドライバーになる,総合診療の追い風になる面があると同時に,逆のベクトルもあると思うんです。総合診療マインドというのは,その人の家族がどうなのか,社会的・公衆衛生的にどんな広がりがある病気なのかというところにも感受性がありますね。
「国家全体で使用可能なPCRの量がこれくらいしかないときに疫学,公衆衛生的に,どういった集団にどのように使ったら最も多くの生命を守れるのか?」といった視点が大事です。総合診療マインドが与える,疫学的な問題の広がりや経済的な問題を見ながら大きな視点からどうアプローチしていくべきかを教えてもらうという,逆のベクトルも大事であり,それに対する謙虚さみたいなものが,臨床医や微生物学者の感染症マインドに必要だと思うのです。
そして,それを上手にコーディネーションしてくれるような人がこの国にはもっと必要だと思うんですね。そういう意味では,微生物,臨床,公衆衛生と,全体像を把握する公衆衛生的な感染症領域の人が,もっと必要だということも,今回のコロナでわかった気がします。
変わらない価値
青木 ぜんぜんよけいな話をしていいですか。すごくこの国の感染症に大事な,歴史的なことなので。
岡本 どうぞ,どうぞ。
青木 沖縄県立中部病院の喜舎場朝和先生は,41年前に僕をしごいていた先生ですが,その喜舎場先生は感染症フェロー時代にRaffというLouisville大学の教授に師事しました。Raff教授は,朝鮮戦争時に軍医として日本に駐屯した経験があり,大の日本ファンでした。彼は米国の感染症の教授にしては珍しく,病歴や身体所見を非常に大事にするOld Schoolだったんです。ニュアンスとしては,南部に住むユダヤ人医師的な感じでSapiraに似ています。そんな教授に日本人フェロー第1号として師事して,彼はそれを日本に持って帰ってきたわけです。
日本人は,デジタルが好きではあるけど,一方で名人芸的なものが非常に好きじゃないですか。一種名人芸的な世界を大事にする日本の人に,喜舎場先生のカラーがマッチしたと思うんですよね。ですから,上原先生や岡本先生が,グラム染色を愛してくれる背景には極めて日本的な要素があるんですよね。米国では,ちょっと望めない。
だから,そういう意味で喜舎場先生がLouisville大学に行ったというのは,非常に僥倖だったというか,そのあと僕もそこで喜舎場先生に教わって,そのあと岩田健太郎先生や本郷偉元先生といった方がそれに触れたのは,よかったなぁと思うんですよね。このテクノロジーの時代に,今も沖縄県立中部病院に脈々と流れる喜舎場イズムというのは,精密な病歴とか身体所見を大切にするんです。
今後もいろいろなテクノロジーが出てきて,あるものは廃れ,あるものは残るでしょう。その中で「何を大切にして,何を基軸にして」残す,残さないを決めるのか・・これが大事です。
なので,これから日本の感染症をどちらのほうに進めていくのかというときに,(最近の米国の市中肺炎のガイドラインのように),本当に「血培なし,グラム染色なし」で良いのかをよく考える必要があります。単純に生死といったハードアウトカムだけを見てガイドラインを作るのではなく,それを見て育った研修医たちがどんな感染症診療をするようになるのか,どのような臨床医として成長していくのか,そういったことに注目し続けることが,すごく大事だと思うんです。
ある意味,岡本先生たちはこれから日本の感染症がキャピタリズムに引っ張られていくかどうか,というcriticalな時代におられると思うんです。先生たちは,アジアや日本人独特のマインドを維持しつつ,いいところは取り入れ,ネガティブなところは排除していく。そういった明晰な能力を持っていると思うので,峻別しながら日本のこれからの感染症を育てていってくれるといいなと思いますね。
上原 米国が全面的によいという雰囲気がある中で,実は日本にもいいところがあるというのは,すごく励まされるお話ですね。私は普段,グラム染色と血液培養は,いくらやっても怒らないと研修医には言っているんです。アナログのよいところといいますか,もちろん米国のよいところも学びつつ,日本のよいところを残すというのは非常に大事だなと思ってお話を伺っておりました。
岡本 本当にそうですね。喜舎場先生のLouisville大学から連綿と続く流れは止まらないでしょうし,皆が,それが当たり前であることすら気づかなくなっていくように思います。
変わらない価値があるというか,忘れてはいけないところがある。それを学生さんや研修医の先生に伝えていくことがより重要になっていくと思います。指導医が提供できる大事なことの1つは,変わらない原則を伝えていくことなのかなと思いました。
(抜粋部分終わり)
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。