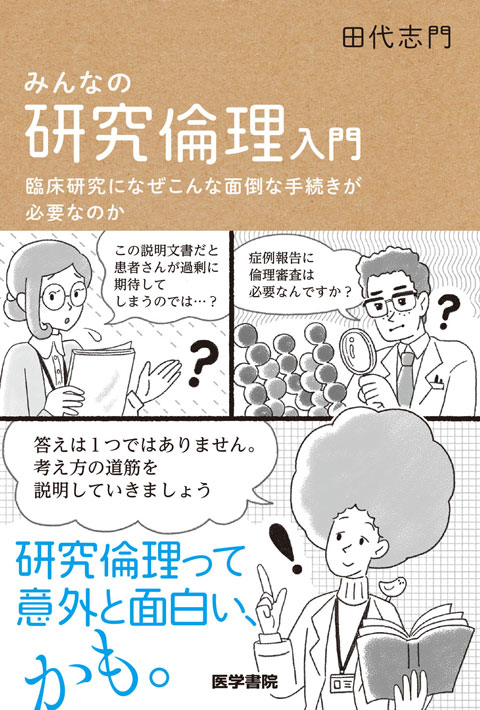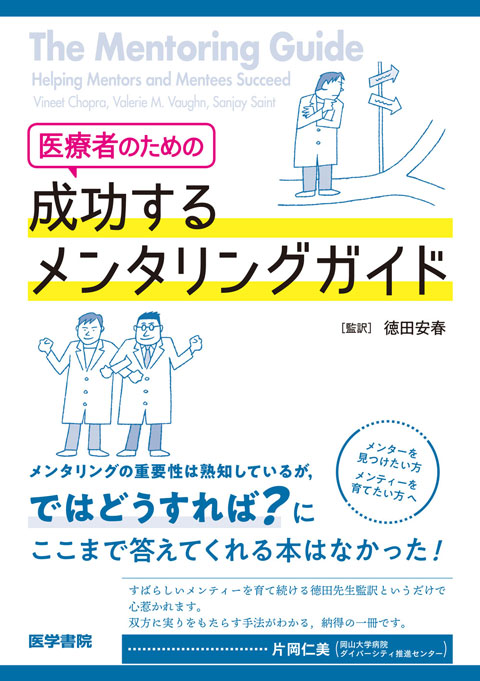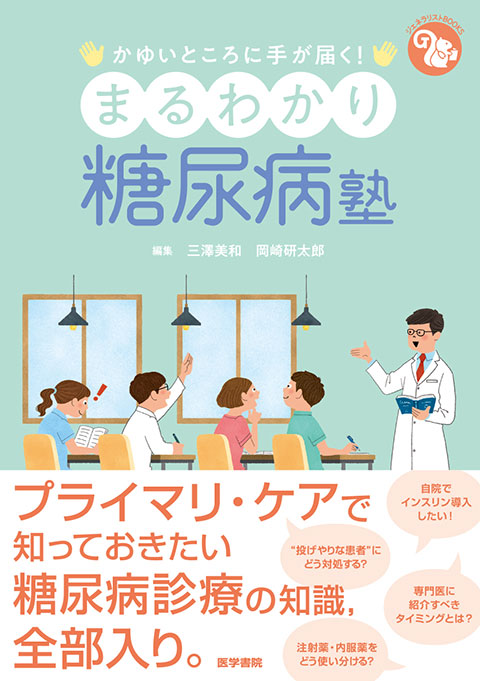MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2021.02.01 週刊医学界新聞(通常号):第3406号より
《評者》 森田 達也 聖隷三方原病院副院長・緩和支持治療科
チェックリストに答えはない,楽しい研究倫理の唯一無二の本
「あいつ,かしこいですよ~」「スマートですよねぇ……はあっ♡てなります」「なんか癒やされる~」「ビッケに似てる!!」……僕の周りの,著者(田代志門)に対する評判である。ビッケというのはスウェーデンのアニメの主人公で,見た感じもなんとなく似ているが,「行く先々で降りかかる困難を知恵と勇気で見事に乗り越えていく」というキャラ設定も重なりそうだ。こうあるべき! から少し離して,「それって,こういうことじゃないですかね?」とさわやかに整理してくれるのは,社会学者という専門性と性格があいまってなせるわざだろう。
さて,本書,細かいルールはちょこちょこ変わるので,背景にある大きな考え方を共有したい,という著者のポリシーに貫かれた1冊である。どこをどう読んでも,自分の研究,臨床と研究の曖昧なところの悩みの背景にある大きな概念が浮かんできて,ああそうだったのか,と気付く。
著者の関心領域である,診療と研究の境目にある診療を研究とみなすべきかについて論じた前半部分は圧巻である。行為を,手段として確立している/いない×目的が患者にベストなことをする/一般化できる知識を得る,の4区分に分け,診療と研究の別を明確にしていく。そして,「手段として確立していないが目的が患者にベストなことをする行為」に対して,著者は,あえて1つの正解を持ってこない。臨床として扱う,研究として扱う,独自の第3のカテゴリーとして扱うべきとの意見がある,とまとめてくれている。そうなのか――専門家の間でも唯一解があるわけでもないのか!
患者が研究を理解する点について語る中盤部分では,何を患者は理解するべきかという点から,「研究は自分のためにベストなものを見つけてくれたものである」という“治療との誤解”と,「効果を希望を持ってちょっと(より多く)見積もっている」という“治療の誤評価”とに分けて説明する。そして,後者については,ある程度の幅で患者の誤解は許容されるという立場もあるといってくれる――幅があるっていいなぁ……。
後半の研究の社会的価値に関する検討でも,真理追究の学問(天文学)を対比させることで,医学研究は有用性の学問としての価値に意識せずに基づいていることを気付かせてくれる。そこで,社会的価値が不足しているから研究として認めないとする立場の是非を,「基本的な価値観をめぐる対立でもありますし,そう簡単に合意できない部分」と言い切る――うんうん,価値は一つに決めないほうが生きやすいよね!
「議論の最前線に行けば行くほど百花繚乱で,そうそう一致した見解があるわけではない」――本当にその通りで,「何とか研究のチェックリスト」に○をつけるのは楽しくないが,自分で考える楽しさ,自分でルールをつくることの楽しさを感じられる本だと思う。研究者はもとより,臨床と研究の間で,「何とかチェックリスト」ではない本質的な課題を楽しみながら考えてみたい読者,おでんの具よりも“だし”に目がいく人にお薦めです。
《評者》 青島 周一 医療法人社団徳仁会中野病院薬局
関係性の内で垣間見る学びの姿
僕は書店が好きだ。書棚にずらりと並ぶ本の背表紙を眺めているだけで,新しい世界との出合いの予感に胸が躍る。装丁に惹かれた書籍を実際に手に取って,ゆっくりとページをめくってみると,紙面に並ぶ言葉たちを通じて自分の知らない景色を垣間見ることができる。手に伝わってくる本の重量は,それが大きなものであれ,小さなものであれ,重さを超えた概念の質量を宿している。
一冊の本との出合いは,物の見方や考え方を大きく変えることがある。その変化の過程に能動性,あるいは主体性というような意識や感覚はなく,ただ自分と本との関係性だけが世界を編み変えていく。このような経験こそが質の高い学びを駆動する一つのきっかけなのかもしれない。
誰かから「勉強しなさい」と言われても,必ずしも主体的に勉強をするようになるわけではない。もちろん,それがきっかけで継続的な学びにつながることもある。しかし他方で,誰に言われるでもなく無我夢中で勉強してしまうこともあるだろう。能動的あるいは主体的な学びと言ったとき,それは学習者の意志の強さというよりはむしろ,学びを欲することに対する自身の応答なのかもしれない。少なくとも,主体的な学びは指導者の一方的な教えの中にあるのではなく,指導者と学習者の関係性の内にあるように思える。
本書は人材育成指導法の一つであるメンタリングについて,医療者に向けて書かれた実践書である。メンターは指導する(能動的な)立場,メンティーは指導される(受動的な)立場というイメージが一般的かもしれない。しかし,メンタリングの具体的な方法論についてあらためて考えたとき,その行為が能動/受動という概念では収まりきらないことに気付く。学びは指導者と学習者の関係性なしでは成り立ちようがないからだ。だからこそ,メンタリングの大切さを理解していたとしても,自分がどうあるべきなのか,あるいは具体的にどのような仕方でメンタリングを行えばよいのか,当惑してしまうことも少なくない。
メンターとして,そしてメンティーとして,双方がどのような仕方で関係性を構築し,またその関係性の中で何を学び,成長の糧としていけば良いのか,本書はメンタリングの具体的なフレームワークを論じている。数々の実践可能なアドバイスは,メンタリングを円滑に進める上で有益な指針となってくれるだろう。さらに,巻末には豊富な参考文献や図書の紹介が収載されており,メンタリングのアウトカムが実り豊かになることを必ずや助けてくれるはずだ。
《評者》 岩岡 秀明 船橋市立医療センター代謝内科部長
深い感銘と少々の嫉妬すら覚える,タイトル通りの良書
正直に書きます。この本を読み終わった私は,深い感銘とともに,糖尿病に関する本も出版させていただいている末席の一人として少々嫉妬も覚えました。
本書は,編著者のお一人三澤美和先生が「まえがき」に書かれている通り,以下の4つを全て満たした本です。
・明日から現場で使える情報,ツールにこだわった実践的な内容
・患者さんや家族の心理社会的背景を知るためのノウハウがつまった内容
・糖尿病専門医とプライマリ・ケア医をつなぐ,架け橋になるような内容
・糖尿病と生きる患者さん,そのご家族が手にとってくださることがあっても理解が深まるような内容
糖尿病に関する本は,医学専門書店にも一般書店にも数多く並んでいますが,これら4つ全てを満たしている本は,今までなかったように思います。
これは,家庭医療専門医と糖尿病専門医の両方を取得されている三澤先生と地域医療教育学の専門家岡崎研太郎先生のお二人が編著者だからこそ可能だった本といえるでしょう。執筆陣も,糖尿病専門医と家庭医療専門医がバランスよく分担して書かれていますし,もちろん薬剤師・訪問看護師・管理栄養士の方々も執筆されています。
目次を見ていただければわかりますが,本書は「診療の心構え―治療法を考える,その前に」,「診療のその前に:患者との出会い」から始まっています。この2項目はとても重要です。
「継続外来“...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。