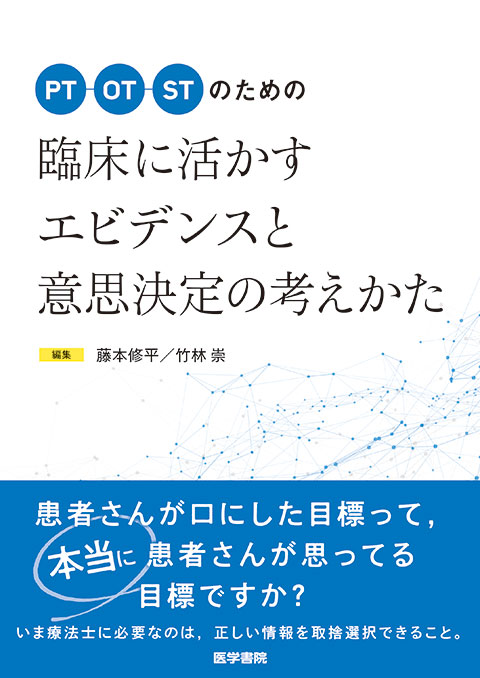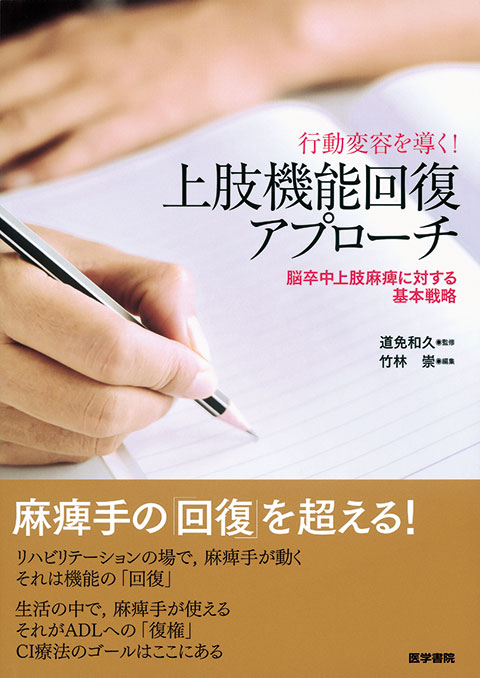療法士の臨床を変える「情報の取捨選択」
対談・座談会 藤本 修平,竹林 崇,尾川 達也
2021.02.01 週刊医学界新聞(通常号):第3406号より
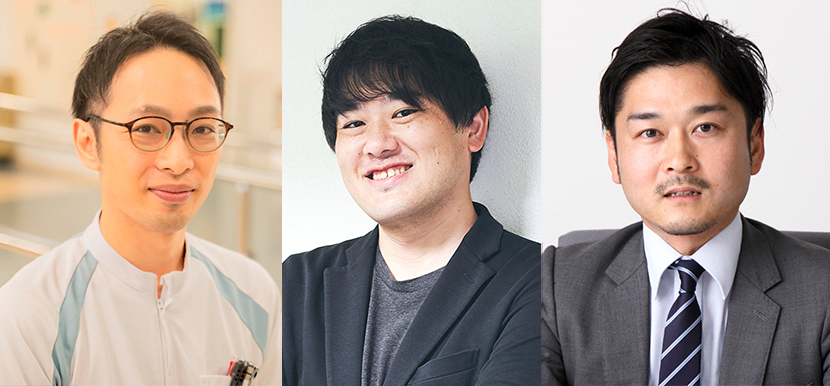
「療法士の中で適切に情報を取捨選択できていると自信を持って言い切れる方はどれほどいるでしょうか」。座談会の冒頭でこう問い掛けたのは,ヘルスコミュニケーションの研究者であり,同テーマで多数の講演会を行う理学療法士の藤本氏。不確実性の高い医療の中で,療法士に求められるスキルとは一体何か。本座談会では藤本氏のほか,『PT/OT/STのための臨床に活かすエビデンスと意思決定の考えかた』(医学書院)を共に編集し大学で教育にも携わる作業療法士の竹林氏,臨床現場で理学療法士として勤務する尾川氏を迎えて議論を交わした。
藤本 最近「療法士の専門性とは何だろう」と思いを巡らすことがあります。「理学療法士及び作業療法士法」では,理学療法は基本的動作能力の回復をめざした技術を提供することと述べられているものの,近年著しく発展するAI技術やロボット技術を用いたほうが高いパフォーマンスを発揮したとの発表を耳にすることが増えてきたからです。
竹林 同感です。そもそもわれわれ療法士がこれまで提供してきた「技術」とは一体何なのでしょうか。
藤本 理学療法・作業療法・言語聴覚療法と,それらに必要な評価のことを指して用いられるケースが多いと思われます。近年ではようやくその中にコミュニケーション技術が含まれるようになってきました。
ただし,ここで用いるコミュニケーション技術とは,単にクレームを受けないために接遇をよくするといったスキルにとどまらず,治療方針等について患者さんと意思決定を共有し,協働していくための高い次元での対話をも包含したスキルのことを指します。こうした高いレベルのコミュニケーション技術を身につけるためには,土台としての「情報」を適切に取捨選択する能力が必要だと私は考えています。
そこで今回の座談会では,その理由の紹介とともに,「情報」というキーワードを軸にして,これからの療法士が身につけておきたいスキルを考えたいと思います。
情報の真の重要性に必ずしも気付けない現状がある
藤本 「情報」という言葉にはさまざまな定義がなされています。医療の文脈における定義としては,世界的に著名な科学者であるクロード・シャノン氏の言葉を借りれば,「不確実性を減じるもの」と表現するのが適切でしょうか。昨今はインターネットが日常に浸透したことで,玉石混交の情報が溢れています。
竹林 2015~17年頃にかけて,医療系メディアによるフェイク記事が批判に晒されたことは記憶に新しいですよね。批判の対象となった記事の中には誰しもがうそと見抜ける情報から,一見真実と錯覚してしまう情報まで含まれていました。
藤本 そうでしたね。もちろん,記事内容を正確に把握していなかったメディアの責任は大きいと言えます。しかし,そもそも不確実性の高い医療の中で,ある程度の根拠を持った情報を用意できる方はどれだけいるのでしょうか。恐らくそう多くはありません。つまり,こと医療に関しては,情報を取捨選択する義務が情報の受け手側にも生じ得るのです。
われわれ療法士に限定してこの問題を考えてみます。療法士の中で適切に情報を取捨選択できていると自信を持って言い切れる方はどれほどいるでしょうか。恐らくこちらも該当者は少ないでしょう。なぜなら,卒前卒後教育ではそうした能力について教授されることはほとんどなく,いわゆる治療・評価の技術に関する教育に終始してしまうためです。
お二人は卒前卒後教育の現状をよくご存じだと思います。まずは竹林先生から卒前教育の状況を共有していただけますか。
竹林 情報の吟味をしなければならない,データを鵜呑みにしてはならないといった話は,主に公衆衛生学の講義で行われます。しかし,同講義は養成校によっては選択必修の科目であり,単位を取得しなくとも卒業できてしまいます。加えて,講義の内容に関しては教員の意識および認識に依存しているのが現状です。
また実習においても同様であり,担当となるスーパーバイザーのモチベーションによって,情報をどこまで吟味して臨床に活かすか,という指導のレベルにはバラつきがあります。属人的な部分が大きい点は課題ですね。
藤本 なるほど。では実際,そうした教育体制を経て療法士となった場合,どのような思考に至るのでしょうか。現在,臨床現場で活躍する入職12年目の尾川先生の経験から,卒後教育の現状を伺えますか。
尾川 大学院へ進学し研究手法等を学んできた今でこそ,情報を吟味する重要性を理解し始めたつもりですが,入職してすぐの頃は情報の取捨選択を意識したことはなく,ただ純粋に先輩の意見が全て正しいと思って勤務していました。右も左もわからない入職初期の段階であれば,誰しもがこのような状況だと思います。
藤本 療法士においては臨床能力の向上を目的とした新人教育プログラムはあるものの,医師や看護師のように系統立てられた研修制度がないために,卒後は各施設の環境に任されてしまっていますよね。そんな状況の中で,なぜ情報の取捨選択が必要だと気付けたのですか。
尾川 入職1年目の秋に学会発表用のスライドを作成していた際,違和感を覚えたことがきっかけです。「間違った内容を発表したら批判されるかもしれない」との不安から,発表内容に関連する学術論文を渉猟していました。すると,間違ってはいないけれども情報が不足していたり,過大な表現になっていたりなど,参考書の内容と学術論文の内容に一部乖離があることに気付いたのです。自分に見えている世界が全てではないことにハッとしました。
情報の取捨選択能力の先に見える「意思決定の共有」
藤本 入職1年目で情報を俯瞰的にとらえる感覚を得られたのは貴重な経験でしたね。ただ,尾川先生のように早い段階で多角的に分析できるようになる方はまれだと思います。特に療法士の中には主体的体験の価値が高く,その経験に依存しやすい方が多い印象です。情報を客観視できないと臨床現場ではどのような問題が生まれるリスクがあるのでしょうか。
尾川 療法士の興味関心...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
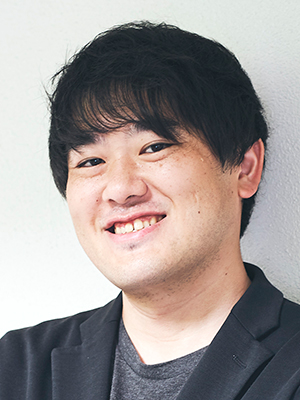
藤本 修平(ふじもと・しゅうへい)氏 株式会社まぁてぃヘルスケア代表取締役
2009年弘前大医学部保健学科理学療法学専攻卒。理学療法士として約7年間の病院勤務後,株式会社メドレーなどのヘルスケア企業,総合商社グループで新規事業のマネージャー職を歴任。19年京大大学院でPh. D(Public Health)を取得。20年より現職。編著に『PT/OT/STのための臨床に活かすエビデンスと意思決定の考えかた』(医学書院)。

竹林 崇(たけばやし・たかし)氏 大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーション学類作業療法学専攻 教授
2003年川崎医療福祉大医療技術学部卒。同年より兵庫医大病院リハビリテーション部に勤務。18年兵庫医大大学院修了。博士(医学)。吉備国際大准教授,大阪府立大准教授を経て,20年より現職。編著に『行動変容を導く! 上肢機能回復アプローチ』『PT/OT/STのための臨床に活かすエビデンスと意思決定の考えかた』(いずれも医学書院)など。
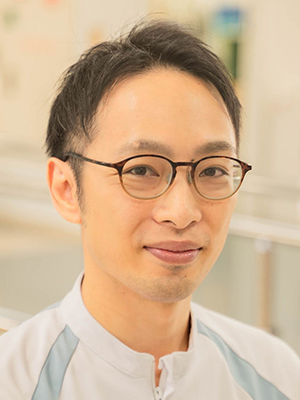
尾川 達也(おがわ・たつや)氏 西大和リハビリテーション病院リハビリテーション部 主任
2009年畿央大健康科学部理学療法学科卒業後,西大和リハビリテーション病院へ入職。15年畿央大大学院修士課程修了。現在も同大大学院博士課程に在籍しながら臨床現場で勤務に励む。リハビリテーション医療における目標設定やShared Decision Makingに関する研究論文を執筆。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。