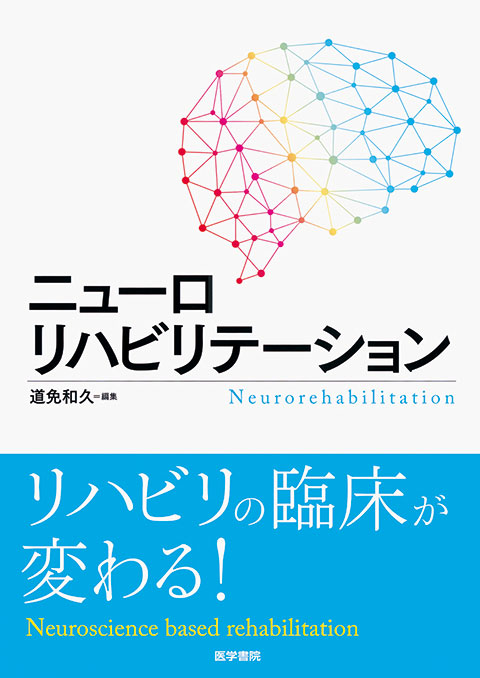行動変容を導く!
上肢機能回復アプローチ
脳卒中上肢麻痺に対する基本戦略
日常生活で麻痺手が使える! CI療法が変える!
もっと見る
脳卒中後の麻痺手の回復は難しいものと従来は考えられていたが、2000年代に入りCI療法が台頭してからは、麻痺手を実生活で使用することは当たり前のことになりつつある。本書は、CI療法を中心に、ニューロサイエンス、行動心理学といった、対象者の行動変容を導く戦略の根幹となる学問をベースとした上肢機能回復アプローチについて、その学術的背景、基礎知識、メカニズムやコンセプト、実際の治療法を凝縮した内容となっている。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
監修の序(道免和久)/序(竹林 崇)
監修の序
本書は脳卒中片麻痺を呈した上肢の機能回復に焦点を絞ったリハビリテーション医学の実践書であるとともに,リハビリテーションアプローチ全般に通じる本質的コンセプトを鋭く考察した書籍でもある.したがって,書名にはあえてCI療法(constraint-induced movement therapy)やニューロリハビリテーションという言葉は入れていない.将来的に本書で示したコンセプトがリハビリテーション全般に広がることを期待している.
私は,2008年に『CI療法-脳卒中リハビリテーションの新たなアプローチ』(中山書店)を,2015年に『ニューロリハビリテーション』(医学書院)を上梓し,CI療法を中心としたニューロリハビリテーションについて啓発を行ってきた.多くのリハビリテーション科医師,療法士だけでなく,脳神経外科や神経内科の医師,あるいは当事者の方々からも多くの反響をいただいた.そのなかで,兵庫医科大学リハビリテーション医学教室主催によるセミナーや実地研修を受けるのが理想であることはわかるが,書籍の形で具体的な方法論が詳しくわかるものが欲しいといった声も多数寄せられていた.そこで本書は,これまでに執筆しきれなかった具体的なアプローチの方法を詳細に記述するとともに,課題指向型アプローチと運動学習の転移について詳しく解説している.
CI療法をはじめとする運動療法と運動学習との関連については,拙著『ニューロリハビリテーション』でも述べている通り,教師あり学習,強化学習,教師なし学習のいずれもがCI療法と密接に関連している.そして,運動学習則を使いこなす能力,メタ学習も重要であることが推察されている.したがって,CI療法は「運動学習療法」と言い換えることができ,CI療法の諸要素を運動学習の文脈で考察しながら,日々研究を推進している.さらに,本書の主題である課題指向型アプローチや運動学習の転移は,運動学習理論をCI療法の臨床実践においてとことん突き詰め,無駄を削ぎ落とした結果,浮き彫りになった最も本質的なキーコンセプトである.したがって,その本質を理解しさえすれば,上肢のリハビリテーションに限らず,歩行や高次脳機能障害といった問題にもそのまま応用が可能と考えている.
私が,1990年代にSteven L. Wolf教授から,日本でCI療法を普及させてはどうかという提案をいただいてから20年以上になる.兵庫医科大学リハビリテーション医学教室に異動し,2002年ごろから予備的研究を始め,当時の作業療法副主任であった佐野恭子氏(現 兵庫医療大学)の協力を得て,CI療法を国内に送り出した.その頃入職した竹林 崇氏(現 吉備国際大学)は一貫してCI療法を現場の中心として実践し,数々のリサーチや講習会の講師も務めてきた.まさに本書の編集者として適任であり,期待通りの内容に仕上がっている.他にも兵庫医科大学病院リハビリテーション部作業療法部門や共同研究者など,項目ごとに最適な執筆者によりまとまった内容となっている.理論やその他のニューロリハビリテーションについては,上述の拙著も併せて参考にしていただきたい.
歴史的には,この20~30年のリハビリテーション医学・医療の大きな議論の流れとして,治療的アプローチによる機能障害の回復か,代償的アプローチによる日常生活活動の改善か,といった二元論的議論が続いてきた.そして今,再生医療を含むニューロリハビリテーションの時代にあって,麻痺を治すという治療的なリハビリテーションの時代が到来した,という考えかたもできる.しかし,本書で示したコンセプトは,単に麻痺を回復させる治療法という二元論的理解を超えて,機能障害を課題指向的に改善させ,改善した機能障害を日常生活活動につなげる(転移させる)という新たなアプローチの考えかたである.それによって習得した活動が患者さん自身が選んだものであればQOLにも直結するであろう.さらに,QOLに直結した活動(利き手で箸で食べる,ゴルフをする,など)は,おそらく日常的に継続されることが予想される.結果として,活動が機能障害の改善を促進し,加えて病理学的・解剖学的な部分での改善につながる可能性も示されている(錐体路線維の増加,神経新生の促進,など).これを私は,リハビリテーション医学・医療におけるパラダイムシフトと呼んでいる.
本書はまさにパラダイムシフトにつながるアプローチを最初に解説した書籍として上梓されるに至った.執筆者諸氏,兵庫医科大学病院リハビリテーション部スタッフ,兵庫医科大学リハビリテーション医学教室医師,秘書などすべての協力者に深謝する.
2017年9月
監修 道免和久
序
筆者は作業療法学科の学生であった2002年当時,脳卒中後の上肢運動麻痺が対象者の方々に与える心理・機能的な障害を臨床実習先の現場でまざまざと感じ,その失われた機能を「回復」させることこそが作業療法士に託された仕事のひとつではないかと感じ,そのための手法を確立する必要性を強く感じた.しかし,当時の世の中の常識は,発症後180日を過ぎた上肢運動麻痺は改善することがなく,残存機能を活かした代償的な手段を用いて,日常生活活動をはじめとした対象者の生活を自立させるリハビリテーションが主流であった.ただ,そのなかにあって,2000年代に入り,課題指向型アプローチの代表格であるconstraint-induced movement therapy(CI療法)が台頭し,世の中の常識にも少しずつ変化の兆しが見え始めた.
卒業後,運良く就職させていただいた兵庫医科大学では,リハビリテーション医学教室の道免和久主任教授が先頭に立ち,先進的な医療を積極的に採用していた.その1つのプロジェクトとして,他大学に先駆けてCI療法を導入し,臨床応用を実施していたのである.限られた先行研究の資料を片手に,対象者の麻痺手の機能改善を目的に日々試行錯誤を繰り返すわれわれにとっての1度目の転機が2006年に訪れる.本書の執筆者のひとりでもある花田恵介氏がCI療法の開発元でもあるUniversity of Alabama at Birmingham(UAB)のDavid Morris准教授(当時.現在は教授),Edward Taub教授が共著で書かれた“Constraint-induced movement therapy:characterizing the intervention protocol.”(Eura Medicophys 42:257-268, 2006)を抄読し,CI療法の重要なコンポーネントの1つであり,練習効果を生活に転移させるための方略である「Transfer package」の知見をわれわれにもたらしてくれたのである.そこで,このコンポーネントを取り入れたところ,アプローチ後の結果がより良好なものに変わることとなった.また,このアプローチによって,麻痺手が「動く」という機能「回復」としての概念よりも,リハビリテーションそのものの概念である「麻痺手を実生活で使用すること」,すなわち「復権」という概念こそが適当なものだと感じた瞬間でもあった.
2度目の転機は2012年にUABのCI therapy training courseに参加した際に訪れた.本書の執筆者のひとりである高橋香代子氏と一緒に参加し,現場の技術を吸収することができた.この参加期間中に,自身の論文“A 6-month follow-up after constraint-induced movement therapy with and without transfer package for patients with hemiparesis after stroke:a pilot quasi-randomized controlled trial.”(Clin Rehabil 27:418-426, 2013)が掲載されたこともあり,現地の開発者たちとアカデミックなディスカッションを経験できた.また,この際に譲り受けた大量の資料をもとに,先述の花田氏に加え,同じく本書の執筆者である橋本幸久氏,梅地篤史氏,天野暁氏,打田明氏,大谷愛氏,彼ら以外にも,陰ながらたゆみのない援助をしてくれた佐東健氏をはじめとした作業療法士がブラッシュアップに尽力してくれたことで,現在の兵庫医科大学のCI療法が形作られたと言っても過言ではない.さらには,麻痺手の使用行動をより促進するためのアプリ「Aid for Decision-making in Occupational Choice for hand(ADOC)」の開発の誘いをいただいた同じく本書執筆者友利幸之介氏には心から御礼を述べたい.また,何よりもわれわれのさまざまな試みを常におおらかに包むようにご援助・ご指導いただいた道免教授と,ご支援をいただいた兵庫医科大学リハビリテーション医学教室の医師の皆様には感謝の念しかない.そして,さまざまな取り組みに付き合っていただき,われわれに新しい知識の提供や成長の機会を与えてくださった歴代の対象者の方々にも深謝したい.
このような経緯により形作られたわれわれのアプローチは,従来法では大きな壁と認識されていた「リハビリテーション室の外における麻痺手の使用行動」に対して確かな影響を与えることが確認されている.本書では,本アプローチと効果判定に用いる機能評価について,6章に分けてそれぞれ詳細に記載している.第1章では,課題指向型アプローチとTransfer packageを含むCI療法の効果とエビデンスについて記している.第2章,第3章では課題指向型アプローチとTransfer packageの概要と実施を,第4章ではその効果を計測するアウトカムについてまとめているが,これは第5章の症例報告へと連なっている.第6章でも実際に使用する課題について触れている.
兵庫医科大学での13年間にわたって発展してきた「行動変容」をキーワードとした上肢機能へのアプローチが,読者の皆様方の臨床に,さらには目の前の対象者の皆様の幸せに寄与できれば望外の喜びである.
2017年8月
編集 竹林 崇
監修の序
本書は脳卒中片麻痺を呈した上肢の機能回復に焦点を絞ったリハビリテーション医学の実践書であるとともに,リハビリテーションアプローチ全般に通じる本質的コンセプトを鋭く考察した書籍でもある.したがって,書名にはあえてCI療法(constraint-induced movement therapy)やニューロリハビリテーションという言葉は入れていない.将来的に本書で示したコンセプトがリハビリテーション全般に広がることを期待している.
私は,2008年に『CI療法-脳卒中リハビリテーションの新たなアプローチ』(中山書店)を,2015年に『ニューロリハビリテーション』(医学書院)を上梓し,CI療法を中心としたニューロリハビリテーションについて啓発を行ってきた.多くのリハビリテーション科医師,療法士だけでなく,脳神経外科や神経内科の医師,あるいは当事者の方々からも多くの反響をいただいた.そのなかで,兵庫医科大学リハビリテーション医学教室主催によるセミナーや実地研修を受けるのが理想であることはわかるが,書籍の形で具体的な方法論が詳しくわかるものが欲しいといった声も多数寄せられていた.そこで本書は,これまでに執筆しきれなかった具体的なアプローチの方法を詳細に記述するとともに,課題指向型アプローチと運動学習の転移について詳しく解説している.
CI療法をはじめとする運動療法と運動学習との関連については,拙著『ニューロリハビリテーション』でも述べている通り,教師あり学習,強化学習,教師なし学習のいずれもがCI療法と密接に関連している.そして,運動学習則を使いこなす能力,メタ学習も重要であることが推察されている.したがって,CI療法は「運動学習療法」と言い換えることができ,CI療法の諸要素を運動学習の文脈で考察しながら,日々研究を推進している.さらに,本書の主題である課題指向型アプローチや運動学習の転移は,運動学習理論をCI療法の臨床実践においてとことん突き詰め,無駄を削ぎ落とした結果,浮き彫りになった最も本質的なキーコンセプトである.したがって,その本質を理解しさえすれば,上肢のリハビリテーションに限らず,歩行や高次脳機能障害といった問題にもそのまま応用が可能と考えている.
私が,1990年代にSteven L. Wolf教授から,日本でCI療法を普及させてはどうかという提案をいただいてから20年以上になる.兵庫医科大学リハビリテーション医学教室に異動し,2002年ごろから予備的研究を始め,当時の作業療法副主任であった佐野恭子氏(現 兵庫医療大学)の協力を得て,CI療法を国内に送り出した.その頃入職した竹林 崇氏(現 吉備国際大学)は一貫してCI療法を現場の中心として実践し,数々のリサーチや講習会の講師も務めてきた.まさに本書の編集者として適任であり,期待通りの内容に仕上がっている.他にも兵庫医科大学病院リハビリテーション部作業療法部門や共同研究者など,項目ごとに最適な執筆者によりまとまった内容となっている.理論やその他のニューロリハビリテーションについては,上述の拙著も併せて参考にしていただきたい.
歴史的には,この20~30年のリハビリテーション医学・医療の大きな議論の流れとして,治療的アプローチによる機能障害の回復か,代償的アプローチによる日常生活活動の改善か,といった二元論的議論が続いてきた.そして今,再生医療を含むニューロリハビリテーションの時代にあって,麻痺を治すという治療的なリハビリテーションの時代が到来した,という考えかたもできる.しかし,本書で示したコンセプトは,単に麻痺を回復させる治療法という二元論的理解を超えて,機能障害を課題指向的に改善させ,改善した機能障害を日常生活活動につなげる(転移させる)という新たなアプローチの考えかたである.それによって習得した活動が患者さん自身が選んだものであればQOLにも直結するであろう.さらに,QOLに直結した活動(利き手で箸で食べる,ゴルフをする,など)は,おそらく日常的に継続されることが予想される.結果として,活動が機能障害の改善を促進し,加えて病理学的・解剖学的な部分での改善につながる可能性も示されている(錐体路線維の増加,神経新生の促進,など).これを私は,リハビリテーション医学・医療におけるパラダイムシフトと呼んでいる.
本書はまさにパラダイムシフトにつながるアプローチを最初に解説した書籍として上梓されるに至った.執筆者諸氏,兵庫医科大学病院リハビリテーション部スタッフ,兵庫医科大学リハビリテーション医学教室医師,秘書などすべての協力者に深謝する.
2017年9月
監修 道免和久
序
筆者は作業療法学科の学生であった2002年当時,脳卒中後の上肢運動麻痺が対象者の方々に与える心理・機能的な障害を臨床実習先の現場でまざまざと感じ,その失われた機能を「回復」させることこそが作業療法士に託された仕事のひとつではないかと感じ,そのための手法を確立する必要性を強く感じた.しかし,当時の世の中の常識は,発症後180日を過ぎた上肢運動麻痺は改善することがなく,残存機能を活かした代償的な手段を用いて,日常生活活動をはじめとした対象者の生活を自立させるリハビリテーションが主流であった.ただ,そのなかにあって,2000年代に入り,課題指向型アプローチの代表格であるconstraint-induced movement therapy(CI療法)が台頭し,世の中の常識にも少しずつ変化の兆しが見え始めた.
卒業後,運良く就職させていただいた兵庫医科大学では,リハビリテーション医学教室の道免和久主任教授が先頭に立ち,先進的な医療を積極的に採用していた.その1つのプロジェクトとして,他大学に先駆けてCI療法を導入し,臨床応用を実施していたのである.限られた先行研究の資料を片手に,対象者の麻痺手の機能改善を目的に日々試行錯誤を繰り返すわれわれにとっての1度目の転機が2006年に訪れる.本書の執筆者のひとりでもある花田恵介氏がCI療法の開発元でもあるUniversity of Alabama at Birmingham(UAB)のDavid Morris准教授(当時.現在は教授),Edward Taub教授が共著で書かれた“Constraint-induced movement therapy:characterizing the intervention protocol.”(Eura Medicophys 42:257-268, 2006)を抄読し,CI療法の重要なコンポーネントの1つであり,練習効果を生活に転移させるための方略である「Transfer package」の知見をわれわれにもたらしてくれたのである.そこで,このコンポーネントを取り入れたところ,アプローチ後の結果がより良好なものに変わることとなった.また,このアプローチによって,麻痺手が「動く」という機能「回復」としての概念よりも,リハビリテーションそのものの概念である「麻痺手を実生活で使用すること」,すなわち「復権」という概念こそが適当なものだと感じた瞬間でもあった.
2度目の転機は2012年にUABのCI therapy training courseに参加した際に訪れた.本書の執筆者のひとりである高橋香代子氏と一緒に参加し,現場の技術を吸収することができた.この参加期間中に,自身の論文“A 6-month follow-up after constraint-induced movement therapy with and without transfer package for patients with hemiparesis after stroke:a pilot quasi-randomized controlled trial.”(Clin Rehabil 27:418-426, 2013)が掲載されたこともあり,現地の開発者たちとアカデミックなディスカッションを経験できた.また,この際に譲り受けた大量の資料をもとに,先述の花田氏に加え,同じく本書の執筆者である橋本幸久氏,梅地篤史氏,天野暁氏,打田明氏,大谷愛氏,彼ら以外にも,陰ながらたゆみのない援助をしてくれた佐東健氏をはじめとした作業療法士がブラッシュアップに尽力してくれたことで,現在の兵庫医科大学のCI療法が形作られたと言っても過言ではない.さらには,麻痺手の使用行動をより促進するためのアプリ「Aid for Decision-making in Occupational Choice for hand(ADOC)」の開発の誘いをいただいた同じく本書執筆者友利幸之介氏には心から御礼を述べたい.また,何よりもわれわれのさまざまな試みを常におおらかに包むようにご援助・ご指導いただいた道免教授と,ご支援をいただいた兵庫医科大学リハビリテーション医学教室の医師の皆様には感謝の念しかない.そして,さまざまな取り組みに付き合っていただき,われわれに新しい知識の提供や成長の機会を与えてくださった歴代の対象者の方々にも深謝したい.
このような経緯により形作られたわれわれのアプローチは,従来法では大きな壁と認識されていた「リハビリテーション室の外における麻痺手の使用行動」に対して確かな影響を与えることが確認されている.本書では,本アプローチと効果判定に用いる機能評価について,6章に分けてそれぞれ詳細に記載している.第1章では,課題指向型アプローチとTransfer packageを含むCI療法の効果とエビデンスについて記している.第2章,第3章では課題指向型アプローチとTransfer packageの概要と実施を,第4章ではその効果を計測するアウトカムについてまとめているが,これは第5章の症例報告へと連なっている.第6章でも実際に使用する課題について触れている.
兵庫医科大学での13年間にわたって発展してきた「行動変容」をキーワードとした上肢機能へのアプローチが,読者の皆様方の臨床に,さらには目の前の対象者の皆様の幸せに寄与できれば望外の喜びである.
2017年8月
編集 竹林 崇
目次
開く
監修の序
序
(1)行動変容を導く上肢機能回復アプローチ
A 上肢機能回復アプローチにおける行動変容とは?
1 「行動」とは
2 アウトカムメジャーの歴史からみる「行動」
3 「機能」と「行動」からみる行動変容の重要性
B 行動変容を導く上肢機能回復アプローチ(CI療法)の3要素
1 行動変容することの意味
2 行動変容を導く3つの要素
3 療法士の介入者・管理者といった役割
C CI療法におけるエビデンス
1 脳卒中後の上肢機能へのアプローチ
2 CI療法のエビデンス
3 mCI療法のエビデンス
4 重度例に対するCI療法のエビデンス
5 CI療法の副次的な効果
6 CI療法に対するガイドラインの評価
D CI療法がもたらす脳の可塑性(メカニズム)
1 脳の可塑性変化とは?
E 脳卒中後の麻痺手の機能予後とアプローチ
1 脳卒中後上肢麻痺の予後
2 回復過程における麻痺手に対するアプローチのストラテジー
(2)麻痺手に対する課題指向型アプローチ
A 麻痺手に対する課題指向型アプローチの重要性
1 非麻痺手の拘束について
2 非麻痺手の拘束の臨床的な効果
3 非麻痺手の拘束以上に麻痺手へのアプローチが重要?
B 麻痺手の練習と半球間抑制
1 半球間抑制と上肢機能の関係
2 麻痺手の単独使用による脳卒中後の半球間抑制の是正
3 両手動作と半球間抑制
C 課題指向型アプローチの概要と理論的背景
1 課題指向型アプローチとは何か?
2 課題指向型アプローチの理論が拠りどころとする知見
3 課題指向型アプローチのエビデンス
4 課題指向型アプローチの実際
D 課題指向型アプローチにおける目標設定の意義と効果
1 上肢機能回復アプローチにおける目標設定の意義
2 目標設定に関する理論
3 目標設定とは
4 リハビリテーションにおける目標設定の効果
5 目標設定に関する意思決定
6 shared decision makingとは?
7 shared decision makingの障壁
8 ADOC・ADOC for handの紹介
E 課題指向型アプローチにおける目標設定と報酬の関連性
1 課題指向型アプローチにおける目標設定とは?
2 報酬とは?
3 行動学習と報酬の関連性
4 報酬はパフォーマンスや行動を変えるのか
5 報酬の種類によってパフォーマンスや行動変容に差があるか
6 外発的動機づけと内発的動機づけのどちらがよいか?
7 目標設定の難易度
8 目標設定と報酬の解釈に関する限界
F 課題指向型アプローチにおける麻痺手を用いた目標の設定方法
1 対象者に漫然と聞いただけで,麻痺手の目標は決まるのか?
2 麻痺手における練習目標の設定方法
3 目標設定の実際
4 補助ツールを使用してみる
G 課題指向型アプローチにおける物品使用や操作にかかわる神経機構
1 物品を知覚する(視覚刺激の認知)
2 物品に手を伸ばす・つかむ(到達運動と把握運動の制御)
3 到達運動の神経機構
4 把握運動の神経機構
5 状況に応じた到達運動・把握運動の選択
6 物品を離す(リリース)
7 両手動作
8 まとめ
H 課題指向型アプローチにおける具体的な練習課題の設定方法
1 課題指向型アプローチの種類
2 shapingとtask practice
3 練習課題を作成するための評価
4 shapingの実際
5 task practiceの実際
I 練習課題における難易度調整
1 課題指向型アプローチにおける難易度調整
2 空間的な拡張性とは?
3 空間的な拡張性における難易度調整
4 練習に用いる物品のもつ文脈による難易度調整
5 練習に用いる物品と周辺環境との相互作用による難易度調整
6 shaping,task practiceにおける難易度調整の実例
J 課題指向型アプローチにおける療法士と対象者のかかわり(相互作用)
1 環境適応における内因性の文脈の影響
2 相互作用とは?
3 課題指向型アプローチにおいて用いられる4つの相互作用
4 各相互作用は何に働きかけているのか?
5 練習中の相互作用を与える頻度
6 練習後の過程を見据えた相互作用の頻度
K 課題指向型アプローチにおける課題の運営方法
1 課題運営と練習環境の重要性
2 練習時間における課題の提示・運営方法
3 実際の練習場面における課題の運用
4 実際の練習頻度への応用
5 練習環境が練習効率に与える影響
L 課題指向型アプローチにおける練習量(時間)と麻痺手の回復
1 手の使用量と発達
2 必要な練習時間
3 1日の練習時間
M 適応と適応外に対する工夫
1 課題指向型アプローチの適応
2 重度上肢麻痺の問題点
3 課題指向型アプローチを進めていくための工夫
4 おわりに
(3)練習効果を生活に転移させるための方略
A 行動変容の重要性
1 手における「機能回復」だけでなく「行動変容」は必要か?
2 脳卒中後に生じる上肢麻痺に対する行動変容プログラムの現在
3 学習性不使用と行動変容
4 麻痺手の不使用による脳の変化
5 脳卒中後の麻痺手における負の行動変容を予防するための行動戦略
B 行動変容に必要な行動心理学
1 self-regulatory理論:「やりたいこと」が「できると思える」と人は行動する
2 locus of control理論:「やらされるリハビリ」から「やるリハビリ」へ
3 社会的学習理論を理解し,行動変容を促すアプローチ戦略を
C 行動変容戦略としてのtransfer package
1 transfer packageとは
2 transfer packageの効果
3 transfer packageの神経基盤
4 UABと筆者らのtransfer packageの違い
5 transfer packageの3つのコンポーネント
D 麻痺手に関する行動への同意取得
1 麻痺手に関する行動への同意取得とは?
2 インフォームドコンセント,shared decision making
3 動機づけ
4 麻痺手に関する行動への同意の取りかた
5 介護者および家族との麻痺手に関する行動への同意
6 同意後の説明
7 実生活における麻痺手の使用場面の設定
E モニタリングの促進
1 モニタリングの促進とは?
2 モニタリングの具体的な手法
3 記録したMALや行動日記
F 麻痺手を生活で用いるための問題解決技法の指導
1 問題解決技法の心理的背景
2 問題解決技法の指導とは
3 問題解決技法の具体的な指導方法
4 問題解決技法の指導による代償動作
5 作成した書類の活用
(4)上肢機能の推移をとらえるアウトカムメジャー
1 “機能評価”とは何か?
2 なぜ評価が重要なのか?
3 機能評価の目的
4 使用する評価手段において検討されるべき重要な特性
(key psychometric property)
5 考慮されるべき付加的因子
6 脳卒中後の上肢麻痺に対する評価手段の紹介
7 機能評価における今後の方向性
8 本報告の限界(limitation)
9 以上のことから,どのような勧告ができるのか?
(5)行動変容を導く症例紹介
A 感覚障害による失調症状を認めた症例
1 はじめに
2 症例紹介
3 上肢機能評価(CI療法前)
4 本症例のニーズ
5 統合と解釈
6 目標
7 経過
8 最終評価
9 考察
B A型ボツリヌス毒素製剤との併用療法を行った症例
1 はじめに
2 症例紹介
3 使用した上肢評価アウトカム
4 A型ボツリヌス毒素製剤施注前評価
5 A型ボツリヌス毒素製剤施注
6 CI療法前評価(A型ボツリヌス毒素製剤施注後評価)
7 CI療法経過
8 CI療法後評価
9 CI療法3か月後評価
10 考察
11 類似した事例にA型ボツリヌス毒素製剤治療と集中練習を併用する際のポイント
12 おわりに
C 重度上肢麻痺を呈した適応外の症例
1 はじめに
2 症例紹介
3 上肢機能評価(CI療法実施前)
4 練習
5 最終評価
6 考察
7 おわりに
D 視神経脊髄炎を呈した症例
1 はじめに
2 症例紹介
3 CI療法前評価
4 課題指向型アプローチ
5 練習効果を生活に転移させるための方略
6 経過
7 CI療法後評価
8 考察
9 本研究の限界と課題
10 類似疾患に対してアプローチする際のポイント
(6)課題指向型アプローチの実際例
1 上肢機能評価
2 課題紹介
3 活動(作業)の手段的練習課題(shaping)
4 活動(作業)の目的的練習課題(task practice)
索引
序
(1)行動変容を導く上肢機能回復アプローチ
A 上肢機能回復アプローチにおける行動変容とは?
1 「行動」とは
2 アウトカムメジャーの歴史からみる「行動」
3 「機能」と「行動」からみる行動変容の重要性
B 行動変容を導く上肢機能回復アプローチ(CI療法)の3要素
1 行動変容することの意味
2 行動変容を導く3つの要素
3 療法士の介入者・管理者といった役割
C CI療法におけるエビデンス
1 脳卒中後の上肢機能へのアプローチ
2 CI療法のエビデンス
3 mCI療法のエビデンス
4 重度例に対するCI療法のエビデンス
5 CI療法の副次的な効果
6 CI療法に対するガイドラインの評価
D CI療法がもたらす脳の可塑性(メカニズム)
1 脳の可塑性変化とは?
E 脳卒中後の麻痺手の機能予後とアプローチ
1 脳卒中後上肢麻痺の予後
2 回復過程における麻痺手に対するアプローチのストラテジー
(2)麻痺手に対する課題指向型アプローチ
A 麻痺手に対する課題指向型アプローチの重要性
1 非麻痺手の拘束について
2 非麻痺手の拘束の臨床的な効果
3 非麻痺手の拘束以上に麻痺手へのアプローチが重要?
B 麻痺手の練習と半球間抑制
1 半球間抑制と上肢機能の関係
2 麻痺手の単独使用による脳卒中後の半球間抑制の是正
3 両手動作と半球間抑制
C 課題指向型アプローチの概要と理論的背景
1 課題指向型アプローチとは何か?
2 課題指向型アプローチの理論が拠りどころとする知見
3 課題指向型アプローチのエビデンス
4 課題指向型アプローチの実際
D 課題指向型アプローチにおける目標設定の意義と効果
1 上肢機能回復アプローチにおける目標設定の意義
2 目標設定に関する理論
3 目標設定とは
4 リハビリテーションにおける目標設定の効果
5 目標設定に関する意思決定
6 shared decision makingとは?
7 shared decision makingの障壁
8 ADOC・ADOC for handの紹介
E 課題指向型アプローチにおける目標設定と報酬の関連性
1 課題指向型アプローチにおける目標設定とは?
2 報酬とは?
3 行動学習と報酬の関連性
4 報酬はパフォーマンスや行動を変えるのか
5 報酬の種類によってパフォーマンスや行動変容に差があるか
6 外発的動機づけと内発的動機づけのどちらがよいか?
7 目標設定の難易度
8 目標設定と報酬の解釈に関する限界
F 課題指向型アプローチにおける麻痺手を用いた目標の設定方法
1 対象者に漫然と聞いただけで,麻痺手の目標は決まるのか?
2 麻痺手における練習目標の設定方法
3 目標設定の実際
4 補助ツールを使用してみる
G 課題指向型アプローチにおける物品使用や操作にかかわる神経機構
1 物品を知覚する(視覚刺激の認知)
2 物品に手を伸ばす・つかむ(到達運動と把握運動の制御)
3 到達運動の神経機構
4 把握運動の神経機構
5 状況に応じた到達運動・把握運動の選択
6 物品を離す(リリース)
7 両手動作
8 まとめ
H 課題指向型アプローチにおける具体的な練習課題の設定方法
1 課題指向型アプローチの種類
2 shapingとtask practice
3 練習課題を作成するための評価
4 shapingの実際
5 task practiceの実際
I 練習課題における難易度調整
1 課題指向型アプローチにおける難易度調整
2 空間的な拡張性とは?
3 空間的な拡張性における難易度調整
4 練習に用いる物品のもつ文脈による難易度調整
5 練習に用いる物品と周辺環境との相互作用による難易度調整
6 shaping,task practiceにおける難易度調整の実例
J 課題指向型アプローチにおける療法士と対象者のかかわり(相互作用)
1 環境適応における内因性の文脈の影響
2 相互作用とは?
3 課題指向型アプローチにおいて用いられる4つの相互作用
4 各相互作用は何に働きかけているのか?
5 練習中の相互作用を与える頻度
6 練習後の過程を見据えた相互作用の頻度
K 課題指向型アプローチにおける課題の運営方法
1 課題運営と練習環境の重要性
2 練習時間における課題の提示・運営方法
3 実際の練習場面における課題の運用
4 実際の練習頻度への応用
5 練習環境が練習効率に与える影響
L 課題指向型アプローチにおける練習量(時間)と麻痺手の回復
1 手の使用量と発達
2 必要な練習時間
3 1日の練習時間
M 適応と適応外に対する工夫
1 課題指向型アプローチの適応
2 重度上肢麻痺の問題点
3 課題指向型アプローチを進めていくための工夫
4 おわりに
(3)練習効果を生活に転移させるための方略
A 行動変容の重要性
1 手における「機能回復」だけでなく「行動変容」は必要か?
2 脳卒中後に生じる上肢麻痺に対する行動変容プログラムの現在
3 学習性不使用と行動変容
4 麻痺手の不使用による脳の変化
5 脳卒中後の麻痺手における負の行動変容を予防するための行動戦略
B 行動変容に必要な行動心理学
1 self-regulatory理論:「やりたいこと」が「できると思える」と人は行動する
2 locus of control理論:「やらされるリハビリ」から「やるリハビリ」へ
3 社会的学習理論を理解し,行動変容を促すアプローチ戦略を
C 行動変容戦略としてのtransfer package
1 transfer packageとは
2 transfer packageの効果
3 transfer packageの神経基盤
4 UABと筆者らのtransfer packageの違い
5 transfer packageの3つのコンポーネント
D 麻痺手に関する行動への同意取得
1 麻痺手に関する行動への同意取得とは?
2 インフォームドコンセント,shared decision making
3 動機づけ
4 麻痺手に関する行動への同意の取りかた
5 介護者および家族との麻痺手に関する行動への同意
6 同意後の説明
7 実生活における麻痺手の使用場面の設定
E モニタリングの促進
1 モニタリングの促進とは?
2 モニタリングの具体的な手法
3 記録したMALや行動日記
F 麻痺手を生活で用いるための問題解決技法の指導
1 問題解決技法の心理的背景
2 問題解決技法の指導とは
3 問題解決技法の具体的な指導方法
4 問題解決技法の指導による代償動作
5 作成した書類の活用
(4)上肢機能の推移をとらえるアウトカムメジャー
1 “機能評価”とは何か?
2 なぜ評価が重要なのか?
3 機能評価の目的
4 使用する評価手段において検討されるべき重要な特性
(key psychometric property)
5 考慮されるべき付加的因子
6 脳卒中後の上肢麻痺に対する評価手段の紹介
7 機能評価における今後の方向性
8 本報告の限界(limitation)
9 以上のことから,どのような勧告ができるのか?
(5)行動変容を導く症例紹介
A 感覚障害による失調症状を認めた症例
1 はじめに
2 症例紹介
3 上肢機能評価(CI療法前)
4 本症例のニーズ
5 統合と解釈
6 目標
7 経過
8 最終評価
9 考察
B A型ボツリヌス毒素製剤との併用療法を行った症例
1 はじめに
2 症例紹介
3 使用した上肢評価アウトカム
4 A型ボツリヌス毒素製剤施注前評価
5 A型ボツリヌス毒素製剤施注
6 CI療法前評価(A型ボツリヌス毒素製剤施注後評価)
7 CI療法経過
8 CI療法後評価
9 CI療法3か月後評価
10 考察
11 類似した事例にA型ボツリヌス毒素製剤治療と集中練習を併用する際のポイント
12 おわりに
C 重度上肢麻痺を呈した適応外の症例
1 はじめに
2 症例紹介
3 上肢機能評価(CI療法実施前)
4 練習
5 最終評価
6 考察
7 おわりに
D 視神経脊髄炎を呈した症例
1 はじめに
2 症例紹介
3 CI療法前評価
4 課題指向型アプローチ
5 練習効果を生活に転移させるための方略
6 経過
7 CI療法後評価
8 考察
9 本研究の限界と課題
10 類似疾患に対してアプローチする際のポイント
(6)課題指向型アプローチの実際例
1 上肢機能評価
2 課題紹介
3 活動(作業)の手段的練習課題(shaping)
4 活動(作業)の目的的練習課題(task practice)
索引
書評
開く
ニューロリハの第一人者による,行動変容へと導く戦略書
書評者: 藤原 俊之 (順大大学院主任教授・リハビリテーション医学)
“道免和久先生と竹林崇先生の本!”と聞いて,「これは読まずにはいられない」と思った。道免先生はわが国における神経科学に基づいた,いわゆるニューロリハビリテーションの第一人者であり,わが国にCI療法を導入し,普及させ,さらにその機序について神経科学的手法を導入することで明らかにした。竹林先生はその道免先生のもとで,作業療法士として上肢機能障害に対する治療を行うとともに,研究を重ねてきた。現在の日本を代表するリハビリテーション科医と作業療法士であり,研究者であるといえる。このお二人が監修,編集をされたのが本書である。
本書のコンセプトは従来からあるような治療法のマニュアル本とは異なり,「単に麻痺を回復させる治療法という二元論的理解を超えて,機能障害を課題指向的に改善させ,改善した機能障害を日常生活活動につなげる(転移させる)という新たなアプローチの考えかたである」と謳っている(「監修の序」より)。
内容を見ていくと,まず「行動変容を導く上肢機能回復アプローチ」と題し,機能と行動を結び付けて行動変容を促す上肢機能アプローチとしてCI療法を紹介。続いて実際の「麻痺手に対する課題指向型アプローチ」について理論的背景を基に述べている。また,「練習効果を生活に転移させるための方略」では機能回復を行動変容に結び付けるための方略について解説している。一方,本書の後半では実際の症例を通して,具体的に臨床現場においてどのように治療を行っていくのかという点について解説が施されている。
神経科学や行動心理学といった行動変容を導く戦略の根幹となる学問をベースとした上肢機能回復アプローチについて,その学術的背景,基礎知識,実際の治療法を一冊に凝縮した内容となっており,一貫してreasonableな理論からどのように考えて治療するのかというプロセスを明らかにした上で治療法が解説されている。
ニューロリハビリテーションや神経科学に関心の深い医師,コメディカルスタッフ,学生にお薦めの一冊である。
脳卒中上肢麻痺対象者のADLの可能性が広がる一冊
書評者: 山本 伸一 (山梨リハビリテーション病院リハビリテーション部・副部長)
作業療法士になって約30年。就職当時,脳卒中上肢麻痺に対する機能回復アプローチという概念は,当然ながらほぼ存在せず,いわゆる健側志向のリハビリテーションが主流であった。しかし一部の療法士は麻痺側の潜在性や可能性を信じ,試行錯誤していたのも事実である。自身もその一人であった。
1980年代よりサルやヒトに対して神経の除去・感覚の遮断や関節の固定などを行い,身体の変化だけでなく大脳皮質などのマッピングが変化するといった論文が数多く発表された。なかでも1996年,Nudoらは「サルに対して巧緻動作の練習(CI therapy-like-procedure)を実施し,一次運動野における手指の領域が拡大・変化する」ことを発見した。言わずと知れたCI療法(constraint-induced movement therapy)の始まりである。これは,脳卒中対象者を担当する全ての療法士に大きな希望,そして患者にとっても光となったことは言うまでもない。
そしてこのたびの本書の出版である。監修の道免和久氏は,日本のトップクラスのリハビリテーション医,そして編集の竹林崇氏は,2012年にCI Therapy Training Courseに参加し,臨床と研究を重ねながら,多くのジャーナルや書籍の執筆や学会の講演などで活躍されている期待の作業療法士である。
道免氏は,「書名には,あえてCI療法やニューロリハビリテーションという言葉は入れていない。将来的に本書で示したコンセプトがリハビリテーション全般に広がることを期待している」と述べている(『監修の序』より)。凝り固まった概念ではなく,対象者の可能性と普及への熱意が込められていると感じた。
本書は全6章で構成されている。第1章では課題指向型アプローチとtransfer packageを含むCI療法の効果とエビデンスを紹介している。その後は,概要と実践のあり方や効果を計測するアウトカムにつなげ,さらには最終章の実際例に至るまで,基礎・基本から応用までもが解説され,研究と臨床の橋渡し的存在となっている。
脳卒中上肢麻痺に対する機能回復アプローチは,われわれ療法士にとって長年の課題である。軽度だけでなく重度の痙性や弛緩,痛みや感覚過敏・鈍麻・脱失,失調症,振戦など,対象者によって十人十色である。そして対象者はやはり,動けないより,動けたほうがよい。それが生活に活かされればなおさらである。ADLアプローチだけが手段ではなく,全人的・包括的に対象者を捉えることが大事である。解決する手法はたくさんあっていい。選択肢が多いほど未来は変えられる。
本書は,リハビリテーションの可能性をさらに広げるきっかけとなるであろう。そう確信した。ぜひとも熟読いただきたい“渾身の一冊”である。
課題志向型の介入を意識した臨床と科学の融合書
書評者: 森岡 周 (畿央大大学院健康科学研究科主任・教授)
リハビリテーションの理念は全人的復権である。故に,それに携わる専門職は対象者の全人的復権に向け日々努力を怠ってはならない。なぜなら,対象者の人らしさを復権するといった究極の目標を掲げているからである。
人らしさを象徴するものとして上肢による道具操作が挙げられる。乳児は環境に対して挑戦的に行動を繰り返すことでスキルを有した上肢機能を獲得していく。人は生まれながらにして意のままに身体を操れる機能を持ってはいない。言い換えれば,司令塔としての脳の組織化のためには,上肢を介した行動を起こすことが優先されるべき必要条件であるわけである。
本書は単純に脳卒中上肢麻痺に対するアプローチと題さず「行動変容を導く!」という修飾語を含んでいるところに特徴がある。行動は目的を伴う。目的を伴わない運動と伴う運動は関節運動が同じであっても,運動の組織化にかかわるニューロン活動が異なることは自明であり,だからこそ課題指向型に介入しなければならない。課題指向型とは単に日常生活活動(ADL)を繰り返すことではなく,療法士の教育の下対象者が能動的に挑戦的課題に取り組むといった志向性を意味するものである。
本書は全6章で構成されている。その特徴は,1章に行動変容を配置し,それを読者に強く意識させるとともに,2章にも課題指向型アプローチを配置しており,その配分が編者の意図を感じるくらい多いところにある。ともすれば臨床関連の書籍はマニュアル本になる傾向があるが,本書は1・2章の理解なくして5・6章の症例検討や実際例に行くべからずという編者の強い意図を感じる。
要するに,本書は単にアプローチの紹介にとどまらず,神経学的かつ心理学的な根拠が記されているところに特徴があり,なぜ運動の量が必要か,なぜ運動の質(難易度調整や目標設定など)が重要かについて十分に解説がなされている。そして,アウトカムメジャーをあえて章立てて構成しているところにも意図を感じる。リハビリテーションは評価に始まり評価に終わる。適切な評価の実施なくしてリハビリテーションの進歩はない。
本書は道免和久先生のチームによる臨床と科学の融合に基づいた結晶であり,そのチームの旗手として大部分を執筆している竹林崇先生の気概を十二分に感じ取ることができる。お二人は一貫して脳卒中後の運動障害に対する臨床・研究・教育に従事されてきた。彼らの長きにわたる経験に加え,現在進行形の科学的根拠を含んでいる本書に収載されている情報は信頼できるものであることは間違いない。
本書は臨床で格闘している療法士の金科玉条として位置付けられる作品と思われるが,それは時に融通のきかない例えとしても用いられる。日々進む科学技術に足並みをそろえながら今後柔軟に改訂を重ねていただきたい。いずれにしても,リハビリテーション関連職種・学生の皆様に手にとっていただきたい良書として自信を持って薦めることができる。
書評者: 藤原 俊之 (順大大学院主任教授・リハビリテーション医学)
“道免和久先生と竹林崇先生の本!”と聞いて,「これは読まずにはいられない」と思った。道免先生はわが国における神経科学に基づいた,いわゆるニューロリハビリテーションの第一人者であり,わが国にCI療法を導入し,普及させ,さらにその機序について神経科学的手法を導入することで明らかにした。竹林先生はその道免先生のもとで,作業療法士として上肢機能障害に対する治療を行うとともに,研究を重ねてきた。現在の日本を代表するリハビリテーション科医と作業療法士であり,研究者であるといえる。このお二人が監修,編集をされたのが本書である。
本書のコンセプトは従来からあるような治療法のマニュアル本とは異なり,「単に麻痺を回復させる治療法という二元論的理解を超えて,機能障害を課題指向的に改善させ,改善した機能障害を日常生活活動につなげる(転移させる)という新たなアプローチの考えかたである」と謳っている(「監修の序」より)。
内容を見ていくと,まず「行動変容を導く上肢機能回復アプローチ」と題し,機能と行動を結び付けて行動変容を促す上肢機能アプローチとしてCI療法を紹介。続いて実際の「麻痺手に対する課題指向型アプローチ」について理論的背景を基に述べている。また,「練習効果を生活に転移させるための方略」では機能回復を行動変容に結び付けるための方略について解説している。一方,本書の後半では実際の症例を通して,具体的に臨床現場においてどのように治療を行っていくのかという点について解説が施されている。
神経科学や行動心理学といった行動変容を導く戦略の根幹となる学問をベースとした上肢機能回復アプローチについて,その学術的背景,基礎知識,実際の治療法を一冊に凝縮した内容となっており,一貫してreasonableな理論からどのように考えて治療するのかというプロセスを明らかにした上で治療法が解説されている。
ニューロリハビリテーションや神経科学に関心の深い医師,コメディカルスタッフ,学生にお薦めの一冊である。
脳卒中上肢麻痺対象者のADLの可能性が広がる一冊
書評者: 山本 伸一 (山梨リハビリテーション病院リハビリテーション部・副部長)
作業療法士になって約30年。就職当時,脳卒中上肢麻痺に対する機能回復アプローチという概念は,当然ながらほぼ存在せず,いわゆる健側志向のリハビリテーションが主流であった。しかし一部の療法士は麻痺側の潜在性や可能性を信じ,試行錯誤していたのも事実である。自身もその一人であった。
1980年代よりサルやヒトに対して神経の除去・感覚の遮断や関節の固定などを行い,身体の変化だけでなく大脳皮質などのマッピングが変化するといった論文が数多く発表された。なかでも1996年,Nudoらは「サルに対して巧緻動作の練習(CI therapy-like-procedure)を実施し,一次運動野における手指の領域が拡大・変化する」ことを発見した。言わずと知れたCI療法(constraint-induced movement therapy)の始まりである。これは,脳卒中対象者を担当する全ての療法士に大きな希望,そして患者にとっても光となったことは言うまでもない。
そしてこのたびの本書の出版である。監修の道免和久氏は,日本のトップクラスのリハビリテーション医,そして編集の竹林崇氏は,2012年にCI Therapy Training Courseに参加し,臨床と研究を重ねながら,多くのジャーナルや書籍の執筆や学会の講演などで活躍されている期待の作業療法士である。
道免氏は,「書名には,あえてCI療法やニューロリハビリテーションという言葉は入れていない。将来的に本書で示したコンセプトがリハビリテーション全般に広がることを期待している」と述べている(『監修の序』より)。凝り固まった概念ではなく,対象者の可能性と普及への熱意が込められていると感じた。
本書は全6章で構成されている。第1章では課題指向型アプローチとtransfer packageを含むCI療法の効果とエビデンスを紹介している。その後は,概要と実践のあり方や効果を計測するアウトカムにつなげ,さらには最終章の実際例に至るまで,基礎・基本から応用までもが解説され,研究と臨床の橋渡し的存在となっている。
脳卒中上肢麻痺に対する機能回復アプローチは,われわれ療法士にとって長年の課題である。軽度だけでなく重度の痙性や弛緩,痛みや感覚過敏・鈍麻・脱失,失調症,振戦など,対象者によって十人十色である。そして対象者はやはり,動けないより,動けたほうがよい。それが生活に活かされればなおさらである。ADLアプローチだけが手段ではなく,全人的・包括的に対象者を捉えることが大事である。解決する手法はたくさんあっていい。選択肢が多いほど未来は変えられる。
本書は,リハビリテーションの可能性をさらに広げるきっかけとなるであろう。そう確信した。ぜひとも熟読いただきたい“渾身の一冊”である。
課題志向型の介入を意識した臨床と科学の融合書
書評者: 森岡 周 (畿央大大学院健康科学研究科主任・教授)
リハビリテーションの理念は全人的復権である。故に,それに携わる専門職は対象者の全人的復権に向け日々努力を怠ってはならない。なぜなら,対象者の人らしさを復権するといった究極の目標を掲げているからである。
人らしさを象徴するものとして上肢による道具操作が挙げられる。乳児は環境に対して挑戦的に行動を繰り返すことでスキルを有した上肢機能を獲得していく。人は生まれながらにして意のままに身体を操れる機能を持ってはいない。言い換えれば,司令塔としての脳の組織化のためには,上肢を介した行動を起こすことが優先されるべき必要条件であるわけである。
本書は単純に脳卒中上肢麻痺に対するアプローチと題さず「行動変容を導く!」という修飾語を含んでいるところに特徴がある。行動は目的を伴う。目的を伴わない運動と伴う運動は関節運動が同じであっても,運動の組織化にかかわるニューロン活動が異なることは自明であり,だからこそ課題指向型に介入しなければならない。課題指向型とは単に日常生活活動(ADL)を繰り返すことではなく,療法士の教育の下対象者が能動的に挑戦的課題に取り組むといった志向性を意味するものである。
本書は全6章で構成されている。その特徴は,1章に行動変容を配置し,それを読者に強く意識させるとともに,2章にも課題指向型アプローチを配置しており,その配分が編者の意図を感じるくらい多いところにある。ともすれば臨床関連の書籍はマニュアル本になる傾向があるが,本書は1・2章の理解なくして5・6章の症例検討や実際例に行くべからずという編者の強い意図を感じる。
要するに,本書は単にアプローチの紹介にとどまらず,神経学的かつ心理学的な根拠が記されているところに特徴があり,なぜ運動の量が必要か,なぜ運動の質(難易度調整や目標設定など)が重要かについて十分に解説がなされている。そして,アウトカムメジャーをあえて章立てて構成しているところにも意図を感じる。リハビリテーションは評価に始まり評価に終わる。適切な評価の実施なくしてリハビリテーションの進歩はない。
本書は道免和久先生のチームによる臨床と科学の融合に基づいた結晶であり,そのチームの旗手として大部分を執筆している竹林崇先生の気概を十二分に感じ取ることができる。お二人は一貫して脳卒中後の運動障害に対する臨床・研究・教育に従事されてきた。彼らの長きにわたる経験に加え,現在進行形の科学的根拠を含んでいる本書に収載されている情報は信頼できるものであることは間違いない。
本書は臨床で格闘している療法士の金科玉条として位置付けられる作品と思われるが,それは時に融通のきかない例えとしても用いられる。日々進む科学技術に足並みをそろえながら今後柔軟に改訂を重ねていただきたい。いずれにしても,リハビリテーション関連職種・学生の皆様に手にとっていただきたい良書として自信を持って薦めることができる。