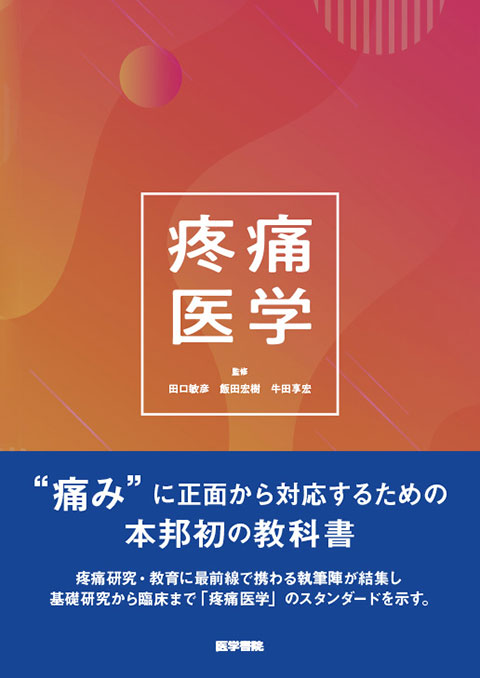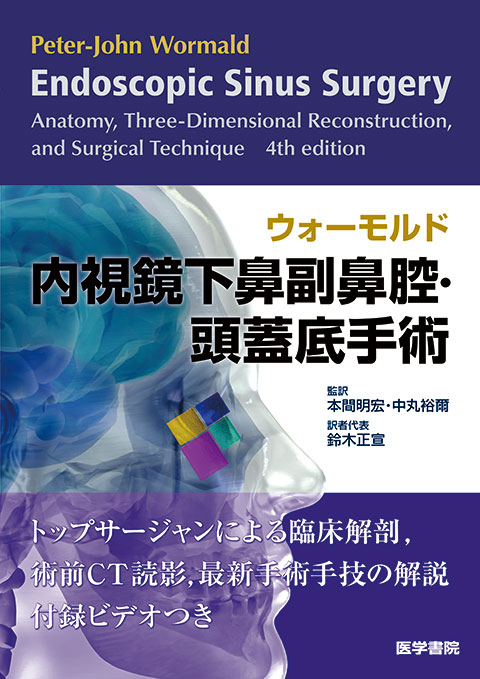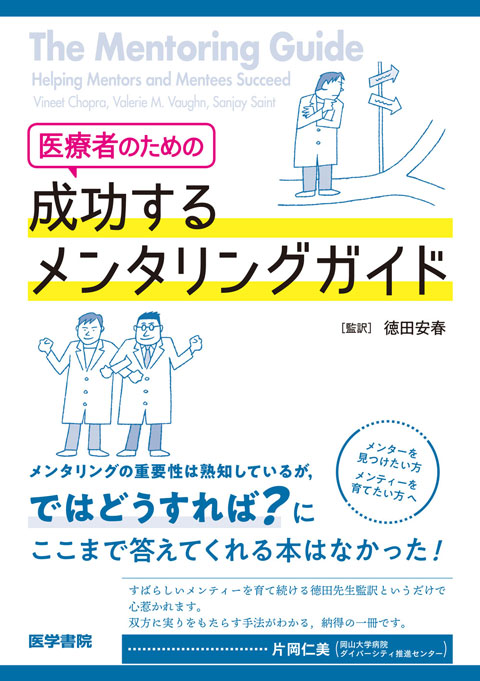MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2021.01.18 週刊医学界新聞(通常号):第3404号より
《評者》 小川 節郎 日大名誉教授
“痛み”に正面から対応するための教科書
「“痛み”に正面から対応するための本邦初の教科書。疼痛研究・教育に最前線で携わる執筆陣が結集し基礎研究から臨床まで『疼痛医学』のスタンダードを示す」。これは本書のカバー帯に書かれている紹介の文章であるが,この紹介文がまさに本書の特徴を正確に表している。
現在におけるわが国の疼痛医学各分野のエキスパートを総動員して完成した本書は,基礎から臨床の隅々に至るまで,詳細で,かつ明快な解説によって構成されている。
1つの例を挙げてみよう。ほとんどの疼痛関係の成書では,痛みの定義を「実際の組織損傷もしくは組織損傷が起こり得る状態に付随する,あるいはそれに似た,感覚かつ情動の不快な体験」とのみ記載し,これに付随する6つの付記については省略していることが多い。実はこの付記が非常に重要な意味を持っている。例えば付記1として「痛みは常に個人的な経験であり,生物学的,心理的,社会的要因によって様々な程度で影響を受けます」と記載され,痛みの複雑性に目を向けるように注意している。本書ではこの6つの付記についてもきちんと触れられており,痛みを正確に理解しようとする科学的態度が見られ,そのような配慮がどの項目においてもよく施されているのである。
本書の構成は,「第I編 総論:痛みの多元性」「第II編 基礎科学」「第III編 臨床病態」「第IV編 痛みの評価と治療」の4項目からなっている。前述したように,痛みに関するさまざまな面に触れている本書の特徴は各所に表れており,全ての項目を紹介できないが,例えば「第I編 総論:痛みの多元性」では,小項目として1.疫学,2.痛みの医療経済,3.痛み研究の歴史と倫理,と普通では省略されることがまれではない領域についても記載されている。
現在,慢性痛への対応が臨床上大きな課題となっており,特に脳機能との関係に興味が注がれているが,第II編においては,痛みの脳科学と疼痛行動の心理学の項目が設けられ,この課題についても最近の知識を得ることができる。
慢性痛患者に接する実際の臨床の場において,医療従事者が最も難渋することの1つは,患者との対話ではないだろうか。この件についても痛み治療におけるコミュニケーションスキルについての項目も設けられており,すぐに役立つ内容となっている。
以上,最初に述べたように,本書はまさに「“痛み”に正面から対応するための本邦初の教科書」である。「痛み」にかかわる全ての医療従事者・研究者にとっていつも手元に置いて勉強する『教科書』と確信した。
《評者》 藤枝 重治 福井大教授・耳鼻咽喉科学
初学者から鼻科専門医まで学ぶことの多い至高の一冊
内視鏡下鼻副鼻腔手術のバイブルであるP. J. Wormaldの原著『Endoscopic Sinus Surgery』の初の邦訳が本書である。P. J. Wormaldは世界でも屈指のrhinologistとして名高く,彼が心血注いで書き続けている原著は第4版まで刊行され,改訂されるごとに手術アプローチやコンセプト,周術期管理に至るまで進化を続けている。もちろん,本書は最新の第4版の邦訳である。内視鏡やナビゲーションなどデバイスの進歩とともに内視鏡下鼻副鼻腔・頭蓋底手術における知識や技術のアップデートが必須であるが,原著を十分に理解するには,多忙な臨床医にとって「言語」という壁が敷居を高くしていた。このたび,P. J. Wormaldのspirit(魂)を受け継ぐ北大の先生たちの手によって待望の訳書が発刊されると聞き,彼の金言をより身近なものとして感じられることに胸が躍った。
あえて紹介するまでもないかもしれないが,P. J. Wormaldはオーストラリアを中心にworld wideに活躍するtop surgeonである。また彼は手術のみならず研究者の顔も持ち,国際誌に330以上の論文を掲載している類いまれなるrhinologistでもある。
本書はFESS(内視鏡下鼻副鼻腔手術)や鼻中隔矯正術など広く市中病院で行われている手術から,前頭蓋底手術など限られた医療施設でしか経験できない手術まで網羅されている。また下垂体腫瘍,前頭蓋手術など経鼻内視鏡下手術を行う脳神経外科医にとっても必要な解剖や手術手技が細部に至るまで書かれている。初学者から鼻科専門医まで非常に学ぶことの多い至高の一冊と言える。
他の手術書と異なる本書の特徴として以下の3点が挙げられる。つまり,①前頭窩に複雑に存在する蜂巣をブロックで3次元的に表現することで,排泄路同定を容易にするbuilding block concept,②解剖学者との協力の下作成された鮮明な手術視野のカダバー画像,そして③個々の医師による経験則ではなく客観的データ(エビデンス)に基づき手術法を評価している点,である。これらの特徴により,読者は解剖についての理解が深まり,合併症を回避しながら世界標準の手術を提供できるようになる。
本書は初学者にとっては歩むべき道を照らす道標として,鼻科専門医にとってはより高みをめざす心強い相棒として,後進を育てる指導医にとっては客観的データを基にした優れた指導書として,その力をいかんなく発揮するだろう。そして,日常診療において「即戦力」としてわれわれに恩恵をもたらしてくれることを確信している。
昨今のコロナ禍において,実際に海外へ渡りP. J. Wormald自身から教えを乞う機会は今まで以上に稀有なものとなってしまったが,幸いなことに本書を通じてP. J. Wormaldの真髄を身近なものとして迎えられることに感謝したい。
《評者》
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。