MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2020.07.27
Medical Library 書評・新刊案内
渡邉 順子 著
《評者》渡邊 昌子(公益社団法人静岡県看護協会会長)
患者の「してほしい看護」を考える,看護のバイブル
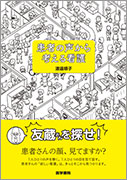 本を手にして最初に目に留まったのは,「友蔵さんを探せ!」という黄色い帯です。ユニークでインパクトがあり,タイトルである『患者の声から考える看護』とどのようにつながっているのか,読んでみたいと関心を持ちました。
本を手にして最初に目に留まったのは,「友蔵さんを探せ!」という黄色い帯です。ユニークでインパクトがあり,タイトルである『患者の声から考える看護』とどのようにつながっているのか,読んでみたいと関心を持ちました。
本の全般を通して,学生が看護師となり,現場において看護専門職として役割を果たすために「五感」を最大限に活用し,知識・技術を提供できるよう,その根拠と方法が著者の長年の教員経験から懇切丁寧に述べられています。そこから教育者としての著者の,学生・看護師への愛情を込めた熱いメッセージとエールを感じとることができました。
この本では,看護を行うには患者の体の中で何が起こっているかという病態生理を理解した上で,根拠をもとに的確な判断を行い,患者にとっての最善の看護を提供することが重要であると伝えています。そして,患者に寄り添うことの本当の意味,看護師の思い込みでなく,患者の訴えを傾聴し,その真意をとらえ,その人らしさを尊重した看護の重要性を伝えるなど,看護の本質が詰まっています。
看護師は患者の思いを受け止め,患者にとって最善の看護を懸命に提供します。しかし,時に最善であると思った看護が,患者の思いと「ズレ」てしまい,患者との関係性,コミュニケーションが円滑に進まなくなります。患者のためにと一生懸命故に「こんなに患者さんのことを考え,看護したのに」という思いが生じ,この重要な「ズレ」に気付かず,葛藤を抱え次の一歩が踏み出せない状況を招きます。
例えば,入院時の患者情報を集めなければと咳き込む患者に矢継ぎ早に質問をしてしまう,リハビリの一環だからとできることは全て自分でやってもらおうとする……そういった場面がマンガで表現され,興味深く一気に読み進めることができます。挙げられた場面はまさに「患者あるある」で,苦笑してしまいました。
読者は読み進める中で立ち止まる機会を得,日常行っている看護について,どのようにすれば患者の「してほしい看護」ができたのか,自分の提供した看護が患者とのズレを最小限にできる看護であったかを内省し,そのプロセスを通して,看護の不足点(ズレ)に気付きます。そして,この経験をもとに次の看護にどのように生かすかを見いだすことができます。
本書はその気付きを与え,患者の声が看護師に届くようにと,そして自信と誇りを持って看護を提供できる看護職であってほしいと,著者のいわば分身であり教育者でもある“ナースレンジャー”の切なる願いを込めた一冊です。教育する側/される側双方が現場で生かせる実践本です。
新人看護師の皆さんをはじめ,教育・指導をされている方,全ての看護職に,ぜひ手に取っていただき,「看護のバイブル」として活用されることをお勧めします。
A5・頁184 定価:本体2,000円+税 医学書院
ISBN978-4-260-03831-7


片田 範子 編
《評者》倉田 慶子(東邦大助教・看護学/小児看護専門看護師)
こども達への尊い思いを感じ,ケアの力強いよりどころとなる書
 こどもセルフケア看護理論は,オレム看護理論(以下,オレム)を基盤としている。看護に携わる者になじみ深いオレムであるが,読み解こうとするとなかなか難しい。大学院生のときに,成人と小児看護学領域の学生が合同でオレムを用いて事例を展開する課題に取り組んだのだが,オレムのいわんとするセルフケア不足をどのようにとらえるのかで議論が白熱した。成人と小児の場合では,明らかにセルフケアできる機能や行動が違うためである。その記憶から,本書が「こどものセルフケア不足」をどのようにとらえて臨床でケアしていくのかを興味深く読み進めた。
こどもセルフケア看護理論は,オレム看護理論(以下,オレム)を基盤としている。看護に携わる者になじみ深いオレムであるが,読み解こうとするとなかなか難しい。大学院生のときに,成人と小児看護学領域の学生が合同でオレムを用いて事例を展開する課題に取り組んだのだが,オレムのいわんとするセルフケア不足をどのようにとらえるのかで議論が白熱した。成人と小児の場合では,明らかにセルフケアできる機能や行動が違うためである。その記憶から,本書が「こどものセルフケア不足」をどのようにとらえて臨床でケアしていくのかを興味深く読み進めた。
こどもにおけるセルフケア不足について,「こどもにおいては,成人と比較して未熟であることや力が不足しているという意味ではなく,こども自身が本来的に期待される力を発揮してもまだこどもであるがゆえに必要なセルフケアが存在する状態である」(p.68)を読み,自身では表現できずにいた概念がすっと頭の中に入った。そして,「こどもは,親または養育者からの支援を必要とする存在であり,セルフケア能力が拡大し,自分自身でセルフケアを充足させることができるようになるまでは,常に誰かによって補完されることが必要となる」(pp.68-9)と述べられ,親や養育者がケアを提供する理由も明確に示されている。また,卵に見立てた図において,「こどものセルフケア」(黄身)と「こどもにとって補完される必要があるセルフケア」(白身)が成長発達と共に変化していく関係が示されている。補完される白身は,成長発達と共に縮小される。「こどもにとって必要なセルフケアを親または養育者が十分に補完できず,セルフケアが満たされない場合は,(中略)親または養育者は,自らの責任に基づいて,他のケア提供者(例えば,祖父母)を活用して,こどものセルフケアを補完することを試みる。このレベルでこどもにとって必要なセルフケアを補完されている場合は,専門者からの介入は不要となる」(p.69)と,介入の目標をイメージできる。看護者は,こどものセルフケア不足の部分,健康上の理由によりこどもが実施すべきでない活動,こどものエネルギー消費と治療範囲などを判断し,看護者が親や養育者に代わって援助をするのか,指導し方向づけるのか,身体的・精神的サポートをするのか,発達を促進する環境を提供・維持するのか,教育するのかを選択するのである。「第6章 こどもセルフケア看護理論の活用事例」は,臨床現場でぜひ活用してもらいたい。
本書では,こどものセルフケア能力は生まれた時から備わっており,セルフケア能力が不足している存在ではなく,一人の人間としてその存在を尊重している。編集の片田範子氏をはじめとした執筆者の「こども達への尊い思い」が存分に伝わる。そして,思いにとどまらず,ケアの土台となる看護理論として構築されたことは,こどもの看護に携わる者にとって,何よ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
