MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2019.04.01
Medical Library 書評・新刊案内
中山 和弘 著
《評者》和座 雅浩(各務原リハビリテーション病院副院長・神経内科)
臨床統計学に携わる全ての臨床家にとってのバイブル
 「統計」と聞くだけで,ささっと後ずさりする病院スタッフの閾値を下げるために,何か良い教材がないかと探していた時に,本書と巡り会った。臨床においてデータ解析を行う意義や面白さは,経験がないとイメージしづらいものであるが,本書は看護研究を例に,わかりやすい図を提示しながら展開している。読者の理解を深めるための「見える化」が,至れり尽くせりのレベルで随所にちりばめられ,臨床統計学を世に広めたいとの著者の熱意を感じる。
「統計」と聞くだけで,ささっと後ずさりする病院スタッフの閾値を下げるために,何か良い教材がないかと探していた時に,本書と巡り会った。臨床においてデータ解析を行う意義や面白さは,経験がないとイメージしづらいものであるが,本書は看護研究を例に,わかりやすい図を提示しながら展開している。読者の理解を深めるための「見える化」が,至れり尽くせりのレベルで随所にちりばめられ,臨床統計学を世に広めたいとの著者の熱意を感じる。
私自身の経験であるが,どの統計解析アプリケーションを扱うにも,わかりやすくイメージしながら進めていくことは必要不可欠であり,そうでないとデータを解析するやりがいや面白みを感じないし,たいていは長続きしない。特に統計学のようなとっつきにくい学問を学び実践していくプロセスにおいては,「見える化」が大切であることをあらためて知った。
第1,2章では,統計学を理解して正しい解析を行う上で必須の基礎事項と用語が,過不足なく網羅されており,時間がある読者はここから熟読されることをお勧めしたい。
第3,4章は本書のメインパートであるが,「多変量解析の基本は重回帰分析」の節タイトル通り,重回帰分析を基礎からしっかりと学び,正しく扱えるようになることが,さまざまな多変量解析の理解を深める早道であることが力説されていて,序文の「重回帰分析は,ダイナミックで奥深いものである」の真の意味がよく理解できる。
私自身,重回帰分析をそれなりに理解したつもりで頻用していたが,実は不十分であることに,大いに反省させられた。個人的には,説明変数の一つとして抑制変数の重要性,ステップワイズ法の結果をそのままうのみにしてはならない理由,また交互作用について,理解を深めることができた。臨床研究においては常に問題となる欠損値の扱い方についても,イメージをしやすい事例でわかりやすくまとめられていて非常に参考になった。欠損値は,モヤモヤしている方も多いと思うので,その理解にはこの書をお薦めしたい。
重回帰分析,ロジスティック回帰分析,Cox比例ハザード分析などの頻用される多変量解析の利用経験はあるも,そのモデルが本当に正しいかの判断に苦慮している臨床家は多いのが実状であろう。本書をじっくり読みながら進めることで,こうした多変量解析モデルの精度・妥当性の検証を正確に行うことができ,自信を持って結果を提示できるようになると思う。また著者の豊富な教育経験に基づき,解析結果の解釈で特に初心者が陥りやすいピットフォールも詳細に説明されており,大学院生とのやりとりを文章化したQ&Aは,学ぶ側と教える側双方にとって非常に参考になる。
先日,当院のリハビリテーション臨床研究を,ある米国ジャーナルに採用してもらうことができた1)。メインとなった多変量解析およびモデルの検証には,本書を大いに活用させていただいた。当初は統計学の面白さを院内に広めるために手に取った本書であったが,何より私自身が多変量解析をより深く勉強することができた。より高度な多変量解析が必要になった時も,本書を活用させていただきたいと思う。
本書の内容を,最初から全て理解するには相当なレベルを求められると思われるが,常に本書を手元に置き,自身がこれから行いたい研究と照らし合わせることで,研究の幅が広がり,何段階も質の高い統計解析が正しくできるはずである。看護師のみならず,臨床研究・医療統計学に携わる医師や他の職種にとっても実践的な臨床統計のバイブルになると確信している。特に臨床統計に興味がありながらも,良き指導者や教育機会に恵まれず,そのチャンスを逸してきた方にはぜひとも一読をお勧めしたい。
参考文献
1)J Am Med Dir Assoc. 2018[PMID:30528795]
B5・頁328 定価:本体4,200円+税 医学書院
ISBN978-4-260-03427-2


佐々木 淳 編
《評者》辻 哲夫(東大高齢社会総合研究機構特任教授・ケア政策学)
「治し支える医療」を築きあげる現代の物語
 本書は,医療法人社団悠翔会理事長の佐々木淳医師が主催して行われている研修会「在宅医療カレッジ」のこれまでの講義のエッセンスを「地域共生社会を支える多職種の学び」との副題でまとめたものである。報道キャスター,記者として各方面で活躍し,自らの両親の介護に向き合った経験を持つ町亞聖さんを学長に迎えたことからわかるように,利用者(当事者)本位を基本理念において,最前線で活躍中の多彩な教授陣からのオリジナリティのある実践に裏打ちされた濃い内容の講義がコンパクトにまとめられており,あっという間に読了した。
本書は,医療法人社団悠翔会理事長の佐々木淳医師が主催して行われている研修会「在宅医療カレッジ」のこれまでの講義のエッセンスを「地域共生社会を支える多職種の学び」との副題でまとめたものである。報道キャスター,記者として各方面で活躍し,自らの両親の介護に向き合った経験を持つ町亞聖さんを学長に迎えたことからわかるように,利用者(当事者)本位を基本理念において,最前線で活躍中の多彩な教授陣からのオリジナリティのある実践に裏打ちされた濃い内容の講義がコンパクトにまとめられており,あっという間に読了した。
第I部「認知症ケアの学び」,第II部「高齢者ケアの学び」,第III部「地域共生社会の学び」の3部構成で21の講義が編集されている。それぞれを丁寧に紹介できないのが残念だが,ここでは各講義の語りから印象的なフレーズを引用し,順次つなぐ形で内容をお伝えしたい。
第I部では,「認知症は『おしまい』か」「介護職は認知症のお年寄りがご近所の公園の掃除をするのを支援するというように地域のデザイナーとして働くことができるのではないか」「介護する本人が楽しいからやり続ける」「『快』の時間を増やす」「一番の特効薬は楽しく笑い合うこと」「おまえが忘れても,俺たちが覚えているから」といった流れで,認知症ケアの取り組みの最前線像が伝わってくる。
第II部では,「薬は,できれば1日1回(だけということ)をお勧めする」「リハビリは,五体満足に近づくことではない,人生の成功者になること」「嚥下障害の人でもその人が本当に食べたいものだとむせなかった」「リハビリテーション栄養とは何か」「最期まで口から食べられる街をめざす」といった流れで,最前線の各専門職の気概が生き生きと描かれている。
第III部では,「スピリチュアルケアの1つは,自分の外の大きなものとの出会いの支援」「独居の方を自宅で看取るには3つの条件がある」「病院がなくても幸せに暮らせる」「ケア者の本当の力とは,たとえ力になれなくても逃げないで最期まで支える力」「人生で自分が生きられる期間を切られてしまったとき(思うことは),仲間との夢を実現する(しようとする)ことが,自分が生きている現実に最期まできちんと向き合うということではないかということ」という流れで,共生社会の本質に迫る話がさまざまな視点から展開されている。そして,カレッジの授業が続けられている最中に,看板教授と言ってよい二人の医師(西村元一,村上智彦両氏)が60歳を間近に控えて立て続けにがんで亡くなるという大変悲しいことが起こった。そこで,今回書籍化された内容の締めくくりのような形で,その親しい友人たちによる講義が行われ,「つないでいってほしい」「公として機能していってほしい」という二人の重い遺言が伝えられている。
今,国の政策は超高齢社会を展望し「治し支える医療」への大転換をめざしている。本書は,まさに「病気を治す」という医療の定義に「支える」という言葉が加えられた意味を追求し,それを築きあげるという壮大な取り組みが始まっていることを雄弁に語る物語でもある。専門職にとどまらず,多くの人にそのことを味わいながら読んでいただけることを願っている。
A5・頁264 定価:本体2,000円+税 医学書院
ISBN978-4-260-03823-2


黒川 由紀子,扇澤 史子 編
《評者》上田 諭(東京医療学院大教授・精神医学)
敬意と共感こそが,アセスメントの「はじめの一歩」
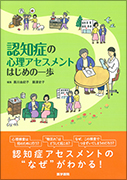 人を診る医療従事者に欠かせない2つの素養がある。ロゴス(理論,言語)とパトス(感情,共感)である。両方を持ってこそ,人に対する真の医療になるはずだ。専門的な理屈ばかりが先行し,思いやりに欠ければ,医療で人を癒やすどころか人を傷つけることになりかねない。残念なことに,現在の医療界は理論・技術(ロゴス)優先が目につき,人の心情や思い(パトス)は二の次にされがちである。認知症の心理アセスメ...
人を診る医療従事者に欠かせない2つの素養がある。ロゴス(理論,言語)とパトス(感情,共感)である。両方を持ってこそ,人に対する真の医療になるはずだ。専門的な理屈ばかりが先行し,思いやりに欠ければ,医療で人を癒やすどころか人を傷つけることになりかねない。残念なことに,現在の医療界は理論・技術(ロゴス)優先が目につき,人の心情や思い(パトス)は二の次にされがちである。認知症の心理アセスメ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
