MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2018.02.05
Medical Library 書評・新刊案内
横地 千仭 著
《評 者》馬場 元毅(東埼玉総合病院附属清地クリニック脳神経外科)
立体画像で見る解剖学アトラス
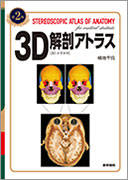 「解剖学は宇宙である」――これは私が日本医科大で初めて受けた解剖学の講義で,当時の解剖学教授であった金子丑之助先生が開口一番言われた言葉です。これを聞いた途端,解剖学の壮大さ,深淵さがおぼろげながら想像でき,これから医学生として未知の学問を学ぶことに期待がみなぎったことをはっきり覚えています。そしてこの学問は,脳神経外科医になった現在の私にとっても重要な分野なのです。
「解剖学は宇宙である」――これは私が日本医科大で初めて受けた解剖学の講義で,当時の解剖学教授であった金子丑之助先生が開口一番言われた言葉です。これを聞いた途端,解剖学の壮大さ,深淵さがおぼろげながら想像でき,これから医学生として未知の学問を学ぶことに期待がみなぎったことをはっきり覚えています。そしてこの学問は,脳神経外科医になった現在の私にとっても重要な分野なのです。
本書の著者の横地千仭先生は1985年にJ. W. Rohen先生との共著である『解剖学カラーアトラス』(初版,医学書院)を出版されています。この解剖図譜は私の愛読書の一つで,拙著『Dr. BABAのメディカルイラストレーション講座』(三輪書店,2017年)の中にも必読の解剖学の参考書として紹介しています。
『解剖学カラーアトラス』の図譜は優れた写真撮影技術で撮られたもので,詳細な部分まで精密に撮影されていますが,あくまでも2次元の平面写真でした。そこで横地先生は,ご自身が所蔵されていた数千枚にのぼる人体解剖の写真の中から,立体画像(3D画像)として見ることのできるように工夫をした『3D解剖アトラス』を1997年に出版されました。この工夫というのは,対象をわずかに方向を変えて2方向から撮影し,これを肉眼で凝視すると立体的に見えてくるというものでした。これを見るためには交差法と呼ばれる特殊な技法が必要で,ある程度の訓練を要するため,全ての読者に容易に立体画像を見てもらうことがやや困難であったと思われました。そこでこのたびの改訂では,この困難点を解決する方法として3Dメガネを用いることが提案されました。3Dメガネを用いて立体画像を見ることは最近の映画などでも頻繁に行われ,2次元映像とは全く異なる世界に引き込まれた経験をされた方も大勢おられることでしょう。
この3Dメガネを用いることで本書の価値はいくつかの点で大きく増幅したように思います。一つは,立体視することで,観察しようとする対象がまさに目の前に“手に取ることができる”位置に見えることです。元画像の写真解像度が良いので,例えば大脳の連合線維束の走行も明瞭に判別できます。もう一点は,本書の携帯性です。前出の『解剖学カラーアトラス』は大型本で,持ち歩けるものではなかったのですが,今回の本はB5サイズと,携帯するにも邪魔にならず,まさしく身近なものとなった点です。
そして特筆すべき点は,組織を立体的に観察してすぐにそのページの上段に目を向けると,組織名が一覧にされていることから,解剖学的構築の理解が容易にできる点です。これこそ本書の神髄と思われます。
本書は医学生をはじめ,歯学,薬学系の学生諸氏,看護師,さらに理学療法士などのコメディカル分野など,医療にかかわるあらゆる方々に必要な知識が容易に習得できる優れた著書と思われます。
B5・頁160 定価:本体2,900円+税 医学書院
ISBN978-4-260-01614-8


坂本 壮 著
《評 者》上田 剛士(洛和会丸太町病院救急・総合診療科副部長)
当直するたびに自身の成長を確信させてくれる良書
 内科救急に携わる全ての医師にとって待望の一冊が手元にある。この書籍は今や「引っ張りだこ」の坂本壮先生による単著第2弾だが,内科救急の15症例を通じて陥りやすいピットフォールについて非常にわかりやすく解説されている。
内科救急に携わる全ての医師にとって待望の一冊が手元にある。この書籍は今や「引っ張りだこ」の坂本壮先生による単著第2弾だが,内科救急の15症例を通じて陥りやすいピットフォールについて非常にわかりやすく解説されている。
一気に読破できるほど“読みやすい”この書は,デザインや書体などにも細かくこだわり,イラストも何度か描き直したそうであるが,“読みやすい”のは見た目のためだけではない。内容が良いのだ。内科救急で働く医師へ伝えたいメッセージが明確となっているからこそ,読み手の心に響く“読みやすい”一冊に仕上がったのであろう。現場で働く坂本先生ならではの作品である。よく出合う疾患の非典型的症状について理解を深めること,バイタルサインを正しく解釈することが最初に解説されており,基本からしっかり押さえることができるため,初期研修医でも安心だ。
本書の端々に救急外来で役立つパールがちりばめられている。「脳卒中にショックなし!」,大動脈解離で「痛いのは裂けているとき。“いま”痛みがなくても安心してはいけない!」など救急外来において患者さんとあなたを救ってくれる一言がきっと見つかるであろう。
病歴聴取に関しては「核心に迫る1フレーズ」が秀逸だ。軽微な意識障害を見逃さないために「普段と変わりませんか?」と家族や施設職員に尋ねよ。倦怠感,脱力,食思不振があれば「腎臓が悪いと言われたことはありませんか?」と一言付け加えよう。80歳で冠動脈疾患となった家族歴があったとしても,臨床的意義は乏しい。そこで「ご家族で若くして冠動脈疾患に罹った方はいますか?」と聞くべきだなど,内科医も唸らせる内容だ。
身体診察に関しても「腹部の触診では患者の表情を見る」「呼吸の異常は,患者の呼吸を真似て瞬時に判断!」「触診を嫌がるほどの痛みならば壊死性軟部組織感染症を考えよ」などすぐに実践できるTipsが多く紹介されている。Kussmaul呼吸と過換気発作を一目瞭然で見分ける方法については救急外来で非常に役立つことだろう。
検査については「検査は答え合わせ」とし,胸部単純X線写真では放射線科医でも肺炎の15%を見落とすことを例に挙げ,初学者にありがちな検査の乱れ打ちをけん制する。その一方,重要な情報が得られるにもかかわらず,非侵襲的で迅速性に優れた超音波検査やグラム染色についてはその有用性を説いている。
当直をただこなすのではなく,自分の頭を使いながら病歴聴取や身体診察を行い,自分の体を動かして検査をする。当直するたびに自分自身が大きく成長できることを確信させてくれる良書だ。いずれの内容も“読みやすい”が故に初学者向けとも思えるが,その内容は上級医が指導する際にも参考になり,内科救急に携わる全ての医師にとって待望の一冊と言える。
A5・頁180 定価:本体3,600円+税 医学書院
ISBN978-4-260-03197-4


この熱「様子見」で大丈夫?
在宅で出会う「なんとなく変」への対応法
家 研也 編
《評 者》齊藤 裕之(山口大病院准教授・総合診療部)
対話形式でひもとかれる“在宅の思考プロセス”
 在宅医療のフィールドほど多職種連携の効果が発揮される場はなく,だからこそ医師,看護師,ケアマネジャーがそれぞれの思考プロセスを共有し,患者のケアに取り組む姿勢が重要である。
在宅医療のフィールドほど多職種連携の効果が発揮される場はなく,だからこそ医師,看護師,ケアマネジャーがそれぞれの思考プロセスを共有し,患者のケアに取り組む姿勢が重要である。
本書は,これまで状態が安定している患者宅へ訪問した際,「あれ!? いつもと違うな?」という小さな変化を感じる場面から始まる。普段は和やかな表情の寝たきり患者の意識レベルがなんとなく変,ここ1か月間の食事量が徐々に少なくなっている,オムツ交換をした際にオムツに少量の出血が付着していたなど,日常の訪問看護・訪問診療で遭遇する頻度の高い状態変化が25話もちりばめられており,看護師と医師の対話形式でお互いの思考プロセスを共有している。
本書は,医師が看護師や介護職を対象に,遭遇頻度の高い状態変化(発熱,皮膚トラブル,悪心・嘔吐など)へのアプローチを紹介しているが,読み進めることで思考が整理される心地よさを感じることができる。在宅医療は使用できる検査器具が限られるうえに,例えば「家族がどうしても病院には行かせたがらない」といったナラティブな要素が絡み合うため,適切な判断がしづらい場面が多い。しかし,本書では在宅特有の複雑な判断基準や思考プロセスが,経験豊富な医師と看護師の対話を通じて徐々にひもとかれていく。
結局のところ,このような対話の繰り返しが各地域での在宅医療の文化を築いているのではと気付かされる。本書は,在宅で遭遇頻度の高い状...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
寄稿 2025.11.11
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
