MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2015.10.12
Medical Library 書評・新刊案内
実践! 皮膚病理道場
バーチャルスライドでみる皮膚腫瘍
[Web付録付]
日本皮膚科学会 編
《評 者》鶴田 大輔(阪市大大学院教授・皮膚病態学)
革命的な書籍,時空を超えた学習ツール
 バーチャルスライドを利用した『実践! 皮膚病理道場 バーチャルスライドでみる皮膚腫瘍[Web付録付]』を強く推薦する。時空を超えた新時代の学習ツールであるからである。
バーチャルスライドを利用した『実践! 皮膚病理道場 バーチャルスライドでみる皮膚腫瘍[Web付録付]』を強く推薦する。時空を超えた新時代の学習ツールであるからである。
初めてバーチャルスライドを体験したのは,2年前に日本皮膚病理組織学会が主催する「皮膚病理道場あどばんすと」にチューターとして参加したときである。とにかく驚いた。なんと楽しいのだろう! 顕微鏡がなくても,コンピューター上で,自分の見たいところを自由自在に心行くまで見ることができ,いつでもどこでも病理組織の学習ができるのである。例えば,腫瘍を構成する個々の細胞において,核と細胞質の形態をじっくり見ることができる。「この腫瘍の構成細胞の核の形態は? 核小体の見え方は? 胞体の色は? 大きさは?」などを目に焼き付けることができる。また,そのときに学んだものをいつでもどこでも,顕微鏡がなくても繰り返し復習できるのである。バーチャルスライドがあれば,学習は時空を超えるのである!
これまで,病理組織学を学ぶためには,大書をひもときながら実際に病理組織標本を顕微鏡を用いて眺め,一つひとつ個々の症例を積み重ねるしかなく,皆で共用する顕微鏡を「取り合いながら」利用せざるを得なかった。このため,これまでの病理学習は,臨床に追われて全ての業務が終了した後の「深夜」あるいは「土日」に行うイメージになっていたと思う。そうした意味では,本書はこのイメージを完全に超越している。なぜなら,コンピューター1台あれば,昼間から空き時間に病理学習ができるからである。
今や,1000 gを切るパソコンは至るところにある時代である。病棟や外来で,ちょっとした細切れ時間でも病理学習ができるようになったメリットは計り知れない。実際に私もバーチャルスライドを見ながらこの書籍を通読してみた。日常診療の合間でも細切れ時間は結構あるものである。実質2,3日で通読可能であった。
通読してみて以下の感想をもった。1)これ一冊で初学者が遭遇するであろう皮膚腫瘍を網羅している,2)大書では目に留まりにくい重要所見がコンパクトに「何度も」まとめられている,3)上級者にとっても必要な所見が書かれている。
書籍に掲載されている写真はどれも秀逸で,記載もコンパクトかつ簡潔,そして重要事項は何度も繰り返し,それぞれの学習レベルに合わせて定着できるようになっている。単著ではないため,ごく一部に統一感のない記載もあるが,それぞれの執筆者の熱い思いが逆に伝わってくるようで好感を持てた。
今後,第二弾として,炎症性疾患についての本書の続編が登場することを強く期待する。そうすれば,病理学習は真に時空を超えることになるであろう。
A4・頁200 定価:本体12,000円+税 医学書院
ISBN978-4-260-02118-0


福原 俊一 編集代表
《評 者》柴垣 有吾(聖マリアンナ医大教授・腎臓・高血圧内科学)
現代医療に疑問を持つ方に読んでいただきたい一冊
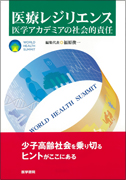 本書は2015年に京都で開催されたWorld Health Summit(WHS)のRegional Meetingで取り上げられたトピックをそれぞれの専門家が解説したものに加えて,同会議の会長を務められた京大医療疫学教授の福原俊一先生による世界のリーダーへのインタビュー記事から成っている。WHSの全体を貫くテーマは「医学アカデミアの社会的責任」とされ,さらにそのキーワードとして医療レジリエンスという言葉が用いられている。
本書は2015年に京都で開催されたWorld Health Summit(WHS)のRegional Meetingで取り上げられたトピックをそれぞれの専門家が解説したものに加えて,同会議の会長を務められた京大医療疫学教授の福原俊一先生による世界のリーダーへのインタビュー記事から成っている。WHSの全体を貫くテーマは「医学アカデミアの社会的責任」とされ,さらにそのキーワードとして医療レジリエンスという言葉が用いられている。
大変に恥ずかしい話ではあるが,私はこれまでレジリエンス(resilience)という言葉の意味をよく知らなかった。レジリエンスはもともと,物理学の用語で「外力によるゆがみをはね返す力」を意味したが,その後,精神・心理学用語として用いられ,脆弱性(vulnerability)の対極の概念として「(精神的)回復力・抵抗力・復元力」を示す言葉として使われるようになったという。今回,評者がこの書評を依頼された理由を推測するに,評者が最近,超高齢社会における現代医療の限界・脆弱性を指摘していたことにあると思われる。もっともその指摘は身内に脆弱高齢者(frail elderly)を抱えた個人的体験によるもので,アカデミックな考察には程遠いものである。
今後の少子高齢社会や日本の社会・経済的現況を考えるに,高度先進医療はmajorityである高齢者が享受できる医療ではないはずであるが,医学アカデミアはこのお金に糸目を付けない医療を志向しているように思えてならない。また,この長寿社会において...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
