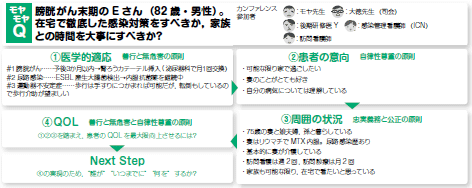在宅での感染対策って?(川口篤也)
連載
2014.10.06
モヤモヤよさらば!
臨床倫理4分割カンファレンス
生活背景も考え方も異なる,さまざまな人の意向が交錯する臨床現場。患者・家族・医療者が足並みをそろえて治療を進められず“なんとなくモヤモヤする”こともしばしばです。そんなとき役立つのが,「臨床倫理」の考え方。この連載では初期研修1年目の「モヤ先生」,総合診療科の指導医「大徳先生」とともに「臨床倫理4分割法」というツールを活用し,モヤモヤ解消のヒントを学びます。
■第10回 在宅での感染対策って?
川口 篤也(勤医協中央病院総合診療センター 副センター長)
(前回からつづく)
(大徳) モヤ先生,最近Y先生について訪問診療に行ってるんだって?
(モヤ) 膀胱がんの末期で,尿路感染で入院したEさんが退院されたため,訪問診療してるんです。でもちょっと,モヤモヤしてることがあって……。
(大徳) ふーん,何だろう。
(モヤ) 入院中の尿培養から,ESBL(Extended Spectrum β -Lactamase:基質特異性拡張型βラクタマーゼ)産生の耐性大腸菌が検出されてるんです。抗菌薬の内服はもう少しで終了しますし,腎ろうカテーテルからの尿の処理は奥さんが行ってます。感染管理看護師(ICN)に感染対策について聞かれて,そういえば何も考えてなかったと思って……。
(大徳) 入院時だと,ESBL産生菌が検出された患者に対しては,接触予防策をとるよね。
(モヤ) はい。手袋やエプロンなどをして,ほかの患者に伝播させない対策をすると勉強しました。それを訪問看護師に伝えたんですけど,「必要であればやるけど,家族はどうするの?」と聞かれてしまって。75歳の奥さんはリウマチでメトトレキサート(MTX)などを内服していて,この前も尿路感染になってますし,確かに感染のリスクは高いんですが……。
(大徳) 在宅での感染対策をどこまですべきか,家族への伝播をどう考えるか,といった問いには,今のところ正解がないんだよね……。でもだからこそ,関係者で話し合ったほうがよい問題でもある。早速日程調整してみようか。
(1)医学的適応
(モヤ) Eさんは82歳男性で,膀胱がんの末期で予後は3か月以内と考えられています。先日尿路感染で入院したのですが,自宅に帰りたい希望が強く,静注抗菌薬投与で症状も改善していたので,内服薬に変更して自宅に帰しました。尿培養からESBL産生大腸菌が検出されていたので,感受性のある内服抗菌薬を処方したのですが,接触予防策については指示してません……。
(訪問看護師) 在宅では今まで「標準予防策」は行っていましたが,「接触予防策」を指示されたことはほとんどなかったですねぇ。
(感染管理看護師〈ICN〉) 最近,ESBLや多剤耐性緑膿菌などが増えていますが,在宅患者では対策が遅れがちだったのは確かです。でも,訪問診療時に医療従事者が,耐性菌が検出されている尿やカテーテルに触れるなどしてそのまま次の患者の診療に向かうと,耐性菌を伝播させる媒介をしてしまうことになるでしょう。ですからきっちり「接...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。