MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2014.01.06
Medical Library 書評・新刊案内
齋藤 昭彦 監訳
新潟大学小児科学教室 翻訳
《評 者》青木 眞(感染症コンサルタント)
内科医にも参考になる精度の高いマニュアル
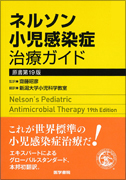 はじめに
はじめに
聖路加国際病院院長(現・理事長)の日野原重明先生のお招きで筆者が帰国した1992年当時,日本の臨床感染症とでも呼ぶべき領域は極めて希薄であった。筆者は臨床感染症の軸となる抗菌薬の削減・適正使用をはじめとする感染管理,感染症診療にと動いた。研修医教育も始め,その対象に当時小児科研修医であった齋藤昭彦先生の姿もあった。時に厳しすぎたかもしれない教育も彼は甘んじて受け入れ,今度はその齋藤先生が小児感染症領域における日本のリーダーとして彼我の格差を是正する番になった。監訳の序で齋藤先生いわく「海外と国内での小児における抗微生物薬の使用に関するギャップがある……(中略)……国内の臨床の現場でこれらの問題は大きく,これをどう解決し,そして世界標準の治療にどう近付けるかはこれからの大きな課題である」と述べている。
使いやすい構成
成人の感染症で定評のあるサンフォードマニュアルと同様,版を重ねた本マニュアルも大変使いやすい構成となっている。その背景には「臨床小児科医マインド」とでもいうべきプリンシプルがあり,それは監訳者の友人であり原著の編集責任者John S. Bradley医師による以下の冒頭の言葉でも明らかである。
「初版から,FDA(米国食品医薬品局)が疾患に対して提示している以外の多くの推奨を本書に記載してきた。その理由として,抗菌薬の初期治療が行われる際には,多くの場合起炎菌が判明していないこと,標的としている感染臓器も原発ではなく続発してその臓器に及んでいる可能性がある……(以下省略)」。病初期,問題の臓器も起炎菌も不明な状態で診療を強いられることが多いのも小児感染症領域の一つの特徴だろう。何より,子どもは自分で訴えることができない。
以下,内科医であっても印象に残った箇所を少し紹介する。全般的に各治療薬,その投与量,投与法の表などはすべてエビデンスのレベルと共に示されておりマニュアルといえども「精度」が高く,内科医にも参考になる点が多い。
〈米国小児感染症臨床レベルの高さを示すもの〉
2章 抗真菌薬の選択:ボリコナゾールはCYP2C19で代謝されるのでアジア人に副作用が出やすい(人種が検討対象になるのは米国教科書の長所)
4章 市中MRSA:過去10年間クリンダマイシンの使用が増加しているがCD腸炎が増加していない(疫学的観察が最初から制度設計されている米国)
13章 腎不全患者に対する抗菌薬療法:米国における臨床薬剤師の活躍は小児科領域でも
16章 抗微生物薬の副反応:複雑性尿路感染症に対するシプロフロキサシンによる筋・関節・腱への影響はFDAへの報告する前方視的研究ではコントロール群よりも大きい(4章と同様に疫学デザインに抜かりがない米国)
〈小児は小さな成人ではない〉
1章 抗菌薬の選択
・経口ペニシリンより経口セファロスポリンは,いくぶん安全性が高く懸濁製剤では味が良い。エステル基のあるセフロキシムとセフポドキシムは最も味が落ちる。後発品は元の製品と比べて好ましい味でないこともある(内科医が「味」を意識することはまれ)
・アモキシシリンの中耳液における長い半減期……(薬物動態の検討は中耳液にまで及ぶ)
12章 肥満児に対する抗菌薬療法
・各薬剤の脂肪組織への移行性の違い・程度を分けて理想体重を利用したり,脂肪量を勘案したりする(体重あたりの投与量が重要な小児科では肥満児の薬物動態は極めて重要)
小児を診るすべての医師に
齋藤先生が帰国されて5年余の歳月が経過。この間,日本のワクチン環境の改善,新潟大学小児科学教室の教授就任など大変な活躍をされたが,出版という点からは雌伏の時期を過ごしていたような気がする。今般,その齋藤先生とその門下の先生方が小児感染症領域でバイブル的存在のマニュアルを翻訳され世に問われた。
私事で恐縮だが西暦2000年,日本人として初めて小児感染症フェローシップを開始するにあたり齋藤先生が下さった手紙を筆者は大切に保管している。それをあらためて読み直しながら平坦ではなかったであろう彼の米国留学・研修生活を思い,また優れた若手医師をその
小児科診療に携わる多くの医療従事者に読者を得て,減少一方のわが国の小児に適切な感染症診療が行き渡ることを期待しています。
B6変・頁296 定価:本体3,400円+税 医学書院
ISBN978-4-260-01808-1


城倉 健 著
《評 者》河野 道宏(東京医大主任教授・脳神経外科学)
神経耳科にも精通した神経内科医による貴重な臨床書
 本書は,城倉健先生が,めまいの診療を一般医家向けにわかりやすく解説した臨床的な教科書である。城倉先生は,神経内科医でありながら,神経耳科の勉強や研究も十分に積み重ねられた,わが国というよりも世界的にも貴重な医師である。耳鼻咽喉科医でめまい・平衡障害を専門とする医師は少数派ながら存在するが,末梢性めまいには詳しくても中枢性めまいとなると途端に臨床経験が不十分で自信を持っていないことが多い。その点,常に脳卒中を救急患者として実際に診ている神経内科医が,神経耳科にも精通していれば,最強のめまい診療医といえる。その城倉先生が満を持して,めまいの診かたをフローチャートや動画を用いて教えてくれている,この上ない貴重な臨床書なのである。
本書は,城倉健先生が,めまいの診療を一般医家向けにわかりやすく解説した臨床的な教科書である。城倉先生は,神経内科医でありながら,神経耳科の勉強や研究も十分に積み重ねられた,わが国というよりも世界的にも貴重な医師である。耳鼻咽喉科医でめまい・平衡障害を専門とする医師は少数派ながら存在するが,末梢性めまいには詳しくても中枢性めまいとなると途端に臨床経験が不十分で自信を持っていないことが多い。その点,常に脳卒中を救急患者として実際に診ている神経内科医が,神経耳科にも精通していれば,最強のめまい診療医といえる。その城倉先生が満を持して,めまいの診かたをフローチャートや動画を用いて教えてくれている,この上ない貴重な臨床書なのである。
脳神経外科におけるめまい診療において,最も頻度が高く,理解を深めておかなければならないのは,本書でも触れられているが,頸筋の異常緊張による頸性めまいである。緊張型頭痛(筋収縮性頭痛)を伴いやすく,その原因としてストレスが強調されやすいが,実際には姿勢の悪さに起因することがほとんどである。背筋の通った,気持ちの良い姿勢の青少年を見る機会が減ってしまった昨今,頸筋の異常緊張による頭痛やめまいは本当に多い。診療の際には,患者の背中に回って両肩の凝りの程度をじかに触って確認し,ツボでいうところの「風池」の圧痛点が陽性であれば,首凝りが強いと判断してよい。また,本書では,頭部回旋に伴うめまい(椎骨脳底動脈循環不全,vertebrobasilar insufficiency ; VBI)として,bow hunter’s strokeとPowers syndromeが解説されているが,これに補うとすれば,頸椎症性(...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
