MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2013.01.07
Medical Library 書評・新刊案内
William Bynum,Helen Bynum 編
鈴木 晃仁,鈴木 実佳 訳
《評 者》山本 和利(札医大教授・地域医療総合医学)
医学史を斬新な切り口で7つのテーマに分けて解説
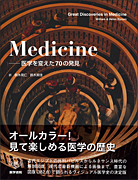 10年以上前から医学部1年生と一緒に医学史を学んでいる。24のテーマを私が設定してそれを学生が調べ,1回2テーマずつをパワーポイントにまとめて,1テーマにつき質疑応答を含めて45分間で発表する授業形式をとっている。学生たちは医学に関することに初めて触れる機会なので,皆,目を輝かせて発表を聴いている。開講当初は,数少ない医学史の本を探したり,関連書籍を図書館で借りたりしながら学生たちは課題をこなしていたが,最近ではもっぱらインターネットで探しているようだ。確かにカビ臭く小さな活字の漢字だらけの参考書籍は敬遠しがちになろう。そのため豊富な画像をカラーで掲載している書籍を待ち望んでいたところであるが,最近そのような要望に応えてくれる書籍が出版された。それが,『Medicine――医学を変えた70の発見』である。
10年以上前から医学部1年生と一緒に医学史を学んでいる。24のテーマを私が設定してそれを学生が調べ,1回2テーマずつをパワーポイントにまとめて,1テーマにつき質疑応答を含めて45分間で発表する授業形式をとっている。学生たちは医学に関することに初めて触れる機会なので,皆,目を輝かせて発表を聴いている。開講当初は,数少ない医学史の本を探したり,関連書籍を図書館で借りたりしながら学生たちは課題をこなしていたが,最近ではもっぱらインターネットで探しているようだ。確かにカビ臭く小さな活字の漢字だらけの参考書籍は敬遠しがちになろう。そのため豊富な画像をカラーで掲載している書籍を待ち望んでいたところであるが,最近そのような要望に応えてくれる書籍が出版された。それが,『Medicine――医学を変えた70の発見』である。
これまでの医学史の本は,時系列に沿った記述に終始しがちであったが,本書は,古代の医学(エジプト,中国,インドなど)における身体のとらえ方から,現代の最新医術までを医療機器,疫病,薬,外科技術,予防など7つの章(70項目)に分けてわかりやすく解説している。特徴は切り口が斬新なことである。その理由は,医学の長い歴史を,単に時系列によるのではなく,その多様なテーマを上手に7つに分けて,テーマごとに一連の流れをつくって描き出しているからである。それゆえ読者は,本書を読むことで7つの視点で7回医学の歴史を振り返ることができる。そして,何よりも幅広い時代・地域から集められた豊富な図版が382点もオールカラーで掲載されているのがうれしい。原書は美術書のように分厚くて重かったが,翻訳版の本書は薄い紙を使って表紙もソフトカバーになり,携帯しやすくなっている。
ここで内容をいくつか紹介してみよう。第1章は「身体の発見」である。エジプト医学,中国医学,インド医学,イスラム医学の歴史や概念がそれらを象徴する貴重な図版とともに述べられている。「ヒポクラテスの伝統」では,体液と精気という4体液説の概念を解説し,古代のギリシャからガレノス主義への道程を,そして現代医学へどうつながるかを考察している。そして,解剖学,病理解剖学,細胞理論,ニューロン理論,分子という項目を設けて一気に現在にまで駆け上ってゆく。
「商売道具」と冠した第3章はユニークである。聴診器,顕微鏡,皮下注射,体温計,X線,血圧計,除細動器,レーザー,内視鏡などの開発の歴史が述べられている。そこでは,最初の体温計,指輪を付けたキューリー夫人の手のX線像などの貴重な図版に触れることができる。
最終章は「医学の勝利」である。ワクチン,ビタミン,インスリン,ヘリコバクター・ピロリなどの項目がある。インスリン療法を受ける前と後の1型糖尿病の少女の同一人物とは思えないほど変化した写真をみると,「医学の勝利」という言葉も頷ける。
本書は,どの項目も図版を含めて見開き2ページまたは4ページに収まっているので,1項目であれば短時間で読むことができる。学生たちの医学史の資料としてのみならず,医師や一般の方々が就寝前などのちょっとした時間に読むのにもうってつけである。ぜひ,一読を勧めたい。
A4変・頁304 定価4,200円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-01518-9


長野 展久 著
《評 者》大野 喜久郎(東京医歯大副学長・理事・名誉教授)
医療事故を防ぎ,備える手がかりを与えてくれる本
 病気を治そうとして,不幸にも医療事故が起こった場合,医師は診療結果に失望し,同時に患者さんや家族との信頼関係が損なわれると,クレームの嵐に晒されることになる。一流の名医と言われる医師でも,人間である限り,医療事故は免れない。そうならないような備えと起こったときにどうするかが重要であり,本書はそのための手がかりを与えてくれる。
病気を治そうとして,不幸にも医療事故が起こった場合,医師は診療結果に失望し,同時に患者さんや家族との信頼関係が損なわれると,クレームの嵐に晒されることになる。一流の名医と言われる医師でも,人間である限り,医療事故は免れない。そうならないような備えと起こったときにどうするかが重要であり,本書はそのための手がかりを与えてくれる。
まず,本書の「はじめに」を読むと著者が本書を著した意図がよくわかる。医学や医療の問題に深く切り込み,医師および患者の心理学,救急診断学に必要な医学的知識,そして救急診療のヒントなどが読みやすく書かれており,このような本は今までなかったように思う。著者のこれまでの経験に基づく優れた洞察力による研究書でもある。医師側および患者側の両者にとって不幸な事例に対し,何が問題であったのかを丁寧に解説し,同じことが起きないようにとの温かい配慮がなされている。これは著者自身の医師としての長い経験と多くの医療事故の分析に裏打ちされていることによるものと思う。日常診療において研修医だけでなく,経験を積んだ医師も気をつけなければならないことが書かれている。そして,時間外当直での診療,あるいは救急患者の診療には恐ろしい落とし穴がいくつもあるように感じる方も多いと思う。確かに,思い込みや忙しさからのミスは起こり得るので,いつも念頭に置く必要がある。
ケースの詳細な記述と一つひとつの事例の教訓,11のコラムも役立つ記載となっている。25のケースでは診療上の注意あるいは説明義務違反が多いようであり,期待権の侵害や自己決定権の侵害が続く。自らが体験してからでは遅いので,すでに起こったことを学習して想像力を働かせることが重要である。「医療の不確実性」にもかかわらず「結果責任」という言葉は常について回る。医療を行う側にとっては極めて不本意で理不尽なものであるが,しばしば一人歩きする。
本書で著者が述べているように,患者の診療に当たっては,特に救急医療においては鑑別診断を挙げて,常にその中で最も危険な疾病の可能性から順に考えていくことが重要と思う。また,こうであろうと考えても,常に急変する疾病や最悪の事態を引き起こす疾病を考慮しておくことが必要であろう。医師に必要な資質は,忍耐力であり,想像力であり,シャーロックホームズばりの推理力であり,またあるときはこれでよいのかという不安感(用心深さ)であると言えるかもしれない。
臨床医であれば誰でも医療事故に巻き込まれる可能性はあるが,本書はその可能性をより小さくしてくれるであろう。そして,たとえそのような状況に陥っても,いつでも緊張を保ち,行うべきことを行って,真摯に患者およびその家族に接することにより,医療裁判へとつながる可能性も小さくなることが期待される。臨床医の皆さんにはぜひ一読していただきたい本である。
A5・頁272 定価2,625円(税5%込)医学書院
ISBN9...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
