MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2012.09.17
Medical Library 書評・新刊案内
坂井 建雄,天野 修 監訳
《評 者》熊木 克治(新潟大名誉教授・肉眼解剖学/日歯大新潟客員教授/新潟リハ大教授)
歯学に,STに,外科に,そして一般に火のごとく世に広がる
 世の中にいわゆる“解剖学書”があふれるように出版されている。『プロメテウス解剖学アトラス 口腔・頭頸部』が出版され,じかに拝見,拝読の機会があった。日歯大で解剖学実習に参加し,新潟リハ大(PT,ST)で解剖学の講義を受け持っている立場と経験から,人体解剖学を学ぶに当たっての困難や問題点,教えるに当たっての重要性を考えながら,このプロメテウスを読み返してみた。まだまだ新しいことを学ばせてもらい,考えさせられる点もたくさんあり新鮮な印象だった。
世の中にいわゆる“解剖学書”があふれるように出版されている。『プロメテウス解剖学アトラス 口腔・頭頸部』が出版され,じかに拝見,拝読の機会があった。日歯大で解剖学実習に参加し,新潟リハ大(PT,ST)で解剖学の講義を受け持っている立場と経験から,人体解剖学を学ぶに当たっての困難や問題点,教えるに当たっての重要性を考えながら,このプロメテウスを読み返してみた。まだまだ新しいことを学ばせてもらい,考えさせられる点もたくさんあり新鮮な印象だった。
歯学部の学生たちは解剖学実習に臨み,登場する多くの学名(ノミナ)になじみが薄く,大きな壁にぶつかる。実物と教科書の間を行ったり来たりして,それらを使いこなせるように努力すると,このプロメテウスはいつの間にか筋肉や関節,さらには脈管系までも上手にくっつけてその機能まで知りたいという気にさせてしまうところが驚きである。特に,神経系については,知覚と運動の伝導経路を示し,中枢と末梢の知識を一体化して構築できるように工夫されている点がユニークといえる。
解剖の勉強には広い机が必要であると冗談半分に言うが,骨・筋,脈管・神経,内臓などの多くの成書を全部広げて,見比べながら,局所解剖学的な知識を組み立てていくのが常套手段である。このプロメテウスは1冊で,そのすべてをこなしている点が特筆に値する。
昨今,歯学部では「歯だけ診ている歯科医師はダメ」「摂食・嚥下までわかる歯科医師であらねばならぬ」と強調されている。年を取るにつれて,おしゃべりに夢中になっていると,危うくむせ返ったりする。献体の会・新潟白菊会の“集い”で,前新潟大歯学部生理学教授の山田好秋先生の「長生きの秘訣-楽しく食べること」というお話で,食べ物の摂食・嚥下の流れを,〈咀嚼期,咽頭期,食道期〉などリハビリの学校で行うように難しく講義しないで,平易に説明してもらった。こんな折の参考書として,専門家にも,学生にも,また一般の人々にも,使い方はそれぞれ違っても,このプロメテウスが大いに役立つと思う。
最近は外科学系の各分野で,手術手技の修練のための解剖の必要性について議論されている。コメディカルの分野での解剖学実習の必要性と合わせて重要な問題である。しかしいずれの場合も,安易に解剖してみるというだけの考えでは不十分なので,常に科学的に観察,考察する解剖学が必要である。そのときにもこの『プロメテウス解剖学アトラス 口腔・頭頸部』は先の3巻の姉妹編ともども,大事なよりどころ,指針として役立つと確信する。
安永3年(1774年),杉田玄白らによって,『ターヘル・アナトミア』の翻訳『解体新書』の出版という偉業が達成された。これを機に西洋医学が世に広がった。このプロメテウス解剖学アトラスも同様に,大きく世に貢献できるに違いないと確信している。日本人の手による解剖学教科書の誕生を後世に期待しつつ。
A4変型・頁384 定価14,700円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-01338-3


吉村 長久,板谷 正紀 著
《評 者》天野 史郎(東大大学院教授・眼科学)
臨床で出合う眼底疾患の知識を身につけられる一冊
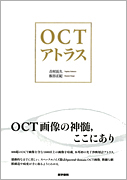 京大眼科の吉村長久教授と板谷正紀准教授の執筆によるOCTアトラスが発行された。光干渉断層計(optical coherence tomography:OCT)は1997年に眼底疾患の診断装置として国内に導入され,網膜の3次元構造を簡単に観察できる装置として急速に臨床の場に普及した。その後,ハード,ソフト両面での改良が大幅に進み,現時点での最新鋭のspectral-domain OCTでは深さ分解能5-7 μmが実現されている。
京大眼科の吉村長久教授と板谷正紀准教授の執筆によるOCTアトラスが発行された。光干渉断層計(optical coherence tomography:OCT)は1997年に眼底疾患の診断装置として国内に導入され,網膜の3次元構造を簡単に観察できる装置として急速に臨床の場に普及した。その後,ハード,ソフト両面での改良が大幅に進み,現時点での最新鋭のspectral-domain OCTでは深さ分解能5-7 μmが実現されている。
最新鋭のspectral-domain OCTによる画像が多用されている本書では,まずOCT読影の基礎として,細胞層が低反射,線維層や境界が高反射という原則,正常網脈絡膜のOCT像の解説,スペックルノイズと加算平均による除去,アーチファクトなどの事項がわかりやすく解説されている。次いで,各論として,黄斑円孔・黄斑上膜など網膜硝子体界面病変,糖尿病網膜症,網膜血管病変,中心性漿液性脈絡網膜症,加齢黄斑変性,網膜変性症,ぶどう膜炎,病的近視,網膜剥離の各疾患が論じられている。疾患ごとにまず概要としてそれぞれの疾患メカニズム研究のこれまでの歴史が語られ,次いで最新のOCT所見を基にした各疾患の発症機序が詳細に述べられている。そしてそれに続く180超の症例でのOCT像が本書の最大の見せ場である。各症例の病態が経時的に変化していく様子がOCT像,眼底写真,造影写真を用いて詳細に示されている。そして,各疾患における典型例はもちろんのこと,バリエーション例も多数示されている。これらの症例をすべて読んでおけば,臨床で出合う上記疾患におけるほとんどのバリエーション症例を経験したのと同じだけの知識を身につけることができるであろう。
本書を読んだ印象としては美しい本だということである。こんなことをいうと不謹慎と言われそうであるが,普段,角膜などの前眼部疾患の患者さんを診察していて,眼底疾患の患者さんの診察をすることが少ない私などがこの本を読んでいると,その美しい写真や装丁を見て感心してしまい,ついついこれら網膜硝子体疾患で悩んでいる患者さんのことを忘れてしまいそうである。しかし,美しく撮られたOCT画像を詳細に検討することが,各種眼底疾患の発症メカニズムを解明することに発展し,個々の患者さんにおいて正しい治療方針を導くことにつながる。このことがこれらの疾患で悩んでいる患者さんに大いに役立つことは明らかであろう。病気の図譜であるのにどうして美しいと感じるかと考えると,spectral-domain OCTで撮られた画像が各種眼底疾患における立体的な変化を手に取るように示しているからであり,これを見ることでそれぞれの疾患の成り立ちが理解できるからである。
網膜硝子体疾患を専門とする先生はもちろんのこと,他のsubspecialityを持つ眼科医,開業医...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
