MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2012.07.16
Medical Library 書評・新刊案内
Francesc Colom,Eduard Vieta 原著
秋山 剛,尾崎 紀夫 監訳
《評 者》加藤 忠史(理化学研究所脳科学総合研究センター 精神疾患動態研究チーム)
役に立ち,読んで面白い,双極性障害の心理教育の教科書
 双極性障害は脳の疾患であり,再発予防効果を持つ薬剤が存在する。それだけに,薬物療法に力点が置かれることが多い。しかし,薬剤は,服用しなければ効果がなく,長期に予防薬を服用することは容易ではない。したがって,薬物療法と心理教育が,双極性障害の治療において,車の両輪となる。
双極性障害は脳の疾患であり,再発予防効果を持つ薬剤が存在する。それだけに,薬物療法に力点が置かれることが多い。しかし,薬剤は,服用しなければ効果がなく,長期に予防薬を服用することは容易ではない。したがって,薬物療法と心理教育が,双極性障害の治療において,車の両輪となる。
本書は,双極性障害の心理教育に特化した初めての日本語の書物である。著者のVieta氏は,新薬の臨床試験の論文を多く発表し,講演会などで引っ張りだこの著名な双極性障害研究者であり,Colom氏と共に,多くの心理教育の論文を執筆している。
本書が述べている方法は,8-12人の患者と2人以上の治療者からなるグループで行われるセッションを,1回90分間,週1回,21週行うものである。半年近くに及ぶ期間は,筆者らも指摘している通りかなり長く,特に薬物療法の部分は少し短縮できそうに感じた。完全にマニュアル通りにしなくても,各施設の事情に合わせて,修正しながら使えばよいと思われる。集団療法の父であるYalom氏が,双極性障害患者を「集団において起こり得る最悪の災害の一つ」などと述べているとは,幸か不幸か知らなかったが,著者らは「我々の経験は,この言葉とは異なる」と言い切る。
読み始めると面白く,あっという間に引き込まれた。著者のずばりと真実を言い切る語り口が小気味よく,また長年の経験に裏打ちされた示唆に富んだアドバイスは,納得するものばかりであった。ほんの一例を挙げれば,「ほとんどの場合,治療者は,セッションの終了後しばらくしてから恋愛に気付く――つまり,恋愛関係はグループ機能を妨げないように思われる」「患者は自分の障害について情報を伝える人と伝えない人を注意深く選ばなければならない。(中略)心理社会的要因の影響については,混乱を避けるために話さないようにアドバイスしている」などは,なるほど,と感じた。
特に,ライフチャートを描く際に,「通常気分の期間を完全な直線で描かないように気を付ける。(中略)ある程度波があることを伝えるためである」という指摘は,目からうろこである。また,「3匹の子ブタ(双極性バージョン)」など,随所にユーモアが満ちあふれている。
また,「精神病症状をことさら強調しないようにする。(中略)精神病症状のない残りの患者が,彼らを重症と決めつけたり,笑ったり,避けたりしないように注意をはらう」「自分自身または創作症例のどちらのライフチャートを作りたいか,患者に質問する――つまり,カモフラージュした方法で自分自身のライフチャートを発表する選択肢を与える」などは,長年の試行錯誤の経験がなければ到底書けない記述である。
再発の初期徴候について,一般論から個別の問題へと落とし込んでいく方法も,よく練られているし,「双極性障害についての10の不愉快な嘘」のリストを示し,1つずつ議論するとか,「2-3人の患者が話し続け,残りの人が黙っているときは,左側の参加者からはじめて時計回りに回るよう,グループの流れを変える」など,非常に実践的な内容ばかりである。
随所にある,訳者からのワンポイント・アドバイスも,一つ一つ味わい深く,有意義である。訳文は非常によく練られており,違和感を覚えるところは一つもなかった。
このような,役に立ち,読んで面白い,双極性障害の心理教育の教科書が出版されたことを心から喜びたい。
B5・頁200 定価3,570円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-01548-6


ソーリー・ワークス!
医療紛争をなくすための共感の表明・情報開示・謝罪プログラム
ダグ・ヴォイチェサック,ジェームズ・W・サクストン,
マギー・M・フィンケルスティーン 著
前田 正一 監訳
児玉 聡,高島 響子 翻訳
《評 者》永井 裕之(医療過誤被害者遺族)
日ごろからの「ソーリー・ワークス」マインドが大切
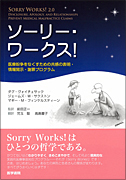 妻は関節リウマチが悪化し,炎症があった左手中指の関節滑膜除去手術を受けた。簡単な手術は成功したが,その翌日(1999年2月11日),点滴後の処置において消毒薬を間違って注入されて急死した。なぜ? 何があったの? 死因は何なの?…などなど,病院の説明対応に不信感が募っていった。その時点で,「医療紛争」にする気もなかったし, 「医療紛争」になるとも思っていなかった。しかし,病院側は医療事故・ミスにならないようにと,初期対応を始めていたことを後で知った。その対応は,「ソーリー・ワークス」ではまったくなかった。
妻は関節リウマチが悪化し,炎症があった左手中指の関節滑膜除去手術を受けた。簡単な手術は成功したが,その翌日(1999年2月11日),点滴後の処置において消毒薬を間違って注入されて急死した。なぜ? 何があったの? 死因は何なの?…などなど,病院の説明対応に不信感が募っていった。その時点で,「医療紛争」にする気もなかったし, 「医療紛争」になるとも思っていなかった。しかし,病院側は医療事故・ミスにならないようにと,初期対応を始めていたことを後で知った。その対応は,「ソーリー・ワークス」ではまったくなかった。
本書は医療事故が過失(ミス)による場合の対応について,「医療紛争をなくすための共感の表明・情報開示・謝罪プログラム」の重要性を説明している。特に「第6章 患者とその家族にどうやって謝罪するか」は,思わぬ医療事故が発生し,さらに突然の死に至った家族に対する対応として「患者は不誠実さを敏感に察知します。誠実に振る舞ってください」,また「初期の反応は怒りや驚き,あるいは激怒であったりします」とし,「落ち着いて次のように答えてください」と,語りかけの言葉が記載されている。
すっきりしない思いを抱きながら本書を読み続けた。「ソーリー・ワークス」の目的は「紛争を防ぐことである」として,スキル・ノウハウ指導・助言をしているように思える。例えば「Sorry Works!は,医療過誤訴訟クライシスを解決するための中道的な方法とした情報開示を提唱する」(xii 著者紹介)などと記載されているが,訴訟が多いアメリカの現状からだろうか?
医療者は患者・家族との信頼関係を深めるために,日ごろから患者第一の「ソーリー・ワークス」(患者サービスに徹するマインド・人間性)が大切である。それができていれば,事故が発生した場合に「ソーリー・ワークス」が功を奏して,訴訟に至らない結果になるのが,日本人の特質である。
医療事故被害者・遺族は「事故原因の究明...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
