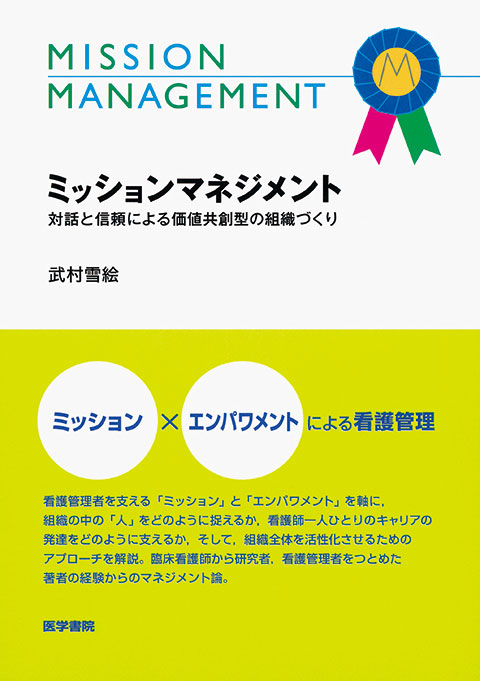新しいルールと意味の創出(1)(武村雪絵)
連載
2012.02.20
看護師のキャリア発達支援
組織と個人,2つの未来をみつめて
【第11回】
新しいルールと意味の創出(1)
武村雪絵(東京大学医科学研究所附属病院看護部長)
(前回よりつづく)
多くの看護師は,何らかの組織に所属して働いています。組織には日常的に繰り返される行動パターンがあり,その組織の知恵,文化,価値観として,構成員が変わっても継承されていきます。そのような組織の日常(ルーティン)は看護の質を保証する一方で,仕事に境界,限界をつくります。組織には変化が必要です。そして,変化をもたらすのは,時に組織の構成員です。本連載では,新しく組織に加わった看護師が組織の一員になる過程,組織の日常を越える過程に注目し,看護師のキャリア発達支援について考えます。
新しいルールと意味の創出
これまでに紹介した,「組織ルーティンの学習」「組織ルーティンを超える行動化」「組織ルーティンからの時折の離脱」の3つは,実践のレパートリーを増やす変化である。これらはそれぞれ組織ルーティンとして提示される「組織ルール」,教育や前職場,自らの経験などから獲得した「固有ルール」,自らの「実践」,のいずれかの不調和が変化の起点となっていた。「組織ルーティンの学習」は組織ルーティンと自らの実践のギャップを埋めようとする変化,「組織ルーティンを超える行動化」は組織ルーティンにない固有ルールを実践しようとする変化,「組織ルーティンからの時折の離脱」はよりよい結果を得られるという見通しを持って,自らの判断で組織ルーティンに従わないことを選択する変化であった。いずれも不調和が解消されたところで実践スタイルが安定した。
一方,「新しいルールと意味の創出」は,実践を再定義・深化する変化である。実践スタイルが安定していた看護師が,何らかのきっかけで,「看護とは何か」「自分の役割は何か」という問いによって,それまで当たり前のものとして受け入れていた組織ルールや固有ルールを問い直し,組織ルールにも固有ルールにもなかった新たな実践を行ったり,すでに行っている実践に新たな意味を見いだしたりするようになる。この変化によって,自己や病棟の価値観や知識,実践が絶対ではないことを自覚した看護師は,別の価値観や知識,実践を受け入れる準備ができた状態での安定,すなわち,「揺らぐ余地を残した安定」に至った。
今回は,「新しいルールと意味の創出」の一つ,「境界の問い直し」(図)について紹介する。
| 図 新しいルールと意味の創出「境界の問い直し」 |
| 網掛けの領域は実践可能なルール,すなわち,実践のレパートリーを表す。人の位置は主なパースペクティブを表す。「境界の問い直し」では,「看護とは何か」「自分の役割は何か」という問いによって組織ルールや固有ルールを問い直し,自らの実践の範囲が見直される。なお,組織ルールおよび固有ルールは漸次的に変化するが,模式図を簡略化するためその変化は図示していない。 |
境界の問い直し
◆広がりへの気付き
病棟で目立った問題もなく対処していることを,あらためて見直すことは少ない。しかし何らかのきっかけで,疑問を持たずに日常的に繰り返している方法が必ずしもよいとはいえないこと,他にも方法があることに気付くことがある。
4年目のSさんは,他の医療機関で働く友人から差し込み便器を使って患者の陰部洗浄を行っていると聞いたとき,「すごくショックを受けた」と話した。些細なことのようでも,彼女にとっては,それまでまったく疑問を持たなかった当たり前が揺らぎ始めた出来事として,強く記憶されていた。
|
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。