MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2011.05.09
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
《脳とソシアル》
ノンバーバルコミュニケーションと脳
自己と他者をつなぐもの
岩田 誠,河村 満 編
《評 者》鈴木 匡子(山形大大学院教授・高次脳機能障害学)
ノンバーバルコミュニケーションの広がりと神経基盤を知るに最適な一冊
 コミュニケーションは「自己と他者をつなぐもの」である。本書は,その中でも言語を使わないノンバーバルコミュニケーションのために脳がどんな仕組みを持っているのかをさまざまな角度からみせてくれる。本書で取り上げられているノンバーバルコミュニケーションは多岐にわたる。目の認知や視線の方向から,顔の表情や向き,身体の姿勢,動きや行為,さらに社会の中での行動までカバーされている。そして,話題はこれらの機能を支える神経基盤だけでなく,ミラーシステム,脳指紋,社会的要因と脳機能の相互関係,脳科学の社会的意義にまで及ぶ。
コミュニケーションは「自己と他者をつなぐもの」である。本書は,その中でも言語を使わないノンバーバルコミュニケーションのために脳がどんな仕組みを持っているのかをさまざまな角度からみせてくれる。本書で取り上げられているノンバーバルコミュニケーションは多岐にわたる。目の認知や視線の方向から,顔の表情や向き,身体の姿勢,動きや行為,さらに社会の中での行動までカバーされている。そして,話題はこれらの機能を支える神経基盤だけでなく,ミラーシステム,脳指紋,社会的要因と脳機能の相互関係,脳科学の社会的意義にまで及ぶ。
本書の斬新さは,広汎な研究をノンバーバルコミュニケーションという視座からとらえ直すことによって,それぞれの研究の意義を浮き彫りにしている点にある。例えば,顔認知を支える脳に関して,神経細胞活動記録,脳波,脳磁図,近赤外線分光法,機能的MRIなどを駆使した各研究は,それぞれ非常に読み応えがある。それだけでなく,岩田誠先生と河村満先生の対談で,ノンバーバルコミュニケーションとしての顔認知の位置付けが明らかにされることによって,個々の研究結果を統合的に理解することができる。
このように,本書はノンバーバルコミュニケーションにかかわる脳機能研究の,現時点での集大成とも言える。さらに,本書は今後の研究の方向性も示している。対談の中で,ある機能がどこの脳部位と関連するかはわかってきたが,そこの神経細胞がどのようなアルゴリズムで機能を生み出しているかはこれからの課題であると指摘されている。また,コミュニケーションの神経基盤として一世を風靡したミラーシステムに対しては慎重な意見が述べられている。
一方,最終章では,ノンバーバルコミュニケーションに限らず,「脳とソシアル」シリーズ全体にかかわると思われる「脳神経科学と社会の関係」が取り上げられている。まだ日本ではあまり知られていない「脳神経倫理」についての話題で,脳神経科学者と社会の双方向コミュニケーションの重要性が述べられている。
本書はいろいろな読み方ができる。コミュニケーションに関心を持つ人は,2つの対談でノンバーバルコミュニケーションについて俯瞰し,その上で各章を読み進めるとよいかもしれない。脳神経科学に興味を持つ人が,一つの課題についての多様な研究方法を学ぶこともできよう。脳神経倫理についての章は,脳神経科学者に一度は読んでほしい内容である。随所に挿入されたこぼれ話は,これだけつまみ食いしたくなるほど印象的な話が多い。もちろん,全体を精読すれば,ノンバーバルコミュニケーションの神経基盤について,十分な知識や洞察が得られることは言うまでもない。
A5・頁240 定価3,780円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00996-6


吉村 長久,喜多 美穂里 編
《評 者》湯澤 美都子(駿河台日大病院教授・眼科学)
網膜硝子体疾患の理解と整理に有用な良書
 京都大学の眼科は網膜硝子体疾患のメッカである。伝統の中で育まれた優秀な研究者たちによって膨大な網膜硝子体の基礎研究と臨床研究がなされてきた。また,日本で最初に硝子体手術を行った盛新之助先生をはじめ,非常に優れた多数の網膜硝子体サージャン,優れた網膜硝子体スペシャリストを輩出されてきた。
京都大学の眼科は網膜硝子体疾患のメッカである。伝統の中で育まれた優秀な研究者たちによって膨大な網膜硝子体の基礎研究と臨床研究がなされてきた。また,日本で最初に硝子体手術を行った盛新之助先生をはじめ,非常に優れた多数の網膜硝子体サージャン,優れた網膜硝子体スペシャリストを輩出されてきた。
その中のおふたり,吉村長久先生と喜多美穂里先生が編集され,京都大学眼科学教室に在籍中あるいはかつて研鑽を積まれた先生方が執筆された『眼科ケーススタディ――網膜硝子体』が上梓された。31の症例提示とそれについての解説がきれいなカラー写真,光干渉断層計,蛍光眼底造影写真を用いて解説してある。必要に応じてシェーマも多用され,よく整理されていて理解しやすい。
31の疾患は黄斑上膜,黄斑円孔,加齢黄斑変性,網膜剥離などの比較的頻度の高いものから家族性滲出性硝子体網膜症,動脈炎性前部虚血性視神経症,癌関連網膜症まで多岐にわたる。優れものはポイントの項で,可能性のある鑑別疾患について,そのポイントが写真付きでわかりやすく解説されている。
ケーススタディの場合,読者は受動的に読むのではなく,症例についていろいろ考えながら読むことになるので,実践向けの知識が身につきやすいと思う。その分書き手には臨床経験と疾患に対する整理された知識が要求される。個々の網膜硝子体疾患のたくさんの患者さんを診て, 治療し,それらの診断,治療について整理してこられた京都大学眼科学教室だから,深みのあるケーススタディができあがったのだと思う。
難は症例提示が31疾患であることである。網膜硝子体疾患は多岐に及び数も多い。ぜひ他疾患について続編を出してもらいたいと思う。その際には,典型症例のみならず,同一疾患のバリエーションについて解説してもらいたいと思う。いずれにせよ本書は網膜硝子体疾患の理解と整理に有用で,明日から自分の臨床に役に立つ「良書」である。また専門医試験の臨床実地試験の対策としても有用であると思う。
B5・頁272 定価13,650円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-01074-0


犀川 哲典,吉松 博信 編
《評 者》吉岡 成人(NTT東日本札幌病院糖尿病内分泌内科部長)
現場で悩む医師にとって大きな助けとなる一冊
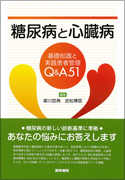 日本における2型糖尿病患者は増加の一途をたどっています。2007年の国民健康・栄養調査によれば,糖尿病とその予備群は合わせて2210万人と推計され,この10年間で1.6倍にも増加しているのです。糖尿病で問題となるのは,何といっても慢性合併症です。
日本における2型糖尿病患者は増加の一途をたどっています。2007年の国民健康・栄養調査によれば,糖尿病とその予備群は合わせて2210万人と推計され,この10年間で1.6倍にも増加しているのです。糖尿病で問題となるのは,何といっても慢性合併症です。
糖...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
