MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2009.08.03
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


病理形態学で疾病を読む
Rethinking Human Pathology
井上 泰 著
《評 者》小田 秀明(東女医大教授・病理学)
読むCPC,読む抄読会
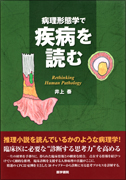 深緑色のカバーで覆われた本書の表紙には,著者である井上泰先生の手描きのイラストが2つ描かれている。バレット食道に出現した腫瘍と血管内膜から発生した腫瘍である。自ら描いたこれら2つの病変が,Rethinking Human Pathologyという文字を,挟んで,包み込んで,にらんでいる。そこに,著者のHuman Pathology(人体病理学)への思いが凝集しているようである。良い医師を育て,より良い医療を行うために,もう一度Human Pathologyを考え,コツコツと手書きの,手作りの教育を展開したいとの思いを感じる。
深緑色のカバーで覆われた本書の表紙には,著者である井上泰先生の手描きのイラストが2つ描かれている。バレット食道に出現した腫瘍と血管内膜から発生した腫瘍である。自ら描いたこれら2つの病変が,Rethinking Human Pathologyという文字を,挟んで,包み込んで,にらんでいる。そこに,著者のHuman Pathology(人体病理学)への思いが凝集しているようである。良い医師を育て,より良い医療を行うために,もう一度Human Pathologyを考え,コツコツと手書きの,手作りの教育を展開したいとの思いを感じる。
「はじめに」をまず読んでもらいたい。よく目にする型にはまった「はじめに」ではない。飛ばさずに,丁寧に読んでもらいたい。そうすることによって,既に医療や医学に携わっている人は自分自身のこれまでの人生を反省することになるだろうし,研修医や学生は将来の自らの姿を想像し,医師として生きるということの意味を考えさせられるのである。
内容は,38のチャプターに分かれ,いずれも良質のCPCや抄読会に参加しているような心地よさがある。CPC形式の症例提示では,臨床と病理がお互いに活発に議論し,画像や検査結果を吟味し,参考文献に当たり,真実に向かって突き進んでいこうという活発なCPCの真っただ中にいるような気分になる。もちろん書名にあるように病理形態学が主体ではあるが,臨床経過や画像を含めた検査結果の読みは適切で深く鋭い。それは熟練の臨床医に匹敵する。本書で扱われた症例が東京厚生年金病院のCPC症例を基本としているとしても,ここまで鋭く深い臨床データの読みができる病理医は全国を探してもそうはいないだろう。
病理像の提示も,極めてユニークだ。肉眼像,ルーペ像が多いのである。最近の病理学の書物には少なくなったが,まじめに形態学をみている病理医にとっては,これら肉眼像やルーペ像が形態学の基本であることはよくわかっている。そういう基本を見直そうと,著者自ら示しているかのようである。極めて多忙で本書を通読できない方には,チャプター12,13の慢性収縮性心膜炎の症例と,チャプター23,24に提示された摂食障害の症例に目を通すことを勧めたい。もっとも,これら2症例を読み終えたときには,すべての症例を読まずにはいられなくなるだろうが。
症例提示ばかりではない。症例の病変に関連して,文献的考察が展開されていく。これらもいくつかのチャプターを構成している。自らの目とルーペ像を頼りに,子宮内膜症の成因に迫ろうとしたSampson,ANCAと補体および腎炎をめぐるJennetteらの研究,そしてClarkとMillerのメラノーマにおける病理組織学的・分子生物学的研究の総体。仕事の内容に関しては丁寧に原著に当たり,かみ砕いた解説がなされている。
ユニークな点は仕事の内容ばかりでなく,その研究者たちが生き生きと描かれていることである。肉声が聞こえるように描かれたこれらのチャプターを読みながら,同じ症例で悩みながらそこで生じた疑問を世界的な仕事に発展させた人々に思いをはせるのである。
このように,本書はユニークな内容と構成を持つ,読むCPC,読む抄読会とも言うべきものである。不自然さを感じないその構成も,的確に見るべきものを提示する画像も見事である。1人でこの広範かつ深遠な内容を書ききったことに敬意を表したい。本書はすべての医療人に読んでいただきたい名著である。
B5・頁352 定価8,820円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00741-2


自治医科大学 監修
《評 者》前田 隆浩(長崎大大学院教授/離島・へき地医療学)
地域医療の実際とその魅力が凝縮された実践的な指導書
 本書は,実際の地域医療業務についてわかりやすく解説し,従事する際に理解しておくべきことや注意点などを見事にまとめた,まさに実践的な指導書である。医療に関する内容だけではなく,保健や福祉はもちろん,わが国の地域医療の歴史や思想的な背景,地域の文化,そして関連する法律など幅広い分野について具体的に記載されている点が興味深い。また,巻頭の「ある地域医師の1日」と最終章の「人々のライフサイクルに関わる地域医療」は,写真やイラストを交えた平易な表現でありながら地域医療人としての役割や業務が実にリアルに描かれており,自分の経験と重ね合わせて思わず引き込まれてしまった。
本書は,実際の地域医療業務についてわかりやすく解説し,従事する際に理解しておくべきことや注意点などを見事にまとめた,まさに実践的な指導書である。医療に関する内容だけではなく,保健や福祉はもちろん,わが国の地域医療の歴史や思想的な背景,地域の文化,そして関連する法律など幅広い分野について具体的に記載されている点が興味深い。また,巻頭の「ある地域医師の1日」と最終章の「人々のライフサイクルに関わる地域医療」は,写真やイラストを交えた平易な表現でありながら地域医療人としての役割や業務が実にリアルに描かれており,自分の経験と重ね合わせて思わず引き込まれてしまった。
さまざまな人たちが指摘しているように,地域医療に必要な要素は多岐にわたる。もちろん充実した医療の提供は不可欠であるが,地域に溶け込み地域で活動していくためには,地域社会のシステムや文化を踏まえた社会学的な視点など,医学的ではないが欠かせない要点がある。本来,この多くは地域医療に従事するようになって初めて気付き,その都度学んでいくようなことである。地域医療教育を担当する立場になって,学生や若い医師にぜひ伝えたいと感じながらも,整理することができずに日ごろから説明の方策を模索していた。本書にはこうした要素についても簡潔に論及されており,ようやく出合えたという思いである。
全国各地で医師不足と地域医療崩壊が叫ばれている中,多くの大学が入学者選抜に地域枠を設けるようになった。地域枠の学生に対しては地域医療に従事するモチベーションを高めていくような教育が求められるが,一方で全体的な地域医療に対する理解を深める教育もまた重要である。そのためには,地域医療の実際とその魅力を伝えていくことが欠かせない。本書にはそのノウハウが凝縮されており,地域医療を志す学生や若い医師はもちろん,何よりも地域医療教育や臨床教育を担当する指導者にぜひ一読をお勧めしたい。
B5・頁224 定価3,990円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00805-1


坂井 建雄,河田 光博 監訳
《評 者》上川 秀士(上川クリニック院長)
従来の神経解剖書では見たことがない,新しい視点から描かれた図
 解剖学の中でも神経解剖は難しく,わかりづらいと言われることが多い。その理由の一つに三次元的な脳神経系を二次元的な書物で説明していることが考えられる。また,解剖のみの記述であれば,臨床医にとっては日常診療と関係づけにくく,その興味も薄れてしまう。もとより海外の教科書には図のきれいなものがたくさんある。しかし,これまでのものは古くからの解剖学のものを踏襲するものが多く,新しさは感じられなかった。また,1つの図で多くのものを説明するため,結局焦点が定まらなくなり,理解しにくくなってしまうことがしばしば見受けられた。多くの解剖学の教科書を見れば見るほど,図の美しさ以外には大きな感動はなくなってしまっていたのである。本書はこれらの問題を見事に解決したといえるであろう。
解剖学の中でも神経解剖は難しく,わかりづらいと言われることが多い。その理由の一つに三次元的な脳神経系を二次元的な書物で説明していることが考えられる。また,解剖のみの記述であれば,臨床医にとっては日常診療と関係づけにくく,その興味も薄れてしまう。もとより海外の教科書には図のきれいなものがたくさんある。しかし,これまでのものは古くからの解剖学のものを踏襲するものが多く,新しさは感じられなかった。また,1つの図で多くのものを説明するため,結局焦点が定まらなくなり,理解しにくくなってしまうことがしばしば見受けられた。多くの解剖学の教科書を見れば見るほど,図の美しさ以外には大きな感動はなくなってしまっていたのである。本書はこれらの問題を見事に解決したといえるであろう。
本書の特色は,図の美しさは当然のことながら,三次元的な理解の助けとなるわかりやすい図が,髄液や静脈系など従来あまり深く述べられていなかったところまで含めて,たくさん盛り込まれている点である。これらの多くは従来の神経解剖書では見たことがないもので,新しい視点から描かれている。そして,それらは解剖学を超え,生理学,組織学,発生学,病理学などにまで及んでいる。また,局所解剖や局所診断など臨床においても必要な事項を,多くのイラストや表を用いてわかりやすく解説しており,その内容は神経内科や脳神経外科の専門医をも満足させるほどのものである。
さらに良いことには,理解を助けるために1つの図の中で多くの事項を説明することを避けている。必要なら同じ図を何度も使い,テーマごとに別々に説明していくなど,読みすすめていくうちに,あたかも大学での講義を聴いているような錯覚に陥る。しかも,それぞれの項目が見開きで整理され,非常に見やすい。これほど多くの図を取り入れながら,図ごとに簡潔かつ適切な説明文も添えられており,アトラスと教科書のいずれの役割をも十分に果たしている贅沢な書である。
私はかつて本書の原書版に出合ったときに,たちまちその素晴らしさに魅了されてしまった。日本語版の出版を待ち望んでいたが,これほど早く実現するとは思わなかった。おそらく多くの人たちも同様の思いだったに違いないと思う。
A4変型・頁432 定価11,550円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00603-3


藤田 郁代 シリーズ監修
藤田 郁代,立石 雅子 編
《評 者》廣瀬 肇(東大名誉教授・音声言語医学)
STの視点で説く失語症の基礎から臨床まで
 本書はわが国の言語聴覚士教育の充実,言語聴覚士の知識の整理とその向上をめざして企画されたシリーズの第1弾で,失語症という大きなテーマに取り組んでいる。
本書はわが国の言語聴覚士教育の充実,言語聴覚士の知識の整理とその向上をめざして企画されたシリーズの第1弾で,失語症という大きなテーマに取り組んでいる。
失語症は言語に関連する脳領域の損傷に伴う言語機能障害で,脳血管障害に伴うことが最も多い。わが国における患者総数は20万人とも30万人ともいわれ,年間の新患数は3万人程度と報告されている。失語症は言語聴覚士にとって特に重要な疾患で,その病態,評価ならびに訓練・治療についての理解を深めることが必要と考えられる。
本書では失語症の基礎から臨床までを,言語聴覚士としての視点を重視しながら9章に分けて詳述している。執筆者としては言語聴覚士を主とする33名が参加しており,特に失語症の症候学,症候群としての分類と各群の特徴の記述...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
