MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2009.04.13
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


吉村 長久 執筆
辻川 明孝,大谷 篤史,田村 寛 執筆協力
《評 者》岸 章治(群馬大大学院教授・視覚病態学)
AMDをめぐる「もやもや」を吹き飛ばす快書
 加齢黄斑変性(AMD)は,近年,高齢者の失明の最大の原因となり,社会的な関心も急速に高まっている。一方で,その実体を明確に説明できる人はほとんどいないであろう。AMDの概念と治療はめまぐるしく変わり,とにかくわかりにくいのである。このたび,上梓された吉村長久氏(京都大学眼科教授)執筆による『加齢黄斑変性』はAMDをめぐる「もやもや」を吹き飛ばす快書である。
加齢黄斑変性(AMD)は,近年,高齢者の失明の最大の原因となり,社会的な関心も急速に高まっている。一方で,その実体を明確に説明できる人はほとんどいないであろう。AMDの概念と治療はめまぐるしく変わり,とにかくわかりにくいのである。このたび,上梓された吉村長久氏(京都大学眼科教授)執筆による『加齢黄斑変性』はAMDをめぐる「もやもや」を吹き飛ばす快書である。
本書は5章からなる。第1章は基礎知識で,混乱しているAMDの疾患概念を明快に分類している。AMDのとらえ方は日本と欧米では異なっている。欧米ではドルーゼンの関与が大きいこと,日本ではインドシアニングリーン(ICG)蛍光造影や光干渉断層計(OCT)の新技術が導入されてからAMDを扱うようになったことがその違いであるという。例えばポリープ状脈絡膜血管症(PCV)はICG造影なくしては診断できない。このことが日本でPCVが多い一因であるという。本邦からの論文が多く,わが国の貢献度の高さがうかがえる。血管新生の項は著者の基礎研究者としての素養がうかがえる。読者は第1章だけでAMDの全体像が把握できるようになったと感じるであろう。第2章では,フルオレセインおよびICG蛍光造影,OCT,微小視野などの検査法が実践的に書かれている。第3章は鑑別疾患であるが,実は黄斑疾患学というべき内容である。中心性漿液性網脈絡膜症,特発性傍中心窩毛細血管拡張症,卵黄様黄斑変性などは,最近概念が変わってきているので注目されたい。第4章はPCVをめぐる諸問題である。PCVの病巣がOCTでどう反映されるか,PCVは新生血管なのか,血管異常なのか,ホットな話題が組織標本とともに展開される。
最も刺激的な話題はゲノムからみたPCVとAMDである。AMDはじつはage-relatedではなく,gene-relatedであること,AMDに関与する遺伝子がコードする蛋白は視細胞内節のミトコンドリアに局在しているというくだりは,ついにAMDの正体を垣間見たようでわくわくする。最終章は治療の実際である。今までに,出ては消えていった治療法の利点と欠点が解説されている。現段階では抗VEGF療法が本命である。新規治療の導入に伴い,さまざまな大規模臨床試験が実施され,学会ではそのデータがしばしば引用される。これらの臨床試験の勘どころが整理されているのはありがたい。
本書は基本的に個人が書いたものである。その点で近年まれな,本らしい本である。分担執筆と異なり,記述に一貫性があり,著者の主張がある。文献の引用は丁寧で,学者としての姿勢が読み取れる。キャリアの大半をAMD研究の最前線で過ごした著者でなければ,俯瞰的で,かつ細部にこだわった本書の執筆は不可能であったであろう。本書は内容が高度であるにもかかわらず,わかりやすく,楽しみながら通読できる。AMDの治療と研究にたずさわる眼科医だけでなく,一般に広く本書をお薦めしたい。
A4・頁272 定価15,750円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00678-1


融 道男 著
《評 者》神庭 重信(九大大学院教授・精神病態医学)
最新でかつ不朽の内容を備えた本
 『向精神薬マニュアル(第3版)』は,初版(1998年)から10年目を迎える息の長い名著である。この間に第2世代抗精神病薬およびSSRI/SNRIが次々に登場し,精神科の薬物療法はそれ以前とは大きく変わった。本書はこれらの新薬情報を漏らすことなく取り入れながらも,薬物療法において変わることのない治療哲学を伝えている,最新でかつ不朽の内容を備えた本であるといえる。
『向精神薬マニュアル(第3版)』は,初版(1998年)から10年目を迎える息の長い名著である。この間に第2世代抗精神病薬およびSSRI/SNRIが次々に登場し,精神科の薬物療法はそれ以前とは大きく変わった。本書はこれらの新薬情報を漏らすことなく取り入れながらも,薬物療法において変わることのない治療哲学を伝えている,最新でかつ不朽の内容を備えた本であるといえる。
著者の融道男氏はよく知られているように,かつて東京医科歯科大学の教授の職にあり,長年にわたって統合失調症の病因・病態研究に従事。統合失調症の解明をライフワークとした研究者である。例えばその業績は,脳内グルタミン酸受容体の減少,ドパミンD2受容体遺伝子異常あるいは作業記憶の低下を説明する前頭葉D1受容体の低下の発見など,枚挙にいとまがない。氏は研究に対しては厳しい姿勢で臨み,いい加減な学会発表には鋭い批判を加えることで知られていたが,評者もかつて氏から直接教えを受けた世代に属する。融道男氏という統合失調症の一流の研究者の手によって長年にわたり丹精込めて作り上げられ,細部にわたって充実していることが他書にない最大の特徴である。
本書は抗精神病薬,抗うつ薬(抗躁薬を含む),抗不安薬と睡眠薬の3章からなる。各章は,薬物発見のストーリーから現在の主流となっている薬物の開発までの歴史をひもとくことから始まる。続いて病態仮説,薬理作用,各種薬物の種類と特徴がきめ細かく紹介され,詳細な副作用解説で完結する。症例報告にまで目配りが行き届いた引用文献が充実しており,必要に応じて原典を調べることができる。『治療薬マニュアル2008』(医学書院)から抜粋された向精神薬のDI集が付録として掲載されており,処方に際して,投与方法,禁忌,副作用,薬物相互作用を確認したいときに,本書は診察室においても活用できる。
圧巻で読み応えがあるのは,本編の約半分を占める抗精神病薬である。本書は,著者が大学を退任される頃から取りかかった仕事であり,言うまでもなく本書にはこうした氏の研究経歴が色濃く表れている。特に統合失調症の神経伝達仮説の節では,著者とそのグループによる研究が諸仮説の展開に及ぼした大きな影響の軌跡を読み取ることができる。
薬物は,疾患の基本的な生物学的病態の理解と薬物の薬理学的特徴を併せて理解して初めて,合理的な使い方ができる。加えて,薬物を処方する医師はまず副作用を知るべきである。副作用は,たとえ一例であっても,重篤なものが報告されているならば,それを記憶しておかなければならない。副作用に関して徹底して一例報告を拾い上げている本書は貴重な資料となっている。
次々に新薬が登場する時代となった。時代に遅れない最適な薬物療法が広く行われていくためにも,本書が多くの方に読まれ,活用されることを期待したい。
A5・頁496 定価5,460円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00599-9


《シリーズ ケアをひらく》
発達障害当事者研究
ゆっくりていねいにつながりたい
綾屋 紗月,熊谷 晋一郎 著
《評 者》内山 登紀夫(よこはま発達クリニック所長・児童精神科医)
これは単なる私的記録ではない。普遍的な価値を持つ「研究書」だ。
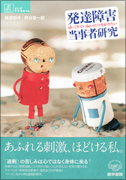 著者の綾屋氏は,2006年にアスペルガー症候群の診断を受けた二児の母,熊谷氏は脳性まひの当事者で小児科医である。
著者の綾屋氏は,2006年にアスペルガー症候群の診断を受けた二児の母,熊谷氏は脳性まひの当事者で小児科医である。
自閉症スペクトラム概念を提唱したWingは,社会性・社会的コミュニケーション・社会的イマジネーションの偏り,すなわち「Wingの3つ組」が発達期から存在することで定義した。自閉症スペクトラムの人は,「3つ組」に加えて感覚情報処理や認知機能の偏り,不器用,実行機能障害などがしばしばみられる――というのが,現在の医学的説明であろう。アスペルガー症候群は自閉症スペクトラムの中核に位置する。
専門家が手をつけにくい感覚情報処理の領域に切り込む
著者は「当事者自身の内部感覚から出発して,新しい自閉観を記述しなおす」ことを意図した。そして「体の内側の声を聞く」ことのわかりにくさの解説から本書は始まる。「おなかがすいた」といった多数派の人々には自明の感覚が,著者にはわかりにくい。身体外部からの情報に加えて,身体の内部から届けられる大量の情報が「等価」に届けられるために,大量の情報を絞り込み,空腹という意味にまとめあげ,「食べる」という具体的行動に移すことがとても難しいという。
感覚情報処理の問題は従来,自閉症スペクトラムに比較的特異的な特性であるとされながらその診断学的位置づけが明確にされず,本格的な研究も少なかった。その理由としては,感覚情報処理の偏りが客観的に観察できる事象(例えば,耳ふさぎ)にとどまらず,主観的に語られる場合が多く「客観的なデータ」が得られにくいこと,感覚の偏りの在り方が非常にまちまちで年齢や個人によるバリエーションが大きいことなどが挙げられよう。
独りよがりにならない文章に乗って著者の感覚を追体験できる
このように専門家には手をつけにくい領域に著者は果敢に取り組み,自己の内部感覚を綿密,冷静に観察し,思索を重ね,多数派にも理解可能な文章という形を与えることに成功した。文体は感覚的で明晰であり,独りよがりの部分は全くなく,読者は著者の体験を実感とともに追体験できる。例えば,育児のなかで著者の行動に子どもが反応するときの著者が語る内的体験。
《このようなときに,私は「ヒトとつながっている」という実感を得る。自分のみぞおちがギュッ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
