MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2009.01.05
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


真野 俊樹 著
《評 者》福田 秀人(立教大大学院教授・危機管理学)
医療をめぐる「お金」の問題を丁寧に解説
 コーネル大学医学部留学中に経済を学ぶことの大事さを痛感し,京都大学で経済学博士号を得た医師であり,また医療経済学者でもある著者は,出来高払いの保険制度は,医師と患者にとっての天国をもたらすものと説く。患者のために高度な診療をするほど,病院や医師に多額の報酬が支払われるからである。しかし,これでは医療費に歯止めがかからず,また,医師と患者の間の情報・知識の格差が,過剰な診療を誘発する。
コーネル大学医学部留学中に経済を学ぶことの大事さを痛感し,京都大学で経済学博士号を得た医師であり,また医療経済学者でもある著者は,出来高払いの保険制度は,医師と患者にとっての天国をもたらすものと説く。患者のために高度な診療をするほど,病院や医師に多額の報酬が支払われるからである。しかし,これでは医療費に歯止めがかからず,また,医師と患者の間の情報・知識の格差が,過剰な診療を誘発する。
さらに,高齢化社会の到来による患者増で,医療費は急増していくとの政府予想と財政赤字の深刻化を受けて,医療費の抑制が重要な政策課題となり,包括払い制度,在院日数の短縮,病床数削減,診療報酬引き下げ,ジェネリック医薬品の奨励,レセプトの審査強化などが推進されるようになった。延命治療も問題視されるようになった。
しかし,医療費がGDPに占める比率はOECD加盟国の中で22位,8.0%(1位米国は15.3%),一人あたり年間医療費(購買力平価換算)は19位にとどまっている。患者数や病床数に対する医師や看護師の比率も,先進国の中で格段に低い。そこで著者は,包括払い制度は医療費の抑制に有効かつ妥当な制度であるが,医療費をもっと増やしてもよいのではないかとし,また,その他の医療費抑制策の前提や効果に,概略,次の疑問を呈している。
医療費の増加は高齢者の増加ではなく,医療技術の進歩による可能性もある/ジェネリック医薬品の普及には,値段,品質,安定供給,的確な情報提供などの課題がある/低コスト,良質の医療,医療への好アクセスの3つを同時に達成することは難しい/医療費の単価をコントロールできても,受診総量をコントロールできない/平均在院日数の短縮が医療費の削減につながるには,患者数,同じ疾患に投入する個別医療,支払い方式が変わらないという非現実的な前提が必要/入院医療の多くを在宅医療でできるのか/医療の専門分化が進み,必要な医師の数が増え,新たな知見が新たな医療サービスを喚起し,医師の仕事が多くなる/医療は専門職が担うため,政府の政策どおりに実行されるとは限らない。
本書は,以上のような医療費,保険,医療の仕組みについて,広範多岐にわたる問題を,用語をきちんと定義し,最新の理論や研究成果を用いて簡潔に解説している。また,経済・経営の観点から,病院,医師,看護師などが取り組むべき課題を示している。さらに,欧米やアジアでの,各国各様の状況と深刻な問題を紹介している。それは,発熱すれば解熱剤を投与すればよしとするに等しい短絡的な発想に陥らず,医療のモンダイを大局的に理解し,解決策を誤らないための手引き書である。なお,本書はどこから読んでもよいが,3章1節「財前と里見はどちらが正しいのか」から読むことを勧める。
A5・頁232 定価2,625円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00659-0


臨床医のための症例プレゼンテーションA to Z
[英語CD付]
齋藤 中哉 著
Alan T. Lefor 編集協力
《評 者》宮城 征四郎(群星沖縄臨床研修センター長)
臨床医学教育のあるべき姿を伝える教則本
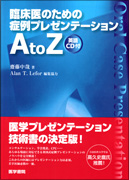 研修医の症例発表の内容を吟味
研修医の症例発表の内容を吟味
医学書院からこのたび,自治医科大学客員教授・齋藤中哉先生による臨床医のための症例プレゼンテーション法を説いた教則本が出版された。
齋藤教授は日本の医療界では数少ない,医学教育学を修めた臨床家である。臨床医学の指導医の立場から本書を出版し,日本の医学界に「臨床医学教育の基礎」を敷衍し,その普及に努めんとしているのである。
したがって本書では,臨床医学教育に携わる人々にとってわかりやすく,症例プレゼンテーションの基礎となる情報が網羅されている。
類書では,異なる病院で3回の1年次レジデントを経験した亀田総合病院リウマチ膠原病内科医長・岸本暢将先生による『米国式症例プレゼンテーションが劇的に上手くなる方法』(羊土社,2004年)があるが,研修医の症例発表の内容を吟味し,その評価を下す指導医の立場から症例プレゼンテーションに必要な知識・技術を網羅的に紹介する本を上梓した例は,わが国では齋藤教授をもって嚆矢とするものであると理解している。
その内容をざっと見渡してみると,問診,理学所見の取り方や問題点の整理法その他,患者を全人的に理解するための10か条や痛みに関する重点項目10か条などが詳述されており,それらが臨床医療のごく一部を表したものであり,すべての主訴についてこのような順序を踏まえた聴取項目が存在していることを示唆するものである。
これらの内容は,著者自身が十分に臨床医学の何たるかを知り,臨床の実力が十分になければ到底書けないような内容ばかりである。
臨床研修事業に従事する医療機関の指導医,あるいは屋根瓦方式の上級研修医は,少なくとも明日の日本の医療を担うことになる現在の下級研修医に対する臨床指導の基本的ノウハウを知るべきであり,本書を臨床指導者として参考にすべきである。また,英語によるプレゼンテーションの実例をいくつかCDを沿えて付録している点でも,この種の本では異例である。
患者を全人的に診る臨床医学教育の実現へ
これまで臓器中心の臨床教育を実施してきたわが国の医療界に対し,患者を全人的に診る臨床医学教育を導入しようとする試みは,大いにあずかって多とすべきである。
日本の医療界では,基礎研究や論文発表が評価の対象とされ,ややもすると臨床医学教育自体がないがしろにされがちである。しかし,その姿勢は,日本の1億3千万人の国民が求める医療とは大きく乖離するものであり,医療自体が受療者たる国民のものであることを思えば,本書の著者のように臨床医学に力を注ぐ人々に,もっと大きな関心が集まってしかるべきである。
願わくば,病棟にあっては主治医のその日の当直医に向けたsign out systemについても,ページを割いて言及してほしかったと思う。そうすれば,各研修医は今よりももっと安心して病院を離れることが可能になるし,各主治医が担当患者管理のために,当直でもないのに夜遅くまで病院に残る現在の臓器中心の臨床教育や研修のあり方にも,いくばくかの改善の糸口を与えることになったに違いないと思う。
しかし,だからといって本書の真価に影響はなく,わが国の医療界に属する医師たちが臨床医学教育のあるべき姿を考える上で大いに参考にすべき良書であり,自信を持って推薦する。
B5・頁248 定価3,990円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00278-3


「人は死ぬ」それでも医師にできること
へき地医療,EBM,医学教育を通して考える
名郷 直樹 著
《評 者》奥野 正孝(鳥羽市立神島診療所所長)
医師頭にしみいる
 台風を避けて朝早く島を出て,母校へき地医科大学での「離島医療」の講義に向かう新幹線の車内でノートパソコンを開いた。いつもこの時間は授業内容を推敲するためのとても大切な時間であるが,その前にこの本を一気に読み切ってしまったのがいけなかった。本のことが頭から離れない,というより何かが脳の中にしみ渡ってしまって,いつものように働いてくれない。なぜだ? 15号車11番E席の窓から,かつて著者がいた作手村の山々が見えている。できすぎている。
台風を避けて朝早く島を出て,母校へき地医科大学での「離島医療」の講義に向かう新幹線の車内でノートパソコンを開いた。いつもこの時間は授業内容を推敲するためのとても大切な時間であるが,その前にこの本を一気に読み切ってしまったのがいけなかった。本のことが頭から離れない,というより何かが脳の中にしみ渡ってしまって,いつものように働いてくれない。なぜだ? 15号車11番E席の窓から,かつて著者がいた作手村の山々が見えている。できすぎている。
たかだか500人しかいない島の診療所での勤務が通算17年を越えた。これだけいれば,何だって知っているし,何にでも対処できて,迷うことなんかないようになるだろうと思っていた。でも結果は逆で,知れば知るほど知らないことは増えていくし,対処できることが増えていくのと同じようにできないことが増えていく。迷いなんて日常茶飯事,いったい自分の頭はどうなってるんだ,どこがいけないんだと自問自答の毎日が過ぎていた。そうこうしているうちに年に一度の大学での講義の機会がやってきたのだが,ここにきて悩んでしまった。迷い悩んでいる私が講義をしたら学生を混乱に陥れるのではなかろうか? 何を話して何を話さないでおくべきなのか? 真実を伝えることは重要だけれどそのまま伝えてよいのか? などと根幹の部分での悩みが頭の中を駆け巡っていた。しかし,本書を一気に読んだ後,私の角張った医師頭は紙ヤスリでゆっくりこすったように丸くなり,垂直に深く切り立った脳溝には何か温かいものが流れ,頭の中が一種の爽快感に満たされた。一つひとつの著者の言葉が大きくまとまってひとつの流れになって医師頭にしみ渡り,軽い高揚感とともに「推敲することも悩むことも十分したのだから,もうやめていいんじゃないか」と自然に気楽に考えるようになってしまっていた。
医学界新聞の著者のコラムを読んでいたとき,禅問答のようになって解釈するのが困難であったり,思考過程をそのまま書いているものだから理解するのに苦労したり,観念奔逸のようにほとばしる言葉の洪水に溺れてしまってその本質に迫れず,逆にきっと著者は研修医の教育で疲れ果てている上に締め切りに追われて書き殴っているのでこんな文になっているのだろうなというくらいにしか思い至らなかったが,なぜか読み続けずにはいられない不思議な魅力があった。しかし,この不思議な魅力も医学界新聞が送られてくる一か月ごとでしか感じることができなかったため,その大きな力を知る由もなかったのだが,この本の登場で,あの不思議な魅力がいっそうパワーアップし,怒濤が押し寄せるように一気に感じることができるようになったのである。
こんなダイナミックな魅力の一方で,この...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
