緩和ケア教育・啓蒙活動の現状,そして今後の展望(内布敦子)
インタビュー
2008.12.15
【interview】
緩和ケア教育・啓蒙活動の現状,そして今後の展望
内布敦子氏(兵庫県立大学看護学部教授・実践基礎看護学)に聞く
2007年4月に施行されたがん対策基本法の第16条では,がん疼痛の緩和が早期から適切に行われることがうたわれた。これまで緩和ケアに対しては,医療者・一般市民ともに関心が低かったとされ,医療者に対しては薬物治療を含む緩和ケアの技術的な教育が,市民に対しては「あきらめの医療ではなく,早期からがん治療と並行して受けられる“治療としての”緩和ケア」への理解を求める啓蒙教育が,日本緩和医療学会などを中心に急ピッチで進められている。
本紙では,実践基礎看護学・教授などのお立場から卒前・卒後の看護職に対する緩和ケア教育に精力的に携わり,また日本緩和医療学会・理事のお立場から「Orange Balloon Project」などを通じ,一般市民への啓蒙活動も牽引している内布敦子氏に,教育・啓蒙活動の現状や課題,今後の展望についてお話を伺った。
――緩和ケアにおいては医療者,一般市民に対する教育・啓蒙が大きな課題です。まずは現在,内布先生が深くかかわっておられる,一般市民への普及啓蒙事業についてお聞かせください。
内布 2007年秋から始まった「Orange Balloon Project(オレンジバルーンプロジェクト,以下OBP)」は,緩和ケアの正しい知識を一般市民に理解していただくための普及啓発事業です。厚労省「がん医療に携わる医師に対する緩和ケア研修等事業」の一環として,日本緩和医療学会が厚労省からの委託事業として企画しています。
同学会の「緩和ケア普及啓発作業部会」(部会長=内布敦子氏)を運営組織に,08年度は他の団体にも参加を呼びかけ,日本がん看護学会,日本ホスピス・在宅ケア研究会,日本死の臨床研究会,日本ホスピス・緩和ケア協会も代表を出しています。
昨年度は,(1)緩和ケアの知識を普及するための媒体制作(ウェブサイト「緩和ケア.net」,ポスター,ちらし,プロモーションDVD,風船,ピンバッジ),(2)制作した媒体を全国(医師会,看護協会,薬剤師会,がん診療連携拠点病院など)へ郵送し,各地で一般市民への普及活動を依頼,(3)緩和ケア普及に関する社会的活動を行っている企業・団体と連携を図り,普及を行う――以上3点の活動を行いました。OBPはオレンジ色の風船をイメージとしていますが,オレンジ色にはすべての苦痛症状をほんのりとやわらげたいという思いを込め,緩和ケアによって患者さんと一緒にバルーンに描かれたような表情になりたいというメッセージも込められています。
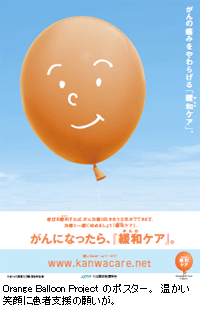 また,ウェブサイト「緩和ケア.net」(註1)は既存のすぐれた緩和ケア関連の情報へのポータル的な役割を果たすサイトとして立ち上げました。このサイトからOBPのポスター,ちらし,資料のダウンロード,DVDの視聴ができます。リンクフリーとなっていて,さまざまな緩和ケアに関連する有益なウェブサイトにリンクが張られるなどしています。
また,ウェブサイト「緩和ケア.net」(註1)は既存のすぐれた緩和ケア関連の情報へのポータル的な役割を果たすサイトとして立ち上げました。このサイトからOBPのポスター,ちらし,資料のダウンロード,DVDの視聴ができます。リンクフリーとなっていて,さまざまな緩和ケアに関連する有益なウェブサイトにリンクが張られるなどしています。
ロゴも無償提供していますが,使用規約があり事前申請が必要です。緩和ケアは人の死と麻薬に関連するものなので,一般市民の目に触れる場合は注意が必要です。違法な麻薬使用と混同するような表現や,自殺サイトなどに使用されると問題ですから,チェックを行っています。
――長く日本では死について語ることがタブー視されてきました。現在の一般市民の緩和ケアに対する認識はどのようなものでしょうか。
内布 05年に国民を対象に行われた「緩和ケア」の認識度調査では「ホスピス・緩和ケアについてよく知っている」と回答した人はわずか11.4%という低い結果が出ています。07年にはがん対策基本法が施行され,OBPの活動も2年目を迎えていますが,緩和ケアに対する一般市民の関心はマスコミも含めてまだまだ低いというのが実情です。
そこでOBPが訴求する内容は「緩和ケアに対する正しい知識の普及」の一語に尽きます。「モルヒネを使うと麻薬中毒になり寿命が縮む」「ホスピスは,安楽死の場であり医療ではない」「なすすべがなく,最後に行われる」などといった間違った知識や否定的なイメージをお持ちの一般市民に,医療用麻薬に関する偏見のない正しい知識を持っていただくとともに,緩和ケアとがん治療は早期から並行して行えるものなのだという理解をしていただき,必要なときに緩和ケアを受けられる文化をつくりたいと思っています。緩和ケアは心理社会的なケア,スピリチュアルなケアも含まれていますので,診断当初からの不安,経済的問題などにも対応するケアであることを覚えてほしいと思います。
各地には,必ずがんの相談支援センターがあります。そこに行って「緩和ケアを受けたい」という患者さんの希望があれば,医療者が必ず対応しなければなりません。緩和ケアができる医療者が不足しているという実情もありますが,患者さんの一言が医療体制を前に進めていきますから,そのための普及活動であるとも考えています。
「人間は死ぬ存在であることをいつも覚えていなさい」
内布 とはいえ,緩和ケアに対しては,自分の身に降りかからないかぎり,自分の問題として考えないというのが実情かと思います。いつも死ぬことばかり考えながら生きていくわけにいかないですから,当然のことではあるのですけれど。それにしても,私たちは死ぬことについて考える機会が少なすぎるのではないでしょうか。いつまでも生きていられるとどこかで思い込んでいる。それはおかしいですよね。人は必ず死ぬ存在なのですから。そのことについても日ごろから考えておく必要がある。
メメント・モリ,つまり,いつか自分にも必ず訪れる死を常に意識の底に置いておく――ということを,私たちはできなくなってしまいました。それは死が病院のなかに隔離されて,日常から消えてしまったことが,根本的な原因だと思います。自分や家族が病にかかり死と直面したときにも,適切な対処行動を想像できずに,ただただ怯えてしまいます。結果として緩和ケアも治療の選択肢から排除してしまう。そうではなくて,緩和ケアは痛みを軽減して,より前向きに生きるためのケアであると,ご理解いただきたいものです。
――OBPの08年度の活動状況をお教えください。
内布 「緩和...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
