MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2007.10.01
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


中村 正人 編
《評 者》横井 良明(岸和田徳洲会病院副院長・循環器科)
尊敬と信頼を得られる血管治療技術としての発展を
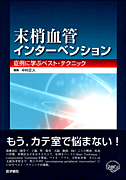 中村正人先生らによる末梢血管インターベンションのガイドブックが刊行された。同書のような末梢血管のインターベンションの症例集はきわめて珍しい。またこの分野が従来は放射線科,血管外科医の領域であったことを考えると,循環器内科医の参入は単なる余技ではなく,PCIの技術を基礎とした,循環器科の新たな血管内治療の試みの書でもある。この書で扱われる末梢血管インターベンションの分野は,鎖骨下動脈,腎動脈,下肢動脈が主に症例とともに解説され,また合併症にも詳細に触れられている。
中村正人先生らによる末梢血管インターベンションのガイドブックが刊行された。同書のような末梢血管のインターベンションの症例集はきわめて珍しい。またこの分野が従来は放射線科,血管外科医の領域であったことを考えると,循環器内科医の参入は単なる余技ではなく,PCIの技術を基礎とした,循環器科の新たな血管内治療の試みの書でもある。この書で扱われる末梢血管インターベンションの分野は,鎖骨下動脈,腎動脈,下肢動脈が主に症例とともに解説され,また合併症にも詳細に触れられている。
鎖骨下動脈のインターベンションでは,川崎友裕先生らが末梢塞栓防止としての簡便な血栓吸引法が具体的に解説されており,明らかなevidenceのある方法とはいえなくても,吸引物質がシースポートから得られていることから,合併症の軽減に役立つことが推察される。
腎動脈のインターベンション,特にステント植え込み術は広く普及してきたが,その安全な施行のためには本書のような基本的テクニックもさることながら,合併症,再狭窄に関する記述に対する十分な知識を備えて治療に臨むことが必須の最低条件として必要である。腎動脈は簡単に見えても難しいことが多く,本書を熟読されたい。
下肢動脈のインターベンションは最も広く行われており,腸骨動脈から膝窩動脈以下までさまざまなテクニック,ワイヤー操作,IVUS,CTO開存方法の記載がなされている。特にparallel wire法,膝窩動脈穿刺などはわが国において進歩している分野であり,そのテクニックは時に必要となる。これが本書の最も特徴といえる。またIVUSと体表面エコーによるインターベンションは今後の末梢インターベンションの新しい方向であり,それがscienceを伴ってきたときには,日本人インターベンショニストから造影剤,放射線をきわめて低減できる,安全な血管内治療の提言がなされることも予感させられる。
ただ,本書は循環器内科医が主で,冠動脈用の装置で画像が撮像されており,画像が不鮮明なのが残念である。循環器領域でもDSA装置の早期普及が望まれる。また膝窩動脈以下,脛骨動脈の穿刺の功罪はいまだ不明であり,単なるCTO再疎通の方法としてではなく,CLI治療全体での位置づけが必要になるのではないだろうか?
いずれにしても,日本の循環器内科医だけでこのような末梢血管インターベンションの実際的な本が生まれてきたのは大変喜ばしい。これはひとえに中村正人先生の企画,努力の賜物と推察するが,新世代の若い先生方が末梢血管インターベンションを新しい方向としてめざしていることも大変好ましい。本書を参考として,末梢インターベンションがPCIの余技としてではなく,他科から尊敬と信頼を得られる血管治療技術として発展していくことを望んでいる。
B5・頁288 定価7,875円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00489-3


原 朋邦,横田 俊一郎,関口 進一郎 編
《評 者》竹村 洋典(三重大附属病院・総合診療部准教授)
思春期患者ケアの醍醐味を感じられる一冊
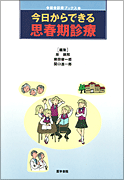 小児の医療は成人の医療の小型版ではないこと,また高齢者の医療は成人の医療と異なっていることは,日本においてもかなり認識されている。では思春期の患者のケアはいかがなものか。小児科医からは大人,内科医を含む成人対象の医師からは小児とみなされていることも少なからずあるのではないか。とくに,思春期の少年少女の疾病が,身体的のみならず,精神的な影響や家族や学校などの社会的な影響があったり,生育歴が大きく関わったりして,診断や治療に苦慮する場合,この年代の患者のケアを苦手とする臨床医は少なくないかもしれない。また思春期の少年少女の扱いが困難で,それゆえに患者-医師関係が形成しにくい場合などは,さらに苦手意識が強くなる。このような苦手意識のある臨床医にとって,この本は,まさしく必読の書といえる。この本を読めば,きっと思春期の患者のケアがおもしろく感じられるであろう。
小児の医療は成人の医療の小型版ではないこと,また高齢者の医療は成人の医療と異なっていることは,日本においてもかなり認識されている。では思春期の患者のケアはいかがなものか。小児科医からは大人,内科医を含む成人対象の医師からは小児とみなされていることも少なからずあるのではないか。とくに,思春期の少年少女の疾病が,身体的のみならず,精神的な影響や家族や学校などの社会的な影響があったり,生育歴が大きく関わったりして,診断や治療に苦慮する場合,この年代の患者のケアを苦手とする臨床医は少なくないかもしれない。また思春期の少年少女の扱いが困難で,それゆえに患者-医師関係が形成しにくい場合などは,さらに苦手意識が強くなる。このような苦手意識のある臨床医にとって,この本は,まさしく必読の書といえる。この本を読めば,きっと思春期の患者のケアがおもしろく感じられるであろう。
最初の総論部分では,思春期患者の診察の特徴や方法をわかりやすく説明している。とくに日本ではあまり触れられない家族志向のケアにも言及していることはすばらしい。総論ではあるが,理屈ばかりの難解さはなく,さすが臨床にどっぷりと浸かっている著者らならではの内容である。内容がすっと身体に入り込んでくる。
次の各論の【思春期に気になる症状・所見】セクションでは,思春期の少年少女が罹りやすい病気を厳選して,その一症例一症例を大切に詳しく説明がなされている。地域の第一線の医師であればきっと遭遇し,そのケアに困ったことがあるであろう症例ばかりであることが嬉しい。「問診のポイント」,「診察のポイント」,「アセスメント」,さらに「マネジメント」に分けたメリハリのある記述は読者を飽きさせない。そこには,日頃,思春期外来を行っている臨床医だからこそ言及できる診療のコツがそこここに記されていて,ワクワクする。「Note」や「メールアドバイス」の内容はそのコツが凝縮されている。各項の最後にまとめられた「Caseの教訓」は,具体的に話すべき会話例や,言い得て妙な表現でドンピシャな内容となっていて,「気になる症状・所見」を整理して記憶にとどめるのに非常に効果的である。随所に図表を多く使用して,かゆいところに手が届くような説明は心地よい。ところどころに書かれている「Clinical Pearls」は,読みものとして最高である。思春期診療に必要なエッセンスをこれだけコンパクトにまとめられたことは,奇跡に近い。
本書は,その対象を小児科医のみ,内科医のみとせずに,広くどの専門診療科の医師にも読みやすくまとめてある。家庭医・総合医である私も,本書を読みながら,外来で診てきた多くの思春期の患者が脳裏に現れ,納得,反省,驚き,たくさんの感情が髣髴してきた。...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
