MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2007.09.17
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


小阪 憲司,田邉 敬貴 著
山鳥 重,彦坂 興秀,河村 満,田邉 敬貴 シリーズ編集
《評 者》葛原 茂樹(国立精神・神経センター武蔵病院長)
認知症学の真髄を絶妙な日本語で躍動的に語った書
 本書は,わが国の臨床認知症学の第一人者である小阪憲司先生と田邉敬貴先生による,認知症症例検討会の活字化である。小阪先生がご自身の症例を,臨床症状,画像所見,病理所見の順に提示し,田邉先生がご自身の経験例を交えながらコメントを加えていくという方式である。アルツハイマー型,レビー小体型,神経原線維型,前頭側頭型,タウ遺伝子変異型,グリアタングル型,基底核・視床変性型,脳血管性の順に,すべての認知症が展開していく。全症例が死後剖検によって確定診断されているので,どんな非定型例であっても,説得力があり納得させられる。逆に,臨床症状と形態画像による診断と,顕微鏡レベルの病理組織学的診断が乖離する例が珍しくないことに驚かされる。症状も画像も肉眼的萎縮所見も典型的ピック病であるのに,病理はアルツハイマー病であったり,その逆であったりの症例の存在を示されると,剖検所見を欠く医学は未完成品であり,剖検なしに医学は進歩しないという主張が説得力を持つ。
本書は,わが国の臨床認知症学の第一人者である小阪憲司先生と田邉敬貴先生による,認知症症例検討会の活字化である。小阪先生がご自身の症例を,臨床症状,画像所見,病理所見の順に提示し,田邉先生がご自身の経験例を交えながらコメントを加えていくという方式である。アルツハイマー型,レビー小体型,神経原線維型,前頭側頭型,タウ遺伝子変異型,グリアタングル型,基底核・視床変性型,脳血管性の順に,すべての認知症が展開していく。全症例が死後剖検によって確定診断されているので,どんな非定型例であっても,説得力があり納得させられる。逆に,臨床症状と形態画像による診断と,顕微鏡レベルの病理組織学的診断が乖離する例が珍しくないことに驚かされる。症状も画像も肉眼的萎縮所見も典型的ピック病であるのに,病理はアルツハイマー病であったり,その逆であったりの症例の存在を示されると,剖検所見を欠く医学は未完成品であり,剖検なしに医学は進歩しないという主張が説得力を持つ。
本書の特徴は,呈示症例が病理診断された確定例であることに加えて,語られている言葉が適切で実に生き生きしていることである。例を挙げよう。アルツハイマー病においては,ニコニコして接触がよく表面的には上手に対応しているように見える症状を,「取り繕い上手」「場合わせ反応上手」,夕方になると落ち着きがなくなり,夕食の準備を始めたり,「家に帰らなくては」と言い出す「夕暮症候群」,きちんとやり遂げられないけれど作業に手を出す「仮性作業」などの表現である。前頭葉型ピック病の,興味が無くなると対話中にも出て行ってしまう「立ち去り行為」,立ち去って居なくなっても,気が向けば元の場所にチャンと戻ってくる「周回」,側頭型ピック病に特有の語義失語=自分ではスラスラしゃべっている簡単な比喩や言葉が,耳から聞いた場合にはまったく理解できないなど,疾患ごとに特徴的臨床症状が,実に絶妙な日本語で躍動的に語られるので,読者は臨床病理カンファレンスに出席しているような気分でどんどんと引き込まれていく。
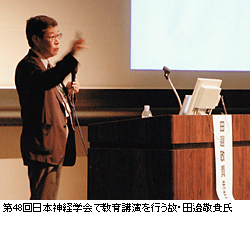 画像も,脳の肉眼所見や顕微鏡学的病理所見と対比させながら,読影のポイントが述べられていく。文中の白黒写真の多くは,口絵のカラー写真に収められているので,絵探しの楽しみもある。随所に「Dr Kosaka's eye」「田邉教授の世界漫遊記」として,疾患にまつわる歴史と研究のエピソードが,楽しい読み物として挿入されていて息抜きになる。
画像も,脳の肉眼所見や顕微鏡学的病理所見と対比させながら,読影のポイントが述べられていく。文中の白黒写真の多くは,口絵のカラー写真に収められているので,絵探しの楽しみもある。随所に「Dr Kosaka's eye」「田邉教授の世界漫遊記」として,疾患にまつわる歴史と研究のエピソードが,楽しい読み物として挿入されていて息抜きになる。
最近の医学と研究者への苦言も語られている。小阪教授の「画像が発達したので,剖検して脳病理を見ることがおろそかになっている」「免疫染色で簡単に答えが出る研究はできるが,ルチーンの染色標本で診断を下せる医師が減っている」という指摘,田邉教授の「神経心理学は決してテストではない,まず患者さんの生の臨床像から学ぶことに原点がある。つまり症候学が基本であり,テストの粗点で表わされるものではない」という鋭い指摘は,昨今の土台軽視への警鐘であろう。
本書は私が2007年会長を務めた第48回日本神経学会総会(5月16-18日)に合わせて,5月15日に発行された。5月18日には田邉教授のライフワークを,教育講演「前頭側頭葉変性症の症候と診たて」としてお話しいただいた。その直後に先生は病に倒れ,7月1日に急逝されたので,奇しくも本書と学会講演は先生の絶筆,最後のご講演となった。認知症学の真髄を二人のトークを通して伝えてくれる本書を,認知症学,神経心理学,神経病理学を学ぶ者の必読書として推薦したい。
A5・頁224 定価3,675円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00336-0


国立がんセンター内科レジデント 編
《評 者》徳田 裕(東海大教授・乳腺内分泌外科)
臨床腫瘍学を志す人に必読・必携の一冊
 臨床腫瘍学に関する情報も湯水のごとく存在しており,authorizeされたguidelineやrecommendationなどを含めてほとんどの情報をonlineで入手することが可能である。しかし,実地医療の現場においては,それぞれを別個に検索し入手しているのでは,診療のスピードについていけない。やはり,基本的な事項については,ある程度まとまったマニュアルが必要である。しかも,実臨床での利用が容易であるためには,ポケット版という携帯性も重要である。そこにも執筆者の配慮が感じられるが,本書はタイトルにも示されているように,対象読者はレジデントであるが,シニアレジデントが中心になって執筆しているのであるからそれももっともなことである。
臨床腫瘍学に関する情報も湯水のごとく存在しており,authorizeされたguidelineやrecommendationなどを含めてほとんどの情報をonlineで入手することが可能である。しかし,実地医療の現場においては,それぞれを別個に検索し入手しているのでは,診療のスピードについていけない。やはり,基本的な事項については,ある程度まとまったマニュアルが必要である。しかも,実臨床での利用が容易であるためには,ポケット版という携帯性も重要である。そこにも執筆者の配慮が感じられるが,本書はタイトルにも示されているように,対象読者はレジデントであるが,シニアレジデントが中心になって執筆しているのであるからそれももっともなことである。
このようなガイドライン的なものは,2-3年ごとの定期的な改訂が求められる。本書は,第4版であり,10年間に4版を重ねているということは,まさに,それを実践しているといっても過言ではない。
Level of evidenceの概念を紹介するとともに,本書の内容にもevidenceの評価を行うという斬新な手法を導入し,また,コミュニケーションスキルや,臨床試験の...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
