第22回日本静脈経腸栄養学会開催
臨床栄養教育の充実に向けて
2007.03.19
臨床栄養教育の充実に向けて
第22回日本静脈経腸栄養学会開催
第22回日本静脈経腸栄養学会が2月8-9日,小林展章会長(愛媛大)のもと,松山市の愛媛県県民文化会館,他にて開催された。今回のメインテーマは「臨床栄養における教育と実践とその評価――次に期待できること」。本紙では,臨床栄養教育と栄養管理実施加算に関するシンポジウムのもようを報告する。
PDCA,研修医教育,NST合宿――臨床栄養教育の実践に学ぶ
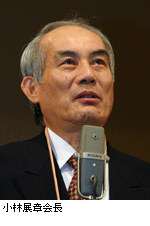 合同シンポジウム「臨床栄養の教育はいかに行われるべきか――新発見に繋げるもの」(座長=川崎病院・井上善文氏,岐阜大・森脇久隆氏)では,各病院の教育実践が報告された。
合同シンポジウム「臨床栄養の教育はいかに行われるべきか――新発見に繋げるもの」(座長=川崎病院・井上善文氏,岐阜大・森脇久隆氏)では,各病院の教育実践が報告された。
若林秀隆氏(済生会横浜市南部病院)は,毎月の勉強会で全職種が順番に講師となることや,一方的な講義ではなくワークショップ形式を主体とする試みを報告した。瀧川洋史氏(松江赤十字病院)は,PDCAサイクル(Plan・Do・Check・Action)に基づくNST活動の実際を紹介。「現場で遭遇する諸問題を試行錯誤しながら解決していく過程によって,教育効果が期待できる」と,継続的質改善を意識した取り組みの利点を述べた。
鷲澤尚宏氏(東邦大大森病院)は,各職種の栄養教育を検証した結果,卒前教育はどの職種も不十分であり,標準化されたテキストも使用されていないと指摘。教育の標準化のためには,関連団体を挙げての働きかけが重要との見解を述べた。
山中英治氏(若草第一病院)は,チュートリアル形式の問題解決型学習の試みを紹介。研修医やコメディカルが講師となり,雰囲気づくりの上手な人をファシリテーターに,臨床経験豊かな人をチューターに置くのがポイントであるとした。
片多史明氏(亀田メディカルセンター)は,年6回のコアレクチャー,各種手技のワークショップなど研修医教育の取り組みを紹介した。研修医に重点を置く理由として,「入院患者の指示出しが多い」「ローテートで各科ベテラン医師との橋渡し役となってくれる」などを挙げ,“ボトムアップによる組織変革”を強調。現在,研修医と初期研修修了者からのNST依頼は全体の7割近くに達すると語った。河野光仁氏(KKR高松病院)は,2004年から毎年4月に実施しているNST合宿を紹介。新メンバーの栄養に対する知識が乏しい場合,任務開始直後からの十分な活動が難しくなるため,集中講義・模擬症例検討会などを初期に行っており,「新メンバーが即戦力として活動できている」と評価した。
林勝次氏(麻生飯塚病院)は,自院における臨床実地修練カリキュラムを紹介した。静脈経腸栄養学会のNST専門療法士の認定申請においては,認定教育施設での40時間の実地...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
