ラインによるケア(6)
上司からの効果的なケアとは
連載
2007.02.26
ストレスマネジメント
その理論と実践
[ 第11回 ラインによるケア(6) 上司からの効果的なケアとは ]
久保田聰美(高知女子大学大学院 健康生活科学研究科 博士課程(後期))
(前回よりつづく)
これまで5回にわたり,ラインマネジャーである師長によるケアの大切さとそのケアが必ずしも効果的に行われていない現実に目を向けて書いてきました。今回は,どうすれば上司からの効果的なケアが実現するのかについて考えてみましょう。
「師長さん,ちょっと相談したいことが」と言われると?
筆者は「ストレスマネジメント」に関する講義の際に,「スタッフから相談を持ちかけられる」場面を設定してロールプレイをよく実施します。その際の師長役の反応でいちばん多いのが,まず「ギクッと」して,「いったい何ごと? まさか退職願い? それともおめでた?」と考えてしまうというものです。相談する側は,「師長さん,ちょっと相談したいことが」と声をかけただけなのに,相談される側がそこまで構えてしまっては,会話自体が成り立たないことさえありそうです。筆者が全国の地域医療支援病院で働く看護師3765名に実施した調査では,「仕事を辞めたいと思うほどのストレスへの対処行動とその効果」について質問した結果(図)は,上司に相談する看護職は意外と少なく(48.2%),それが効果的と評価した割合も他の対処行動よりも低い(53.0%,上位7項目で最低順位)という結果がでました。
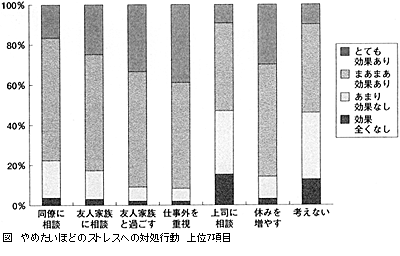
また,先日参加した学会において,「中堅看護師の退職を思い留まらせる看護師長の関わり方」1)という興味深いテーマの研究発表もありました。その結果では,「目標・課題を与える」「放置」「日常的な働きかけ」「時期をみた段階的な働きかけ」等の師長による関わりがありましたが,残念ながら直接退職を思い留まらせることには寄与していなかったようです。では,対象者の看護師が退職を思い留まったのはどんな理由なのでしょうか?「タイミングの喪失」「情緒的つながり」「労力とリスク」「やりがい」「労働改善」等が挙げられていました。具体的には,自分が退職することにより残されたスタッフに迷惑をかけることへの危惧と同時に,「今回は留まったけれど来年は必ず」という潜在的な離職願望は引き続き持っている状態を示しています。一部には「上司である師長が変わったので今はなんとか思い留まっている」という現象まであったようです。
こうした離職希望の看護師が増え続ける中,対応に追われ,疲弊した師長は,相談に来たスタッフへの対応も逃げ腰になり,ますます「辞めたいスタッフ」が増えてしまうという悪循環に陥っているようです。
部署異動時の関わり
一方,師長からスタッフに相談したいこと,話しておきたいことがある場合にはどうでしょうか。師長からスタッフに話すことで,いちばんのトピックスといえば,「異動」に関する話でしょう。医療制度改革の影響により,院内の部署異動の場面もどんどん増えてきています。年度末の人事異動の時期以外にも,病棟再編,休職者,退職者への対応等に伴い...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
この記事の連載
ストレスマネジメント(終了)
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編
外科研修のトリセツ連載 2025.05.05
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
寄稿 2024.10.08
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
