全5回シリーズセミナー
2021カリキュラム編成セミナー【オンライン受講】
2022年3月31日23:59まで配信
- 開催終了
5月17日~(全5回)
お詫びと訂正:税込金額の誤りについて
本セミナーのお申込をご検討いただきありがとうございます。
各種ご案内に「税込50,000円」と記載をしておりましたが金額の訂正がございます。
昨年と同じ本体45,455円+消費税10%での開催となりますが、サイトリニューアルに伴い計算方法が変わり「税込50,001円」となります。
ご案内から金額が変更となり誠に申し訳ございません。
引き続き本セミナーのお申込をご検討いただければ幸甚です。
2022年4月1日より、新たな保健師助産師看護師学校養成所指定規則が適用されます。多くの教育機関では、すでに未来をみすえた看護基礎教育のカリキュラムについて、編成・申請の準備を進められていることと存じます。
加えて、Covid-19の影響により、看護基礎教育においても、ICT導入の活用、また演習・実習のあり方について、多くの再考を求められる状況となっています。
2021年度セミナーでは,昨年行いました「カリキュラム編成準備セミナー」でお寄せいただいたご質問への講師からの回答に加え、改正ポイントの解説からさらに発展的に、ICT活用、シミュレーション教育、臨床判断能力、また新たな教育の枠組みとして試行されている実践例について、全5回にわたって解説いたします。
- 開催終了しました
セミナー概要
-
受講料
1施設:50,001円(税込)
・資料はダウンロード式です。
・5回セットのみのご提供となります。
・1名でお申込みいただくことも可能ですが、受講料は50,001円になります。
・支払い方法:クレジットカード決済・コンビニ決済(現金)
※クレジットカード決済の場合ウェブサイトから領収書の発行が可能です。
コンビニ決済(現金)については、お支払いいただくコンビニ各社様より領収書が発行されます。
※一度ご入金いただいた受講料は、お客様都合でのキャンセル等の場合、お返しいたしかねます。あらかじめご了承ください。
※リアルタイムでのご視聴を希望の方は、開催日3日までにお申し込みおよびご入金を完了してください。
それ以降の場合、ご視聴用URL等の準備が間に合わない可能性がございます。その場合は、アーカイブ版でのご視聴になります。-
日時
アーカイブ配信視聴可能期間
2022年3月31日 (木) 23:59まで
※先生へのご質問はリアルタイム配信でのみ可能です。 -
開催形態
オンライン配信。質疑応答は配信開始日にリアルタイムで受付
-
対象
看護教員
-
配信環境
オンライン環境であれば、PC・タブレット・スマートフォンいずれでも視聴できます。
(申込み前に必ず、以下より動作環境をご確認ください。)
動作環境 -
オンライン受講とは
・オンライン受講は、専用の視聴用URLにアクセスすることで、Web環境下で動画として視聴いただけるプランです。視聴されている方のお顔が講師や他の視聴者から見えることはありません。
・リアルタイム配信では、講師への質疑応答にも参加可能です(進行等の都合により全ての質問にはお答えできない場合もございます)。
・リアルタイムで視聴した場合も、後日アーカイブで再度視聴可能です。
・リアルタイム視聴用URLと、アーカイブ閲覧用URLは同一です。
・リアルタイム視聴用URLは各回開催2日前のお昼までにお送りする予定です。
・セミナーについてご不明な点がある際は、「セミナーについて」または「よくあるご質問」をご確認ください。 -
注意事項
配信の撮影・録画・キャプチャー等および資料の無断転載・複製等は固く禁止いたします。
-
プログラム(予定)
第1回 EXTRA:2020年カリキュラム編成準備セミナーの振り返りとご質問へのご回答
講師:2020年カリキュラム編成準備セミナー講師10名
① 指定規則改正のポイント
山田雅子先生(聖路加国際大学大学院看護学研究科在宅看護学分野・教授)
池西靜江先生(Office Kyo-Shien代表、日本看護学校協議会会長)
任和子先生(京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻・教授)
② 地域:在宅看護論の位置づけと教育内容
河原加代子先生(東京都立大学大学院人間健康科学研究科看護科学域・教授)
水方智子先生(パナソニック健康保険組合立松下看護専門学校・副学校長兼教務部長)
③ ICT活用のための基礎的能力の育成/専門職連携教育の理解と導入
酒井郁子先生(千葉大学大学院看護学研究科 ケア施設看護システム管理学・教授/専門職連携教育研究センター・センター長)
渡辺美保子先生(公益財団法人星総合病院教育研修センター・課長)
④ カリキュラムの評価と開発
藤江康彦先生(東京大学大学院教育学研究科・教授)
⑤ 臨床判断能力に必要な基礎的能力の強化
山内豊明先生(放送大学大学院・教授/名古屋大学・名誉教授)
三浦友理子先生(聖路加国際大学大学院看護学研究科看護教育学・助教)
※アーカイブ配信中。各講師15~30分。
※第1回は講師により、ダウンロード資料のあるご講演とないご講演がございます。
※第1回の内容は、「振り返りとご質問への回答」というテーマで新規に収録したものです。
2020年セミナーの内容を閲覧できるものではございません(2020年セミナーはすでにご覧いただいていることを前提にした内容となります)。
2020年セミナーの閲覧には、別途2020年セミナーのお申込みが必要となります。
2020年セミナーはこちらからお申込みください。
第2回 ICTをどう活用していくか
看護基礎教育においてもICTが加速度的に導入されつつあります。一方で、こうした状況は、Covid-19の流行に伴う緊急対応といった側面が強く、改正指定規則において記載された「看護基礎教育においても、ICT を活用するための基礎的能力を養うこと」の具体的な方法や内容については、今後の重要な課題の1つといえるでしょう。
本回では、あらためて、個々の授業やカリキュラム全体にICTをどのように組み込んでいくか、東京医療保健大学の西村礼子先生にお話しいただくとともに、富士市立看護専門学校の関野恭子先生に、具体的な導入、活用の工夫、課題をお示しいただきます。
アーカイブ配信中
第1部 カリキュラム・授業設計にICTを組み込むポイント:西村礼子先生(東京医療保健大学医療保健学部看護学科・准教授)
第2部 ICT導入・活用の実践例 2020年度1年間の取り組み:関野恭子先生(富士市立看護専門学校専任教員)
第3部 質疑応答
第3回 シミュレーション教育の効果的な活用に向けて
改正指定規則において、専門分野 基礎看護学の留意点にて、シミュレーション等を活用した演習の推進についての文言が追記されました。また、Covid-19流行の影響により、多くの教育機関でシミュレーション教育などの実習代替が行われました。演習・実習の見直しをふくめ、新たなカリキュラムではさらなるシミュレーション教育の導入が急務といえるでしょう。
本回では、領域を超えて学内全体でシミュレーション教育に取り組まれている藤野ユリ子先生に、カリキュラム構築におけるシミュレーション教育導入のポイントと、そうした教育を実現するうえでの組織づくり、また教員育成についてお話しいただきます。
また、埼玉県立高等看護学院におけるシミュレーション教育の実際を出﨑由華先生にご紹介いただきながら、さまざまな組織でシミュレーション教育を実践されている内藤知佐子先生に、取り組みのポイントや実践のためのヒントをお伝えいただきます。
アーカイブ配信中
第1部 カリキュラムへの導入と、シミュレーション教育を担う組織・教員のあり方
:藤野ユリ子先生(福岡女学院看護大学看護学部・教授/シミュレーション教育センター・センター長)
第2部 シミュレーション教育実践のヒント ~埼玉県立高等看護学院の実例から~
:出﨑由華先生(埼玉県立高等看護学院 教員)
・内藤知佐子先生(京都大学大学院医学系研究科先端看護科学コース/先端中核看護科学講座 生活習慣病看護学分野 研究員)
第3部 質疑応答
第4回 新たなカリキュラムに向けて、教育の枠組みをとらえ直す
改正指定規則では、専門分野の実習について「教育効果を高める観点から、各養成所の裁量で領域ごとの実習単位数を一定程度自由に設定できるよう、領域ごとの最低単位数」が示されることとなりました。実習での学びを検討することは、講義・演習・実習の構成もふくめ、何をどのように学ぶか、という看護教育の枠組み自体の検討につながるでしょう。
本回では、「看護基礎教育検討会」構成員として改正にご尽力されてきた池西靜江先生に、看護教育の枠組みの再考についてご提言いただくとともに、イムス横浜国際看護専門学校の佐藤尚治先生、泉佐野泉南医師会看護専門学校の皆様に、新たな枠組みの萌芽といえる、具体的な教育実践をご紹介いただきます。
アーカイブ配信中
第1部 新たなカリキュラムにむけて教育の枠組みをとらえ直す~講義・演習・実習の再構築~:池西靜江先生(Office Kyo-Shien代表)
第2部 第5次カリキュラム改正に向けたプレ実施~プロジェクト3+one~:佐藤尚治先生(イムス横浜国際看護専門学校・副校長)
第3部 コンセプト学習を成人看護学実習Ⅰの学内実習に導入しちゃいました~事例紹介~:西田好江先生(泉佐野泉南医師会看護専門学校 副校長)・泉佐野泉南医師会看護専門学校教員一同
第4部 質疑応答
第5回 看護基礎教育における看護過程と臨床判断の伝え方
カリキュラム改正により,基礎看護学の留意点が「臨床判断能力や看護の基盤となる基礎的理論や基礎的技術、看護の展開方法等を学ぶ内容」と変更され,従来の看護基礎教育での教授内容に加え,臨床判断の基盤となる内容を教授することが求められることになりました。看護基礎教育では,多くの先生方が看護過程を用いて学生に看護の考え方を教授されておられることと思います。本セミナーでは,神奈川県立保健福祉大学の水戸優子先生と渡邉惠先生が取り組んでおられる授業での工夫とあわせ,看護過程を基盤とした臨床判断の教授の考え方・伝え方をお話しいただきます。
リアルタイム配信日:8月28日(土)
13:00~13:05 開演・開会の挨拶
13:05~13:55 基礎看護学で看護過程と併せて臨床判断を伝えるには:水戸優子先生(神奈川県立保健福祉大学・教授)
14:00~14:50 基礎看護学で臨床判断を育む方法:水戸優子先生、渡邉惠先生(神奈川県立保健福祉大学・講師)
14:55~15:25 質疑応答
15:25~15:30 閉会挨拶
EXTRA 2年課程対象
2023年に向けて、2年課程においても、今この時期から現行のカリキュラムを見直し、その評価を始められるとよいのではないでしょうか。本講演では池西靜江先生より、指定規則・指導ガイドライン改正のポイントの解説と共に、2年課程のカリキュラムを考える上で重要となる積み上げ教育の視点や遠隔授業、領域横断といった考え方の例をご紹介いただきます。続いて、2年課程の3校の先生方とのパネルディスカッション方式で、地域や各校の特性を活かしたカリキュラムづくりについてお話しいただきます。
配信開始日:8月2日(月)12:00 ※アーカイブ配信のみ(リアルタイム配信なし)
第1部 講演「指定規則等改正と今、取り組みたいカリキュラム編成」:池西靜江先生(Office Kyo-Shien代表)
第2部 パネルディスカッション:池西靜江先生、恒﨑康子先生(八事看護専門学校・副学校長)、大澤優子先生(水戸市医師会看護専門学院・教務長)、藍原美鈴先生(徳島県立総合看護学校第二看護学科・学科長)
講師

山田 雅子 先生(第1回) 聖路加国際大学大学院看護学研究科在宅看護学分野・教授
1986年聖路加看護大学卒。新卒時に聖路加国際病院公衆衛生看護部で訪問看護に携わる。セコム在宅医療システム株式会社(当時)、セコメディック病院看護部長、厚労省医政局看護課在宅看護専門官を経て2007年より現職。著書に『≪系統看護学講座 統合分野≫在宅看護論(第5版)』(共著、医学書院)等多数。厚労省「看護基礎教育検討会」構成員、「看護師ワーキンググループ」座長。

任 和子 先生(第1回) 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻・教授
京都大学医療技術短大卒。大阪教育大教育学研究科修士課程、京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。京都大学医学部附属病院での8年間にわたる臨床経験の後、京都大学医療技術短大助手、名古屋大学医学部保健学科助教授、滋賀医科大学助教授を経て、2005年京都大学医学部附属病院副看護部長、2007年同病院長補佐・ 看護部長。2011年より現職。

河原 加代子 先生(第1回) 東京都立大学大学院人間健康科学研究科看護科学域・教授
1990年聖路加看護大学卒。聖路加国際病院勤務(内科病棟)を経て、2000年聖路加看護大学大学院看護学研究科博士課程修了(看護学博士)。2001年東京都立保健科学大学助教授(地域看護学)、2005年首都大学東京教授(地域・在宅看護学)を経て、2020年より現職(在宅看護学)。

水方 智子 先生(第1回) パナソニック健康保険組合立松下看護専門学校・副学校長兼教務部長
1985年看護師免許取得、大阪府立千里看護専門学校を経て、パナソニック健康保険組合立松下看護専門学校専任教員、2010年同校副学校長兼教務部長。
学生が看護師として活き活きと働きつづけることをめざし、2019年に同校にてカリキュラム改正を行う。
厚労省「看護師ワーキンググループ」構成員。雑誌『看護教育』にて「松下看護専門学校の挑戦」連載中。

酒井 郁子 先生(第1回) 千葉大学大学院看護学研究科 ケア施設看護システム管理学・教授/専門職連携教育研究センター・センター長
千葉大学看護学部卒業後、千葉県千葉リハビリテーションセンター看護師を経て、千葉県立衛生短期大学助手、その後東京大学大学院医学系研究科保健学専攻にて博士号取得、川崎市立看護短期大学助教授就任後、千葉大学大学院看護学研究科助教授、2007年よりケア施設看護システム管理学教授、2015年専門職連携教育研究センターセンター長兼務、現在に至る。

渡辺 美保子 先生(第1回) 公益財団法人星総合病院教育研修センター・課長
1991年4月公益財団法人星総合病院に看護師として入職、1998年4月ポラリス保健看護学院で専任教員として看護基礎教育に携わる。2011年から3年間、精神科病院で医療安全管理者を任務後、再び2015年4月から同学院の教務主任として着任し、多職種連携教育を企画・運営する。その経験を活かし、日本看護学校協議会の専門職連携教育ガイドライン発行や厚労省「看護師ワーキンググループ」構成員に携わり、2019年度に厚生労働省看護課出向後、2020年より現職に至る。

藤江 康彦 先生(第1回) 東京大学大学院教育学研究科・教授
1997年東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程修了。2000年広島大学大学院教育学研究科博士課程修了。2002年お茶の水女子大学生活科学部講師などを経て、2011年東京大学大学院教育学研究科准教授。2017年より現職。
教育方法学、教育心理学を専門とし、授業におけるコミュニケーションの研究、教育改革を契機とした教師の学習の研究に取り組む。
著書に『小中一貫教育をデザインする―カリキュラム・マネジメント52の疑問』(編著、東洋館出版社)、『学習指導案ガイダンス 看護教育を深める授業づくりの基本伝授』(共著、医学書院)等多数。
厚労省「看護師ワーキンググループ」構成員。

山内 豊明 先生(第1回) 放送大学大学院・教授/名古屋大学・名誉教授
1985年新潟大学医学部医学科卒業。1991年同大学院博士課程修了、医学博士。内科医・神経内科医として通算8年間の臨床経験の後、カリフォルニア大学医学部勤務。1996年ペース大学看護学部卒業。米国・登録看護師免許取得。1997年同大学院看護学修士課程修了。米国・診療看護師(NP:ナース・プラクティショナー)免許取得。1998年ケース・ウェスタン・リザーブ大学看護学部大学院博士課程修了、看護学博士。同年に帰国し、1999年看護師、保健師免許取得。2002年より名古屋大学大学院医学系研究科基礎・臨床看護学講座教授。2018年4月より現職。著書に『フィジカルアセスメントガイドブック 目と手と耳でここまでわかる(第2版)』(単著、医学書院)等多数。

三浦 友理子 先生(第1回) 聖路加国際大学大学院看護学研究科看護教育学・助教
聖路加看護大学卒業後、聖路加国際病院等で臨床実践を行う。その後、聖路加看護大学大学院修士・博士課程を修了し、2013年より現職。大学院生の看護系大学教員としての教員力を向上させる「フューチャー・ナースファカルティ」育成プログラムの開発および運営を行っている。
著書に『臨床判断ティーチングメソッド』(共著、医学書院)。

西村 礼子 先生(第2回) 東京医療保健大学医療保健学部看護学科・准教授
名古屋大学医学部保健学科看護学専攻卒業。東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科博士前期課程・博士後期課程修了。看護学博士。順天堂大学医学部附属順天堂医院看護師勤務、東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科非常勤、東京医科大学医学部看護学科助教を経て、2019年より東京医療保健大学医療保健学部看護学科准教授(基礎看護学領域)、現在に至る。前期・後期博士課程において研究テーマ「ICTを活用した教育が観察場面での看護師の認知プロセスに与える影響」に取り組み、現在はICTを活用したアクティブラーニングを実践しながら、授業設計・教育効果・看護師や看護学生の看護実践能力の検証を行っている。

関野恭子先生(第2回) 富士市立看護専門学校専任教員
静岡県立大学経営情報学部で、行政経営学、情報学、コンピューターの基礎を学んだのち、富士市立看護専門学校看護学科卒業。浜松医科大学付属病院(集中治療室・救急部)、聖隷沼津病院などで経験を積み、現職。人間総合科学大学 看護教員養成コース修了。
富士市立看護専門学校のアクティブラーニング・ICT推進検討会の担当教員として、組織的な協力のもと、教育体制構築に尽力。この取り組みは「富士市事務改善報告・表彰制度」で優秀賞を得た。

藤野ユリ子先生(第3回) 福岡女学院看護大学看護学部・教授/シミュレーション教育センター・センター長
産業医科大学医療技術短期大学卒業後、同大学病院・大学にて勤務。その後聖路加看護大学大学院にて修士課程修了後、九州大学病院看護部勤務、九州大学大学院にて博士(看護学)取得を経て、2014年より福岡女学院看護大学に着任し、2017年より現職。全学でシミュレーション教育を活用した、ワクワクする教育をめざしてシミュレーション教育センターの運営に取り組んでいる。
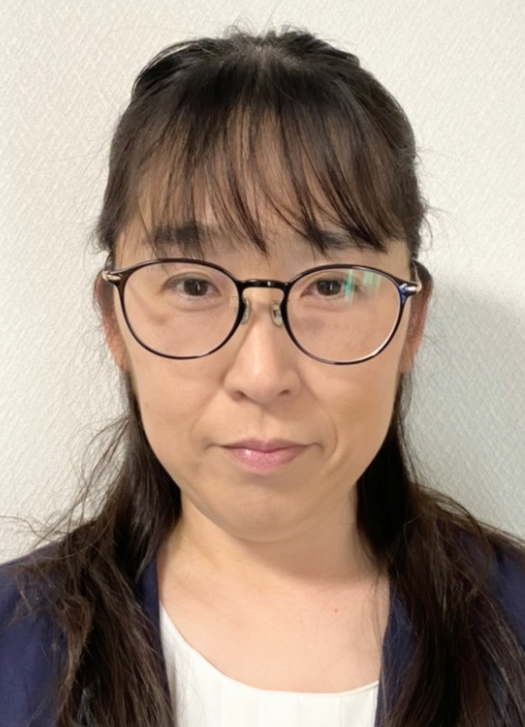
出﨑由華先生(第3回) 埼玉県立高等看護学院 教員
栃木県立衛生福祉大学校看護学科卒業後、那須赤十字病院で勤務する。その後、公益社団法人埼玉県看護協会で勤務し、2019年より埼玉県立高等看護学院で教員として働き始め、基礎看護学担当となる。現在、教員3年目。

内藤 知佐子先生(第3回) 京都大学大学院医学系研究科先端看護科学コース/先端中核看護科学講座 生活習慣病看護学分野 研究員
1999年国際医療福祉大保健学部看護学科卒,東京大学医学部附属病院勤務。2004年新潟県立看護大学助手,2008年同大学大学院看護学修士課程修了。同年,京都大学医学部附属病院勤務,教育担当。2010年同院内の総合臨床教育・研修センター助教。2020年京都大学大学院医学系研究科先端看護科学コース研究員として着任,現在に至る。著書に『シミュレーション教育の効果を高める ファシリテーターSkills&Tips』(共著、医学書院)など。

池西 靜江 先生(第4回、第1回、EXTRA・2年課程) Office Kyo-Shien代表
国立京都病院附属看護助産学院、京都府立保健婦専門学校(現京都府立医科大学)卒。国立京都病院を経て、京都府医師会看護専門学校、京都中央看護保健大学校での勤務の後、2013年にOffice Kyo-Shien開設。2017年より日本看護学校協議会会長を務める。
著書に『看護教育へようこそ』(共著、医学書院)等多数。
厚労省「看護基礎教育検討会」および「看護師ワーキンググループ」「准看護師ワーキンググループ」構成員。

佐藤尚治先生(第4回) イムス横浜国際看護専門学校・副校長
「看護師等養成所におけるカリキュラム改正支援事業」 カリキュラム編成ガイドライン作成委員。
看護教育に従事する以前は、終末期看護に従事。緩和ケア病棟の顧問として出会った、元日大名誉教授の岡安大志先生の「医師になるものには“基礎となる思いやりの資質”が不可欠」という考えが、現在の看護教育の礎になっている。
2008年より板橋中央看護専門学校教員。2019年にイムス横浜国際看護専門学校に移動となり、学校運営の改善と見直しを行なっている。

西田好江先生・泉佐野泉南医師会看護専門学校教員一同(第4回) 泉佐野泉南医師会看護専門学校 副校長
2002年に創設された、大阪府最南端に位置している医師会立の3年課程養成校。豊かな人間性と国際的視野をもって地域医療に貢献できる看護師の育成を、教職員が一丸となって実践している。教職員には、社会福祉士、鍼灸師、在宅看護の専門看護師、海外・他府県・僻地での医療体験者などがおり、3学年合同キャンプやアメリカ海外研修、畑作業や陶芸、関西空港救難訓練など、ユニークなカリキュラムが沢山の個性豊かで明るい学校をめざしている。

水戸優子先生(第5回) 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科・教授
2002年聖路加看護大学博士後期課程修了。1987年北海道大学医学部付属病院に看護師として入職、1993年以降、札幌医科大学、東京都立保健科学大学、神奈川県立保健福祉大学の基礎看護学教員として勤務。2012年4月より現職。著書に『系統看護学講座-専門分野Ⅰ 基礎看護学[4]臨床看護総論』、『新看護学7基礎看護学[2]』、『計画・実施・評価を循環させる授業設計』(いずれも医学書院)等がある。

渡邉惠先生(第5回) 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科・講師
神奈川県立衛生短期大学卒。昭和大学病院看護師を経て、放送大学教養学部卒業、首都大学東京看護教員養成課程修了。東京都内看護専門学校専任教員時代に埼玉県立大学大学院修士課程修了。現在、博士後期課程在学中。2013年神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科(基礎看護学)に着任、現在に至る。看護実践能力の向上を目指した状況基盤型教育の実現を研究テーマとしている。

恒﨑康子先生(EXTRA・2年課程) 八事看護専門学校・副学校長
1980年に愛知県立看護短期大学卒業、看護師免許取得。名古屋第一赤十字病院での臨床経験の後、名古屋市立中央看護専門学校での経験を経て、1995年に八事看護専門学校専任教員、2004年教務部長、2015年より現職。2020年より愛知県看護協会・看護制度委員、2021年より日本看護学校協議会・常任理事を務める。

大澤優子先生(EXTRA・2年課程) 水戸市医師会看護専門学院・教務長
筑波大学附属病院・茨城県立こども病院の臨床経験を経て、看護教員となる。そこで出会った学生たちの『働きながら学ぶ』学び方に触発され、教員の傍ら大学院で修士課程を修了する。教育歴20年を過ぎた現在は、看護教育の楽しさを伝えられるよう後輩教員の育成に注力している。また、#8000(こどもの救急電話相談)の相談事業の経験から、こどもと保護者自身のヘルスプロモーションの発達を気がかりごととして、実践的活動をしている。

藍原美鈴先生(EXTRA・2年課程) 徳島県立総合看護学校第二看護学科・学科長
1985年に国立徳島大学教育学部特別教科(看護)教員養成課程卒業後、愛媛大学医学部附属病院などで看護師として勤務。1997年より徳島県立看護学院において2年課程および2年課程(通信制)、准看護師養成課程で専任教員として勤務。2011年他校と統合して現在の校名(徳島県立総合看護学校)へ変更。2015年同校准看護学科学科長を経て2017年同校第二看護学科学科長となり現在に至る。
- 開催終了しました
本セミナーに関するお問い合わせ
株式会社医学書院 販売・PR部 セミナー担当
TEL:03-3817-5698 / FAX:03-5804-7850
E-mail:pr_web@igaku-shoin.co.jp
お電話でのお問い合わせは平日9:00~12:00、13:00~17:00にお願いいたします。
TEL、FAX、E-mailでのお申し込みは受け付けておりません。