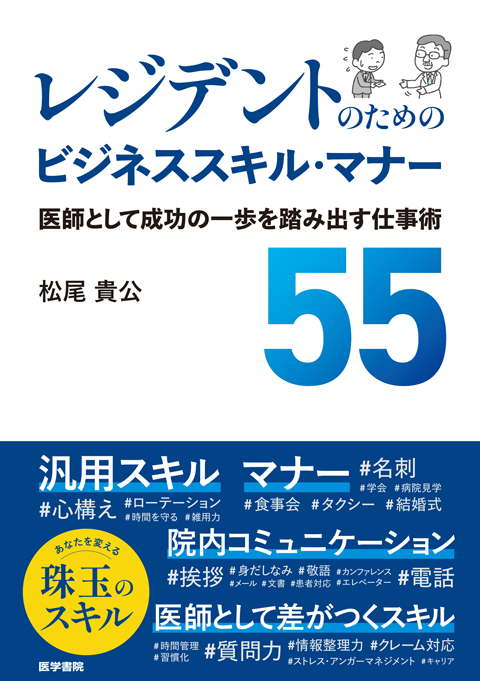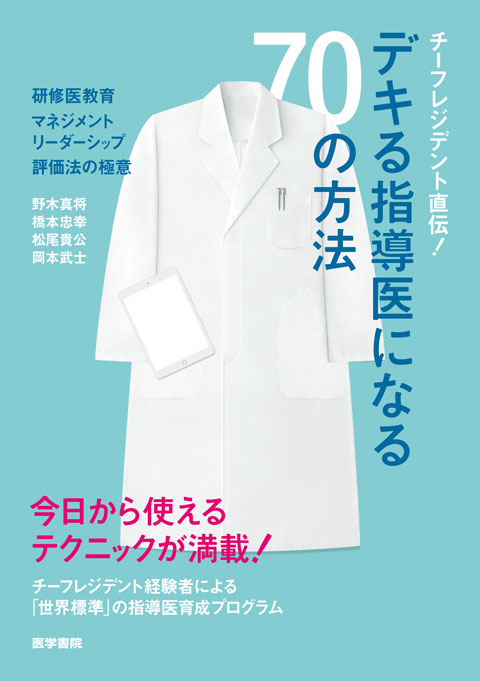- HOME
- 医学界新聞プラス
- 医学界新聞プラス記事一覧
- 2024年
- 医学界新聞プラス [第1回]ローテーションの始まり,ローテーション終了時
医学界新聞プラス
[第1回]ローテーションの始まり,ローテーション終了時
『レジデントのためのビジネススキル・マナー――医師として成功の一歩を踏み出す仕事術55』より
連載 松尾 貴公
2024.03.29
レジデントのためのビジネススキル・マナー
医師として成功の一歩を踏み出す仕事術55
企業に入職した会社員は新人研修で一通りの社会人としての基本的なマナーや仕事術を系統的に学ぶことが多いものの,医師にはそのような機会が乏しいのが現状です。その結果,医療者以外の方と共に仕事をしたり,コミュニケーションをとったりする中で,恥をかく経験やトラブルに至ってしまうケースもあります。そんな状況を防ぐために,社会人として必要な基本的な心得,院内・院外で必要なマナー,医師として必要な仕事術について紹介したのが『レジデントのためのビジネススキル・マナー』です。「医学界新聞プラス」では,本書の中から全3回にわたって内容を一部抜粋して紹介をしていきます。
ローテーションの始まり
ローテーション開始時に習慣づける3つのこと
#準備する
研修医の皆さんの多くは、約1~3か月の単位でさまざまな診療科をローテーションしていくことが一般的です。数週間経ってようやく慣れた頃には次の診療科に移動しなければならない状況が多くあると思います。業務内容を覚えたり、新しい人間関係を構築したりと皆さんにとって精神的にも身体的にも大変なことと思います。このような状況のなか、スムーズな研修を行うためには短い期間でいかに1日でも早くスムーズに仕事ができるようになるかが鍵となります。ここではローテーションを開始するにあたり重要なポイントを3つご紹介します。
既に実践している方も多いと思いますが、まずはローテーション先の情報を仕入れることが重要です。研修を始める前に、すでに該当のローテーションを経験したことのある同期や先輩から事前に準備すべき資料や教材、お作法、コツについての情報を集めることが重要です。日々の業務の流れやカルテの書き方(テンプレートがあれば譲ってもらうことも検討)、日々の回診やカンファレンスで必ず聞かれるポイントや、プレゼンテーション中に必ず含めるべき項目などです。病院や診療科によっては事前に資料として準備されているところもあると思いますが、生の情報をできる限り自分で収集することが大事です。なかには先輩から引き継がれる、指導医対策を含めたローテーションを乗り越えるための秘訣などが盛り込まれたサバイバルガイドなどが存在する施設もあります。

社会人として当たり前のことにもかかわらず意外に実行しない人が多いのが、ローテーションを行う診療科や病棟スタッフに対しての事前挨拶です。指導医の立場からすると、次の週から誰がローテーションを開始するかは気になるものです。直接足を運んで挨拶を述べるのが理想的ですが、難しい場合は院内のメールがあれば前の週の半ばから後半にかけてローテーション開始の挨拶のメールを送りましょう。もちろん病院によって規模や習慣が異なるため、この事前挨拶が必ずしも一般化できるとは思いません。それぞれの病院の文化に合わせながら、皆さんの施設においてどのように事前挨拶ができるかを今一度考えてみましょう。
また、看護師を含めたコメディカルへのスタッフに対しても同様です。指導医への挨拶はできたとしても、このコメディカルへの挨拶は差がつくポイントです。研修医の皆さんが日ごろの病棟や外来業務で頻繁に接することの多い看護師やコメディカルスタッフと良好なコミュニケーションをとることは、大変重要な要素です。できるだけスタッフの名前と顔をいち早く覚えることに努め、「看護師さん」ではなく名前で呼べるようになることを心がけましょう。検査の追加や薬剤の変更などを伝えたり何か頼みごとをしたりする場面が多くあると思いますが、より受け入れてもらえるかどうかに名前で呼ぶことが少なからず影響を与えるかもしれません。皆さんのなかには忙しいからそんな時間はないと思う人もいるかもしれません。しかし、どれだけ忙しくても短時間で良いので次のローテーションに移る前にこの小さな努力を心がけてみてください。次第に習慣化され、特に意識しなくても当たり前にできるようになるはずです。事前挨拶により上級医にはやる気を見せることができ、また看護師やコメディカルスタッフには顔と名前を早く覚えてもらい信頼を勝ち取るためのきっかけになるはずです。開始初日からスムーズな仕事を行うことができるよう、この事前挨拶は社会人として是非身に付けてもらいたいスキルの1つです。

各ローテーションでは、毎回開始時に終了時までの目標、週単位での中期目標、日々の短期目標を立てることをお勧めします。
ローテーション終了までに達成したい目標を立てることはもちろんのこと、定められた期間を細かく分解して、振り返りの機会を定期的に設けることでより有意義なローテーションにすることができます。週の目標では1週間の中でどのようなことができたか、またどのようなことをもっと改善することができるかを振り返り、次の週につなげます。そして日々の短期目標では、その日に自分がどのようなことを心がけたいか、どのようなことを学習したいかなどをイメージします。例えば、「今日は担当患者さんの現在の問題である低カリウム血症についてしっかり把握し、人に説明できるようになろう」「カンファレンスで必ず質問してみよう」「爽やかな挨拶を心がけよう」など、何でも結構です。できれば自分が目に見えるように記録に残し、後に述べる振り返りがしやすいようにしましょう。
ローテーション終了時
ここで差がつく終了時にやるべき3つのこと
#振り返る
次に、ローテーション終了時に心がけることについてです。1つの区切りでほっと一安心している人も多いと思います。あるいは次に回る診療科の準備のことで頭がいっぱいになる人も少なくないと思います。ここでは、ローテーション終了時にやると差がつく2つの重要なポイントについて解説します。
自分が経験できた手技や症例に関してはできるだけ小まめに記録していくようにします。後でまとめて記入しようと思っても記憶は曖昧になります。自分の経験した手技や症例を可視化することで、自分のマイルストーンを逐次確認することができます。経験できなかったものに関しては、必要に応じて早めに指導医と相談することでその後の別のローテーション期間に補填するなど、対処できる可能性があります。症例の振り返りは、後々同様の症例に会ったときに必ず役に立ちます。また、日々の疑問点で解決できていなかった内容があれば時間が許す限り早めに消化するようにしましょう。さらには、自分なりにローテーション中にうまくできた点やもう少し改善することができた点をできるだけ思い起こし、記録として書き留めるようにします。この自分なりの細かな振り返りは、自分を成長させるうえでの最も重要なコツの1つであると言っても過言ではありません。
1つのローテーションが終わったら、必ず指導医に自分からフィードバックをもらうようにします。研修施設ではフィードバックがなされることが必須になっていますが、忙しい臨床現場で診療科や施設によっては形式的なものだけで実際にされないこともあります。研修医として周囲からのフィードバックは成長のための絶好の機会です。学生だったこれまでと違い、社会人として自分に対するフィードバックを受ける機会は自然に減ってきます。年次が上がるにつれ、自分に対して注意してくれたり改善のための提案をしてくれたりする人は必然的に少なくなるのです。自分では気づかない改善点を修正するために、他人から客観的に評価してもらうことはとても重要なことです。皆さんの施設でフィードバックがなされない場合は、能動的に指導医にフィードバックの場を設けてもらえるように依頼しましょう。自分の良かった点や改善すべき点などの振り返りを行うことにより、次のローテーションに向けてまたひとつ前に進むことができます。

前の項で述べたローテーション前の指導医やコメディカルスタッフへの挨拶と同様に、ローテーション後にも挨拶を必ず行うようにします。その診療科での研修が終わったとしても、その後のローテーションでもお世話になる機会は必ずあるはずです。看護師さんが研修医の評価表を記入する際に「あれ? この研修医、もうローテーション終了したんだっけ?」とつぶやいている場面に出くわしたことが何度かあります。お世話になったスタッフには必ず感謝の意を述べましょう。社会人として当たり前のことですが、意外に適切になされない場面も少なからず見受けられるため、実は差がつくポイントです。
レジデントのためのビジネススキル・マナー
医師として成功の一歩を踏み出す仕事術55
あなたを変える、医師としてのビジネススキルとマナー集
<内容紹介>なかなか教えてもらえない、院内でのコミュニケーション、電話対応、メールの時短方法、学会での自分の売り込み方、カンファレンスでの質問ポイントなど、忙しい研修でも無駄なくソツなくこなせるビジネススキル集。白衣やスーツの着こなし、名刺の渡し方、正しい敬語や目上の人とのタクシーの乗り方など、マナーについても詳しく学べます。一生使える、医師として成長するためのビジネススキルとマナーを集めました!
目次はこちらから
タグキーワード
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。