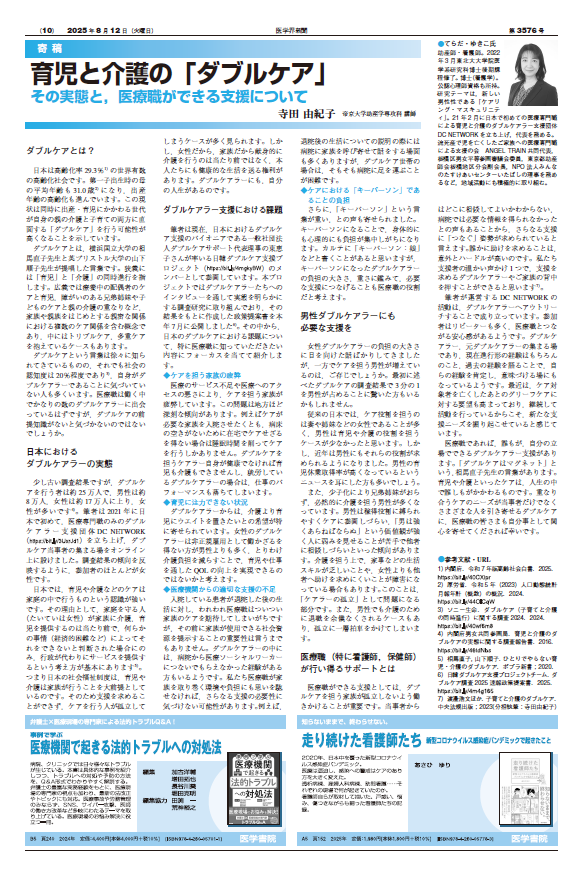育児と介護の「ダブルケア」
その実態と,医療職ができる支援について
寄稿 寺田 由紀子
2025.08.12 医学界新聞:第3576号より
ダブルケアとは?
日本は高齢化率29.3%1)の世界有数の高齢化社会です。第一子出生時の母の平均年齢も31.0歳2)になり,出産年齢の高齢化も進んでいます。この現状は同時に出産・育児にかかわる世代が自身の親の介護と子育ての両方に直面する「ダブルケア」を行う可能性が高くなることを示しています。
ダブルケアとは,横浜国立大学の相馬直子先生と英ブリストル大学の山下順子先生が提唱した言葉です。狭義には「育児」と「介護」の同時進行を指します。広義では療養中の配偶者のケアと育児,障がいのある兄弟姉妹や子どものケアと親の介護の重なりなど,家族や親族をはじめとする親密な関係における複数のケア関係を含む概念であり,中にはトリプルケア,多重ケアを抱えているケースもあります。
ダブルケアという言葉は徐々に知られてきているものの,それでも社会の認知度は20%程度であり3),自身がダブルケアラーであることに気づいていない人も多くいます。医療職は働く中でかなりの数のダブルケアラーに出会っているはずですが,ダブルケアの前提知識がないと気づかないのではないでしょうか。
日本におけるダブルケアラーの実態
少し古い調査結果ですが,ダブルケアを行う者は約25万人で,男性は約8万人,女性は約17万人に上り,女性が多いです4)。筆者は2021年に日本で初めて,医療専門職のみのダブルケアラー支援団体DC NETWORKを立ち上げ,ダブルケア当事者の集まる場をオンライン上に設けました。調査結果の傾向を反映するように,参加者のほとんどが女性です。
日本では,育児や介護などのケアは家庭の中で行うものという認識が強いです。その理由として,家庭を守る人(たいていは女性)が家族に介護,育児を提供するのは当たり前で,何らかの事情(経済的困難など)によってそれをできないと判断された場合にのみ,行政が代わりにサービスを提供するという考え方が基本にあります5)。つまり日本の社会福祉制度は,育児や介護は家族が行うことを大前提としているのです。そのため支援を求めることができず,ケアを行う人が孤立してしまうケースが多く見られます。しかし,女性だから,家族だから献身的に介護を行うのは当たり前ではなく,本人たちにも健康的な生活を送る権利があります。ダブルケアラーにも,自分の人生があるのです。
ダブルケアラー支援における課題
筆者は現在,日本におけるダブルケア支援のパイオニアである一般社団法人ダブルケアサポート代表理事の東恵子さんが率いる日韓ダブルケア支援プロジェクトのメンバーとして参画しています。本プロジェクトではダブルケアラーたちへのインタビューを通して実態を明らかにする調査研究に取り組んでおり,その結果をもとに作成した政策提案書を本年7月に公開しました6)。その中から,日本のダブルケアにおける課題について,特に医療職に知っていただきたい内容にフォーカスを当てて紹介します。
◆ケアを担う家族の疲弊
医療のサービス不足や医療へのアクセスの悪さにより,ケアを担う家族が疲弊しています。この問題は地方ほど深刻な傾向があります。例えばケアが必要な家族を入院させたくとも,病床の空きがないために在宅でケアせざるを得ない場合は睡眠時間を削ってケアを行うしかありません。ダブルケアを担うケアラー自身が健康でなければ育児も介護もできませんし,就労しているダブルケアラーの場合は,仕事のパフォーマンスも落ちてしまいます。
◆育児に注力できない状況
ダブルケアラーからは,介護より育児にウエイトを置きたいとの希望が特に寄せられています。女性のダブルケアラーは非正規雇用として働かざるを得ない方が男性よりも多く,とりわけ介護負担を減らすことで,育児や仕事を通したQOLの向上を実現できるのではないかと考えます。
◆医療機関からの適切な支援の不足
入院している患者が退院した後の生活に対し,われわれ医療職はついつい家族のケアを期待してしまいがちですが,その前に家族が使用できる社会資源を提示することの重要性は言うまでもありません。ダブルケアラーの中には,病院から医療ソーシャルワーカーにつないでもらえなかった経験がある方もいるようです。私たち医療職が家族を取り巻く環境や負担にも思いを馳せなければ,さらなる支援の必要性に気づけない可能性があります。例えば,退院後の生活についての説明の際には病院に家族を呼び寄せて話をする場面も多くありますが,ダブルケア世帯の場合は,そもそも病院に足を運ぶことが困難です。
◆ケアにおける「キーパーソン」であることの負担
さらに,「キーパーソン」という言葉が重い,との声も寄せられました。キーパーソンになることで,身体的にも心理的にも負担が集中しがちになります。カルテに「キーパーソン:娘」などと書くことがあると思いますが,キーパーソンになったダブルケアラーの負担の大きさ,重さに鑑みて,必要な支援につなげることも医療職の役割だと考えます。
男性ダブルケアラーにも必要な支援を
女性ダブルケアラーの負担の大きさに目を向けた話ばかりしてきましたが,一方でケアを担う男性が増えているのは,ご存じでしょうか。最初に述べたダブルケアの調査結果で3分の1を男性が占めることに驚いた方もいるかもしれません。
従来の日本では,ケア役割を担うのは妻や姉妹などの女性であることが多く,男性は育児や介護の役割を担うケースが少なかったと思います。しかし,近年は男性にもそれらの役割が求められるようになりました。男性の育児休業取得率が高くなっているというニュースを耳にした方も多いでしょう。
また,少子化により兄弟姉妹がおらず,必然的に介護を担う男性が多くなっています。男性は稼得役割に縛られやすくケアに参画しづらい,「男は強くあらねばならぬ」という価値観が強く人に弱みを見せることが苦手で他者に相談しづらいといった傾向があります。介護を担う上で,家事などの生活スキルが乏しいことや,女性よりも他者へ助けを求めにくいことが障害になっている場合もあります。このことは,「ケアラーの孤立」として問題になる部分です。また,男性でも介護のために退職を余儀なくされるケースもあり,孤立に一層拍車をかけてしまいます。
医療職(特に看護師,保健師)が行い得るサポートとは
医療職ができる支援としては,ダブルケアを担う家族が孤立しないよう働きかけることが重要です。当事者からはどこに相談してよいかわからない,病院では必要な情報を得られなかったとの声もあることから,さらなる支援に「つなぐ」姿勢が求められていると言えます。誰かに助けを求めることは,意外とハードルが高いのです。私たち支援者の温かい声かけ1つで,支援を求めるダブルケアラーやご家族の背中を押すことができると思います7)。
筆者が運営するDC NETWORKの活動は,ダブルケアラーへアウトリーチすることで成り立っています。参加者はリピーターも多く,医療職とつながる安心感があるようです。ダブルケアラー,元ダブルケアラーの集まる場であり,現在進行形の経験はもちろんのこと,過去の経験を語ることで,自らの経験を肯定し,意味づける場にもなっているようです。最近は,ケア対象者を亡くしたあとのグリーフケアに対する要望も高まっており,継続して活動を行っているからこそ,新たな支援ニーズを掘り起こせていると感じています。
医療職であれば,誰もが,自分の立場でできるダブルケアラー支援があります。「ダブルケアはマグネット」という,相馬直子先生の言葉があります。育児や介護といったケアは,人生の中で誰しもがかかわるものです。重なり合うケアのニーズが当事者だけでなくさまざまな人を引き寄せるダブルケアに,医療職の皆さまも自分事として関心を寄せてくだされば幸いです。
参考文献・URL
1)内閣府.令和7年版高齢社会白書.2025.
2)厚労省.令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況.2024.
3)ソニー生命.ダブルケア(子育てと介護の同時進行)に関する調査2024.2024.
4)内閣府男女共同参画局.育児と介護のダブルケアの実態に関する調査報告書.2016.
5)相馬直子,山下順子.ひとりでやらない育児・介護のダブルケア.ポプラ新書;2020.
6)日韓ダブルケア支援プロジェクトチーム.ダブルケア調査2025速報政策提案書.2025.
7)渡邉浩文ほか.子育てと介護のダブルケア.中央法規出版;2023(分担執筆:寺田由紀子)

寺田 由紀子(てらだ・ゆきこ)氏 帝京大学助産学専攻科 講師
助産師・看護師。2022年3月東北大大学院医学系研究科博士後期課程修了。博士(看護学)。公認心理師資格も所持。研究テーマは,新しい男性性である「ケアリング・マスキュリニティ」。21年2月に日本で初めての医療専門職による育児と介護のダブルケアラー支援団体DC NETWORKを立ち上げ,代表を務める。流死産で児を亡くしたご家族への医療専門職による支援の会ANGEL TRAIN共同代表,板橋区男女平等参画審議会委員,東京都助産師会板橋地区分会副会長,NPO法人みんなのたすけあいセンターいたばしの理事を務めるなど,地域活動にも積極的に取り組む。
いま話題の記事
-
取材記事 2026.02.10
-
あせらないためのER呼吸管理トレーニング
[ミッション4] HFNC vs. NPPV――病態生理に基づいて使い分けよう連載 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。