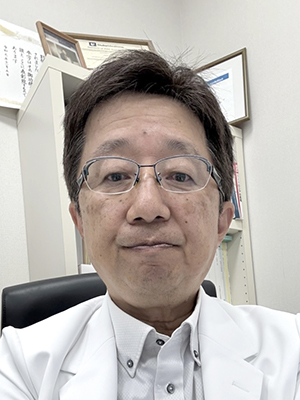院内を駆け回るための18の“Tips”
寄稿 辰巳 陽一,丸山 和希,門村 将太,木村 泰,松田 奈々,平野 匠
2025.05.13 医学界新聞:第3573号より

医師としての輝かしいキャリアの第一歩を踏み出した新研修医の皆さんにとって,この1か月間はどのような日々だったでしょうか。一人でできることが少しずつ増え,「楽しい」と感じる機会もきっと多くなってきたことでしょう。しかし,時には困難も待ち受けているのが人生です。壁にぶつかった時,悩んだ時は,頼りになる先輩医師や同期,そして院内にいる専門職の方々からの知恵を借りることも一手です。
そこで今回は,研修医とのかかわりの深い各部門の専門家6人に,病院内で活躍する研修医になるための“Tips(ヒント)”を3つずつ伝授してもらいました。
Tip 1 「私の言っていること,わかりますか?」――それ,患者さんにも自分にも聞いてみて
医師として説明の機会が増えてくると,「わかりましたか?」と形式的に尋ねてしまっている自分に,いつか気づく日がやってきます。しかしインフォームド・コンセント(informed consent:IC)の本質は,「インフォーム(説明)」ではなく,「コンセント(理解と納得)」にあります。伝わっていなければ,説明したことにはなりません。つまり,医療者はICを「する」ことはできず,ICを患者から「もらう」,あるいは「してもらう」しかすべがありません。
そもそも,医師自身が十分に咀嚼できていない専門用語を,患者が理解できるはずもありません。例えば「挿管」という言葉です。医療者にとっては日常用語でも,患者からすれば,ニュースで度々話題に上がる密入国者の強制「送還」や,「AとBの『相関』関係」という意味しか思い浮かばないかもしれません。
人は,一度わかってしまうと,わからなかったときのことを忘れてしまう生き物です。「同意書にサインをもらうこと」がゴールではなく,「どう理解されましたか?」と確かめることがICの本質です。その第一歩として,自分が使っている言葉を丁寧に解きほぐし,相手に伝わる言葉に言い換える練習から始めてみましょう。
Tip 2 「私って,心理的に安全ですか?」――沈黙はチームの空気を映す鏡
「こんなこと聞いたら怒られるかも」「これって言わないほうがいいかな」。そんなふうに感じたことがあれば,そこには心理的に安全でない“小骨”が喉にひっかかっているかもしれません。心理的安全性は「仲がいいこと」ではなく,「間違いや疑問を口にできる,ダメ出しできる空気」です。研修医が「わからない」と言えない環境では,小さなミス,小さな掛け違えが大きな事故につながります。「安心して発言できる場所に自分はいるだろうか」。そう自身に問いかけることから,安全なチームづくりが始まります。そして,誰かの一言に耳を傾ける余白を持つことが,次の仲間の声を引き出します。
Tip 3 「掃除のおっちゃんに,あいさつできますか?」――あなたの無意識が,チームの意識をつくります
清掃スタッフや警備員,事務職員など,病院にはさまざまな職種がかかわっています。彼らは医療行為こそ行いませんが,日々の現場を支える“見えないチーム”の一員であり,時に最初に異変に気づく人でもあります。「おはようございます」と自然に声をかけられるかどうかは,あなたがその人を“人として”見ているかどうかの証(あかし)です。そして,その関係性が,いざという時に声をかけてもらえるか,見過ごされるかを左右します。
この問いは,「今しているか」「意識すればできるか」ではなく,「当たり前のようにできるか」を問うものです。医師になって1 年もすると,天上界に居る自分に気づく方もおられることでしょう。肩書きや役割を越えて,誰にでも敬意を払えること。それが医療者としての土台であり,安全文化の第一歩です。医師以外に,周りにどんな人たちがいて,どんな風に支えてくれているのか,その空気を感じることができるアンテナを,まず組み立ててみてはどうでしょう?
●新研修医への一言メッセージ
説明は,伝わり理解してもらい初めて説明になります。安心は,声に出して言えたときに初めて生まれ,敬意は,声をかけて相手を知ったその瞬間に生まれます。そして,医療は,人と人のあいだにあります。これから訪れる忙しい日々の中でも,どうか,言葉の行方を忘れずに。応援しています。
Tip 1 返事は「YES」か「ハイ」か「喜んで」
日常の研修,診療業務に加え,とにかくさまざまなタスクが研修医の皆さんには集まってきます。カンファレンスでの症例提示,他職種向けのレクチャー,学会発表の準備や合同説明会での病院紹介,実習生がいればその対応,施設によっては患者さんや地域住民向けの講演などです。無理難題やオーバーワークな状況でも引き受けろとは言いませんが,頼まれごとは積極的に引き受けていただきたいと思います。
他者に向けて話す=アウトプットの経験は,自身の学習のきっかけや知識の整理につながります。また頼まれごとを引き受けることで信頼の獲得にもつながり,その後の研修にも良い影響を及ぼすことでしょう。全ては「経験」です。雑用と思えばそれまでですし,どうせやるのであれば,与えられたタスクを自身で「意味のあるもの」に昇華させ,前向きに取り組んでみましょう。
Tip 2 その街の「住民」になってみよう
今の病院は,何を理由に選びましたか? 指導体制や研修環境,専門研修を見据えて,あるいは2次募集で……と,さまざまな理由があると思います。
多くの人が2年間(たすきがけでは1年間),その街で診療することになります。病院は基本的に具合の悪くなった患者さんが来るのを「待つ」ところです。ぜひ自分の足で街に繰り出し,その医療圏や生活圏を多角的に見てみましょう。医学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版)1)でも「総合的に患者・生活者をみる姿勢」が問われています。スーパーや日用品店はどこにあるか,バスや電車など公共交通機関はどんな状況か,地域の産業や名産は何か,観光スポットは何があるのか。多くの場合,患者さんや他職種のスタッフはその地域の「先輩」です。そうした方々との共通言語が増えることは信頼関係の構築につながりますし,患者さんの生活を具体的にイメージできることが診療面で役立つこともあるでしょう。
Tip 3 もう1人の「自分」を用意しよう
就職してしばらくの間は,慣れない環境と医師としての責任,命に向き合うプレッシャーで心身ともに疲弊することと思います。一説では研修医の20%が抑うつ状態を呈し,1%が研修中断を経験しているといった報告もあります2)。
働き方改革もあり,研修医だからといって24時間365日呼び出されるという時代ではなくなったと思いますが,社会人1年目では息抜きや休みの取り方・使い方で苦慮する研修医も多いのではないでしょうか。ON/OFFの切り替えは精神衛生を保つために重要なものの,その方法は誰かが教えてくれるものではありません。自分なりにリフレッシュするための方法や場所を用意しておきましょう。読書が趣味なら落ち着ける公園やカフェを探したり,お酒が趣味ならお気に入りの居酒屋やバーを見つけたり,運動が趣味なら地域のサークルやクラブチームに参加したりと,「自分を解放」できる方法や場所をぜひ見つけてください。
●新研修医への一言メッセージ
研修担当事務は,研修医の皆さんが無事に研修を修了できるようにサポートすることが任務です。仕事でも,プライベートでも,何か困ったことがあればまずは相談してみてください。
参考文献・URL
1)文科省.医学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版).2022.
2)瀬尾恵美子,他.初期研修における研修医のうつ状態とストレス要因,緩和要因に関する全国調査――必修化開始直後との比較.医教育.2017;48(2):71-7.
Tip 1 人は誰でも間違える。だから処方する前にDI を確認しましょう
『To Err is Human』(人は誰でも間違える)はご存じの方も多いと思います。これは,米国医療の質委員会・医学研究所がまとめた医療事故に関する報告です1)。この報告の中には,医薬品過誤の事象も含まれています。こうした医療事故が発生するのは米国だけに限りません。日本でも研修医が処方あるいは投与した医薬品過誤による死亡事例が報告されています。例えば持参薬にあった関節リウマチに用いるメトトレキサートの用法用量の指示誤り(週1回のところ連日投与)2),脊髄造影を行う際にイオトロランを尿路に用いる造影剤アミドトリゾ酸と取り違え投与3)した死亡事例があります。これらの事例は,事前確認さえ十分に行っていれば防げた「予防可能な薬剤有害事象」と考えられています。
では,どうすれば医薬品...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。