外科志望者の裾野拡大をめざして
田尻 達郎氏に聞く
インタビュー 田尻 達郎
2025.02.11 医学界新聞:第3570号より
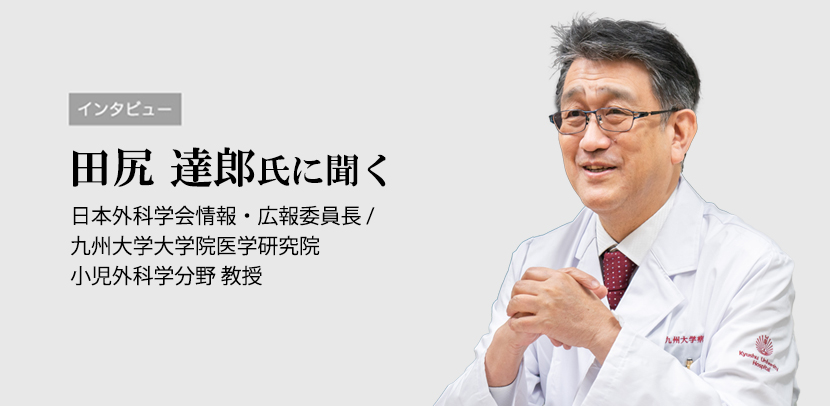
外科医不足を何とかしたい――。外科医の魅力を伝えるため日本外科学会は2024年11月17日(日)に日本科学未来館(東京都江東区)で高校生以下を対象にした市民講座「オペスル――ほんもので学ぼう! 触れる手術室」を開催した。ガウンを着用しての手技体験や外科医とのトークイベントなどが催され,親子連れも含めた639人が来場し,成功裏に終わった。しかしながら,1つの疑問が残る。それは,なぜ参加対象を高校生以下にしたのかという点だ。市民講座を企画・運営した日本外科学会情報・広報委員長の田尻氏に,狙いと今後の展望を聞いた。
――日本外科学会主催の市民講座「オペスル――ほんもので学ぼう! 触れる手術室」は,高校生以下を対象に外科医の魅力を伝えるという新たな取り組みで,多くのメディアの注目を集めました。高校生以下を参加対象とした理由を教えてください。
田尻 外科医不足を何とかしたいという思いがあるからです。外科は3K(きつい,汚い,危険)と言われ敬遠される傾向にあり,なり手不足の問題が顕在化しています。手術によって人を助けるという仕事の魅力とやりがいを伝え,将来外科医になりたいと思うきっかけづくりになればと考え企画しました。たとえ参加してくれた子どもたちが外科医とならなくても,このイベントをきっかけに「医療者になることが将来の夢」と思ってもらえれば,十分に成功だと考えています。
――参加された子どもたちの反応はいかがだったのでしょうか。
田尻 非常に好評でした。本物の電気メスで豚肉を切ったり,縫合体験したりするコーナーは特に人気があり,何度も並ぶ子がいました(写真)。現役の外科医から直接教えてもらえることもあり,楽しむだけでなく真剣に取り組む子どもが多かったのも印象的でした。また,外科医は子どもたちに怖いイメージを持たれることが多いので,リアルな外科医の姿を知ってもらえたのも良かったと振り返っています。

学会員も大切に新たな取り組みを
田尻 今回は主に一般のお子さんを対象に開催しましたが,将来的には日本外科学会の定期学術集会と併催して,学術集会に参加される外科医のお子さんにも多く参加してもらえるイベントができないかと考えています。
――医師をめざす子どもの親が医師であるケースが多いと言われていることも背景にあるのでしょうか。
田尻 そういった狙いもありますが,外科医として働く学会員を大切にしたいという気持ちが大きいです。働き方改革も進んでいますが,帰宅が遅かったり,休日に家を空けていたりと家族に負担をかけている面が少なからずあるはずです。全国各地で毎年開催される定期学術集会と併催することで,旅行も兼ねて家族で参加したり,お子さんに手技を教えられたりと家族サービスにもつながるのではと考えています。
――普段とは異なる格好良い親の姿も見せられそうですね。
田尻 ええ。仕事を知ってもらうことは,子どものみならず親にとっても重要だと考えています。子どもから「医師をめざしたいけれども,親と一緒の外科医...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
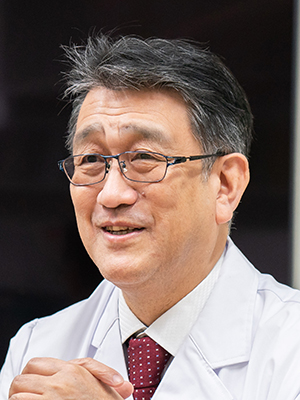
田尻 達郎(たじり・たつろう)氏 日本外科学会情報・広報委員長 / 九州大学大学院医学研究院小児外科学分野 教授
1988年九大卒業後,同大病院小児外科,福岡市立こども病院等で小児外科研修を積む。その後,米フィラデルフィアこども病院研究員,九大小児外科准教授,京都府立医大小児外科教授などを経て21年より現職。19~21年日本小児外科学会理事長。20年より日本外科学会理事を務め,同年より情報・広報委員長を担当している。編書に『標準小児外科学 第8版』(医学書院)。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
