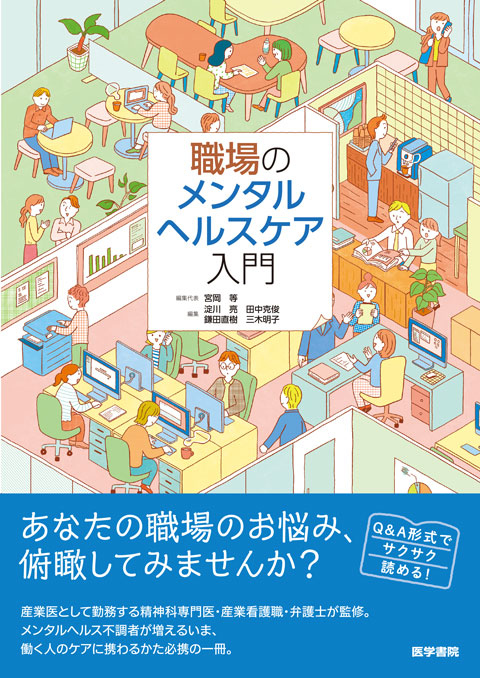治療と就労の両立に医療機関は何ができるか
対談・座談会 安藤明美,遠藤源樹,錦戸典子,海永千怜
2024.09.10 医学界新聞(通常号):第3565号より

メンタルヘルスの問題やがん,脳卒中,心筋梗塞といった病の治療と職業生活の維持を両立させるために,一人ひとりに適した支援が求められる。一方で,こうした支援を求める方は年々増加し,扱うべき問題も多様化していることから,中心的な存在として従来対応に当たってきた産業医だけではカバーできなくなってきた。また,全労働者の約6割が産業医・産業保健師の在籍しない中小企業で働いていることも,この問題を複雑化させる要因となっている。本紙では,総合診療医として長年従事し,産業医としても活躍する安藤氏を司会に,両立支援を研究する産業医の遠藤氏,産業保健師の錦戸氏,総合診療医の海永氏による座談会から両立支援のヒントを探った。
安藤 近年,労働者人口の減少に伴い,治療と就労の両立支援の重要性が増しています。両立支援においては企業の産業医や産業保健師が中心的な役割を担っているものの,全労働者の約6割が産業医・産業保健師の在籍しない中小企業で働いています。こうした現状の中,一人ひとりに適した両立支援を行うことは産業医・産業保健師のみならず全ての医療者に求められています。
私はプライマリ・ケア医と産業医それぞれの経験を生かした産業保健活動を行っています。本日は産業医の遠藤先生,産業保健師の錦戸先生に加え,臨床医の立場から総合診療科で働く海永先生に参加していただき,治療と仕事の両立で悩む方々にどのような手を差し伸べていけるのかをお話しできればと思っています。
身近な疾患こそ両立支援が求められる
安藤 はじめに,臨床医の素直な気持ちとして海永先生は両立支援にどのようなイメージを持たれていますか。
海永 「職場での健康診断の結果,紹介状を持って2次精査で来られた方を診療するもの」というイメージを持っていました。自覚症状もなく,受診するよう言われて来られる方もいます。血圧や栄養面など予防的な指導をするものの,再診時に変化が見られないことも多く,職場の産業医や産業保健師と連携しなければならないとの思いを抱えています。産業医や産業保健師がいない中小企業で働く人は多いので,受け持ちの患者が仕事を続けられるようかかわる必要性を感じていますが,十分にできていません。
錦戸 産業医や産業保健師が企業にいると,患者本人の背景や価値観を聞きながら,仕事を続けるための予防も含めた支援をじっくり行えます。ただ,治療を主とする臨床医が就労に関する側面まで対応することの難しさはとても理解できます。
安藤 私は“働く世代”の最初の相談先となり得るプライマリ・ケア医は両立支援の受け皿になると考えています。遠藤先生はこれまで多くの両立支援研究をされています。両立支援の現状と,プライマリ・ケア医のかかわりについてどうお考えでしょうか。
遠藤 がん領域では両立支援が進んでいますが,それでもまだ必要とする方に行き届いているとは言えません。両立支援の対象となる疾患で最も多いのがメンタルヘルス不調で,次いでがん,脳卒中,心筋梗塞となります。がんに関しては,がん診療連携拠点病院が全国に約400か所あり,院内のがん相談支援センターなどで両立支援に取り組みやすい環境があります。
一方で,メンタルヘルス不調は大病院でなくクリニックで治療することが多く,また他の疾患であれば初めは大病院で治療しても徐々に地域移行していくので,組織的に取り組んだ経験のないプライマリ・ケア医はどのように両立支援すれば良いのか手探りなのかもしれません。
安藤 同感です。認知症,心不全,糖尿病といったプライマリ・ケア医にとって身近な疾患こそ両立支援が求められ,積極的にかかわることが期待されますので,関心を持ってもらいたいです。
多職種で協働し,診療報酬も取りにいく
安藤 しかし,両立支援の全てを医師だけで行うには無理があります。どのような職種や組織と連携すれば,多くの医療機関で両立支援が活性化されるでしょうか。
海永 プライマリに患者とかかわる機会の多い看護師との連携は想像が付きやすいです。加えて,入院中はセラピストの方々も日常的に復職を視野に入れたかかわりをしていただいているので,一緒に取り組んでいけるのではないでしょうか。看護師やセラピストとは日ごろから「お家に帰るために」どうすれば良いかを話し合っています。この話し合いに「働くこと」をプラスできないかと思いました。
錦戸 医療ソーシャルワーカー(MSW)の方がいらっしゃる病院ではMSWを中心に両立支援することも欠かせません。現在,治療と就労の両立への指導や情報提供をすることで「療養・就労両立支援指導料」として診療報酬加算を算定できますので,医師だけでなく看護師やMSWとも連携して病院規模で取り組めると良いですね。
遠藤 両立支援が進むがん相談支援センターでの経験でも,看護師やMSWとの連携があって成り立つことを実感しました。両立支援が機能している病院の中には看護師やMSWが医局会などに顔を出して多職種間での信頼関係を構築した上で,積極的に就労支援の連携を取り,診療報酬も取りにいこうとされている施設もあります。
海永 両立支援によって診療報酬加算を算定できること,恥ずかしながら今まで知りませんでした。
安藤 いえ,知らない先生が大半だと思います。メンタルヘルス不調はまだ加算の対象ではないのですが,内科系の疾患や若年性認知症では加算が付きました。臨床医の皆さんは治療や診療のガイドライン,診療報酬改定に関する情報は関心も高く知る機会が多いのですが,両立支援に関する情報は触れる機会も少なく,今日を機に知っていただけてうれしいです。
錦戸 治療と就労の両立支援について情報提供する際,全国47都道府県にある産業保健総合支援センター(https://bit.ly/4dEggjB)では保健師が会社に訪問し個別調整する支援を行っていることや,勤務する会社が協会けんぽに加入していればそこの保健指導も頼りにできることも知ってほしいですね。ぜひ患者本人にその情報を伝え,会社経由で産業保健総合支援センターへ相談することを勧めてもらえれば,その人に適した働き方や職場としての適切な配慮の方法を見いだせるのではないでしょうか。
海永 患者本人に産業保健総合支援センターへの相談を提案するのが正しい紹介ルートなのでしょうか。医療機関から産業保健総合支援センターへ直接「この人の支援をお願いします」と紹介でき...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

安藤 明美(あんどう・あけみ)氏 安藤労働衛生コンサルタント事務所
2001年島根大卒業後,岡大病院,生協浮間診療所で総合診療医として従事する。13年に労働衛生コンサルタント資格を取得する。その後中小~大企業の嘱託産業医を経て,22年より現職。現在は,IT企業の統括産業医を務め,家庭医療,社会医学などの幅広い医学知識を生かした産業保健活動を行う。編集に『プライマリ・ケア医のための 働く世代のみかた』(南山堂)。

遠藤 源樹(えんどう・もとき)氏 東京産業医学情報センター 所長
2003年産業医大卒業後,JR東京総合病院を経て,05年こころとからだの元氣プラザ,08年NTT東日本専属産業医を務める。14年より東京女子医大助教,17年順大准教授を経て,24年より現職。人事院健康専門委員,東京都がん対策推進協議会専門委員,北里大非常勤講師等を兼務。専門は産業医学。著書に『治療と就労の両立支援ガイダンス』(労務行政)など多数。土屋健三郎記念産業医学推進賞,日本医師会医学研究奨励賞など受賞歴多数。

錦戸 典子(にしきど・のりこ)氏 東海大学医学部看護学科 客員教授
産業保健師として10年間IT企業に勤務後,1997年聖路加看護大(当時)准教授,2002年東大准教授,04年東海大教授を経て24年より現職。産業医や産業保健師がいない中小企業で働く方の健康確保をテーマに,治療と仕事の両立支援等の研究を行う。編著に『企業のためのがん就労支援マニュアル――病気になっても働き続けることができる職場づくり』(労働調査会)ほか。

海永 千怜(かいなが・ちさと)氏 東京北医療センター総合診療科
2014年長崎大卒業後,佐久総合病院/佐久医療センターで初期研修,地域医療振興協会「地域医療のススメ」で後期研修を修了し20年より現職。家庭医療専門医,総合内科専門医。臨床医として急性期病棟/外来診療に従事するなかで,患者さんを「まるごと診る」には,「具体的にどんな働き方や仕事をしているか」への想像力が大切であることを実感している。自身もタイムマネジメントやワークライフバランスにもがく働き世代。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
寄稿 2025.11.11
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。