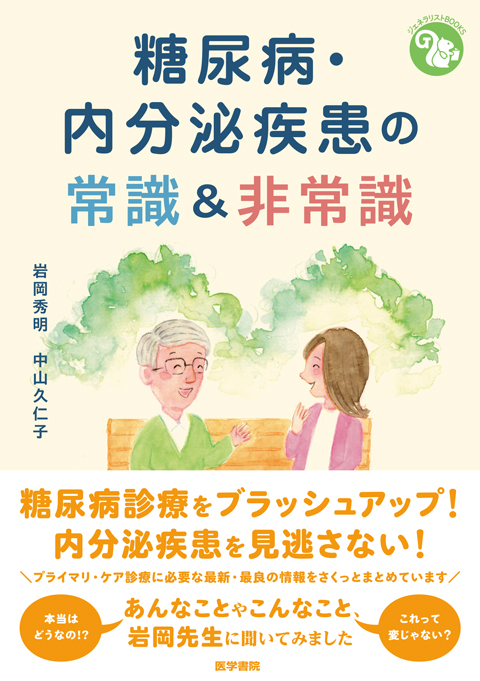糖尿病診療のプライマリ・ケア
今,求められる役割とは
岩岡 秀明氏に聞く
インタビュー 岩岡秀明
2024.06.11 医学界新聞(通常号):第3562号より
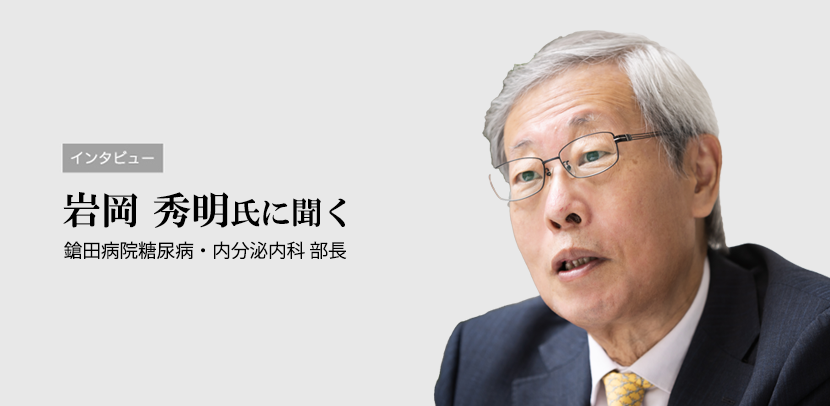
プライマリ・ケア領域において糖尿病は頻回に遭遇する疾患である。近年は新薬の増加を背景に治療の選択肢が広がっており,患者ごとに最適な選択を見極めるには情報のアップデートがますます欠かせなくなっている。生活習慣の改善から薬物療法の実践までを幅広く,長期的に管理していかなくてはならない糖尿病診療において,非専門医がおさえておくべきポイントを『糖尿病・内分泌疾患の常識&非常識』(医学書院)にまとめた岩岡氏に話を聞いた。
治療薬の多様化がもたらした糖尿病診療の進歩
――岩岡先生のキャリア初期から現在まで,糖尿病の治療はどのように変わってきたのでしょうか。
岩岡 私が初期研修医だった1980年代半ばはヒトインスリン製剤が認可されたばかりでした。それまではウシ由来のインスリン製剤が主に使用され,経口薬の選択肢はスルホニル尿素薬(以下,SU薬)しかありません。とにかく血糖値が下がればそれでいいと考えられており,糖尿病診療全体の黎明期だったと言えます。
その後,α-グルコシダーゼ阻害薬やグリニド薬,DPP-4阻害薬など,次々に新しい薬が出てきました。現在はGLP-1受容体作動薬とSGLT2阻害薬の2つが大きな存在感を放つ時代です。治療薬の多様化によりインスリンの分泌促進やインスリン抵抗性の改善がさまざまなかたちで可能になっただけでなく,インスリン以外のアプローチによって血糖の改善が図れるようにもなりました。薬物療法が進歩したおかげで,糖尿病を治せるとまでは言えずとも悪化させずに管理することが可能になり,患者の平均寿命も糖尿病を持たない場合とほとんど変わらない時代になってきた1)ことは非常に感慨深いです。
一方で,患者の状態とそれに応じた治療法の組み合わせは無数にありますから,糖尿病の専門医でなければ判断に迷ってしまうケースも出てきています。
――プライマリ・ケアの現場において糖尿病は頻繁に出合う疾患です。日常診療ではどのようなことを心がけるべきなのでしょう。
岩岡 「低血糖を起こさない」「体重を増やさない」「心血管イベントを抑える」という治療薬選択時の三大条件を踏まえ,年齢や体重,血糖値の状態を含め患者の状態を丁寧に分析し,慎重に検討することです。血糖値を下げるためにとりあえずSU薬を処方する医師もいますが,副作用で低血糖に陥ることもあり,服薬自体に恐怖感を抱いた患者が治療をドロップアウトしてしまう可能性もあります。
糖尿病は患者数が非常に多く,専門医が全ての患者を診ることは現実的ではありません。プライマリ・ケア医がこうしたポイントを押さえて診療できると重篤な症状の発生や急変に至るリスクは大幅に下がりますから,専門医はマ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

岩岡 秀明(いわおか・ひであき)氏 鎗田病院糖尿病・内分泌内科 部長
1981年千葉大医学部卒。千葉大病院第二内科(当時),成田赤十字病院内科,船橋市立医療センター代謝内科などを経て,2023年より現職。日本糖尿病学会専門医・研修指導医,日本内分泌学会専門医,日本内科学会総合内科専門医。著書に『糖尿病・内分泌疾患の常識&非常識』(医学書院)ほか多数。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。