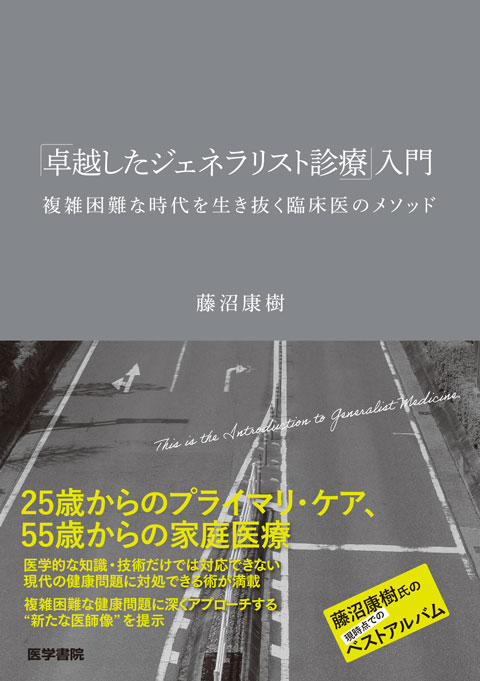ジェネラリストであるということ
対談・座談会 藤沼康樹,岩浪悟
2024.06.11 医学界新聞(通常号):第3562号より

現代日本のプライマリ・ケア医は,医学的な知識・経験だけではハンドリングの難しい問題に直面することが増えています。そこで本紙では,新刊『「卓越したジェネラリスト診療」入門――複雑困難な時代を生き抜く臨床医のメソッド』(医学書院)にて,複雑困難な健康問題に深くアプローチする“新たな医師像”を提示する藤沼氏,総合病院の救急・総合診療科で働く傍ら,地域のクリニックでの外来診療,在宅医療まで幅広く患者を診る岩浪氏による対談を企画。ジェネラリストとして患者にかかわることの諸相を探りました。
藤沼 僕は医師になってもう40年。今振り返ると最初に出会った指導医が非常にジェネラルな考え方の持ち主で,その影響もあって家庭医療,プライマリ・ケアと呼ばれる領域で活動してきました。岩浪先生はどういった経緯で総合診療を専門とすることになったのですか。
岩浪 初期研修での学びを深めたいと考え,教育で有名な都立多摩総合医療センターの門を叩いたところ,入職後に開設された総合診療科に誘っていただいたためです。総合診療を選んだ背景には,初期研修医の頃に覚えた違和感の影響もあるかもしれません。教科書で学んだ症状,例えば心筋梗塞を臨床で目にした際に沸き立つ同期を横目に,目の前の患者さんは苦しんでいるのに……と乗り切れない自分がいました。
藤沼 学習した医学的知識を患者を通じて確認することへの違和感は,僕も共感するところです。今回の書籍タイトルにも入っている「卓越したジェネラリスト診療」とも関連する話ですが,医学的な知には普遍性があります。例えば心筋梗塞を起こした場合の心電図は,AさんとBさんで基本的に同じだと考えます。だから学んだ知識を目の前の患者に適用できるわけです。しかし,実際に診療を通して患者に向き合う中で,そこにある個別性にもまた気付く瞬間があります。同じ心不全でもAさんとBさんで生活の中での困り事が異なることは当然あり得ます。
「卓越したジェネラリスト診療」は,患者の個別性に寄せた診療ができることを指します。僕はそうした診療がジェネラリストの本道だと考え,そのための方法論の言語化を書籍内で試みました。個別性が特に大事になってくるのは,一見何が問題かわからない未分化な健康問題を抱えた事例,複数次元の問題が複雑に絡み合った困難事例,多疾患併存などの場合です。
私生活に浸み込んでくるジェネラリストという仕事
岩浪 個別性というものを考えたとき,医療者がかかわったことで患者,周囲の人間を含めて何か“いい感じ”になっていると感じることがあります。
藤沼 “いい感じ”,確かにありますね。well-beingとは異なるし対応する英語は思いつかないけれど,いい具合に進んでいるなとの実感はよくわかります。
岩浪 そうした“いい感じ”も含んだ個別の医療に関しては,標準化も言語化もなされず,まだまだ“自分流”で行われている部分が大きいのではないかと感じています。
藤沼 そう思います。医師の資質や性格,価値観といったものが,個別性に寄せた診療にはダイレクトに反映されますから。しかし,言語化しないと人に伝えられないし,知として蓄積することもできないです。個別性の高いケアを,単に「性格の良い先生」に還元したくないですね。
岩浪 一方で,サイエンスとしての医学,普遍的な知は,随分標準化が進みました。現在では多くの医師が研修医の頃から身に付けられるスキルとして定着してきた感があります。
藤沼 EBMのムーヴメントに関しては,福井次矢先生がDavid Sackettの『Clinical Epidemiology』を日本で紹介したのが1980年代の後半で,それ以来ガイドラインの整備を含めた医療の標準化は大きく進みました。その一方で,近年は個別性にもスポットが当たるようになってきた流れかと思います。
岩浪 総合診療以外の分野が“自分流”になりにくいのは,科学的な側面が比較的大きくて,標準化がなされているからです。職業人として,そうした専門性を高めたくなる気持ちも理解できる部分があります。
藤沼 専門医制度はよくできたシステムで,それにのっとって訓練を積むと,いわゆるやぶ医者にはなりにくいんです(笑)。例えば,年々手技が下手になる消化器内視鏡専門医の存在は想定しにくい。ある特定の領域の仕事をエクスクルーシブに行うということは,特定の医学的知を何度も繰り返し適用するということで,毎日の仕事が生涯学習になっているわけです。
岩浪 何でも相談に乗りますよと看板を掲げるジェネラリストはその反対で,非常にインクルーシブな仕事である分,何がやってくるのか予想できない大変さがあります。
藤沼 仕事と私生活を完全に切り離すことが難しいとも言えます。診療にやって来た患者とのコミュニケーションが,医療者である以前の,一個の人間としての自分の人生に影響を及ぼすわけです。それを面白いと思えるかが,ジェネラリストに向いているかどうかの分水嶺なのかもしれません。
岩浪 わかります。自分自身が置かれた状況と同じ地平にある悩みを抱えた人が患者として目の前にやって来て,身につまされることもしばしばです。夫婦問題で悩んでいる方から「先生はそんなことなさらないでしょうけれど,うちの夫はこうなんです」と相談されたときに,「いや,私もそういうときがあります……」と返さざるを得ない場面もありました。臨床で伺う話と自分の生活が容易に接続するといいますか。
藤沼 自身の人間としての時間的蓄積,人生経験のようなものが生きる場面もままありますね。定年退職した夫が自宅に長時間いることで夫婦関係が悪化することはライフサイクル論上普遍的な現象として指摘されていますが,「しがみついてでも仕事をしたほうが良いです」なんてアドバイスは,若い医師だとしづらいでしょうから。
でも,先ほどの例で,自分も例外ではないと岩浪先生が謙虚に話している間に,患者がじっと話を聞いているだけかというと実はそうではなくて,患者の中では無意識下にリフレクションのサイクルが回っていて,自分なりの気付きを得ているものです。医師が患者の話を謙虚に聞いて,そこから学んだり自分の話をしたりすること自体にヒーリング効果があるのではと僕は思います。医師側の...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

藤沼 康樹(ふじぬま・やすき)氏 生協浮間診療所 所長 / 医療福祉生協連家庭医療学開発センター センター長
1983年新潟大医学部卒。東京都老人医療センター(当時),生協浮間診療所所長などを経て,2006年より現職。15~17年千葉大大学院専門職連携教育研究センター特任講師。専門は家庭医療学,医学教育。近著に『「卓越したジェネラリスト診療」入門――複雑困難な時代を生き抜く臨床医のメソッド』(医学書院)。

岩浪 悟(いわなみ・さとる)氏 都立多摩総合医療センター 救急・総合診療科
2014年山梨大医学部卒。16年社会医療法人社団順江会江東病院にて初期臨床研修を行う。東京都立多摩総合医療センター内科後期研修プログラムを修了後,20年より現職。その他,武蔵国分寺公園クリニック,ファミリーケアクリニック吉祥寺,吉祥寺南病院と地域の一次,二次,三次医療機関で勤務し,地域を縦断した働き方をめざしている。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第1回]心エコーレポートの見方をざっくり教えてください
『循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』より連載 2024.04.26
-
医学界新聞プラス
千葉大学看護学部 創立50周年記念式典開催取材記事 2025.12.22
-
医学界新聞プラス
[第1回]PPI(プロトンポンプ阻害薬)の副作用で下痢が発現する理由は? 機序は?
『医薬品情報のひきだし』より連載 2022.07.29
-
医学界新聞プラス
[第2回]アセトアミノフェン経口製剤(カロナールⓇ)は 空腹時に服薬することが可能か?
『医薬品情報のひきだし』より連載 2022.08.05
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
最新の記事
-
厳しさや大量の課題は本当に必要か?
教育現場の「当たり前」を問い直す対談・座談会 2025.12.09
-
対談・座談会 2025.12.09
-
対談・座談会 2025.12.09
-
インタビュー 2025.12.09
-
ロボット,AIとARが拓く看護・在宅ケア
安全はテクノロジーに,安心は人に寄稿 2025.12.09
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。