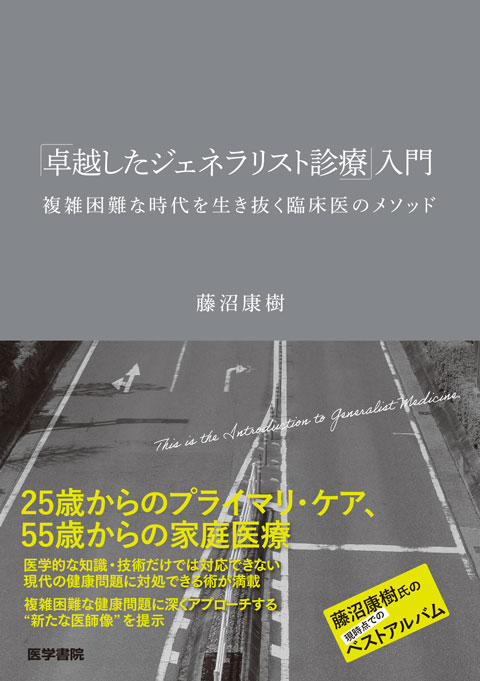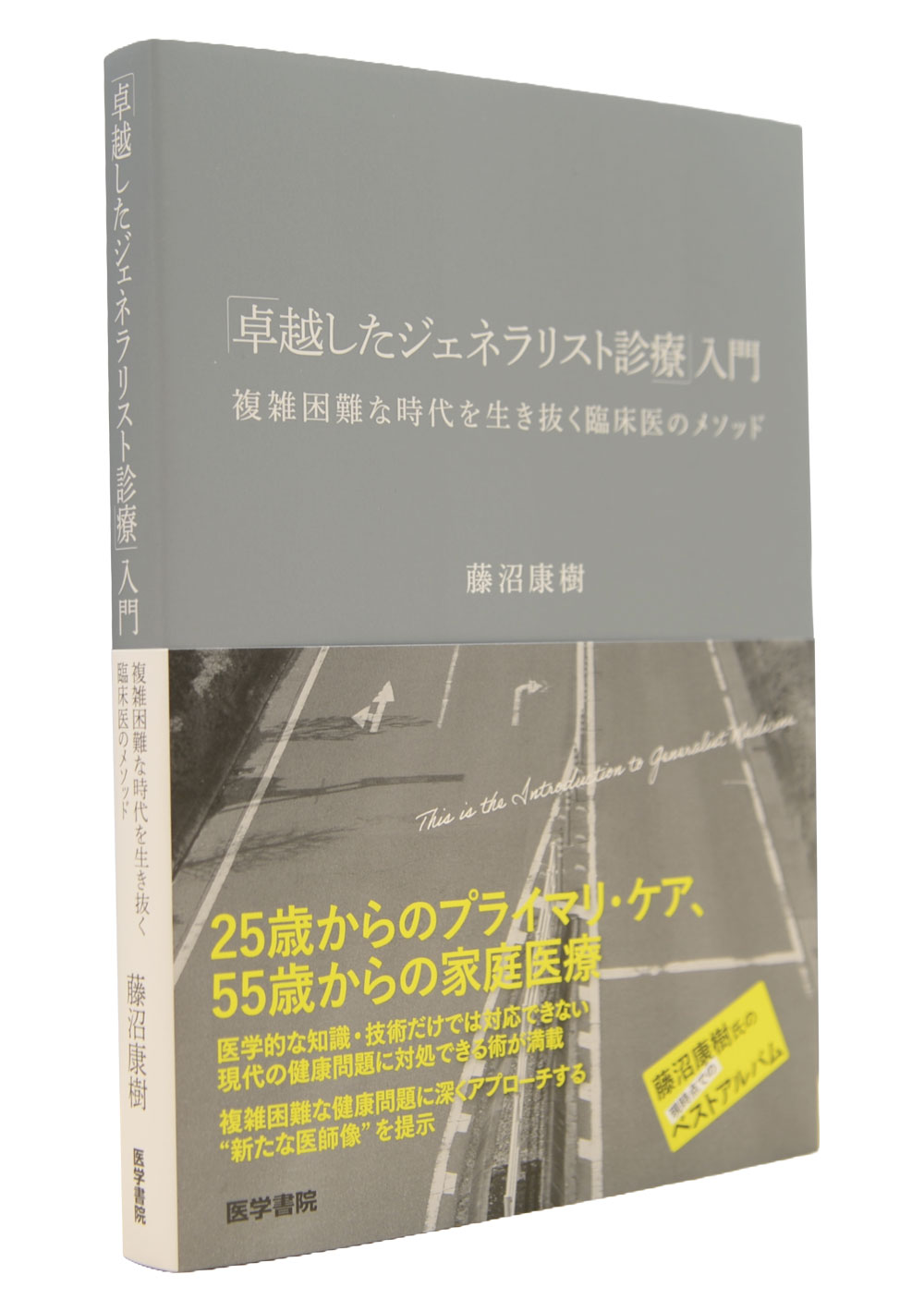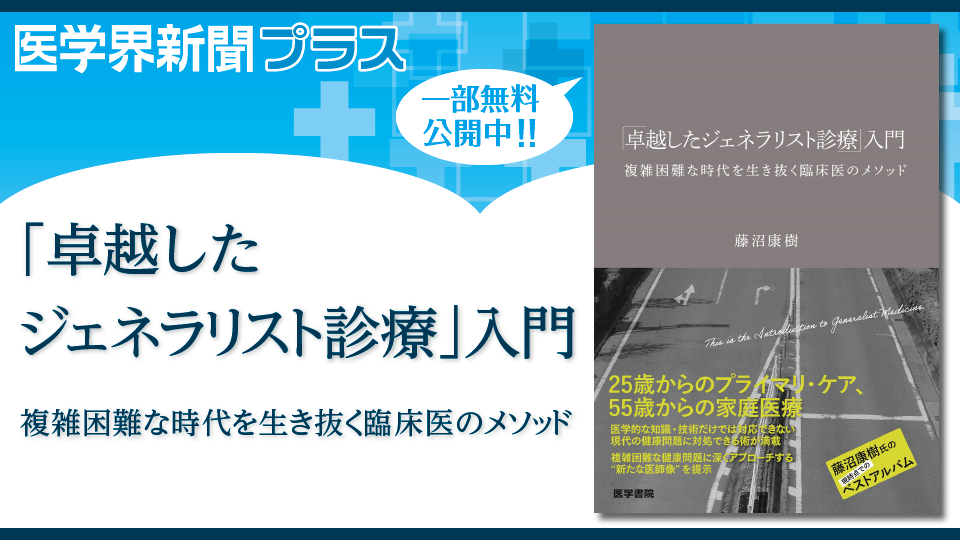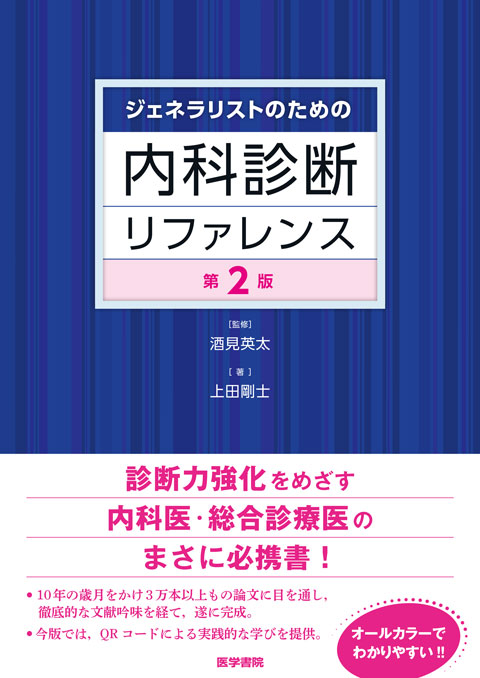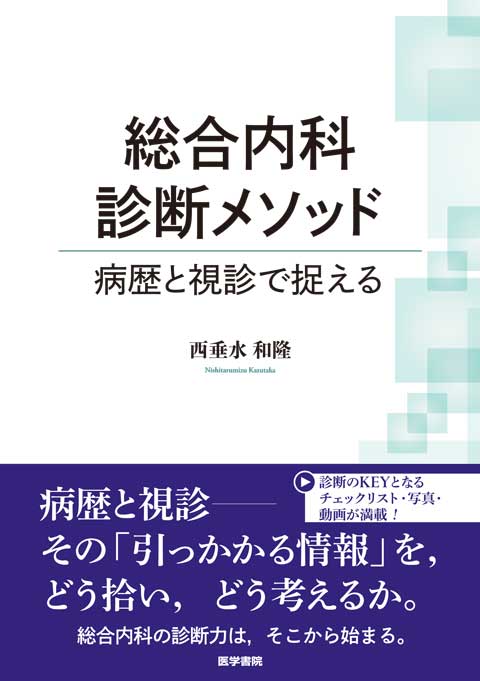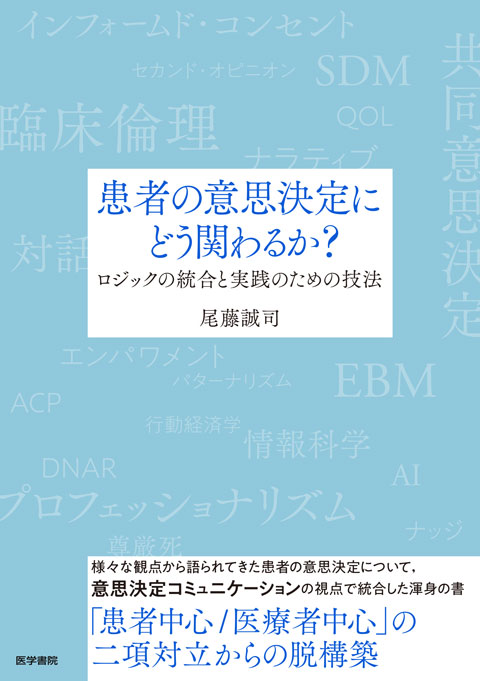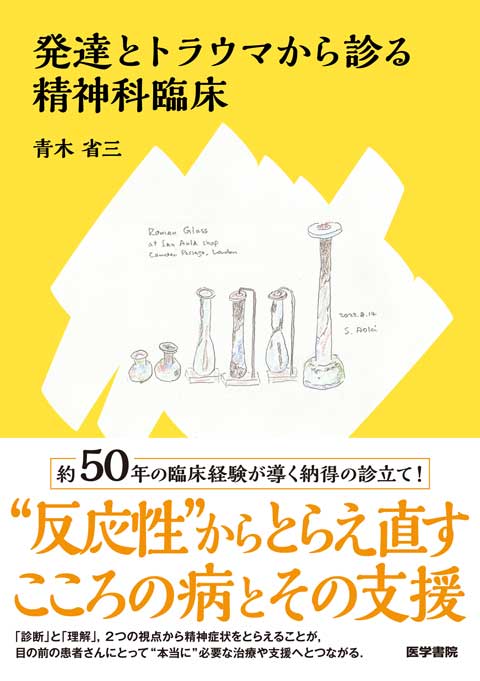「卓越したジェネラリスト診療」入門
複雑困難な時代を生き抜く臨床医のメソッド
ガイドラインじゃ解決できぬ臨床課題に答えるエキスパートジェネラリストのメソッド集
もっと見る
マルチモビディティ、下降期慢性疾患、複雑困難事例、心理・社会的問題、未分化健康問題…。現代の臨床医は外来で、ガイドラインや医学的知識だけでは太刀打ちできない、さまざまな患者・家族の健康問題に直面する。そんな時、医師として、どう考え何ができるか? 日本のプライマリ・ケアと家庭医療学を牽引してきた著者が、そのメソッドを開示し“新たな医師像”を提示した。藤沼康樹氏の現時点での集大成、待望の単著。
| 著 | 藤沼 康樹 |
|---|---|
| 発行 | 2024年06月判型:A5頁:296 |
| ISBN | 978-4-260-05354-9 |
| 定価 | 4,400円 (本体4,000円+税) |
更新情報
-
【2024年10月16日開催終了】本書に関連したWebセミナーを開催しました。
2024.10.17
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
医学・医療は日進月歩です。新たな疾患メカニズムの解明、新たな治療法の開発などは、目を見張るものがあります。私が医師になってから40年の間にも、不治の病いとされてきたさまざまな疾患が根治可能になったり、症状を抑えたりできるようになっています。近代以降、医療が、こうした生物学をはじめとした自然科学と結びつくことによって、多くの画期的な成果をあげてきたことは厳然たる事実です。しかし、そうした自然科学のパラダイムでは、ある疾患に罹患している1人の患者は、その疾患における「症例1」とされます。また、そうしなければ臨床研究を実施することはできません。
この自然科学のパラダイムでは、個々の患者の家族や仕事、ライフヒストリー、価値観、感情など個別性の高い要素は捨象されます。また、「こころ」は脳内代謝の影として扱われ、自然科学の対象とはならなくなります。しかし現実の医療の場面、特に日々生活している患者の健康問題の相談にのるプライマリ・ケアの場面では、これらの「個別性」に寄せた医療が必要になることが多いのです。
従来の医療は、「サイエンス(科学)」と「アート(技芸)」から成ると言われてきました。本書では、サイエンスに原則があるように、アートについても、曖昧なものではなく行動原則があり、ガイドラインがあるということを、できるだけ厳密かつ明快に語っています。このアートの領域は歴史的に、自然科学の発展とは違って、多くの哲学者や思想家、人類学者、心理学者、社会学者など、医学以外のさまざまな領域の到達に基づいて豊かに進んできました。私たちは、こうした領域における過去の偉大な賢人たちの視点を借りつつ、自らの臨床経験とその省察に基づいて、より妥当性のある「医療のアート」を深めていくことができます。
そして「卓越したジェネラリスト」は、医療のサイエンスとアートを同等の価値をもつものとして取り扱います。そこにこそ、卓越したジェネラリストの最大の特徴があります。本書では、そうした立場から医療の「アート」の側面を、これまでになく幅広く議論しています。通読することによって、さまざまなunlearning、“学びほぐし”が生じる仕かけになっています。読者のみなさんに、ぜひ最後まで読んでほしいと願っています。
本書は、『総合診療』誌での3年余にわたる連載「55歳からの家庭医療──明日から地域で働く技術とエビデンス」をもとに、加筆・再構成したものです。連載中にさまざまな感想、重要な示唆やアドバイスをくれた多くの同僚家庭医に感謝します。そして、連載開始当初から医学書院の杉本佳子さんは、何度も連載継続を諦めそうになった私を常に励ましてくれました。杉本さんの存在なしには、本書が世に出ることはなかったと思います。ここで改めて深く感謝の意を伝えたいと思います。
2024年5月
藤沼康樹
目次
開く
はじめに
プライマリ・ケア外来の一般要件
プライマリ・ケア外来の「独自性」
「卓越したジェネラリスト診療(EGP)」とは
第I章 プライマリ・ケア外来の一般要件
1 「臨床診断」の技芸
病院の一般外来とは異なる“診断戦略”が必要なワケ
危険な疾患を除外する方法
プライマリ・ケア独自の「事前確率の見積もり」
プライマリ・ケアに多い「診断の遅れ」
「診断エラー」を防ぐ方法
12の診断エラー経験と12のパール
重大疾患を除外したあとは
医学的診断がつかない場合
2 「外来診療」を構造化する
時間をかければいいわけではない
病棟・救急外来との違い
「かかりつけ医」機能をもつ外来とは
まず「アジェンダ」をつくる
アジェンダを「1患者10分」で達成する10の手順
「患者中心の医療の方法」による時短
「家庭医療」ができる外来をデザインする
「半予約制」のススメ
3 「家族」を診る方法
なぜ「家族(family)」を診るか
診療ツールとしての「家族図」
現代の「家族問題」と家族図
「家族療法」の可能性
家族を「構造的」に診るためのポイント
4 外来診療におけるクリニカル・スキルズ
「身体診察」の4つの意義
身体診察に関する私的パール集
「子ども」のかぜ
「大人」のかぜ
「高齢者」のかぜ
「禁煙外来」を成功させる4つの認識
「私はこれでタバコをやめました」
5 プライマリ・ケアにおける「治療学」
Doctor as Drug──診断=治療である
プライマリ・ケアにおける8つの「治療法」
「処方」の原則
私のパーソナルドラッグ40
リアシュアランス:「安心」を導く7つのフレーズ
“クローズド・クエスチョン”から始めよ
シンプルな精神療法(カウンセリング)のエッセンス
“医学的には必要ない点滴”の治療的意義
診療所における注射
小外科処置をどこまでやるか
物理療法の“心理的”効果
鍼灸・マッサージの意外な可能性
第II章 卓越したジェネラリスト診療の実践
「ジェネラリスト」の専門性とは何か?
1 なぜ「卓越した」ジェネラリスト診療か
「問題が何かわからない(未分化健康問題)」という問題
従来型の診断・治療のパラダイムが使えない
「意識変容」に不可欠なunlearning
時代が求める“新たな医師像”
2 医学的治療が問題解決にならない場合:「病い」へのアプローチ
「病い」にアプローチする4つの道筋
①FIFE:「共感」ではなく、患者にとっての意味を知る
F:feelings(感情)
I:ideas(概念)
F:functions(生活機能)
E:expectations(医療への期待)
②ライフヒストリーの聴取:治療を拒否する患者へのアプローチ
ライフヒストリー聴取の実際
ライフヒストリーを引き出す3つのトリガー質問
③健康生成論に基づく診療:患者の“強み”に注目する
疾患ではなく「健康」に直接アプローチする臨床的方法
④解釈学的医療:患者の「主体/自己」を対象とする
ジェネラリズムは「身体化された主体」を対象とする
患者の「主体/自己」を支える「一貫性」(ルーチン)と「エンゲージメント」
3 「患者中心」の診断推論
一般的な診断推論(仮説演繹型)との違い
“無限”の問題空間を扱う
「帰納的採集」と「トリガー・ルーチン」
患者と協同で行う「アブダクション・アプローチ」
“演繹的に考える癖”から脱する方法
「患者中心のプロブレムリスト」をどうつくるか?
4 「複雑困難事例」へのアプローチ
あなたのストレス・陰性感情も徴候です
①“複雑な状態”を表現する用語やコンセプトを使う
②患者の「creative capacity」を同定・援助する
③“インフォーマルなリソース”も使う(社会的処方)
④「チーム力の向上」もアウトカムと考える
5 「マルチモビディティ」へのアプローチ
コモビディティとは違う
マルチモビディティはなぜ問題か?
ためしにガイドラインどおりにやってみると…
「治療負担」のマネジメントを起点に
複雑な介入法とシンプルなポイント
マルチモビディティへの介入における7つのパール
6 「下降期慢性疾患」へのアプローチ
“下降期”でもできることはある
下降期慢性疾患の5つの構造的特徴
下降期慢性疾患へのアプローチの実践例
7 診察室から地域への“水路”としての「社会的処方」
「孤独」や「寂しさ」につける薬はないのか?
患者の“居場所”と“出番”をつくる「テーマ・コミュニティ」
診察室とテーマ・コミュニティをつなぐ「リンク・ワーカー」
「患者」としてみることと「生活者」としてみることの“中間”を行く
日本における「社会的処方」の課題
社会的処方の理論的根拠となる「社会関係資本」
8 プライマリ・ケアにおける「回復」の構造
それは本当に「治療効果」か?
「回復」を構成する6つの性質
回復が生じやすい環境「ヒーリング・ランドスケープ」
回復に関わる「患者」の4つの側面
第III章 卓越性を支える「チーム」と「教育」
1 地域医療における「チームワーク」
個別に仕事を行う時代は終わった
「統合ケア=多職種協働」ではない
チームワークの「促進因子」と「阻害因子」
「阻害因子」としての医師
「医師誘発性困難事例」
介護(施設)vs看護(病院)
異文化感受性発達モデル
チーム内の「異文化≒多様性」を活用する方法
2 「振り返り(省察)」と実践をつなぐ方法
“きれいごと”では「振り返り」にならない
「振り返り」をする前に認識しておきたい4つのこと
「振り返り」をする時に意識しておきたい6つのこと
後悔から「省察」へ
たとえば「告知」の事前アドバイス
事後に「自分のこと」も振り返る
不確実性に向き合う「省察的実践家」
3 ジェネラリストの教育・生涯学習
「一般外来研修」での教え方の枠組み
「外来ケースカンファレンス」の方法
「病院」で使える家庭医療の教育コンテンツ
「病院」の複雑困難事例へのアドバイス
価値転倒をもたらす「レクチャー」の方法
“サブカル”も教材になる
価値観の幅を広げるトレーニング
「正解がないこと」を教えるための事例集
おわりに
これからのジェネラリスト診療
“コロナ禍”があぶり出したプライマリ・ケアの本質的役割
「気候変動」は健康問題だ
長い医師人生をどう生きるか?
新たな時代を肯定的に生き抜くための6つのアドバイス
最後に改めて「卓越したジェネラリスト診療」とは何か?
「卓越したジェネラリスト診療」への4つのステップ
索引
書評
開く
『卓ジェネ』が今日問いかけるもの―門外漢の視点
書評者:青木 眞(感染症コンサルタント)
書評を見る閉じる
◆はじめに
本稿は書評になっていない。感染症専門医が家庭医の執筆した本の書評を書くこと。それは,町中華のおやじが寿司屋のシャリやネタを講評する,あるいは火星人が『地球の歩き方』を書くようなものだ。依頼があった時,あまりに門外漢である評者は,藤沼康樹先生の浮間診療所を訪問し,外来にも陪席させていただいた。そこで見えてきたものを書き並べてみることで,今回はお許しいただきたい。
コロナ禍が始まる少し前,赤羽の飲み屋で初めてお会いした藤沼先生の印象は,言わば「ごんぎつね」であった。おおらかにゆったりと日々を過ごされる診療所のお医者さん。朝,藤沼先生が診療所の戸を開けると,地元の患者さんから野菜や煮物が届いている……(笑)。しかし,これは極めて表層的な印象であることを,やがて評者は思い知るのである。
ちなみに,すでに著名な総合診療や看護領域の先生方から優れた書評が寄せられているので,ぜひ併せて参照していただきたい。
のっけから迂遠な話になるが,米国感染症専門医は制度設立当初,放射線科医師と同様に患者を持たない職能として位置付けられた。評者は,患者とのやりとりで“I型アレルギー”を起こすことが多く,教え子たちは「プライマリ・ケアは絶対無理」と太鼓判を押す。そのような評者にとって,患者を持たない米国感染症専門医はうってつけの専門領域といえた。
しかし,これをHIV感染症が変える。感染症専門医もAIDS患者の主治医となるのである。評者が初めて米国の地を踏んだ1984年,それはくしくもHIVが発見された年だ。その後10年あまり,若者がニューモシスチス肺炎でAIDS発症,彼らの100%近くが2~3年以内に死亡するという凄絶な時代が続いた。評者は,「若者の生命を1日でも長く」に注力した。
それが今や,HIV陽性者も1日1錠で天寿を全うする。HIV感染症の問題は「CMV網膜炎による失明」から,天寿を全うできるが「生きがいがない」という問題に変化したのである。まさに,『卓ジェネ』でいう「疾病(disease)」から「病い(illness)」への変化である。評者は,この変化を生きないで医師として歩んできた。しかし71歳となり,コロナ禍に加え,プロフェッショナルにも潮時と思い自宅で過ごす時間を増やすと,“卓ジェネワールド”は,患者側の立場に移りつつある自分に近いものとなり見えてきたものもある。
◆藤沼先生の外来
藤沼先生の外来に陪席させていただいた。90分ほどの間に10名前後の患者さんを診療されている。急いでいる(rushな)感じは全くしない。そこに,大病院を渡り歩きインターネットで検索して藤沼先生に「辿り着いた」一人の青年が不定愁訴で来院した。その青年に藤沼先生は,熟練工のルーチンのように“卓ジェネ診療”を展開される。「あなたの苦しみはリアルである(仮病ではない)」「診断はつかないかもしれないが,大事なことは問題を抱えつつも生活を続ける工夫」「診断書と処方箋(服薬の事実)があれば,休職しても社会は納得する」と至れり尽くせりの診療を提供後,評者にひと言,「この青年が再診に戻ってくる確率はせいぜい半分」……。
そのほか,統合失調症の患者の診療後に「基本,精神科は精神疾患の専門外来であり,こころや生活全般の問題を丸投げできるところではないです」「診療看護師やレジデントにより書き添えられて育っていく家族図がデフォルトで組み込まれているカルテ」などなど,さまざまな人間関係や感情が交錯する町の診療所で長く過ごした医師だけが魅せる“卓ジェネ外来”だった。お弟子さんによる訪問診療にも同行させていただいた。2時間かけて入浴するのが日々の楽しみである102歳の女性にお会いし,「日常生活のルーチンを辿る重要性」も『卓ジェネ』の教えだったことを思い出した。
本書には,プライマリ・ケア医ならば必然的に直面する「達成感の欠如」「多疾患併存・下降期慢性疾患といった困難症例」への対処法などが具体的に,あたかも『ワシントンマニュアル』のように記載されている。「Bio」を自然科学のエビデンスが支えるように,「Psycho」「Social」,それ以上に「人間を診る視点」を,藤沼先生の大きな人文領域の知恵がエビデンスのように支えているのだ。藤沼先生ご自身がおっしゃるように,一見つかみどころのない家庭医の診療現場にも「明確な行動原則」があり,「ガイドライン」もあるし,本書を絶賛する某コンサルティング会社OBの表現を借りれば,常に当てはめる「フレームワーク」があることを示す外来だった。
◆藤沼先生の世代とその周辺
外来陪席時,藤沼先生に「なぜ門外漢の青木に書評をご依頼くださったのか?」とお聞きしたところ,「同世代だから」とのことだった。「同世代」の評者が今,日本で「卓越したジェネラリスト診療」とそれが内包するものが置かれている場所を,門外漢ならではの視点で概観することは案外有用と考えられたのかもしれない。
評者と藤沼先生は,1980年代に同じ病院で研修している。当時の都立養育院附属病院,現在の東京都健康長寿医療センターがそれだが,残念ながら少し時期がずれており,病院の廊下ですれ違うことはなかった。1980年代と言えば,日本は世界第2位の経済大国となり最も活況を呈していた時期の1つである。医学界・医療界は細分化が進み,それを可能にするお金もあったと思う。経済力が医学・医療の機械化・専門分化を推し進める時代であり,病歴や身体所見を大切にする家庭医療学や総合診療とは反対のベクトルが強い時代だった。
特筆すべきは,この時期,旧厚生省とシステマティックな家庭医の養成が必要と考えていたさまざまな分野の医師たちが日本にプライマリ・ケアや家庭医の制度を根付かせることを試みられたが,大きな力が反対した。この頃,家庭医療・総合診療といった概念を日本に導入しようとされた先生方の苦労は筆舌に尽くしがたく,その反対勢力があまりに強大であるが故に,その痕跡さえ辿るのが困難である。最近,頻繁に遭遇する「かかりつけ医」という言葉の形而上学的な難解さ,「総合」の名を冠した医局がほとんどの大学において思うように発展せず,また必ずしも総合性を志向しない医師の“猟官運動”による焦土とも見えることを改めて考えている。
◆藤沼先生と評者
同じ臓器横断的な医師とはいえ,東と西くらいスペクトラムの異なる仕事をする藤沼先生と評者をつなぐものは何であろうか? 藤沼先生は外来で患者との会話で診療を進めるが,評者はホワイトボード派。ICUで挿管されている患者について,他の医師が抽出した病歴・身体所見・検査データを相手にしている。生活習慣病には終わりはないが,感染症はたいてい終わる。藤沼先生は評者が苦手なプロレスや仮面ライダーの大ファンだし,評者の好きなクラシック音楽を藤沼先生は基本お嫌いであると聞く。それでも無礼を承知で評者との共通点を挙げてみる。
(1)フレームワーク:藤沼先生と評者の共通点。それは,「フレームワーク」を基軸にしている点だと思う。評者の「臓器・起炎菌・抗菌薬」といったシンプルなものではないが,藤沼先生も「行動原則/ガイドライン」を大切にされる。評者の教え子たちは困難症例ほど「フレームワーク」に立ち戻ることの有用性を指摘するが,おそらく藤沼チルドレンも同様の経験をしていると思う。また,「フレームワーク」の提示は教育の効率や診療の質も上げる。
さらに「フレームワーク」を大切にすることは,家庭医療という世界そのものの深化・分析を助け,本来あるべき姿から外れないようにするための羅針盤としての助けにもなると想像している。臨床風景は変幻自在であり「フレームワーク」という羅針盤なしでは同じ過ちを繰り返し,学会レベルでは刻一刻と変化するプライマリ・ケアに対する時代の要請にも気付かないかもしれない。
(2)教育重視:藤沼先生は教育に熱心であり,高弟も多い。彼のもとで訓練中の研修医も,良き臨床医の素質を感じさせる。患者の人生航路や価値観を大切にする彼らを見ると,「このような若者をこそ,もっと医学部に入れたい」と思う。『卓ジェネ』は,医学部入学時点での選抜をより文系的にシフトさせる必要性も示しているのかもしれない。ちなみに藤沼先生も評者も,現在の医学部入学に求められる偏差値は高すぎると考えている。
(3)カウンターカルチャー:藤沼先生も評者もoutlawである。それは学会・行政などのestablishmentに対してだけでなく,所属領域内に対してもである。これは,本人のcharacterもあるが,何よりprofessionalとしての矜持による。「ちょっと違うんだけどな……」といった感じでプライマリ・ケア学会場を遠慮がちに歩く藤沼先生である。
◆おわりに
評者はここ数年,全ての書評依頼をお断りしてきた。それは,決してご依頼のあった書籍に問題があったわけではない。むしろ優れた書物であったことがほとんどであり,著者の方々も評者が尊敬する臨床家であることが多かった。ただ,評者がご依頼のあった本を精読し,その参考文献の調査にまで注ぐ時間とエネルギーはそれなりのもので,体力・知力ともに衰えつつある評者の残された時間を書評にあてるのには無理があり,半端な仕事は著者の方にも出版社の方にも失礼にあたると考えていたからである。
では,なぜ全く専門外であるジェネラリストのための本の書評を引き受けたのか……? それは,急速に高齢化する日本の医療のインフラとして最も必要とされる家庭医療・総合診療といった「総合」領域の重要性と,その広がりを妨げる仕組みの再確認のためだった。もっというなれば,「総合」という全ての医師の養成に必須の要素が,卒前・卒後の教育を通して圧倒的に欠けている状態が数十年も続いている,この国の臨床教育の宿痾(しゅくあ)について書き残しておく必要を感じたためである。このような教育は結果として,診療現場において,いわゆるたらい回しや,専門科領域外の診療拒否・誤診などを延々と続けさせている(もちろん例外はあるが,絶望的に例外的である)。
2018年には「総合診療」が,内科・小児科・外科などの従来の18の基本領域に「並び」,新たに19番目の基本領域として加わった。19番目に入れるための関係者の努力は大変なものであったに違いない。しかし評者は,この仕組みに大きな危険性を感じている。なぜなら,「家庭医療」「総合診療」といった「総合」領域は内科・外科・眼科・耳鼻科の隣に「並ぶ」ものではなく,全ての診療科の土台であり,医学教育・医療のインフラであるからだ。「臓器別」に分かれる前に全員が「総合」の基本を押さえることは本来,optionとして「並ぶ」ものではなく,将来の専門科を問わず全ての医師にとっての土台であり,スタート地点なのである。
「直美(ちょくび)」(初期研修もそこそこに高収入が期待できる美容領域に進むこと)が問題になっていると聞く。しかしこれは,根本的な問題から目を反らした,呆れるほど表層的な視点である。本当に問題なのは,卒前では医学部の国試予備校化,卒後は臓器別診療界による研修医の青田買いの常態化といった,「総合」を基礎とする臨床教育が荒廃していること,専門医制度があまりに複雑で,専門医取得までの手続きが理不尽なまでに過剰であり脱落者が絶えないこと,専門医になっても勤務医になれば過労死に怯えることになること……などではないだろうか? この国は,どのような医療を提供するために,どのような医師をどのくらい提供しようとしているのか? この問いは,医師不足問題が,その数と分布(偏在)で語られることはあっても,決してその質(診療科)で語られないことと深いところでつながっている。
▼
藤沼先生が米国家庭医療学の専門誌を手に取り,その道に進むことを決意したその日の図書室の風景を評者は想像できる。インターネットという媒体が存在しない時代に,藤沼先生がその専門誌と出会った偶然,それによって今,ここに与えられている『卓ジェネ』が日本の医学・医療に問いかけるものを考えている。
臨床医にそっと寄り添い,背中を押してくれる「読むメンター」
書評者:片岡 仁美(京大医学教育・国際化推進センター副センター長)
書評を見る閉じる
藤沼康樹先生のファンである。まだ先生を存じ上げなかった頃,『日本内科学会雑誌』に掲載されていた文章に感銘を受けた。その後,『総合診療』誌の編集委員としてご一緒させていただく機会が増え,いっそうファンの度合いが増している。しかし,それを差し引いても,序文を読んでいる最中から涙してしまうとは自分でも予想外であった。新幹線で席に着くや本を開いて,1ページ目から涙ぐんでいるせわしない私を見て,隣の方も不審に思ったかもしれない。
医療はサイエンスとアートである。よく聞く言葉であるが,「本書では,サイエンスに原則があるように,アートについても,曖昧なものではなく行動原則があり,ガイドラインがあるということを,できるだけ厳密かつ明快に語っています」(本書p.iv)と述べられている。そして,「『卓越したジェネラリスト』は,医療のサイエンスとアートを同等の価値をもつものとして取り扱います。そこにこそ,卓越したジェネラリストの最大の特徴があります」(同前)という文章を読んだ時,前述のごとく胸が熱くなってしまったのである。
一般にサイエンスに偏りがちな診療環境や交わされる会話の中で,「患者さんを丸ごと診たい。全てを受け止めたい」「いつでも頼れる存在でありたい」と常に希求し診療をしてきた。そのことに誇りを持っているが,一方で複雑困難事例や医学だけでは答えが出ない患者さんを多く診ていると,「これでいいのだろうか?」と時に孤独を感じることもある。自分を信じてやっているけれど,本当にこれでみんな幸せになっているのだろうか? 人には言わない,そんな素の気持ちにそっと寄り添い,「それでいいんだよ」と背中を押してもらった気持ちになった。言語化が難しいアートの側面が,見事に言語化・構造化・見える化されているだけではない。日々の名もないと思っていた取り組みが,個別の経験にとどまらず体系化されたアートを形成する一部であることが理解できた。
加えて,本書の卓越した部分は,どの部分を読んでも自身の「実践」に反映されること,また,実践からの学びを言語化・客観化・相対化するというループを実感できることである。「ああ,あの患者さんにはこうアプローチすればよかったのか」「自然に行ったことではあったけど,このような理論に基づいた妥当性があったのだ」と,実践と理論を行き来しながら深い省察を得られることが何とも心地よく,優しくあたたかい文章とも相まって,まるで藤沼先生と語り合っているような気持ちにさえなった。医師としての経験年数が増えてくると,自身の診療を他者にフィードバックしてもらう機会が減っていく。このことが前述の孤独感にもつながっていると思うが,本書を読むことで藤沼先生の言葉をたどりながら深く自分自身とも語り合う機会になっているのだと思う。
「実は,ベテラン医師のロールモデルを見つけることが困難な時代になっている」(本書p.261)という一節に続き,「ベテラン医師になり歳を重ねていっても,たとえ細くとも粘り強く未来に役立つよう生き抜いていきたいという思いで,本書を執筆しました」(本書p.266)と藤沼先生は述べられている。本書の締めくくりにおいて,再度グッと心に迫る部分である。このような素晴らしい先達が背中を見せるだけでなく語りかけてくれる本書は,「卓越したジェネラリスト」をめざすわれわれにとって,いつでもページを開くことができ,勇気づけられる必携の書である。
医療化しすぎてはいけない:専門職のための学びほぐし
書評者:太田 充胤(東大大学院・科学史・科学哲学/北多摩生協診療所)
書評を見る閉じる
私のように病院から診療所に拠点を移したばかりの医師にとって,本書はかゆいところに手が届く本であり,それ以上に,なんというか元気が出る本でもあった。
臓器別の専門家として訓練を受けてきた医師は,プライマリ・ケアに転向する時に必ず,ある種の「無力感」や「カルチャーショック」に直面する。プライマリ・ケアの仕事は,宿命的に“治療した感”(本書p.101)に乏しいからだ。
例えば私は内分泌代謝・糖尿病内科専門医なので,糖尿病の未治療例や難渋例にうまく対処できれば,専門家として“治療した感”で満たされることができる。基幹病院の専門外来にはそういう患者さんが集まってくるので,おおむね常に“治療した感”を得ることができるようになっている。しかし診療所では,そういう仕事ばかりではない。安定した患者さんの維持治療では役に立っている感覚を得づらいし,下降期慢性疾患や複雑困難事例では治療してよくなる部分を見つけること自体が難しい(正直,糖尿病などあまり問題にしなくていいケースも多い)。ましてや,検査上は異常がない不定愁訴の患者さんなど,自分に何ができるのかさえよくわからない。
プライマリ・ケア外来の大半は,こういう“治療した感”を得づらい患者さんで占められている。さて,それではジェネラリストは,専門家としての喜びをいったいどこに見出せばよいのだろうか?
本書では,このカルチャーショックを乗り越える方法として,大きく分けて2つの提案がなされている。1つは,家庭医やプライマリ・ケア医と呼ばれる医療資源の役割を学び,診断・治療を中心とした診療のツールボックスを充実させること(第I章)。これはすなわち,“治療した感”を得られる局面を増やしていくための方法だ。しかし,この方法でもやはり,“治療した感”を報酬とした働き方の限界を乗り越えることはできない。いたずらに診断治療の道具を増やすことはむしろ,手ごたえのなさを過剰な検査・投薬で埋めることにもつながりかねない。
そこでもう1つの提案が,これまで医師として学習してきた診断・治療の思考や行動規範を解体するということである(第II~III章)。著者は端的に,ジェネラリストとしての訓練は医師にとって「unlearning」(本書p.110)のプロセスだと述べている。患者の苦痛を医学の言葉に翻訳する技術,疾患を診断して治療する手ごたえと喜び……。こういう枠組みを,いま一度学びほぐすことで見えてくる診療のスタイルがある。本書を貫く思想の核心は,むしろこちらのほうにありそうだ。
とりわけ面白いのは,「医療化しない」という目から鱗の逆説である。医学によって訓練された医師はつい,「医療現場に持ち込まれる『つらい』『しんどい』といったdistress(苦痛)に医学的診断をつけ治療しようとする」(本書p.267)。著者はこれを「医療化(medicalization)」と呼び,ジェネラリストの卓越性を「医療化しない」ことに位置付ける。
「医療化」とは,ある問題が医学・医療の領分に組み込まれていくことを指す概念である。歴史的にさまざまな領域が医療化されてきたが(自殺,肥満,不妊,発達障害など),これには常に功罪がある。その問題が解決可能であるという希望につながる一方で,ひとたび医療化された問題では,その根本原因が無視されやすくなったり,医学以外による解決策が選ばれづらくなったりするからだ。
言われてみれば,診療所でよく経験する下降期慢性疾患や社会的・経済的複雑困難事例もまた,医療化が解決につながるとは限らないばかりか,時に本人への不利益ももたらすようなタイプの問題だろう。だとすると,「医療化しない」という判断もまた,今日の医師が担うべき重要な役割なのである。もちろんそれは,「診療しない」こととは違う。場合によっては医療化しないことが最適な診療であり得るということだ。したがって,「医療化しない」という選択肢の先には,“治療した感”に依存しない課題解決の手ごたえ──“診療した感”があり得る。
ジェネラリストは,自らのツールボックスに「医療化しない」という医学外的なカテゴリを加えておく必要がある。本書にぎっしりと詰め込まれたtipsの大半は,とどのつまりこのカテゴリを充実させるための道具ではないかと思う。それらは医師にとって,医療・医学の周縁を自らの守備範囲として切り拓くための道具になるはずだ。
精神科医で医療人類学者のアーサー・クラインマンは『病いの語り』(1996,誠信書房)で,現代社会で人が病気と向き合うためのシステムは「専門職セクター」「民間セクター」「民俗セクター」の3つから成っていると書いている。医師を中心とした専門職セクターが主として生物医学的な「疾病(disease)」に焦点を当てるのに対し,患者さんが経験する「病い(illness)」そのものへのケアの大半は,実は民間セクターで供給されているのだという。クラインマンは,専門職セクターが病い(illness)のケアをも担うことが望ましいとしながら,さまざまな理由でそれが困難であることも指摘していた(法的・経済的制約,質の保証,教育システム……)。
分割されたシステムは,患者さんだけでなく治療者にも不利益を及ぼす。クラインマンはこうも書いている。「ケアの専門機関は治療者をも失望させる。とくに,患者と家族の病いの問題に焦点を当てることに関心のある医者はそうである」(同書p.348)。思うに問題は,患者に対峙する医師もまた一人の人間であり,このようにセクターが分割すれば治療主体として分裂せざるを得なくなるということではなかろうか。医療セクター以外の役割をパージすれば,医師はただ“普通の人”として診察室にいることが許されなくなってしまう。
こうして分裂した治療主体は,例えば「この前ペットの犬が亡くなって,ごはんが食べられなくて…」といったような“普通の相談”に応える機能を失う(あるいは逆に,無理に医療化しようとして六君子湯とかエンシュアリキッドを処方してしまうかもしれないが)。医療化できない相談に応える時間は,専門職セクターにとって医療資源を逼迫する無駄な時間でしかない。とはいえ“普通の人”としての医師は,医療資源として求められる挙動と,“普通の人”として感じたり考えたりしてしまうことのギャップに,少なからず苦痛を覚えるのではなかろうか。
本書を読んで救われたような気持ちになったのは,クラインマンがある種の理想として語ったことが,一人の医師による極めて具体的な実践として語られていたからだった。専門家が「疾病(disease)」と「病い(illness)」とに包括的に対応するための手法が,誰にでも使えるようなかたちでモデル化され,道具化された状態でまとまっていたからだった。
病い(illness)に対峙するためのスキルは,過剰な医療化に拠らない診療を可能にする道具であり,分裂した治療主体を再統合するための枠組みでもある。考えてみれば当然のことではあるが,われわれは必ずしも専門職セクターの資源として振舞わなければいけないわけではない。医師は“普通の相談”を受けることができるし,そのためのスキルを磨くことがあってよい。ああ,そういえば,初期研修医の時に出会った訪問診療のベテラン医師は,患者から信頼され慕われる様子がまるでお坊さんのようだった。つまるところジェネラリストとは,3つのセクターが混然一体となったような治療主体でもあるのかもしれない。そのように思い至った時,私の中で積年のわだかまりが溶けたような気がした。
本書を読み終えると,さまざまなことが自分の手に負える課題として浮かび上がってくる。「これが知りたかった」「こういうのどうしているんだろう?」といった疑問への答えが見つかるだけでなく,「言われてみれば,このパターン昨日あったな」「そうか,こういう立ち回りもできたのか」という気付きが多々ある。読み終えた後の外来では,「これ『卓ジェネ』に書いてあったやつだ!」ということもあった。要するに,意外とよくあるが医療化しづらいからスルーしてしまっているような状況が,本書を通じて診療の対象として立ち現れるのである。
プライマリ・ケア医やジェネラリストをめざす医師にはもちろんのこと,臓器別専門家としての働き方にモヤモヤを抱える医師にも,ぜひ一度手に取っていただきたい。
灰色の衝撃:不確実性への転換的挑戦
書評者:志水 太郎(獨協医大主任教授・総合診療医学)
書評を見る閉じる
日本の多くの若手総合診療医に“oyabun”と慕われ,私自身も敬愛してやまない藤沼康樹先生(医療福祉生協連 家庭医療学開発センター長)の初の単著を拝読しました。読了後に浮かんだのは,米国の医師フランシス・ピーボディ(1881~1927)の格言「患者ケアの秘訣は患者をケアすることにある」1)でした。「臨床医の重要な資質の1つは人間性への関心である」とするこの格言が,本書の箴言の数々と共鳴し,胸を撃ち抜かれたような衝撃を何度も感じました。それが,この本の通読1回目の感想でした。
本書の第I章1節の最初のページに明記されているように,医療は「不確実性」が高いものです。現代の医学教育では,多くは説明可能でクリアカットな部分が好まれ,不確実な「灰色」な部分(グレーゾーン)は全体からすれば補集合の扱いに甘んじ,時に無視されてきたのではないかと思います。しかし,この不確実な領域への関心と探索がなければ,全体をつかむことはできないでしょう。コントロール可能な壁の中の世界にだけ生きていたのでは,エルディア人たちは自分たちの始祖のことを決して知り得なかったのではないでしょうか(『進撃の巨人』)。本書にはその不確実性をも可能な限り言語化して構造化する試みが随所にあり,本邦で現在これに比肩する類書は存在しないとみます。
本書は3章からなります。第I章は,家庭医の技芸が光る診断・治療について,そして外来マネジメントのクリニカルパールなどの具体的なアドバイスに満ちています。個人的には,5節の「プライマリ・ケアにおける『治療学』」の中でも「リアシュアランス」の項(本書p.88~)に強い共感を覚えました。また,3節の「『家族』を診る方法」(本書p.44~)にも大いに学びました。第II章は,本書の中核をなすと思われます。“卓越したジェネラリスト”の技術や考え方,振り返りの内訳を明確に言語化し,さらにそれを達成する方策を明示し,わかりやすいケースとともに詳述しています。これら大量のケースの藤沼先生のself-reflectionを追体験したい,というのはさすがにわがままな願いでもあり,そこは藤沼先生のPodcastやSNSでのコメントなどで補完するのが理解を深める方法としてよいと思います(あるいは次作に大いに期待します)。第III章は,II章で解説された「個」の卓越性から離れ,「チーム」や「未来」にどのように卓越性を展開・継承させるかという,より発展的な記述となっています。加えて,20ページ近い長めの「おわりに」には,未練を感じつつ次作への接続を期待させる内容となっています。
本書の装丁は,「灰色」が基調になっています。これには,さまざまな意匠が込められていると感じます。1つの解釈は不確実な医療,すなわち“グレーゾーン”に焦点を当てるという示唆かもしれません。本書が東洋で生まれたことに感謝しつつ,ファッション史における「黒の衝撃」ならぬ,「灰色の衝撃」として不確実性への対処に新たな角度から意味を与えたことが医学史に記憶され,そこに内挿されたオリジナルのプリンシプルや技芸とともに,長く愛される一冊となることを願います。
●参考文献
1)Peabody FW:The Care of the Patient. JAMA 88(12):877-882, 1927.
魔法の書でも奥義の巻でも自己啓発本でもない
書評者:酒井 郁子(千葉大大学院教授・高度実践看護学/専門職連携教育研究センター長)
書評を見る閉じる
本書は,家庭医としての藤沼康樹氏(医療福祉生協連家庭医療学開発センター長)が,これまでの自身のジェネラリストとしての実践知を,多様な領域の大理論や概念モデルと照らし合わせ解説し,今後の発展の方向性を論述したものである。
第I章「プライマリ・ケア外来の一般要件」は,家庭医としての実践を始めたばかりの方へのパール集となっており,独り立ちする際に「ここは気をつけよう」と先輩としてアドバイスするような内容となっている。第II章「卓越したジェネラリスト診療の実践」では,既存の大理論や概念モデルについて基礎知識の整理を行い,かつ“医師らしく”考えるその方法は「診断推論」だけではなく,患者を理解していくにはいろいろな見方があるということを,豊富な事例を基に解説している。特にこの章の4~8節は,看護学領域でのパトリシア・ベナーの著書『From Novice to Expert』をほうふつとさせる内容でエキスパートになっていく(卓越していく)ときのものの見方・考え方が具体的に論述されている。第III章「卓越性を支える『チーム』と『教育』」では,多職種連携教育の3つのメリット「チームスキルの獲得」「共同学習の方法の獲得」「省察と経験学習の方法の獲得」のうち共同学習・省察・経験学習について考察している。専門職連携教育は,チームビルディングなどのチームスキルの獲得のみに焦点が当てられがちだが,実は,チームを俯瞰し,どんなチームであってもその職種の役割を果たし,かつ他の職種の役割発揮を支援する「共同学習」「省察」「経験学習」のスキルが必要である。家庭医として,というか,臨床家として,全ての職種が長く活動するために必須のコンピテンシーであると思う。
終章「おわりに」が秀逸だと思う。医師が保有しがちなシニカルな態度(すみません…)を封印し,自己と他者の人生を肯定し,希望を持ちながら,できることをやっていく,という宣言として読んだ。これから高齢の医療専門職も増えていくのだが,この「おわりに」は大ベテランとなった専門職が,これからの仕事人生を生きていくときの灯台になるような文章だと思う。
最後に,看護職の皆さんが本書を読むと,特に第II章あたりで,「だから,今まで看護はそう言ってきたじゃん!」「人生の意味とか価値とか,病みの軌跡とか,病気を治すだけが医療じゃないって言ってきたのに,医師は全然聞いてくれなかったじゃないか!」という気持ちが湧く人も一定数おられると思う。共感するとともに,これまでの対立の歴史が頭に浮かぶというか……。でも冷静に考えてみると,看護師だって,特定行為研修で医師の診断推論などを学び,医師の知識やスキル,考え方を共有した上で看護することにより,患者さんへの看護実践に幅が出る。そして,それをよく思わない医師も確かに一定数いる。つまり,令和の今は,いろいろな職種が他の職種の保有する知識とスキルを共有することが実現しつつあるということであって,とある専門職集団が,とある知識体系を独占することに何の意味があるのか,ということを考えるきっかけにもなると思う。