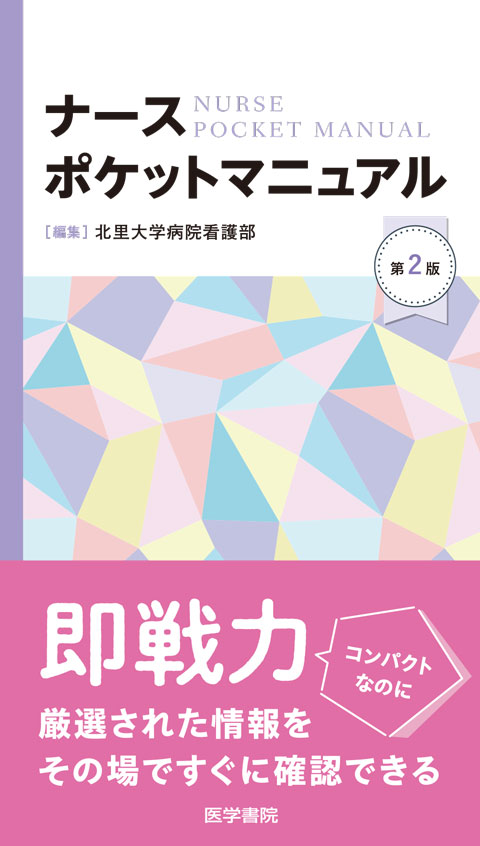新人看護師育成を社会化から考える
看護の仕事のコアを体得し,楽しく働ける看護師になってもらうために
対談・座談会 末永由理,谷口陽子
2024.03.25 週刊医学界新聞(看護号):第3559号より

新人看護師育成に関して,現場の管理者,先輩看護師,プリセプターといった立場の方たちの悩みは尽きないものです。COVID-19感染拡大の影響が実習や研修,臨床での日々の教育にまで及んだことにより,新たな困り事も生まれているかもしれません。本紙では,大学で基礎教育に携わりながら看護師の継続教育について研究を続ける末永由理氏,大学病院で副看護部長として教育に当たり,書籍『ナースポケットマニュアル 第2版』(医学書院)で編集協力も務める谷口陽子氏による対談を企画。新人教育を行う中で感じていることやもやもやについてお話しいただきました。
谷口 私は新卒で北里大学病院看護部に入職して以来,長らく同院で臨床看護師として勤務してきました。文科省の補助金事業に当院が採択された際,高度実践者の育成プログラム担当になったことをきっかけに院内の教育に携わるようになり10年以上が経過しています。本日は新人看護師育成について,基礎教育での話題も交えながらお話しできれば幸いです。
末永 基礎教育に携わるようになって30年近くになります。自身に必要なことを認識し,その習得のために自律して行動し学び続ける看護師となるための基盤は,基礎教育と新人時代の学びで形作られるのではと考えています。臨床で教育に当たる中での実感をたくさん伺いたいです。
入職後両輪で進む職業社会化と組織社会化
谷口 新人看護師育成について話をするに当たって,末永先生が研究テーマの一つにされている社会化に引き寄せながら考えていきたいです。まずは,社会化とはどのようなものか説明していただいてもよいでしょうか。
末永 社会化とは,人が新しい集団・社会に入っていく際に,その社会の中でふさわしいとされる振る舞いを身に付けるプロセスのことです。このプロセスは「職業社会化」と「組織社会化」に分けられ,前者は職業技能的側面での社会化を指します。看護師の場合は専門職として求められる知識や技術といったものを身に付けて,看護師としてのアイデンティティを確立していく。名実ともに看護師になっていくプロセスと言うとイメージしやすいでしょうか。
谷口 看護師は職務に当たる前提として国家資格を有しているわけですが,資格だけではなく,実質的な業務面においても看護師になっていくということですね。
末永 そうです。一方の組織社会化は,病院や配属された部署において,所属する組織の一員として求められる適切な振る舞いを獲得する過程を指します。組織の中で自身はどういった役割を担っていくのかを理解し,そのために必要な知識や技術を身に付けていくのです。組織が大切にしている価値観を理解したり身に付けたりすることで,場になじんでいくことも含まれます。組織の中に自身の居場所を見つけることだととらえると,わかりやすいかもしれません。
谷口 新人看護師には,職業社会化と組織社会化の両方が求められると考えてよいのでしょうか。
末永 はい。両者は重なる部分も多く,2つの社会化は互いに影響し合って進んでいくのが一般的です。そうした社会化がうまくいかないと,離職につながり得ます。これまで看護の研究分野では,新人看護師の職場適応をテーマにさまざまな研究が行われ,臨床現場での支援もなされてきました。そこで扱われる職場適応の中には,社会化における課題も多分に含まれるものと考え,私自身研究に取り組んできた次第です。
休職,離職の理由が見えにくくなってきた
末永 近年の新人看護師の社会化に関してお尋ねしたいことがあります。COVID-19感染拡大による日常生活上の制限は現在ではほとんど緩和され,学生たちの看護実習もほぼ通常通りに行われていますが,感染拡大前後で,入職者の職場適応における違いは何か見られるのでしょうか。
というのも,2021年度の病院における新卒採用者の離職率は10.3%で,2005年の調査開始以来初めて10%を超えました1)。2021年度の新卒採用者は,看護基礎教育での最終学年時に臨地実習が大幅に制限された世代です。ですから,離職率の上昇にコロナ禍による制限がかかわっているのではないかと考えたのですが。
谷口 当院では入職者の社会化が難しくなる可能性を考慮して,あれこれと支援策を講じました。しかし,蓋を開けてみると職場適応に関しては大きな変化を感じるほどのことはなかったというのが実情です。
末永 実は私たちの行った調査2)でも,似たような結果が出ました。研修責任者に対する調査の中で,2021年4月に入職した新人看護師の入職後早期(4~6月頃)を対象に,「チームになじむ」「理解できていない点をそのままにせず確認する」など実習経験が少ないことが関与しそうな働く場での振る舞いについて,「例年よりできていた」「例年とそれほど変わらなかった」「例年と比べできていなかった」の3択で回答を求めたのです。結果,「例年と比べできていなかった」の回答が2~3割あったものの,5~6割は「例年とそれほど変わらなかった」とのことでした。2021年度の新人看護師の多くは職場での支援を受けて必要な知識や技術,態度を身に付けたものと思われましたが,一方で離職率は前述の通り上昇しています。
谷口 離職率に関して言うと,当院では新人看護師の離職率が2%を切っているのが長年の自慢でした。それがコロナ禍の少し前から徐々に上昇し始めて,ここ2年ほどで8%にまで至りました。その原因には大学病院離れなどさまざまなファクターが関係していると考えています。1年以内に離職した新人看護師と一口に言っても,その退職理由は多様です。過去の経験では,年度末に辞める新人は次の仕事でも看護師として働くという方が多く,年度途中で辞める新人は自身のやりたいことと看護のズレを感じて違う職種に……という傾向があったように思います。気に掛かっているのは,最近の離職者は退職後の見通しがないパターンが多いことです。「とりあえず辞めてから考えます」という方が圧倒的に多くなりました。また,問題なく働いていた新人看護師が突然出勤できなくなり休職に入るパターンも多く,その理由が見えにくいです。こちらはコロナ禍でソーシャルサポートが手薄になったことも関係している気はしています。いずれにしても,以前に比べて新人看護師の休職・退職理由が見えなくなってきてい...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

末永 由理(すえなが・ゆり)氏 東京医療保健大学医療保健学部 看護学科 教授
1991年千葉大看護学部を卒業。東京医療保健大医療保健学部講師,准教授等を経て,2018年より現職。また,16年には埼玉大大学院経済科学研究科を修了する。博士(経済学)。「看護師の継続教育」をテーマに研究を続ける。編著書に『臨床事例で学ぶコミュニケーションエラーの“心理学的"対処法――看護師・医療従事者のだれもが陥るワナを解く』(メディカ出版)など。

谷口 陽子(たにぐち・ようこ)氏 北里大学病院看護部 副看護部長 / 看護研修・教育センター長
1988年神戸大医療技術短大卒。同年北里大病院看護部に入職後,2004年同大病院看護部師長を経て,17年より現職。北里大看護学部臨床教授を兼任。17年慈恵医大大学院修士課程看護管理分野を修了。北里大病院看護部が編集する『ナースポケットマニュアル 第2版』(医学書院)では,編集協力として内容の取りまとめに尽力した。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
寄稿 2025.11.11
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。