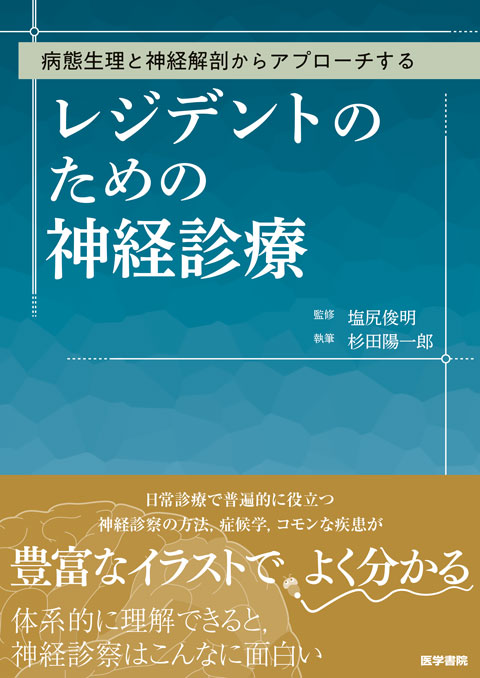FAQ
神経診療における病歴聴取
寄稿 杉田陽一郎
2023.11.13 週刊医学界新聞(レジデント号):第3541号より
神経診療で最も重要な点はいきなり病名に飛びつくのではなく,病歴と神経所見から①「神経解剖のどの部位が障害されているのか?(病巣はどこか?)」,②「どのような機序か?(病因は何か?)」という2点を推定することです。この作業なくしていきなり「〇〇病」という鑑別を挙げると診療が混乱し,またキーワードから病名を連想するという短絡的な思考回路は誤診のもとになります。本稿では「いかに病歴を聴取するか?」という点に絞って解説していきます。
FAQ 1
問診の際に患者さんが「突然」と言っていたので,そのままカルテに「突然発症」と記載しました。この判断で正しかったでしょうか?
問診で患者さんが話した言葉をそのままカルテに記載するのはディクテーションであり,病歴聴取ではありません。患者さんは前日まで健康であったが当日昼から調子が悪いことを「突然」とよく表現しますが,医療用語の「突然発症(sudden onset)」は発症起点が何時何分と特定できる状況を指します。このように患者さんが使う言葉と医療用語の意味に乖離を認める場合が多々あるため注意が必要です。
このように患者さんが「突然」と表現したからといって「突然発症」と医学的に解釈して良いわけではありません。では,どうすれば発症起点をとらえられるでしょうか?
ここでのポイントは「何をしている時にどのような症状が出ましたか?」と具体的なエピソードを尋ねることです。例えば,皿洗いの最中にそれまで普通に洗えていたにもかかわらず急に右手に力が入らずお皿を落してしまった場合は,発症が何時何分と特定可能なので「突然発症」と客観的に判断可能です。しかし,何をしている時かは思い出せないけれど気が付いたら何となく右手が動かしづらいという病歴では発症起点が特定しきれないので「突然発症」とは断定できません。
このように患者さんの使う言葉の表現や形容詞を詰めていくのではなく,「発症時に何をしていたのか?」という具体的なエピソードを引き出していく作業こそが病歴聴取です。得てして病歴聴取が患者さんの言葉をそのままカルテに記載するディクテーションになってしまっている場合があるので,注意が必要です。
Answer
患者さんの言葉をそのままカルテに記載するのはディクテーションであり,病歴聴取ではありません。突然発症の病歴かどうか判断するために...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
杉田 陽一郎(すぎた・よういちろう)氏 東京ベイ・浦安市川医療センター神経内科 医長
2015年東京医歯大卒。武蔵野赤十字病院で初期研修修了し,東京医科歯科大学医学部附属病院脳神経内科などで後期研修を修了。22年に東京ベイ・浦安市川医療センターに神経内科を立ち上げ現在に至る。医學事始というホームページで医学情報の発信を行う。著書に『病態生理と神経解剖からアプローチする レジデントのための神経診療(医学書院)ほか。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。