ここを押さえておけばもう迷わない!?
国際学会の歩き方
寄稿 若林秀隆,後藤慎平,菊地良介,石木寛人,神谷健太郎,横江正道
2023.03.20 週刊医学界新聞(通常号):第3510号より
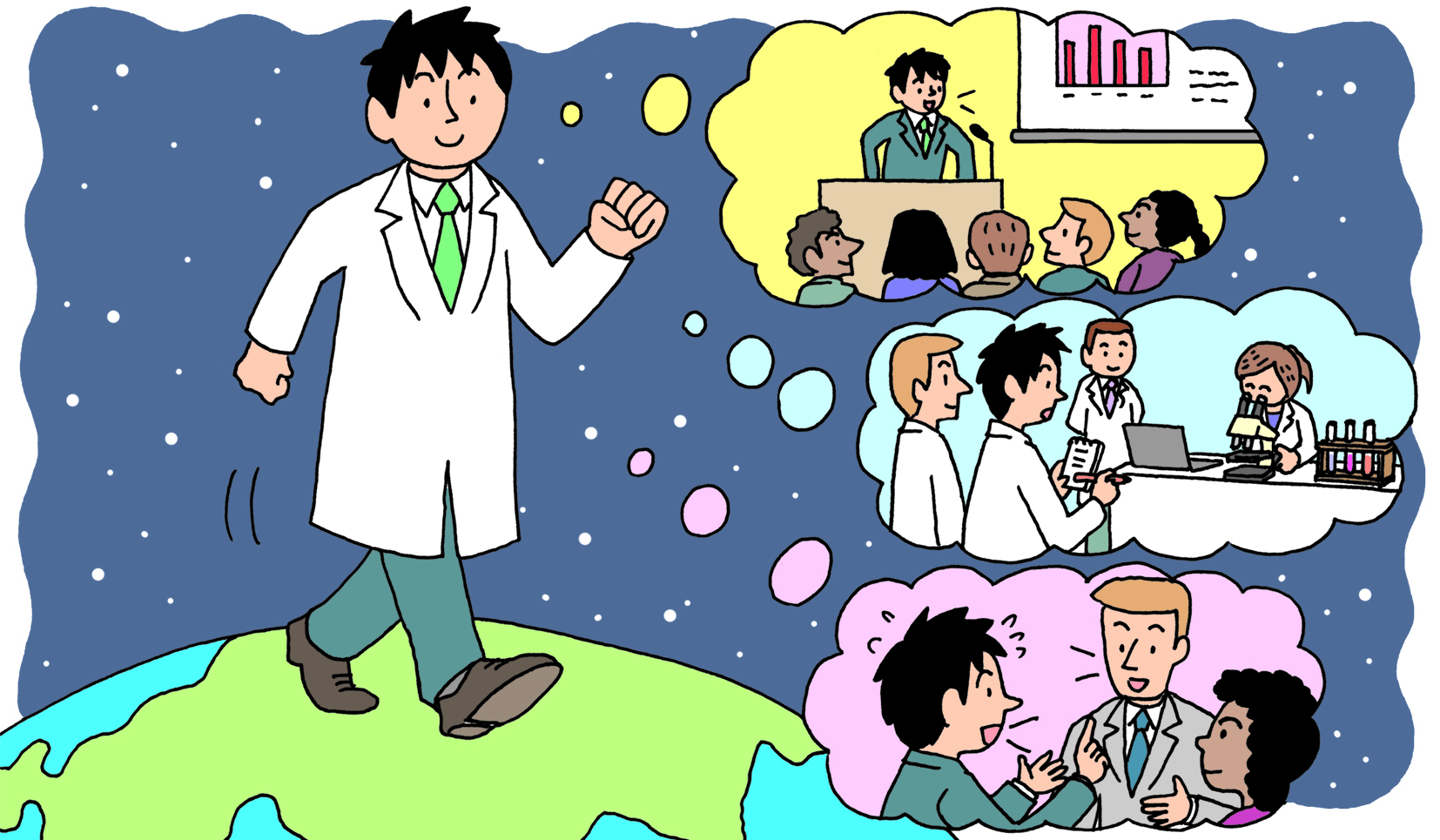
学術集会は,知識の獲得はもちろんのこと,自身の経験を通じて得た知見を発信したり,共同研究者を見つけたりできる貴重な場です。国内で開催される学術集会であれば参加方法も明確で,いざとなれば近くに仲間がいるために,臆することなく参加できる方も多いはず。では,国際学会となったらどうですか。どのような雰囲気か,そもそも研究内容を理解できる語学力があるのかなど,不安が尽きず参加するかどうかという段階から迷う方も少なくないでしょう。
そこで,国際学会に挑戦する方々を応援すべく,数多くの経験をお持ちの先生方に国際学会参加を一層有意義な時間とするための心得を紹介していただきました。各先生から示された“ガイドブック”を片手に,世界を旅してみませんか?
こんなことを聞いてみました
①国際学会参加の心得
②国際学会にチャレンジする方々へのメッセージ

ネットワークを広げるためのアグレッシブな戦略
若林 秀隆
東京女子医科大学病院 リハビリテーション科 教授
①初学者の頃は,主に開催される国・都市で参加する国際学会を選んで演題登録していました。主目的は,観光と日本からの参加者との交流です。国内学会で知り合うよりも,国際学会で知り合うほうがより仲良くなりやすいと言えるでしょう。英語での質疑応答が怖くて,ポスター発表の貼り逃げ(ポスターの前に立っているようにと指示された時間帯にポスターの前にいない)もしました。発表内容を英語原著論文にすることはありませんでした。当時は主に自費で参加していたので,ご容赦ください。
学会場とかなり距離が離れているホテルに宿泊した際,ネームカードをホテルに忘れたことがありました。その学会はセキュリティーが厳しく,ネームカードがなければ会場に入れてもらえず,再発行料は紙切れ1枚なのに何と約2万円。結局,その日は学会参加を諦めて観光しました(苦笑)。
現在は,演者や座長で招待されて参加する専門領域の国際学会が多いです。主に研究費で参加しています。主目的は,学術と国内外からの参加者との交流です。もちろん観光もします。海外の研究者とのネットワークがあるほうが,国際学会に招待されやすいだけでなく,英語論文がアクセプトされやすいと経験上感じています。自分の発表セッションの座長がどなたかわかれば,発表前にごあいさつ。より多くの研究者に自分自身と自分の研究を知ってもらいたいので,なるべく前方に座り,1回は質問するように心がけています。前方に座っていると,座長から無茶ぶりで指名されて質問する機会を作っていただけることもあります。
国内開催の国際学会で,仲間と一緒に発表するのもよいでしょう。2015年に名古屋で開催された第16回アジア静脈経腸栄養学会学術集会(PENSA)では,日本リハビリテーション栄養学会会員の管理栄養士20人前後の発表を支援しました。中には初めての学会発表が国際学会という方も。PENSAでは,管理栄養士の小蔵要司さん(当時・恵寿総合病院)がBest Free Paper Award Poster Presentationを,私がBest Free Paper Award Oral Presentationを受賞しました。共に受賞できたことは,一生の思い出です。
国際学会に招待されたいのであれば,PubMed収載の英語論文の質と量が一定以上あることが必要条件です。研究費の取得もほぼ同様です。全くコネのない国際学会に招待された時,なぜ招待してくれたのかと主催者に聞いたところ,「PubMedで検索して興味深い論文を執筆していたから」と言われたことがあります。初学者でも国際学会で発表した研究内容は,英語論文にしてPubMed収載雑誌に載せましょう。
②参加費は国内学会よりだいぶ高いですが,営利目的のジャンク学会でなければ,それだけの価値はあります。国内学会では知り合えない方と知り合えて,人生の宝になります。ぜひ国際学会での発表に挑戦してください。初学者のうちは,メンターや仲間と共に参加・発表することをお勧めします。

発表後にブラジルの臨床栄養の研究者に声をかけられて,一緒に写真を撮りました。撮影後に高名な研究者であることを知りました(苦笑)。今でもメールやSNSで交流しています。

偶然の出会いが大きな成果につながる
後藤 慎平
京都大学 iPS細胞研究所 臨床応用研究部門 教授
①私の研究分野は呼吸器と幹細胞なので,毎年演題を出す学会は国際幹細胞学会(ISSCR)と米国胸部学会(ATS)に決めています。目的は大きく3つあります。1つ目はまだ論文になっていない情報の交換,2つ目は普通に過ごしていたら誌面でしか会えない研究者との交流や知り合いとの再会,3つ目は自分にとって今まであまり意識していなかった研究内容や技術についてのインプットです。この3年間はWeb参加が中心であり,1つ目の目的だけは何とかクリアできても他は積極的に動かないと難しい状況でした。今までの現地参加では3つの目的は必ず達成できていた上,やはり行かなければ絶対に得られなかったチャンスがあります。それはたまたま知り合った研究者と一緒に食事したことがきっかけになるなど,偶然の要素が大きい貴重な出会いです。その偶然は次の機会につながるかもしれません。今年はいよいよ現地参加できるとワクワクしています。
偶然のチャンスを得るためにも,ぜひ論文がアクセプトされる前に国際学会で自身の研究内容を発表することを勧めます。同じ分野の研究者が演題を出す学会に自分たちの研究成果を持っていけば,抄録をチェックして見に来てくれたり,通りすがりに声をかけてくれたりして交流が生まれるからです。こうした表現をするのも何を隠そう私がその体験者だからです。それは大学院生活があっという間に終了し,オーバードクターを始めた2014年にバンクーバーで開かれた国際幹細胞学会(ISSCR)に初めて参加した時のこと。論文はリバイス実験の最中でアクセプトされるかまだわからない状況でしたが(多くの学会では論文発表前の内容を求められます),この機会にどうしても行かせてもらいたいと医局に交渉してポスター発表で参加しました。若手研究者が一流の研究者と円卓を囲んで対話できるMeet the Professorのセッションにも参加して自分の研究を話したところ,たまたま招待講演に招かれていた呼吸器発生学の大御所の先生が実際にポスターを見に来てくださり,感動的な時間を過ごすことができました。そして後日,その先生の研究室を訪問させてもらったり,来日された時にセミナーをしていただいたり,後輩の留学先の決定にもつながりました。ほかにも,私が現在所属する京都大学に雇用されたのは,この時のポスター発表をきっかけに知り合った企業の研究者と共同研究する話が進んだことに端を発します。ポスター発表をきっかけに次々と成果を出すことができたため,今こうして大学に勤務し続けることができているとも言えるでしょう。
②私の場合,この時の国際学会なしにはその後に続く成果を得ることは難しかったと思います。あなたが求めて得られた偶然のチャンスこそ,きっと大きなブレークスルーにつながるはずです。ですから,国際学会への現地参加での発表を積極的にお勧めしたい次第です。

ラフな格好ですが学会開催地での食事も楽しみの一つです。

国際交流から日本を知る
菊地 良介
岐阜大学医学部附属 病院検査部 臨床検査技師長
①臨床検査技師の業界には,世界33か国が加盟している世界臨床検査技師連盟(IFBLS)があり,2年に一度学術集会を開催しています。私は,2022年10月5~9日に韓国スウォン市で開催されたThe 35th World Congress of IFBLS(IFBLS 2022)に参加してきました(写真1)。

国際学会には,自身の研究の成果発表にひもづく学術交流の側面と,他国との関係にひもづく国際交流の側面があると思います。今回は,上記学会に参加した際の“私の国際学会の歩き方”を例に,臨床検査技師の視点から見た,「国際交流の場としての国際学会」を紹介します。
IFBLS 2022はコロナ禍でありながらも30か国の国と地域から1万1151人が参加し,日本からは40人が参加しました。開会式ではFlag Ceremony(写真2)が開かれ,各国の騎手が国旗を掲げて登場してくる様子はまるでオリンピックかのような雰囲気でした。講演を含む発表演題は18か国から160演題,ポスター発表は16か国から154演題ありました。各国からの演題発表を聴講することで世界の臨床検査業界の動向を把握でき,日常業務を行う際の自身のモチベーション向上につながります。

日本の騎手を務めました。
IFBLS主幹の学会では,学会プログラムの一つとしてラボツアーがあります。今回は,2020年3月に開院した,5Gネットワークを活用するYongin Severance Hospitalの検査室を見学できました。自施設と比較することで,良いところや真似したいところが一目でわかり,施設全体のアップデートへの意欲が湧いてきます。
私は学会中,「積極的に他国の参加者に話しかける」というルールを自分に課しています。どんなに拙い語学力でもボディランゲージを駆使して交流を持つことで,自身の検査室の課題についての他国の状況を把握できます。日本と同じ課題で悩んでいることを共有できると,初対面の相手でも一気に打ち解けます。そして課題共有の中で,国内では当たり前にできていることが実は当たり前ではなく,いかに恵まれているかに気が付くこともあります。国内の仲間を作ることも重要ですが,それ以上に国際学会でしか得られない情報も多分にあることを知っていただきたいです。
②国際舞台で活躍している方との交流は,今後の学術活動意欲を駆り立てるだけではなく,業務改善や自身の世界観を大きく広げるきっかけにもなります。国際学会に少しでも興味がある方は,ぜひいずれか...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

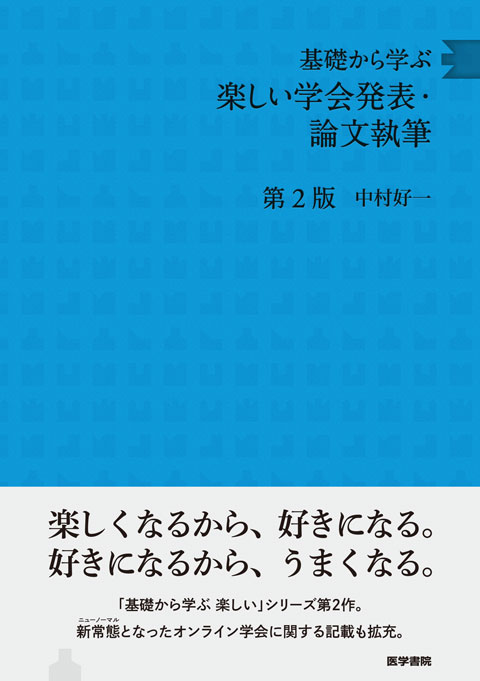
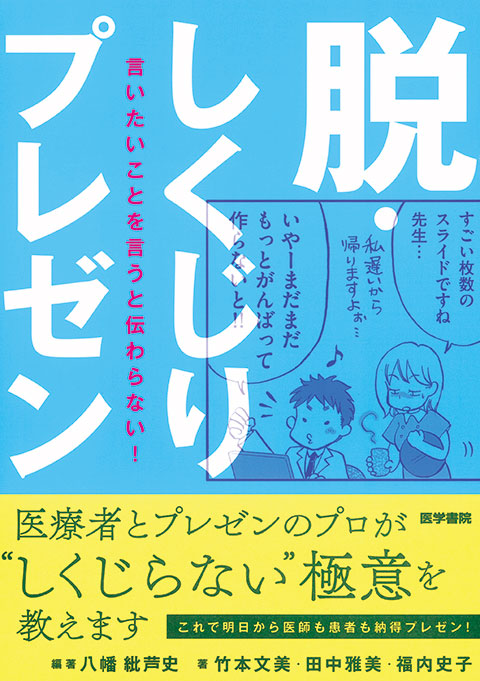
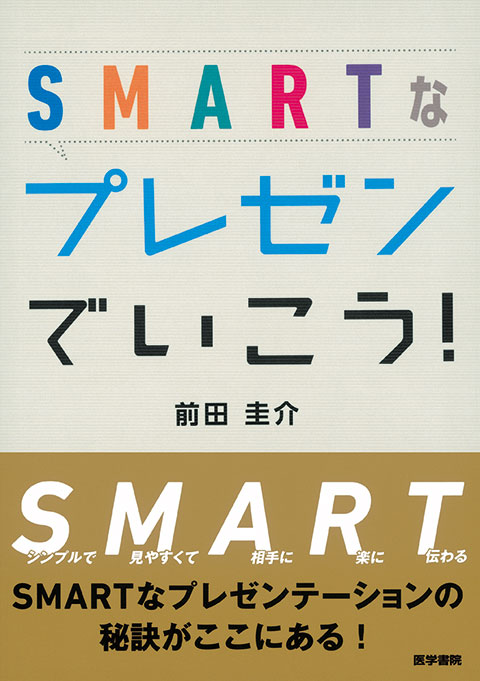
![最強の医学英語学習メソッド[Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/7716/0458/9929/107485.jpg)