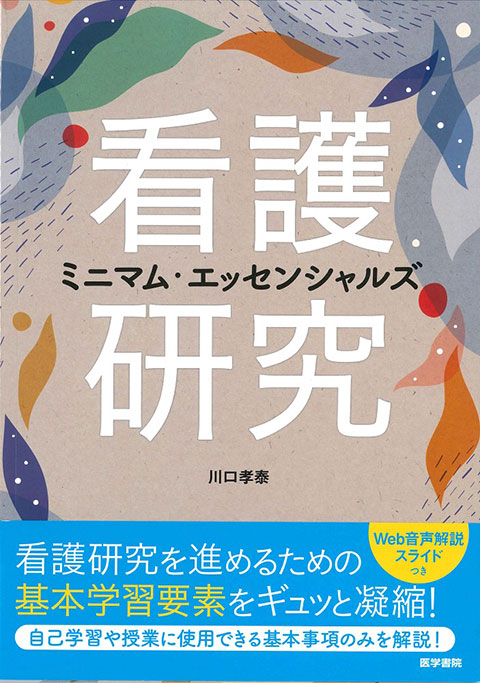DNPで実践と研究に橋梁を架ける
対談・座談会 麻原きよみ,石田佳奈子,井出由美,佐藤直子
2022.12.12 週刊医学界新聞(看護号):第3497号より

米国において,高度実践看護師の最高学位としてDNP(Doctor of Nursing Practice)が発展を遂げている(MEMO)。DNPとは,より良い実践のために既存のエビデンスを最大限に活用できる看護師の養成をめざす教育課程だ。本紙では,国内初のDNP課程を擁する聖路加国際大学大学院の麻原氏,同課程を修了しそこで得た学びを臨床実践に生かす井出氏と佐藤氏,そして米国でDNP課程を修了し現在は後進の教育に携わる石田氏による座談会を企画。DNP課程の内実や,修了の先にあるものについて話した。
麻原 専門看護師(Certified Nurse Specialist:CNS)へのさらなる教育を検討する中で,聖路加国際大ではDNPというモデルに出合い,2017年に教育課程として設立しました。米国で生まれた博士号であるDNPは,実践に焦点を当て,研究成果を活用できる臨床看護師(=高度実践看護師)の育成を志向します。
高度実践看護の担い手を養成するといっても,何を学び,どう臨床での実践に生かすのか,イメージを抱きにくい方も少なくないでしょう。本日は,米イリノイ大シカゴ校でDNP課程を修めた石田さん,弊学でDNP課程を修めた井出さんと佐藤さんにお越しいただきました。実際にDNP課程で学んだお三方に話を伺い,その内実を多くの方にお伝えできればと思います。
理想の看護を実践するスキルセットを求めて
麻原 まずは,DNP課程に進むことにした契機や目的を伺えますか。
石田 実践家としての知識とスキルに磨きをかけたかったからです。臨床ですぐ近くにいる医師の判断力や疾患・薬剤についての知識,院内でのリーダーシップといったスキルセットに魅力を感じるようになり,FNP(Family Nurse Practitioner)としてなら自身の思い描く理想的な看護師としての働き方ができると考えました。患者さんや医療従事者とかかわることが楽しく臨床を離れるつもりはなかったので,Ph.D.は選ばなかったです。また,臨床で働く中で組織レベルでの問題に疑問を抱くことがあり,そうした問題の解決にもDNP課程で得られる学びが役立つと考えました。
佐藤 CNSの役割である看護の質改善に研究的に取り組む力を養う目的で進学しました。私は2012年に日本で初めて在宅看護分野のCNSとなったため,認定審査を受ける1年以上前から,CNSが実践で上げられる成果について問われ続けました。そうした経験から看護の質の担保・向上に研究的に取り組みたいとの思いが生まれ,DNP課程への進学を決めました。「あくまでも実践につながる学位を」との思いもあり,Ph.D.は選びませんでした。
井出 自身の実践の成果を管理者に伝わる形で示せるようになりたいと考え,進学しました。私は修士課程を修了後,小児看護CNSを取得しNICUで働いていました。当院にはCNSや認定看護師等のリソースナースを活用しようとする組織風土があり,年に一度各自の活動を報告・発表する機会が設けられています。しかし,自身の活動の成果を説得力をもって示すだけの力が私には不足していて,管理者から「客観的な成果が見えない」と指摘されることもありました。管理者の納得が得られないままでは自分の思い描く働き方を実現できないと考え,DNP課程の門を叩いたという経緯です。
麻原 皆さん,何らかの実務的なスキルを手に入れることを求めてDNP課程に進んだのですね。
教育プログラムを実装する
麻原 DNP課程では,現場の実践を変える方策を探すプロジェクト研究に取り組むという特徴があります。この点が,一般化を志向した研究に取り組むPh.D.とは大きく異なります。どのようなDNPプロジェクトに取り組んだのかを教えてください。
井出 NICUの新人看護師を対象にした移行支援プログラムを作成し,実装しました。職場適応に困難を抱える新人看護師が多いことを受けて,厚労省は『新人看護職員研修ガイドライン』2)を公開し,新人看護師を迎える環境整備を推進しています。しかし,NICUに関しては基礎教育での学習が限定的な分野である上に,現場ではOJTが中心で,有効な新人教育プログラムが存在しません。政策的にNICUを増床したにもかかわらず,人材育成に関しては昔と変わらないままでした。まずは日本の周産期医療の実情に即した新人教育プログラムを自施設で実施し,ゆくゆくは全国規模で研修体制が確立できればとプロジェクトを立ち上げた次第です。NICUの新人が取り扱える技術項目の範囲を確定し,評価ツール,カリキュラム開発等に取り組んで,移行支援プログラムを完成させました。自施設への実装後4年間を通して新人看護師の退職がゼロになったことは1つの成果ととらえています。現在は,プログラムを導入してくれた他施設で定期的に講義を行っています。
石田 日本では,新人研修は勤務時間内に行われているのですか。
井出 前出のガイドラインが発出されて以降,勤務時間内に組み込む体制をとる施設が多いです。ただ,通常の新人研修に加えてNICU用のプログラムも行うとなると時間が長くなります。そこで,全国の周産期センターを設置する施設の看護部長を対象に,許容範囲と考える講義時間について質問紙調査を行ったところ,プログラム全体で25.7時間が平均的な許容時間とされました。ですから,90分17コマにどうにか収めたのです。
麻原 佐藤さんのDNPプロジェクトはいかがですか。
佐藤 私のプロジェクトも教育プログラムを作る点では井出さんと同様です。しかし,対象はプリセプター,フィールドは訪問看護のためアプローチが異なります。訪問看護ステーションは経営母体が異なる施設が点在していて各施設の所属看護師数は少ない傾向にあり,離職率が高いです。そこで,1つの区域内にあるステーションをまとめて対象とし,各施設のプリセプターとその候補者たちに合同の研修を受けてもらう教育プログラムを作成,現場に受け入れられる改善を図りました。その後,区域内で研修を行う中で管理者の教育に対する考え方に課題があることが見えてきたため,管理者の教育研修プログラムを作成しました。これらのプログラムは全国から問い合わせをいただき,現在は6県で実施されています。
麻原 お二方とも,作成した教育プログラムが他施設に普及するレベルにまで達していて素晴らしいですね。DNP課程での学びがしっかり生きている何よりの証拠です。
実装する介入法について費用対効果も含めて検証を
麻原 石田さんのプロジェクトはどのようなものですか。
石田 大腸がんスクリーニング検査の受診率を上昇させることを目標に,患者さんへの効果的な情報提供方法を探るプロジェクトを行いました。当時私が臨床ローテーションを行っていた施設では,大腸がんリスクが高いとされる黒人患者さんが多いにもかかわらず,スクリーニング検査の受診率の低さが目立っていたからです。多くの論文をサーチした上で3つの介入法を選定し実施,その結果を解析しました。
具体的には,①自動音...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

麻原 きよみ(あさはら・きよみ)氏 聖路加国際大学大学院看護学研究科 研究科長/教授
1981年聖路加看護大卒。95年長野県看護大助教授,2002年信州大医学部保健学科教授,04年聖路加看護大教授等を経て,20年より現職。DNP養成コースでは新設時より院生指導にかかわる。専門は公衆衛生看護学。

石田 佳奈子(いしだ・かなこ)氏 米ラッシュ大学看護学部地域・システム看護学/精神看護学科 助教授
2018年米イリノイ大シカゴ校にてDNPを取得(Family Nurse Practitioner)。VNA Health Care(プライマリ・ケアクリニック),MD at Home(訪問診療)などを経て,22年より現職。

井出 由美(いで・ゆみ)氏 昭和大学病院総合周産期母子医療センター新生児部門 係長
2000年昭和大病院に入職,NICUに配属。同院小児医療センターなどを経て,16年より現職。20年聖路加国際大DNPコース修了。小児看護専門看護師。

佐藤 直子(さとう・なおこ)氏 東京ひかりナースステーションクオリティマネジメント部 部長
2003年から訪問看護師として勤務。16年聖路加国際大大学院看護学研究科助教を経て,19年より現職。20年聖路加国際大DNPコース修了。在宅看護専門看護師。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.03
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。