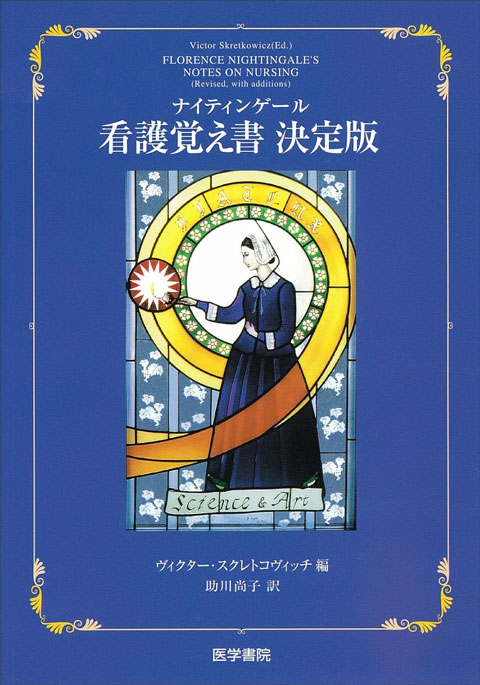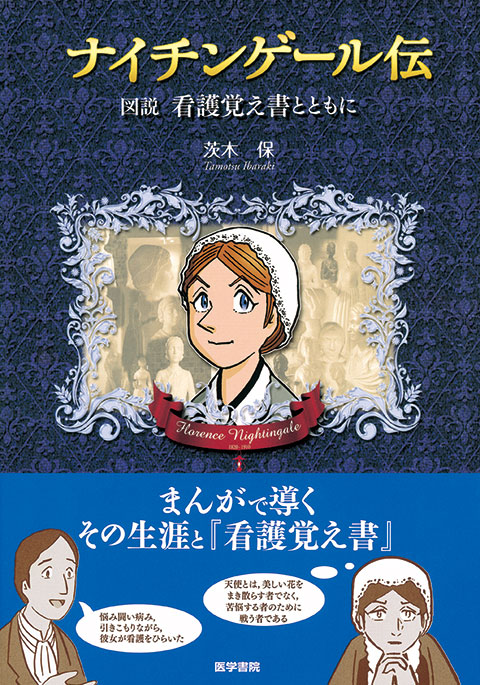私とナイチンゲール「看護覚え書」
寄稿 平尾真智子,城ヶ端初子,金井一薫,小川典子,和住淑子
2022.11.28 週刊医学界新聞(看護号):第3495号より

ナイチンゲール(1820~1910)の生涯と「看護覚え書」について学びながら,基礎看護学で学ぶ普遍的な看護への理解を深めることをめざす『ナイチンゲール「看護覚え書き」入門』(医学書院)がまもなく刊行されます。そこで,ナイチンゲールが唱えた看護理論を現代看護にどう活用すればよいか悩む看護師・看護学生に対して,ナイチンゲールの看護理論に造詣の深い先生方からメッセージをいただきました。
平尾 真智子
健康科学大学看護学部 看護学科 教授
看護理論のテキストでは,ナイチンゲールが最初の看護理論家として登場する。ナイチンゲールの思想は19世紀に突如として現れたものなのか。医療は古代から連綿と続いており,それに伴い医療に不可欠な要素として,看護に類する行為も並行して行われてきたのではないか。医学史の中にヒントになる考え方はないだろうか。
1981年に筆者は日本看護協会看護研修学校で,微生物学者で医学史研究者の川喜田愛郎先生の講演「医学史からみたナイチンゲール――健康の意味をめぐって」を聞き,医学史上の「non-naturals(非自然的なもの)」という概念とナイチンゲールが『看護覚え書き』(看護学生が読み間違いをしないように,本稿では『看護覚え書き』表記を使用した)で主張している内容とが類似していることを初めて知った。Non-naturalsは古代ローマのギリシア人医学者ガレノスの医学思想の重要概念の1つで,今日の衛生学に相当する。その内容は光と空気,食物と飲物,運動と休息,睡眠と覚醒,排泄と保持,心のはりの6項目(いわゆるsix non-naturals)から構成される。川喜田先生は,病人を中心にした場合に医療はケアしかなく,キュアはケアの特殊な形であるととらえていた。この視点こそが,筆者が看護職でありながら医学史を含めて看護史を研究する糸口となった。医学も看護学も患者の治癒という共通の目的に仕える広義の技術学で,近代科学の発展と社会・制度の変容とが医師と看護師という2つの独立したプロフェッションを生んだのは歴史的な必然であり,それらは本質的に1つの技術(アート,テクネー)とみるのが妥当であるとしていた。
長い間,看護は言語化されず,経験知,実践知,暗黙知で伝えられてきた。ナイチンゲールはドイツで受けた看護の教育,ロンドンの病院やクリミア戦争での看護体験などを基に看護を初めて言葉にし,『看護覚え書き』に表現した。ナイチンゲールの看護論は現在の新たな看護理論の基盤にもなっており,同書の内容を理解するには現代からの解釈だけでなく歴史的な視点が欠かせない。このことを教えてくださったのは川喜田先生である。先生は,中世ヨーロッパにナイチンゲールの看護論に類する概念(non-naturals)があったことを強調された。この概念が川喜田先生によって日本の医学史界に紹介されたのは1979年のことで,それまでの日本ではほとんど知られていなかった。
まもなく発行される『ナイチンゲール「看護覚え書き」入門』(医学書院)は『看護覚え書き』に医学史の視点も含めてナイチンゲール看護論を解説したもので,筆者の40年間に及ぶ研究の結晶である。ナイチンゲールの著作はいつ読んでも必ず何かの発見がある。ぜひ原書を手元に置いて,その高い香りに触れてほしい。
城ケ端 初子
聖泉大学大学院 看護学研究科 教授
私が『看護覚え書』を初めて読んだのは看護学校1年生の夏休みであり,「看護学概論」の授業の課題レポートに取り組んだのがきっかけであった。『看護覚え書』からは病気や人間,環境を看護の視点でとらえる重要性を学び,初めて読んだ時は驚きの連続であった。私がとらえていた「病気」や「看護」に対する考えが根底から覆されたからである。
当時の私は,病気とは「全身あるいは身体の一部に異常を来たし,本来の機能が働かず何らかの支障や症状が現われた状態」ととらえていたので,「病気が回復過程である」というナイチンゲールの主張に納得できず混乱していた。しかし,数日後に再度病気という概念を考え直す中で次の文に注目した。「病気とは外因によって侵されたり内因によって衰えたりする過程を癒そうとする自然の働きである」1)。確かに人間は,外部から害や毒があるものから侵襲を受け,体内ではそれに対応しバランスを取る働きが生まれるではないか。そうした侵襲や衰えを癒す自然の働きが病気であると知った。医学とは異なる看護独自の視点から病気をとらえる重要性を知り,とても大きな喜びになったことを今でも鮮明に思い出せる。
また本書には,看護とは「患者の生命力の消耗を最少にするように生活を整えること」1)とある。これも当時の私には難問であった。しかし,本書を読み進める中で,看護とは与薬を行い湿布を貼ることではなく,新鮮な空気・陽光・暖かさ・静けさ・清潔さを適正に保ち,食事の選択と管理などで生活を整え,患者の生命力の消耗を最少にするよう支援することであるととらえられるようになった。看護の意味がわかると,長らく気になっていた本書のサブタイトル「看護であること,看護でないこと」の真意が理解できたのであった。私の夏休みはほとんど『看護覚え書』との格闘に費やされたものの,充実した学びの多い時であった。
『看護覚え書』を初めて読む者は本書を難解であると思いがちだ。しかし,一歩進めて読み込むことで,本書の解釈はもちろん,新しい気づきや考えが湧いてきて大きな学びにつながっていく。本書は看護に関してくめども尽きない豊かな泉のようである。また,本書は時代や国・地域が異なっても,普遍的な看護思想として私たちに看護の基盤となるものを教えてくれる頼もしく素晴らしい一冊である。私は看護師として仕事をしてきた中で,何か行き詰まった時はいつも本書を読み,解決を図ってきた。私にはなくてはならない一冊である。ぜひ本書を機会あるごとに読みこんでいただきたい。
なお,私は今「ナイチンゲール看護研究会・滋賀」という研修会を開いており,地域の看護職や本学の教員・学生を対象に,ナイチンゲールの看護思想を実践に生かすことをめざしている。現在はコロナ禍の影響によりオンライン上で開催しているものの,臨床の看護師や看護学生であれば誰でも参加できるので,もし興味のある方がいればご参加いただきたい。
参考文献
1)F. Nightingale(著),湯槇ます,他(訳).看護覚え書――看護であること看護でないこと.現代社;1968.
金井 一薫
ナイチンゲール看護研究所 所長
私が看護師のライセンスを取得して間もない頃,初めて手に取った『看護覚え書』に,「なぜ,ナイチンゲールは『看護覚え書』の冒頭に“病気とは何か”」という難しい課題を持ってきたのだろう?」「“病気とは回復過程である”とは,いったいどういうことなのか?」という疑問を抱いた。私の知る限り,アメリカの看護理論と名の付く著作において,病気とは何かという課題から解き起こした書物は存在しない。『看護覚え書』の特徴はまさにこ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編
外科研修のトリセツ連載 2025.05.05
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
寄稿 2024.10.08
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。