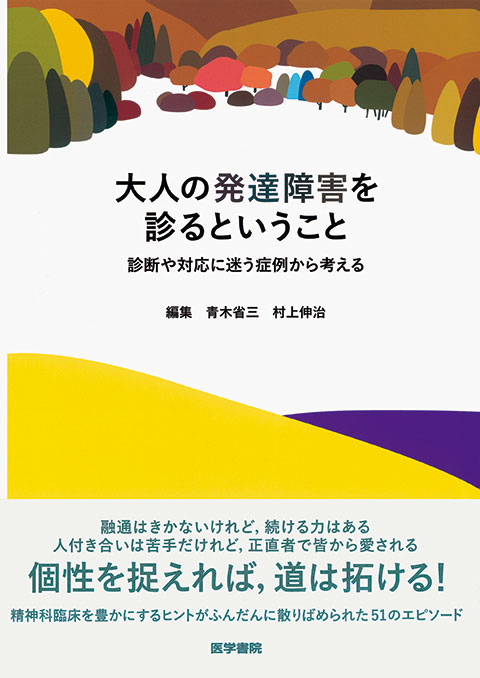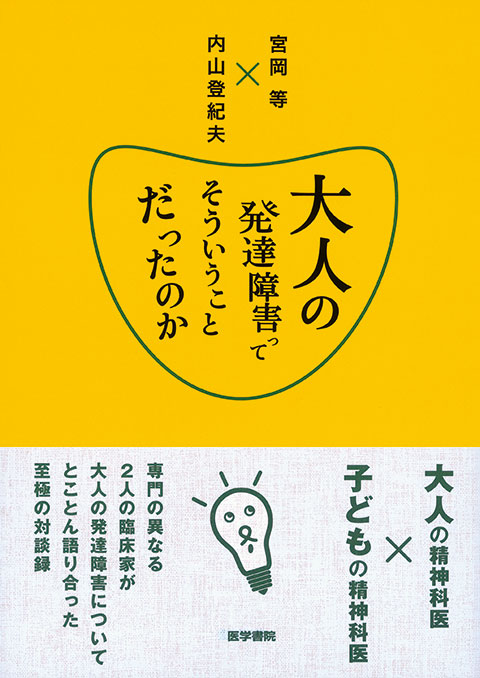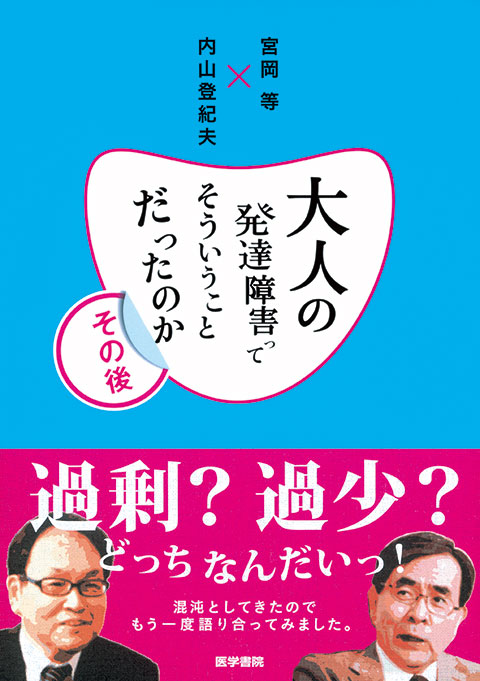認知症と見分けにくい高齢者の発達障害を見逃がさないために
寄稿 佐々木博之
2022.11.21 週刊医学界新聞(通常号):第3494号より
私が所属する研究グループは,以前,認知症と見分けにくい高齢の発達障害患者を見いだし,症例報告を行いました1)。この症例では,認知症を疑われ当院認知症専門外来を受診した60歳前後の方が,詳細な検査や検証の結果,認知症ではなく加齢により顕在化したADHDと診断されました。患者に対してADHDの薬物療法を行ったところ,物忘れや不注意の症状が改善し,復職を果たしています。発達障害と認知症では,治療薬や予後が大きく異なるため,両者の鑑別は意義深いと考えられています。この知見を踏まえて今回,認知症と見分けにくい高齢者の発達障害がどの程度存在するかを明らかにする目的で研究を行いました。本稿では研究の概要を紹介します。
研究を着想したきっかけは,2013年に出会った60代半ばの患者です。介護ヘルパーをしていたその方は,利用者の薬を取り違える,仕事の約束を忘れる,備品を紛失するなど,仕事での不手際が増え,仕事の継続が難しくなっていました。年齢や経過から考えれば認知症の発症の典型的なパターンですが,すでに認知症専門外来を受診し「認知症は否定的」と診断されており,さらにうつ病専門外来や総合病院の内科などでも「異常なし」とされていました。そこでよくよくお話を伺ってみると,支障の多くは注意障害に起因していることがわかり,「この方はADHDなのでは」と考えるに至りました。当時精神科医3年目であった私だけでは本来たどり着けなかった考えですが,それぞれの専門の先生方に認知症やうつ病などの可能性を除外していただいた後だったために診断を下せたのです(いわゆる,「後医は名医」)。実際にADHDとして治療したところ,支障は目立たなくなり,結果仕事を継続できるようになりました。この経験から認知症のように見えるADHD...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

佐々木 博之(ささき・ひろゆき)氏 熊本大学病院神経精神科 特任助教
熊本大医学部を卒業し初期研修の後,熊本医療センター,熊本県立こころの医療センター,東京都立小児総合医療センターにて勤務。その後,現在の熊本大病院神経精神科の特任助教と発達障がい医療センターを兼任。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編
外科研修のトリセツ連載 2025.05.05
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
寄稿 2024.10.08
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。