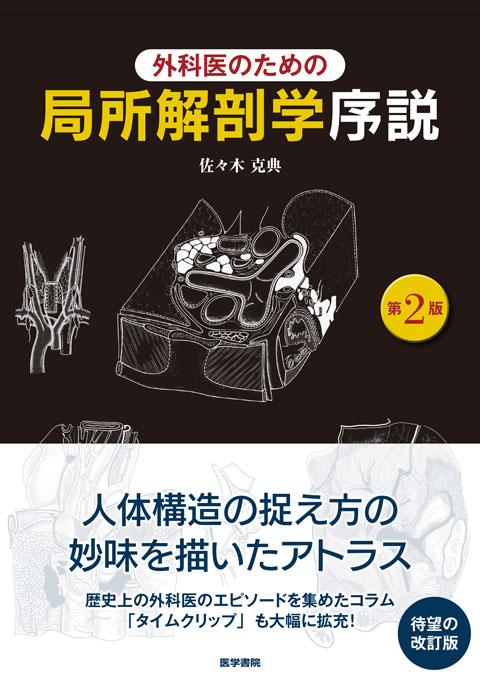MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
書評
2022.10.03 週刊医学界新聞(通常号):第3488号より
《評者》 森 博隆 福島県立医大・血液内科学
解剖と人生の補助線
著者の佐々木克典先生に教わっていた学生の頃,膝を叩きながら本書の初版を読んだ。解剖の質感が伝わる語り口に加えて,初版にも第2版にもその序文に,人体を深く理解するにはカギになる構造があり,それはちょうど幾何学の補助線を引くことで難しい問題がたちまち解決する感覚に似ている,と書いてある通りであったからだ。その考えを「第I章 頸部」から早速実感できる。特に筋・神経・血管と入り組んだ構造を鰓原性嚢腫という奇形を補助線として,鮮やかに解き明かされているところは必読である。
「第II章 胸部」は本書で最もページ数を割いて,解剖の基本を丁寧に説明している。初めて先生の解剖学入門の講義を受けたことを思い出した。どの章も体表解剖から始まるが,この章の体表解剖は他の章より長く,しかしランドマークは胸骨だけで重要な脈管の走行と心臓の構造とを関連付けている。それはちょうど優れた臨床医が患者の些細な仕草を一見して病気を診断しているようで,熟知しているとはこのことを言うのだろう。心臓・肺の解剖は読むのに体力が要るが,どの節よりも多彩なFigureを見ながら一つひとつ理解して読み終われば,それらの構造を手に取るように理解できる。学問に王道はないのだと言われているようだが,その王道は決して無味乾燥な道ではなく,他の解剖学書にはないような視点からの景色が見えて面白い。
「第III章 腹部」では,第II章の9節から続くように,主に横断解剖が行われている。各横断面でのランドマークから始まり,細部の構造まで一つひとつ発生学・生理学の知識も応用し体系的に積み重ねて,1つの横断面を完成させていく。その読後感は数学の証明を読んで最後に理解できたときの爽快感に似ているところがある。
「第IV章 骨盤部」は常に膜層構造の解釈で進んでいく。この膜...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。