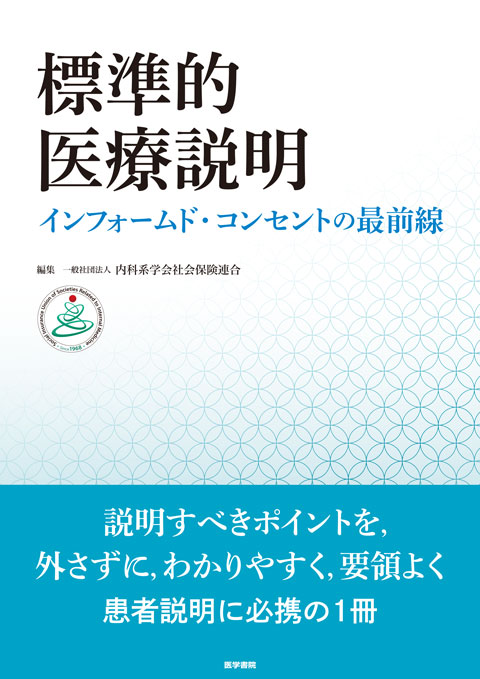心理療法的アプローチを用いて外来患者の本音を引き出す
インタビュー 山田 宇以
2022.09.19 週刊医学界新聞(通常号):第3486号より

外来診療時にガイドラインで示される治療方針を患者に伝えると,すぐに受け入れてもらえる医師と,そうでない医師がいる――。このようなコミュニケーションの行き違いは,医師と患者との間で信頼関係が十分に構築できていないばかりに起こってしまう。患者に心を開いてもらうには,一体どうすればよいのだろうか。聖路加国際病院で研修医に「心療内科で学べるコミュニケーションスキル」を指導する山田宇以氏に,患者の本音を引き出す心理療法的アプローチの技法について聞いた。
経験値が貯まりやすい米国の研修手法
――山田先生は2010年に米国のサンディエゴ大に留学されていますね。そこで見たレジデントへの教育法を,現在所属している心療内科での研修医教育に取り入れていると伺いました。留学時に何か気付きがあったのでしょうか。
山田 留学先で出会ったレジデントの行動科学面での優秀さに驚きました。当時,研修に携わっていた当科の研修医にうつ病の診断基準等を聞いても答えられませんでしたが,彼らは即答したのです。この違いは,恐らく教育手法の違いに起因するのではと考えました。
――日米で大きく異なっていた点はどこでしょうか。
山田 外来における問診の指導の仕方です。留学先では,指導医やチーフレジデントが別室でモニタリングする中で,レジデントが事前に評価や介入法といった目標を立て一人で問診を行っていました。問診の途中や問診後に研修医がモニタリングルームに移動して指導医等に相談することもありましたが,患者と接するのは基本的にレジデントのみでした。
一方,日本の研修では外来初診の問診を研修医が担当し,その後は指導医の診察を見学するだけで,治療方針も指導医が決めるパターンが一般的と思います。米国のほうが明らかにレジデントが主体的で,経験値が貯まりやすかったのです。
――そうした気付きを得て,研修体制を刷新したのですね。
山田 ええ。外来を担当する前には問診法・コミュニケーションの教育を行い,ロールプレイで経験を積むこと,外来では指導医と相談しながらも,研修医が一人で患者への病態説明を行うことを決めました。その結果,「実用的で成長を感じられる」と心療内科研修が評判となり,院内で必修化されました(現在は選択制)。
共感と反映で患者の気持ちに寄り添う
――研修に携わる中で何か気付いたことはありましたか。
山田 問診の際に言葉に詰まってしまう研修医が多いことです。患者の主訴を傾聴する,感情を受け止める必要があることは理解していても,その次に何を言うかまでを考えられていないからでしょう。相づちを打った後の一言が出てこず,次々と鑑別を探る質問をしてしまう。そうした研修医には心理療法的アプローチを実践するように指導しています。
――どのようなアプローチ方法なのでしょう。
山田 患者と信頼関係を構築して心理的問題の解決をめざすコミュニケーションの手法です(図)。初めに患者の主訴を傾聴し共感することで患者に安心感を与え本音を語ってもらい,必要な情報を得て正確に診断を行います。ここで意識すべきは,感情的共感と認知的共感の2...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

山田 宇以(やまだ・うい)氏 聖路加国際病院心療内科 医長
2000年徳島大医学部を卒業後,東邦大医療センター大森病院心療内科に入職。07年聖路加国際病院心療内科に赴任。10年米サンディエゴ大大学院の夫婦家族療法プログラムの国際研究員として留学。同年,カリフォルニア大サンディエゴ校の家庭医療部門,サンディエゴホスピスの研修にも参加する。心療内科専門医。医療者が家族支援について学びを深めるコミュニティ「ファミラボ プライマリ・ケア医のための家族支援研究所」(https://www.facebook.com/familabo113rd/)で教育顧問として運営にも携わる。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.03
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。