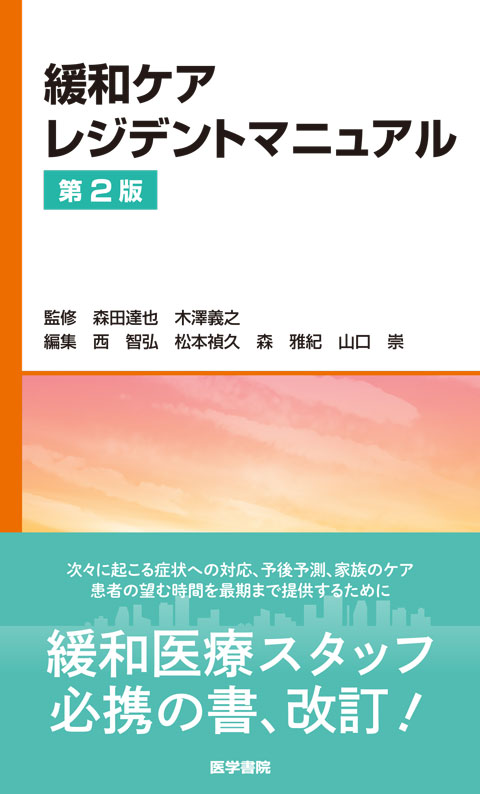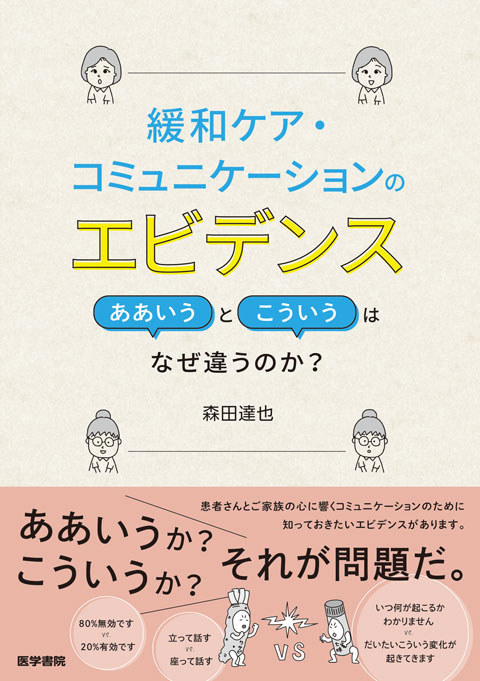第27回日本緩和医療学会
取材記事
2022.07.25 週刊医学界新聞(看護号):第3479号より

第27回日本緩和医療学会学術大会(大会長=東北大大学院・宮下光令氏:右写真)が7月1~2日,「現状を評価し,前に進む」をテーマに神戸国際展示場(兵庫県神戸市)他にて開催された。
本紙では大会テーマに鑑み,がん対策における緩和ケア推進の現状と課題をデータで評価した特別講演,30年に及ぶACPの理論・実践・実証を国際的潮流を踏まえてレビューした講演の2題を報告する。
データで見る緩和ケアの進展と残された課題
がん対策基本法の基本理念のひとつが「がん医療の均てん化の促進」だ。これを受けて,がん医療の現状をQuality Indicator(QI)を用いてモニタリングする事業や,患者体験調査による実態把握が進んでいる。東尚弘氏(国立がん研究センター)による特別講演「データに見るわが国の緩和ケア」では,これらのデータをもとにがん医療・緩和医療の課題が提示された。
がん診療連携拠点病院の「現況報告」や「指定要件に関する意見・実態調査」などを踏まえると,緩和ケアチームの人員などのストラクチャー(構造)は整備されつつある。その一方で,東氏が問題提起したのは,緩和ケアのプロセス(過程)やアウトカム(結果指標)の現状だ。
例えば院内がん登録およびDPCデータによるQI研究を踏まえると,症状緩和的治療の実施は診断初期で1割程度,Ⅳ期胃がん・経過観察例においても緩和ケア関連加算の算定は3割に留まる。また,肺がん・死亡1か月前の化学療法は2割で実施,2週間前でも1割で実施されており,終末期におけるQOLの悪化が懸念される。さらに患者体験調査の結果,診断から約3年後において「苦痛のある」患者は35%,「日常生活に困っている」患者は19%に上った。特にAYA世代において,医療者との対話や身体的つらさの相談ができていない傾向が顕著であるという。
最後に氏は,こう...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。