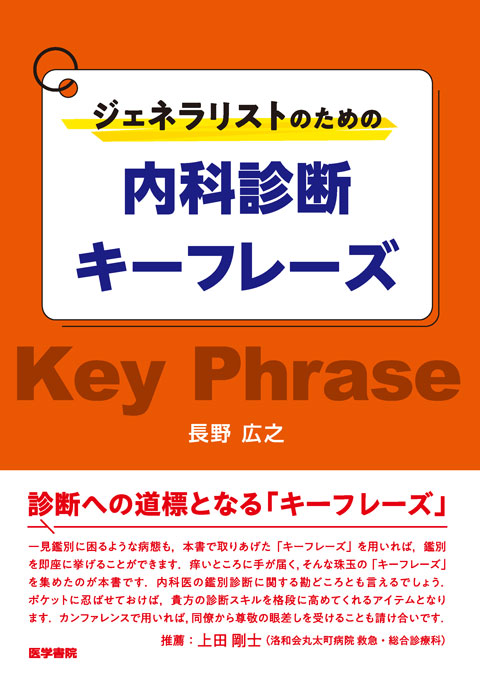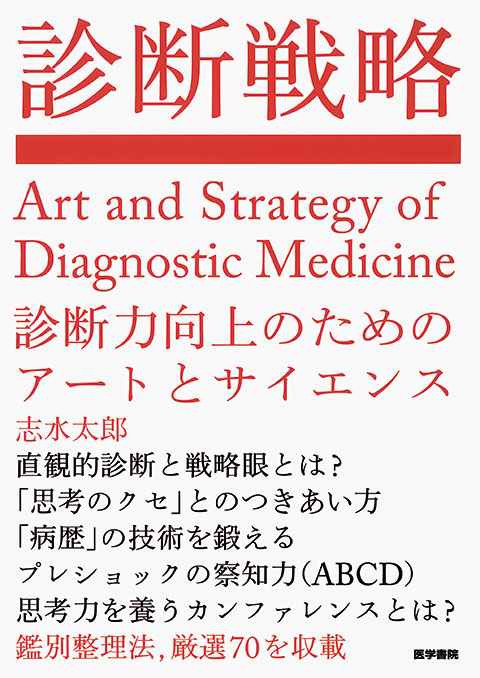「キーフレーズ」を用いてネクストレベルの臨床推論をめざす
対談・座談会 志水 太郎,長野 広之
2022.07.18 週刊医学界新聞(通常号):第3478号より

患者の訴えから診断を導き出す思考過程である「臨床推論」を学ぶ機会が近年増えている。しかし,学んできた臨床推論による対応だけでは診断が難しい症例に出合うこともままある中,得られた情報をどう整理し診断につなげればいいのか,途方に暮れる若手医師は少なくない。近刊『ジェネラリストのための内科診断キーフレーズ』(医学書院)では,臨床推論をスムースに行うための道具立てとして,鑑別診断を絞るための「キーフレーズ」を提示している。
本紙では,同書著者の長野広之氏と,『診断戦略――診断力向上のためのアートとサイエンス』(医学書院)著者で診断学領域の発展に尽力する志水太郎氏の対談を企画。「キーフレーズ」の有用性や診断学領域の今後の展開について議論した。
長野 本日はよろしくお願いします。私の医学生時代,志水先生を大阪大学にお呼びして臨床推論に関する勉強会を開いたことを思い出して,感慨深いです。
志水 懐かしいですね。
長野 今でこそ臨床推論は一般的になりましたが,私が学生だった12,3年前は,教えてくれる先生はそう多くいませんでした。志水先生のレクチャーが非常に魅力的に映ったのを覚えています。
志水 診断学領域では,「診断の卓越(diagnostic excellence)」というキーワードが2021年に登場しました。患者の状態について,正確で精密な説明を達成するための最適な(タイムリーで,費用対効果が高く,便利で,患者に理解しやすい)診断プロセスを指します1)。診断エラーをどう減らしていくかという従来の観点から,卓越性の向上をめざし,診断にまつわる臨床のアウトカムをさまざまな角度から良くしようとする動きが世界的に広がっています。医師の思考過程がクローズアップされたこの10年でしたが,今後は外部の環境やシステムを含めた診断の在り方にフォーカスを当てる流れになっていくでしょう。
この10年に関して言うと,日本ほど診断技術の研さんに熱い国は世界を見渡してもおそらくないと思います。勉強会が国内のあちこちで多数開かれています。そうした動きは診断学分野が発展するためのエンジンとして働いてきたのでしょう。一つのムーブメントであり,日本の独自性だと思います。
今回先生が上梓された『ジェネラリストのための内科診断キーフレーズ』は,まさにそうしたムーブメントに新たな角度から焦点を当てた,大きな意味合いのある本だと私は考えています。
長野 ありがとうございます。
難しい症例を診断するロジックを押さえる
志水 長野先生は,なぜ本書を書こうと思ったのですか。
長野 医師として働き始めた当初の体験がベースにあります。臨床推論の勉強会に,私も学生・研修医時代から参加してきました。けれども優れた医師が診断に当たって一体どのような思考過程を経ているのか見えない状況が,卒後3年目ぐらいまで続きました。勉強会自体は楽しいのですが,最終診断となった疾患名も知らなければ,診断に至るプロセスもよくわからない。自身の力不足を感じさせられるという意味ではつらい経験でもありました。
しかし,卒後5年目を過ぎた頃に,卓越した医師に共通している部分に気がつきました。彼らは病歴や身体所見,提示される検査所見から診断特異的な情報を取り出してくることに優れていたのです。そのことに気づいて以来,私も同様のポイントに注目するようになりました。そういった情報,拙著で言うところの「キーフレーズ」を日々の診療の中でメモ書きとして蓄積し始めました。そしてメモ書きがある程度集まった時点で,『medicina』誌の連載で発表する機会を得ました。それが今回の単著に結実したという経緯です。
志水 書籍のタイトルにもなっている「キーフレーズ」とはどのようなものか,改めて説明してもらえますか。
長野 一言で言うと,「鑑別診断を絞るのに特異的であり,知っておくと役に立つproblem」を指します。臨床では鑑別を挙げたり絞ったりするのに困りがちなパターンが存在します。そうしたものをキーフレーズとして収集しておくことで,次にまた同じ症状に出合った時に,鑑別を素早く挙げられます。診断に至るまでにはいくつかのプロセスがありますが,患者さんから得た情報を適切に医学言語化(例えば「気を失った」なら,「失神」に言い換え)した上で,それに対して鑑別診断を絞る情報(semantic qualifier,註)を付け加え,診断に特異的なキーフレーズとして取り出すのです。
志水 なるほど。患者さんを診た時に,「こういう状況があったら何を考える?」ということですね。よくある例を挙げると「突然発症の頭痛」などでしょうか。
長野 そうです。ただ,今例に挙がった突然発症の頭痛の鑑別は,初学者が勉強する初級レベルに当たります。その次のレベルで困るのは,例えば「くも膜下出血と考えてCTを撮ったものの出血がない」などです。そこで,「CT正常のthunderclap headache」といった具合に情報を付け加えると,さらに特異的になるという...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
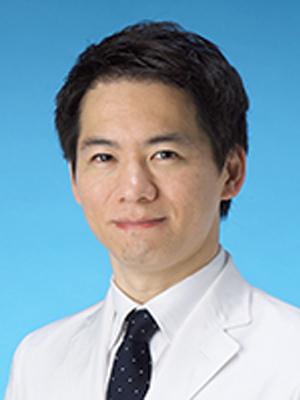
志水 太郎(しみず・たろう)氏 獨協医科大学総合診療医学 主任教授
2005年愛媛大卒,18年より現職。専門は診断戦略学。病歴,フィジカル,診断思考を軸に,診療,研究と後進指導に従事している。博士(医学),修士(公衆衛生学),修士(経営学)。Diagnosis(De Gruyter)国際編集委員。主な著書に『診断戦略――診断力向上のためのアートとサイエンス』(医学書院)。

長野 広之(ながの・ひろゆき)氏 京都大学大学院医学研究科 医療経済学分野博士課程
2011年阪大卒。天理よろづ相談所病院総合内科,洛和会丸太町病院救急総合診療科などを経て,20年より京大大学院医学研究科医療経済学分野博士課程。臨床研究や医療経済,Quality indicatorについて学び,データベース研究に取り組む。著書に『ジェネラリストのための内科診断キーフレーズ』(医学書院)。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。