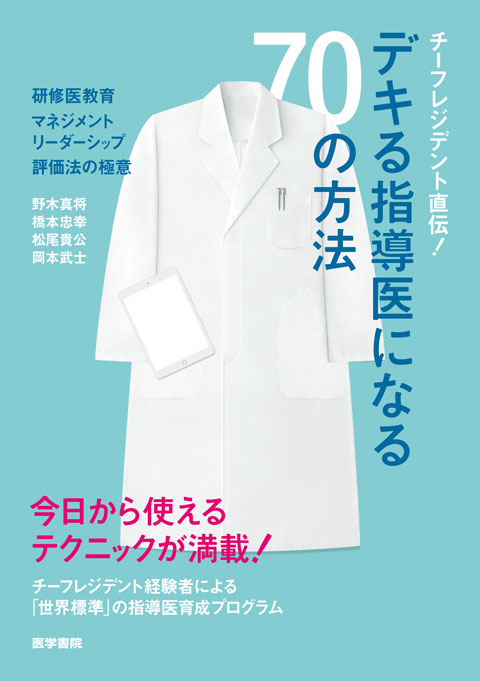学びを支援する学習環境の構築を
対談・座談会 清水 郁夫,川上 ちひろ
2022.07.11 週刊医学界新聞(レジデント号):第3477号より

自身はうまく指導しているつもりでも,思ったように後輩が成長せずいまひとつ伸び悩んでいる――。このような経験がある指導者は多いのではないか。学習者が失敗から教訓を得て成長していくためには,指導者との間に失敗を共有できる信頼関係が必要であり,教育学の知見では「指導者との関係」も学習環境を構成する一つの要素とされる。では,指導者はどのように信頼関係を築き,学習者が学習に集中できる環境を構築していけばよいのか。
本紙では医療者教育の専門家である清水氏,川上氏による対談を企画した。本対談を通じて,最適な学習環境を整備するポイントを探っていきたい。
清水 卒後8年目,私は専攻医として市中病院の救急外来で研修医を指導していました。ある日,私と同年代の内科医にコンサルトをお願いしたところ,その医師が「お前はなんでこんなこともやっていないんだ」と,ものすごいけんまくで研修医を罵倒したのです。研修医も勉強不足であったのは確かですし,命を預かる現場の先輩としての,彼なりの正義感が働いたのだと思います。しかし,30歳を過ぎて多少なりとも経験を積んだ指導医と呼ばれる人間が,このような指導しかできないのかと感じました。この体験は,私が医学教育や学習環境に関心を持つきっかけの1つです。川上先生も長年,学習者支援に関する研究に取り組まれていますよね。関心を抱くきっかけはあったのでしょうか。
川上 私は20年くらい前まで,養護教諭として公立の小中学校に勤務していました。ある研究会で発達障害の存在を知り,「自分にできることはあるだろうか?」と考え,看護の道に進みました。そして,看護学生をしながら模擬患者として活動する中で医療者教育にかかわるようになり,教員になってからは発達障害など支援ニーズがある医療系学生や医療者の学習者支援に関心を持つようになりました。現在,岐阜大学大学院医療者教育学専攻修士課程でも演習などを担当しています。同学では清水先生にも非常勤講師として,認知心理学を応用した医療者教育の授業を行っていただいていますね。
指導医との関係や業務の性質も学習環境に含まれる
清水 研修医教育を考えた時に,研修医(学習者)が1人で育っていけばそれに越したことはありません。一方で,教育にかけた時間の割に研修医が伸び悩むと,「あいつは全然勉強しない」と指導医は思ってしまいがちです。言い方を変えれば,成長しない研修医は「問題がある学習者」と思われてしまうのです。学習者自身に改善の余地があることもありますが,指導者や環境との相性が合わないことで成長しづらい場合もあるでしょう。
川上 そう思います。おっとりした性格の新人看護師が集中治療・救急現場での勤務となった場合に,現場のスピード感についていけず挫折してしまうことがあると以前聞きました。
清水 臨床研修のケースで考えると,自身の希望先とは異なる診療科をローテートする際に,同様に適応しにくいとの話はよく聞きます。これらは学習者側だけの問題ではなく,指導者や研修システム,設備によっても生じるとSteinertは指摘しています1)。また西城らは,これらを環境に起因した問題としてまとめています2)。学習環境と言えば学校の設備などの物理的なモノが想起されがちですが,診療業務の性質や求められるスピード感も学習環境と表現できます。加えて,もし研修医数名で診療科をローテーションしているのであれば,その人たちとの関係も重要であり,指導医や他職種との関係,院内のルールなども環境に含まれます。ルールや大掛かりな設備はやすやすと変えられない一方,研修医とのかかわり方といった対人関係は改善しやすく,かつ効果が望めるものと考えられます。
川上 学習者の中にはどんな環境でも適応できる,あるいは逆にどの環境でも適応できない人がいます。さらに,その両者の間に環境によって適応できたり,できなかったりする人もいます。
清水 他者からの援助を必要とせず自分で育つ,どこでも適応できる理想的な学習者は,教育学では「自己調整学習ができる人材」と定義付けられます。自己調整学習とは,①自分は何ができていないか,何をしなければいけないかがわかっている,②学ぼうという動機がある,③学び方がわかっている,の3つがそろう学習です。①~③がそろう学習者はどんな環境でも適応できますが,大抵の学習者は完璧ではありませんから,①~③のどれか,あるいは複数が不十分で,状況によっては「要領が悪い」とみなされてしまうかもしれません。
川上 環境への適応能力も含め,学習者は何がしか能力にグラデーションがあって,場合によっては「問題がある学習者」と判断されてしまうことがあるのですね。
清水 ええ。したがって,まずは何が不足しているかを指導医が把握することが重要です。①が足りなければできていない部分を伝え,②が足りなければ動機付けになるような学習の意義を共有します。③が足りない場合は,指導者自身が学んできた方法を教えることがよく行われます。ただし,自分自身の経験は熱意を持って伝えやすいかもしれませんが,その方法が必ずしも相手に合うとは限りませんので,ここはさまざまな教育理論や技法などをいかに活用するか,腕の見せどころと言えるでしょう。
川上 加えて,学習者にとって合う/合わないやり方や環境があること,学習者にもさまざまなタ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

清水 郁夫(しみず・いくお)氏 信州大学医学部医学教育研修センター/附属病院医療安全管理室 助教
2004年信州大医学部卒。研修医指導を契機に医学教育に関心を持ち,13年より現職。16年蘭マーストリヒト大医療者教育学修士課程修了。博士(医学)。20年度医学教育振興財団懸田賞受賞。近年は医療安全領域にも活動を拡げている。

川上 ちひろ(かわかみ・ちひろ)氏 岐阜大学医学教育開発研究センター 併任講師
養護教諭として岐阜県の公立小中学校に勤務の後,2001年に退職。05年岐阜大医学部看護学科を卒業。12年名大大学院医学系研究科博士課程修了。11年より助教を経て現職。専門は発達障害を持つ学習者の教育・支援。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編
外科研修のトリセツ連載 2025.05.05
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
-
寄稿 2024.10.08
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。