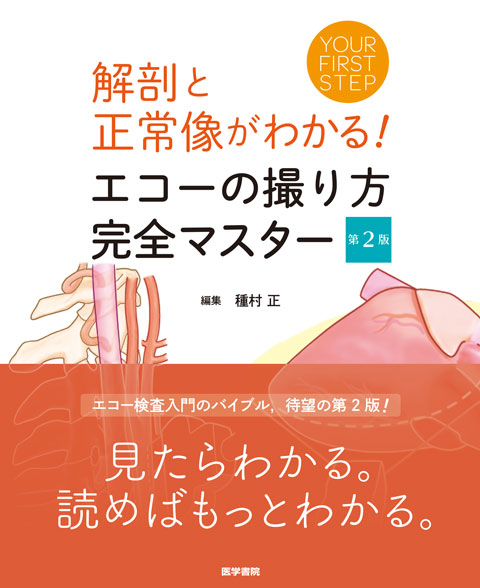嚥下機能評価におけるエコー利用の可能性
寄稿 三浦 由佳,他
2022.04.25 週刊医学界新聞(看護号):第3467号より
近年,超音波画像診断装置(以下,エコー)は技術の発展により,ポケットサイズでも高画質でクリアに観察できる機器が増えている。エコーは,非侵襲かつリアルタイムに体内を可視化できる点にメリットがある。そのため,看護師が通常行う問診,視診,触診,打診,聴診に加え,第6のフィジカルアセスメント「可視化」のためのツールとして,幅広い場面で活用されつつある。
これまで看護師はベッドサイドで,食事中あるいは食後のむせの観察や水飲みテスト,フードテスト,頸部聴診法などを用いて嚥下機能を評価してきた。特に,誤嚥や咽頭残留は誤嚥性肺炎の高リスク因子となるため重要な評価ポイントである。上記の嚥下機能評価法に加え,エコーを用いて非侵襲的にかつ普段の食事場面で誤嚥・咽頭残留を可視化できれば,食形態や姿勢の調整,咽頭内の吸引など,誤嚥や残留を減らし誤嚥性肺炎を予防するためのケアを,施設や在宅においても提供可能となる。本稿では,エコーを用いた誤嚥・咽頭残留のアセスメントの有用性とその方法を紹介する。
エコーを用いた誤嚥・咽頭残留評価の有用性
まずエコーを用いた誤嚥・咽頭残留の評価に基づくケアが,誤嚥性肺炎の予防に効果がある可能性を示したランダム化比較試験を紹介する1)。対象は特別養護老人ホームに入居中の65歳以上の高齢者である。筆者らは,対象者を介入群23人,対照群23人に分け,8週にわたる観察期間を設けた。介入群はエコーを用いた誤嚥と咽頭残留の評価を2週に1回行い,結果に基づいて食形態の変更や交互嚥下を勧めた。対照群ではエコーを用いず,従来通りの食事場面の観察,水飲みテストなどのスクリーニングテスト,そして誤嚥を強く疑う対象にのみ嚥下内視鏡検査を実施し,結果に基づいて誤嚥や咽頭残留の低減を試みた。
介入群では初回の観察時3人に誤嚥がみられ,8週後にはエコーで評価した合計嚥下回数に占める誤嚥の割合が中央値で31%減少していた。一方,対照群では初回観察時に3人に誤嚥がみられ,誤嚥の割合の減少は中央値で11%であった。観察期間内での誤嚥性肺炎の発症は介入群が2人,対照群が1人であり有意差はみられなかったものの,食事場面の観察やスクリーニングテスト,嚥下内視鏡に加え,エコーで評価した誤嚥や咽頭残留の結果に基づく介入が肺炎予防に効果的である可能性を示した。
実際の評価方法
エコーを用いて嚥下機能を評価する際,機器の選択が重要なポイントの一つとなる。気管内の誤嚥物や咽頭内の残留物のアセスメントでは,体表に近い浅い部位の観察に適したリニアプローブが接続可能で,画像の中で目印(ランドマーク)となる甲状軟骨や喉頭蓋,総頸動脈の輪郭を描出可能な程度の解像度を有する,周波数5~15MHzの帯域幅の機器の使用を推奨する。
同時に,評価のタイミングやプローブの当て方について,患者の安楽を考慮することも重要であ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

三浦由佳(みうら・ゆか)氏 藤田医科大学研究推進本部 社会実装看護創成研究センター
2009年東大医学部健康科学・看護学科卒業後,同大病院にて勤務。16年同大大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻博士課程修了。博士(保健学)。16年金沢大新学術創成研究機構特別研究員,19年東大大学院医学系研究科社会連携講座イメージング看護学特任助教を経て,22年4月より現職。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。