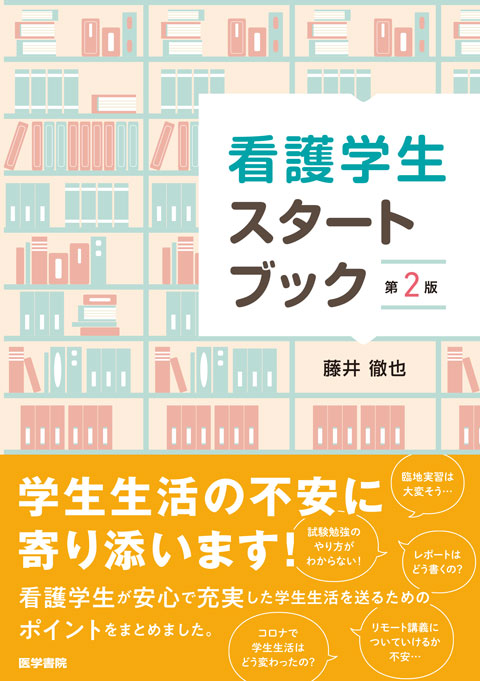FAQ
新看護学生を受け入れる準備を整えよう!
患者や医療者のFAQ(Frequently Asked Questions;頻繁に尋ねられる質問)に,その領域のエキスパートが答えます。
寄稿 藤井 徹也
2022.02.28 週刊医学界新聞(看護号):第3459号より
もうすぐ春,入学の季節が訪れます。新入生の迎え入れ準備を進めている学校も多いのではないでしょうか。文科省によると,新入生を対象に行われる「初年次教育」は,「高等学校や他大学からの円滑な移行を図り,学習及び人格的な成長に向け,大学での学問的・社会的な諸経験を成功させるべく,主に新入生を対象に総合的につくられた教育プログラム」あるいは「初年次学生が大学生になることを支援するプログラム」と定義されています1)。
わが国の初年次教育では,「レポート・論文などの文章技法」「プレゼンテーションやディスカッションなどの口頭発表の技法」「学問や大学教育全般に対する動機付け」「図書館の利用・文献検索の方法」などが重視されています1)。看護系大学も例に漏れず,初年次教育で取り組まれている内容として「図書館の使い方」(80.2%)や「アカデミックスキルとしてのレポートの書き方」(77.8%)などが多いようです2)。
少子化や大学数の増加に伴い「大学全入時代」と言われる近年,入学生の学力低下や目的意識の低下などに鑑みて,初年次教育が一層注目されています。この傾向は大学のみならず看護基礎教育課程全体に言えると筆者は考えています。そこで今回は,看護基礎教育課程における初年次教育について,①受け入れる側の教員の準備,②学生からよくある質問,③継続的な教育が必要である可能性について私見も踏まえて述べます。なお本稿では,高等学校までに習得しておくべき基礎学力の補完を目的とするリメディアル教育は「初年次教育」に含まず,前述の「初年次学生が大学生になることを支援するプログラム」としてお伝えします。
FAQ 1
初年次教育を行うに当たって,気を付けたいポイントを教えてください。
各看護系専修学校・大学等はアドミッションポリシーを掲げ,多様な入試方法で学生を募っています。入試方法別の定員数の比率も学校によって異なります。つまり,入学する学生の特徴は学校ごとに差があるのです。そのため新入生を受け入れる教員は,所属する学校の学生の特徴を把握した上で,その特徴に合った初年次教育のプログラムを準備しましょう。自主的に学修する習慣が身についた新入生が多い学校であれば,クリティカルシンキングや文献検索,プレゼンテーションなどの大学生に必要なスタディスキルを重点的に学べるプログラムがよいと考えます。一方で,受動的に学ぶ“生徒”から能動的に学ぶ“学生”への移行に手助けが必要な新入生が多い場合,まずは主体的な学修方法を教授し,その後に演習等も通じてスタディスキルを修得できるプログラムを設計するのがよいでしょう。
さらに初年次教育のプログラムを構築する際には,その効果を測定する方法についても検討する必要があります。これは,初年次教育をどのようなプログラムとして位置付けるかによって変わります。例えば,リベラルアーツの科目を初年次教育として位置付けるなら,対象科目の成績を基に算出したfGPA(functional Grade Point Average)の値から学生の修得状況を把握します。あるいは,初年次教育そのものを1つの科目としてカリキュラムに組み込む場合は,学生個々の対象科目の成績と中央値,該当学期の他の科目のfGPAの値との比較で修得状況を評価します。
ただし,初年次教育を「初年次学生が大学生になることを支援するプログラム」であるととらえるならば,当該科目とは別に,他...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
藤井 徹也(ふじい・てつや)氏 豊橋創造大学保健医療学部 教授
1994年藤田保衛大(現・藤田医大)大学院修了,博士(医学)。愛知県立看護大(現・愛知県立大看護学部)講師,名大准教授,聖隷クリストファー大教授などを経て,2017年より現職。専門は基礎看護学。著書に『看護学生スタートブック(第2版)』(医学書院)。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。